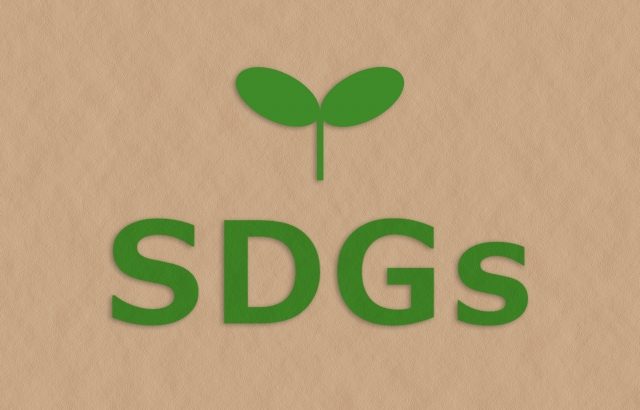金融業界がSDGsに取り組む目的
金融業界ではSDGsに対して積極的に取り組んでいます。
金融業界は法人や個人などと取引することになるので、取引先がSDGsに対しての活動をおこなっていることが多いことから金融業界でもSDGsに取り組んでいます。
金融業界は社会的に担っている責任が大きいことからも、SDGsに取り組むことで社会的な責任を自覚して果たすことをアピールすることができるでしょう。他にも金融業界がSDGsに取り組む目的について紹介していきます。
企業のイメージアップ
SDGsに取り組むことで企業のイメージアップに繋がるので、SDGsに取り組んでいる企業と取り組んでいない企業ではイメージがこれからは大きく異なると予測されています。
また、日本ではSDGsに対する認知度は高くなってきていますが、実際に取り組んでいる企業は少ないことから、SDGsを積極的に取り組むことができれば社会的な責任を果たした目の努力をしていることを対外的にアピールが可能です。
SDGsに沿った投資や融資を行うことで、貧困の削減、教育の向上、環境保護など、社会的インパクトを創出することができます。これにより、金融機関は自社のブランド価値を高め、顧客や投資家からの支持を得ることができます。
社会的責任とリスク管理
金融機関は、社会的責任を果たすことで、ステークホルダーからの信頼を得ると同時に、持続可能なビジネスモデルを構築することが求められています。気候変動や社会的不平等など、グローバルな課題は金融業界にとっても大きなリスク要因となります。これらのリスクを軽減し、長期的な安定性を確保するために、SDGsへの取り組みが重要視されています。
SDGsの目標には社会全体に対する課題などが設定されているので、SDGsへの取り組みをすることで将来的な企業のリスクを回避することにも繋がるでしょう。
持続可能な企業を目指せる
SDGsへの取り組みは持続可能な社会を実現するための目標が設定されていることから、SDGsへの取り組み自体が持続可能な企業を実現するためには重要です。すべての取り組みは実現することは困難ですが、現在取り組むことができる目標から取り組んでいくことで持続可能な企業を目指すことができるでしょう。
新たなビジネス機会の創出
SDGsへの取り組みは、金融機関にとって新たなビジネスチャンスをもたらします。持続可能なプロジェクトへの投資や、グリーンボンド、ソーシャルボンドといった持続可能性に特化した金融商品が注目されています。これらの分野は今後成長が見込まれており、金融機関にとって収益性の高い分野として期待されています。
例えば、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、持続可能なプロジェクトへの融資や投資を拡大し、グリーンボンドの発行を支援することで、持続可能な開発に貢献しています。
これらの目的を通じて、金融業界は持続可能な開発に積極的に貢献しながら、自社の成長と社会的責任のバランスを保つことが求められています。
金融業界のSDGsの事例
日本国内の金融業界では、SDGs(持続可能な開発目標)への取り組みが広がっており、各金融機関が積極的に社会的・環境的課題に対応するための戦略を打ち出しています。
金融業界のSDGsの事例について紹介していきます。
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)
■ 環境分野
・再エネ融資やグリーンボンドの引受・販売など、脱炭素社会に向けたファイナンスを推進。
・2030年度までにサステナブルファイナンス累計35兆円を目指す(当初20兆円目標を引き上げ)。
・「MUFG環境・社会ポリシーフレームワーク」を策定し、石炭火力発電への新規ファイナンスは原則禁止。
■ 社会分野
・スタートアップ支援、雇用創出、貧困改善に資する事業への融資を強化。
・「グリーン/ソーシャル/サステナビリティボンドフレームワーク」を導入し、教育・医療・コロナ対応等も資金使途に追加。
・日本の民間銀行初のソーシャルボンド発行(2019年)、コロナ対応のサステナビリティボンド発行(2020年)など実績あり。
■ 自社の環境対応
・2030年までに調達電力の100%再エネ化を目標。
・2019年に水力電源のみの電力契約を邦銀で初導入、丸の内本館ビルの電力を再エネに切り替え。
出典)https://www.saiyo.bk.mufg.jp/strategy/sdgs/
三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ
■水素ビジネスへの支援
三井住友銀行は、脱炭素社会の実現に向けて水素エネルギーに着目し、金融面からの支援を行っています。2020年には「水素バリューチェーン推進協議会」を設立し、2021年には世界初のグリーン水素プロジェクトへのファイナンスに邦銀で唯一参加しました。また、2023年には水素還元製鉄案件へのプロジェクトファイナンスにも参画しています。
◾️カーボンクレジットビジネスの推進
2005年から排出権ビジネスを展開し、日本政府の「二国間クレジット制度(JCM)」を活用した海外の省エネルギー・再生可能エネルギー事業を金融面から支援しています。2022年にはカーボンクレジット取引プラットフォーム「Carbonplace」に参画し、2023年にはJ-クレジットの売買・創出支援を行う企業と提携しました。
◾️グリーン設備導入
グリーンビルディングや再生可能エネルギー発電施設を信託財産とし、受託者であるSMBC信託銀行が借入人となって受益者の資金調達のために行う資産担保借入を行っています。
三井住友ファイナンス&リースの戦略子会社であるSMFLみらいパートナーズは、オンサイト型の太陽光発電エネルギーサービス(PPAモデル)を行っており、お客さまの建物屋根等に太陽光発電設備を設置し、発電したCO2フリー電力をお客さまに供給しています。
SMFLグループではこのほかにもオフサイト型の太陽光発電エネルギーサービスや、省エネ設備のリース、補助金コンサルティング、LEDレンタル等の脱炭素ソリューションを提供し、お客さまの温室効果ガス排出量削減に貢献しています。
出典)https://www.smfg.co.jp/sustainability/sdgs/
日本国内の金融業界は、SDGsの達成に向けて積極的に取り組んでおり、持続可能な社会の実現に向けた具体的な行動を起こしています。これらの取り組みは、金融機関が社会的責任を果たしつつ、ビジネスチャンスを広げる重要な役割を果たしています。
金融機関のSDGs融資について
SDGs融資とは?
SDGs融資とは、持続可能な開発目標に合致するプロジェクトや企業活動に対して、金融機関が資金を提供する融資形態のことです。この融資は、環境保護、社会的包摂、ガバナンスの改善など、SDGsの目標を達成するための取り組みに対して行われます。
SDGs融資の主な対象分野
環境分野:SDGsの「気候変動への対策」(目標13)や「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」(目標7)
再生可能エネルギー、エネルギー効率の向上、環境保護プロジェクトなど。
社会分野:SDGsの「質の高い教育をみんなに」(目標4)、「すべての人に健康と福祉を」(目標3)
教育、医療、住宅支援、貧困削減プログラムなど。
ガバナンス分野:SDGsの「働きがいも経済成長も」(目標8)、「平和と公正をすべての人に」(目標16)
コンプライアンスの強化や企業の透明性向上、労働条件の改善など。
SDGs融資の具体的な仕組み
SDGs融資は、通常の融資と異なり、特定の条件や目標達成に連動する形で提供されます。以下にその仕組みの例を示します。
グリーンボンド:環境保護や気候変動対策に資金を提供するための債券です。発行体は、グリーンボンドで調達した資金を環境に配慮したプロジェクトに限定して使用することが求められます。
例えば、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、グリーンボンドの発行を通じて再生可能エネルギープロジェクトやクリーンテクノロジーに対する融資を拡大しています。また、TCFDに基づく気候関連財務情報の開示を進め、環境リスクを管理しつつ持続可能な投資を推進しています。
サステナブルローン:融資先が特定のSDGs目標に向けた成果を達成した場合、金利が減少するなどのインセンティブが設けられます。例えば、再生可能エネルギーの導入や二酸化炭素排出量の削減が達成された場合に、金利が引き下げられることがあります。
ソーシャルボンド:社会的インパクトのあるプロジェクトに対して資金を提供するための債券です。例えば、低所得者向けの住宅提供や医療サービスの拡充に資金が使用されます。
例えば、三井住友フィナンシャルグループ(SMBC)は、ソーシャルボンドを発行し、教育や医療、福祉プロジェクトへの資金提供を行っています。
SDGs融資の課題
SDGs融資は、社会的価値の創出とともに、投資リスクの低減を図ることができる一方で、評価基準の統一やプロジェクトの持続可能性の確認など、いくつかの課題も存在します。主な課題を見ていきましょう。
評価基準の統一
SDGsは17の目標・169のターゲットと広範囲にわたり、融資先の活動がSDGsのどれに該当するかの評価が曖昧になりがちです。CO₂削減などの環境面は定量化しやすい一方で、社会分野(貧困対策、雇用、教育)などは成果が見えにくく、効果測定が困難です。「SDGsに取り組んでいる」とうたっていても、どこまで効果があるのか不明確な場合があります。
グリーンウォッシュへの懸念
実質的な貢献がない、または非常に小さいにもかかわらず、「SDGsに取り組んでいる」と称する企業が存在し、投資家・金融機関の信頼を損なう可能性があります。また、融資側にも「SDGsっぽい案件だから支援する」といった、形骸化した判断が入り込むリスクがあります。
利回りと社会的意義のバランス
融資である以上、返済能力や収益性の担保は不可欠ですが、社会課題に取り組む事業は必ずしも収益性が高いとは限らないため、金融機関がリスクをとりづらいという面があります。「社会貢献はしたいが、金融機関としては収益も必要」というジレンマが生じる可能性があります。
法的および規制上の課題
SDGs融資は、国際的な枠組みや国内法規制に対応する必要がありますが、各国の法的環境が異なるため、国境を越えた融資や投資において法的な複雑さが増しています。SDGs融資やサステナブルファイナンスに関して、国際的に統一された認証・格付け基準はまだ途上です。これにより、実際に資金を供給する際に多くの手続きや調整が必要となることがあります。
これらの課題を克服しつつ、金融業界が持続可能な開発に貢献するためには、さらに透明性の高い情報開示と効果的なリスク管理が求められます。
SDGsと金融業界の未来とは?
SDGs(持続可能な開発目標)は、国連が掲げる2030年までに達成すべき17の目標であり、環境、社会、経済の3つの側面から持続可能な世界を実現することを目指しています。金融業界は、資金の流れを通じてこれらの目標達成に大きな影響を与える立場にあり、その役割は今後ますます重要になっていくと考えられています。
資金の流れの変革
SDGsを達成するためには、環境に配慮し、社会的責任を果たす企業やプロジェクトに資金を提供することが必要です。金融業界がSDGsに基づいた融資や投資を推進することで、持続可能なプロジェクトへの資金流入が増加し、資金の流れが大きく変わることが期待されています。
新しい金融商品の創出
SDGsに向けた取り組みは、グリーンボンドやソーシャルボンド、サステナブルファイナンスといった新たな金融商品やサービスの開発を促進します。これらの新しい商品は、社会的課題を解決しつつ、投資家にとって魅力的なリターンを提供するものとなります。
リスク管理の進化
SDGsに取り組むことで、金融業界は新たなリスク管理手法を開発し、適用する必要があります。例えば、気候変動による物理的リスクや低炭素経済への移行リスクを評価し、投資や融資の決定に反映させることが求められます。これにより、長期的に安定した収益を確保しつつ、社会全体のリスクを軽減することが可能となります。
金融業界は、SDGsの達成において中心的な役割を果たすと同時に、新しいビジネスチャンスを創出し、社会全体のリスク管理を進化させることが期待されています。規制の整備、技術の活用、消費者意識の向上といった要素が組み合わさることで、金融業界は持続可能な未来に向けた重要な推進力となるでしょう。
まとめ
金融業界ではSDGsに対する取り組みが積極的におこなわれているので、それに伴ってSDGs融資も活発的にしている金融機関が増えてきています。現在でもSDGsの認知度は高まってきており、SDGsに取り組んでいる企業も増加傾向にあることから将来的にはSDGsに取り組んでおくことでビジネスチャンスに繋がるともいえるでしょう。
持続可能な企業を目指すためにもSDGsに対する理解と取り組みはこれからの企業経営においては非常に重要です。取り組み自体はすべておこなうのは難しいので、できる目標から取り組むようにしましょう。
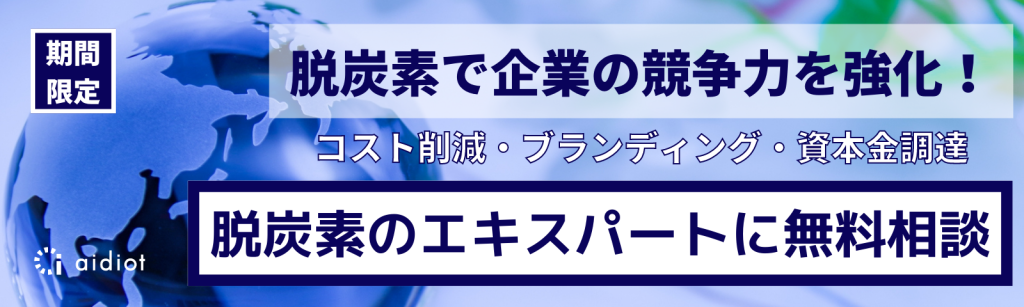
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。