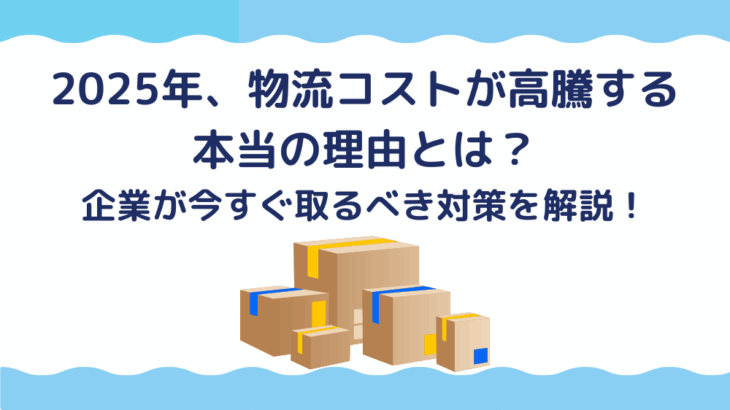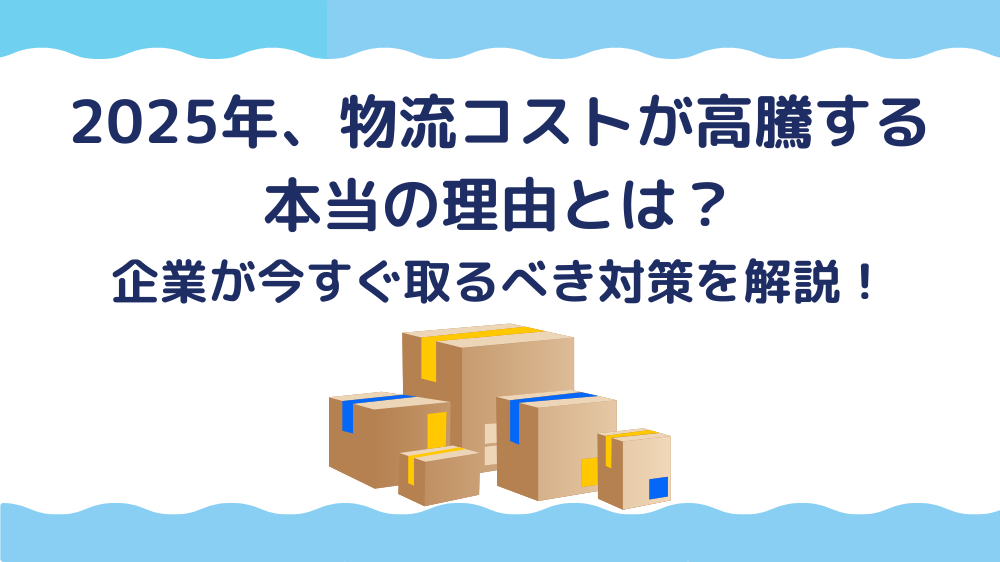
働き方改革関連法によるトラックドライバーの時間外労働の上限規制(年960時間)「2024年問題」をきっかけに、物流の現場ではコスト上昇の兆しが表れています。
2025年にかけては、運賃の高騰、人手不足によるリードタイムの長期化、さらには外注先の確保難など、企業にとって避けられない課題が一層深刻化していく見通しです。
本記事では、物流コストが今後さらに上昇すると言われる背景を整理しながら、現実に何が起きているのかをわかりやすく解説します。また、コストのコントロールと物流品質を両立させるために、企業が今すぐ着手すべき対策についても具体的にご紹介します。
【物流危機】2025年に物流コストが急上昇する背景とは
2024年問題を境に、物流業界の構造が大きく揺らぎ始めています。
時間外労働の制限、人手不足、物価高騰といった複数の要因が重なり、企業にとって「これまで通りの物流」が立ち行かなくなってきました。特に2025年以降は、コスト上昇が避けられないフェーズに突入すると見られており、今のうちから準備しておくことが求められます。
2024年問題が本格化:ドライバーの時間外労働規制の影響
2024年4月から適用された働き方改革関連法によって、トラックドライバーの時間外労働に上限規制(年960時間)が設けられたことにより、従来よりも長距離・多頻度の配送が難しくなり、輸送力の確保が課題となっています。
結果として、1件あたりの運賃は上昇傾向にあり、従来と同じ量を運ぶために複数便への分散や中継拠点の設置など、追加コストが発生するケースが増えています。
燃料費・人件費・倉庫費の高騰
原油価格の変動に加え、人件費や倉庫賃料の上昇も物流コストを押し上げる要因となっています。とくに都市部では倉庫スペースの確保が難しく、賃料が高騰しているほか、ドライバーや庫内作業員の確保にもコストがかかるようになっています。
この流れは一過性のものではなく、長期的なコスト構造の変化として捉える必要があります。
再配達・ラストワンマイル問題の深刻化
EC市場の拡大にともない、個別配送が増加する中で、再配達率の高さや非効率な配送ルートが課題になっています。特に都市部のラストワンマイル配送では、人手に頼らざるを得ないケースが多く、効率化が進まない領域としてコスト圧迫の要因となっています。
宅配ボックスや置き配の促進だけでは抜本的な解決には至らず、配送設計の見直しや自動化の検討が求められています。
少子高齢化による労働力不足と人件費上昇
物流業界に限らず、少子高齢化による人材確保難は深刻です。若手の入職率は低く、ベテラン層の退職も加速しており、人材確保にはより高い賃金や待遇改善が必要となっています。
この結果、人件費の上昇が避けられず、間接的に運賃や倉庫費用、業務委託料など、あらゆるコストに波及しているのが現状です。
物流コスト増加がもたらす企業への影響
物流コストの上昇は、単に「運賃が高くなる」という問題にとどまりません。調達から販売まで、企業活動のあらゆる場面に波及し、場合によっては事業そのものの競争力を左右するリスクにもなります。
ここでは、物流コストの増加が企業にどのような影響を与えるのか、3つの視点から整理します。
商品価格への転嫁と顧客離れのリスク
輸送費や保管費などの物流コストが上がれば、最終的にその負担は商品価格に反映されることになります。
しかし、価格競争が激しい市場では、簡単に値上げできないケースも多く、企業側が利幅を削って吸収する状況が続いています。
価格転嫁に踏み切った場合も、顧客離れや競合への乗り換えリスクが生じ、売上減につながる可能性があるため、判断は非常に慎重を要します。
リードタイムの遅延と業務効率の低下
ドライバー不足や運行制限によって配送リードタイムが延びると、生産・販売・顧客対応など、社内外のあらゆる業務に影響が出ます。
とくに、Just in Timeで動いている製造業や、納期が厳しいBtoB取引では、物流の乱れがそのままビジネス全体の信用問題にも直結します。
業務の効率を保つためには、出荷・納品の再設計や在庫の持ち方を見直すなど、従来のオペレーションを抜本的に変える必要も出てきます。
サプライチェーン全体への影響
物流は単体の機能ではなく、調達・生産・販売のすべてをつなぐ存在です。
この流れが滞ると、欠品や納期遅延、過剰在庫などが連鎖的に発生し、全体のコストや業務負荷が膨らんでいきます。
また、サプライチェーン全体の見通しが悪化することで、取引先や顧客との信頼関係にも影響を与えるおそれがあります。物流を「コスト」ではなく「競争力」として捉える発想が、いま企業に求められています。
今、企業がとるべき5つの回避策
物流コストの上昇やドライバー不足といった課題は、一時的なものではなく、今後も続く構造的な問題です。待ちの姿勢ではなく、物流の「設計そのもの」を見直すことが、安定供給とコストコントロールの両立につながります。
ここでは、企業が今すぐ実践できる5つの対策について整理します。
1. 配送の共同化・混載便の活用
同一エリアへの出荷や、配送先が重なる他社と協業し、トラックをシェアする取り組みが広がっています。共同配送や混載便の活用により、積載率の向上と車両数の削減が可能となり、結果として輸送コストの抑制や環境負荷の軽減にもつながります。
特に都市部やラストワンマイルの領域では、個社単位での配送効率に限界があり、柔軟な発想が求められます。
▼あわせて読みたい!
2. 物流拠点の見直し・再配置
拠点の立地が需要地や供給元と合っていない場合、無駄な輸送距離や中継回数が発生し、コスト増の要因になります。
再配置の検討によってリードタイムの短縮や在庫の分散が可能になり、結果的に配送計画の柔軟性も高まります。
現状の物量データや出荷頻度をもとに、拠点戦略そのものを再設計する企業が増えています。
▼あわせて読みたい!
3. 配車・ルート最適化AIの導入
配車担当者の経験に頼った運行計画は、人的リソースに依存するうえに最適化の余地も限られます。AIや最適化ソフトを活用することで、複数の条件を瞬時に計算し、効率の良いルートや配車パターンを提案することが可能になります。
実運用での試行を通じて、燃料費・人件費の削減だけでなく、ドライバーの拘束時間短縮にもつながっています。
▼あわせて読みたい!
4. 3PL・外部委託の活用と見直し
すべての物流業務を自社内で抱えるのではなく、外部パートナーを戦略的に活用することで、業務の安定性と柔軟性を確保することができます。
ただし、委託の見直しは「丸投げ」にしないことが重要です。サービス品質やKPIを共有し、定例の振り返りや改善提案を受けながら、パートナーとしての関係を築くことがポイントです。
5. 在庫戦略の転換
調達リードタイムが長くなったり、配送リスクが高まったりする中で、在庫をどう持つかが経営に直結するテーマになっています。
過去の出荷実績や販促計画をもとに需要を予測し、拠点ごとの適正在庫を維持することで、欠品リスクを抑えながら無駄な在庫も防ぐことが可能です。
WMSや需要予測ツールの活用により、属人的な判断に頼らない在庫設計が進んでいます。
今後の展望と企業が備えるべき戦略
物流業界を取り巻く環境は今、抜本的な変革を迫られています。ドライバー不足や2024年問題による制約に加え、コスト高騰、自然災害や感染症といった予測困難なリスクにも備えなければなりません。こうした中で、企業がこれからの数年を見据えて取り組むべきは、「変化に強い物流体制づくり」です。
ここでは、その軸となる2つの戦略的視点を紹介します。
物流DX・省人化への投資が生き残りの鍵
物流の現場では、これまで人手に依存してきた多くの業務が限界を迎えています。今後、持続的に事業を継続するには、自動化・省人化を前提とした設計へのシフトが不可欠です。
たとえば、倉庫内の自動搬送やスマートピッキング、TMS(輸配送管理)やWMS(倉庫管理)を連携させた可視化・最適化の仕組みなど、テクノロジーを活用した「物流DX」の導入が加速しています。これらは単なるコスト削減策ではなく、限られた人材でも安定した物流を維持するための投資です。
省人化は、倉庫でのAGV(無人搬送車)の導入やピッキング業務の自動化が行われています。ゼロタッチ物流(人の手を介さずに物流業務を完結させる仕組み)とも親和性が高く、段階的な導入で着実に効果を上げている企業も増えています。
BCP視点での拠点分散・リスク分散の重要性
自然災害やパンデミックなどの突発的な事態に直面した際、物流拠点や輸配送ネットワークの「柔軟性」が事業継続に大きく影響します。特定の地域や機能に依存しすぎていると、1拠点の停止がサプライチェーン全体を止めるリスクになりかねません。
そのため、複数拠点でのバックアップ体制を整えたり、異なる輸送手段・ルートを持っておくといった「リスク分散型の設計」が、BCP(事業継続計画)の観点からも注目されています。
拠点の再配置に際しては、ただ分散するだけでなく、在庫配置や需要地との距離、輸送コストなどを総合的に判断する必要があります。
▼あわせて読みたい!
まとめ
本記事では、2025年にかけて物流コストが高騰すると言われる背景を整理し、企業が今すぐ取るべき対策について解説しました。ドライバーの労働規制強化や人件費・燃料費の上昇、ラストワンマイルの非効率といった複合的な要因により、物流を取り巻く環境は確実に変化しています。こうした中で企業に求められるのは、短期的なコスト削減ではなく、構造的な見直しです。拠点戦略の再設計や、テクノロジーの導入による業務の最適化など、できることから一つずつ取り組むことが、安定した事業継続への第一歩となります。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。