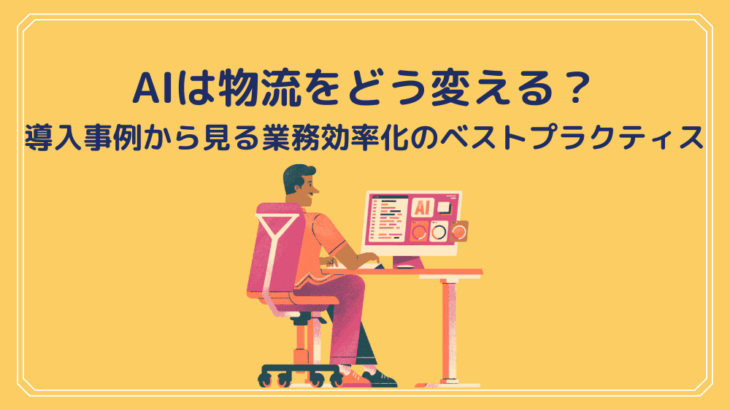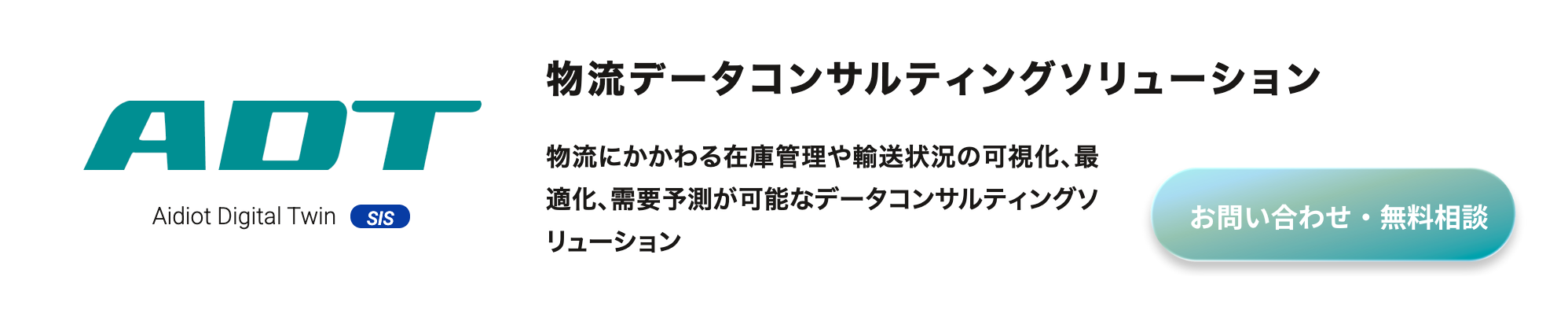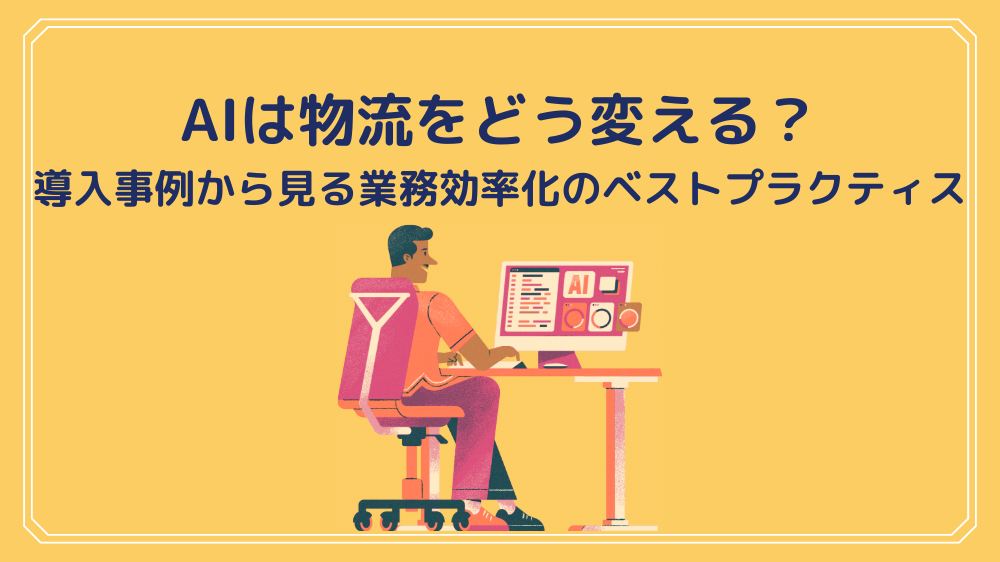
人手不足・配送遅延・コスト高騰──。深刻化する物流課題に、AIが革新をもたらし始めています。
倉庫内の自動化、配送ルートの最適化、伝票処理の省力化など、物流現場ではすでにAIの実用化が進み、業務効率と精度の両立が実現しつつあります。この記事では、日本企業の最新導入事例をもとに、物流におけるAI活用の具体的な効果と、実務レベルでの成功要因=“ベストプラクティス”を詳しく解説します。自社の物流改革を考える企業にとって、実践的なヒントが満載の内容です。
物流業界で進むAI導入の背景と注目の理由
かつて「経験と勘」がものを言った物流の現場に、今、大きな変化の波が押し寄せています。人手不足、需要の多様化、そして「2024年問題」こうした業界を取り巻く構造的な課題に対して、多くの企業が解決策のひとつとしてAI技術に注目しています。
▼あわせて読みたい!
背景にあるのは、慢性的な人手不足と働き方改革
物流ドライバーや倉庫作業員の高齢化が進み、若年層の担い手が減っている現在。とくにトラック業界では、労働時間の上限規制(2024年問題)によって、一人のドライバーが運べる荷物量にも限界が生じています。この課題に対してAIを活用して業務を効率化し、限られた人員でも現場を回せる体制づくりが求められているのです。
注目される理由①:業務の「見える化」と最適化
AIを活用することで、物流の各工程におけるデータが蓄積・可視化され、たとえば配送ルートの最適化や倉庫内の動線改善といった判断がスムーズに行えるようになります。勘と経験に頼っていた判断が、データドリブンに変わることで、属人化の解消にもつながります。
注目される理由②:リアルタイムの意思決定が可能に
需要予測や在庫管理にAIを活用することで、天候や交通状況、注文量の急変といった「今起きていること」に即応できる柔軟な運用も実現します。結果として、欠品や過剰在庫のリスクを抑えつつ、サービス品質の向上にも貢献します。
物流におけるAI活用の主な領域と機能
「AIを導入すれば物流が変わる」と言われても、実際にどの業務でどう活用されるのかが分からなければ、現場では動けません。ここでは、物流業務の中でも特に注目されている5つの領域について、それぞれの役割と導入効果を整理します。
① 配車・ルート最適化|ドライバー不足と燃料コストに対応
AIが複数の配送条件をもとに、最も効率的なルートと車両の割り当てを自動で計算します。従来はベテラン担当者の勘と経験に頼っていた配車業務も、スピーディかつ安定的に対応できます。その結果、ドライバーの拘束時間短縮や空車率の低下が期待でき、燃料費削減にもつながります。
▼あわせて読みたい!
② 倉庫内業務の自動化|ピッキング・棚卸・仕分けでのAI活用
倉庫では、作業員の移動ルートやピッキング手順をAIが最適化します。ロボットとの連携や画像認識技術により、棚卸や仕分けも自動で処理できるようになり作業効率だけでなく、ヒューマンエラーの削減や繁忙期の生産性維持にも有効です。
③ 需要予測と在庫最適化|過不足在庫と欠品リスクを回避
過去の販売データや季節要因、天候などをもとに、AIが需要を高精度で予測します。仕入れや出荷のタイミングを最適化することで、在庫の持ちすぎや欠品のリスクを回避でき、無駄な保管コストや販売機会の損失も抑えられます。
④ シフト・人員最適化|AIで現場配置の効率化
倉庫や配送センターでの人員配置も、AIが最適化をサポートします。受注量や繁閑に応じたシフト案を自動で提示することで、現場管理者の負担軽減と人件費の適正化を両立します。特に人手不足に悩む中小企業では、導入効果が出やすい分野です。
⑤ 生成AIによる業務支援|マニュアル・日報作成の省力化
最近では、文章生成型AIの活用も進んでいます。作業マニュアルの下書きや業務報告書(日報)の自動作成、問い合わせ対応のたたき台作成など、「なんとなく手間がかかっていた事務作業」が効率化されます。現場のちょっと面倒を減らす役割として重宝されています。
物流業界におけるAI導入の成功事例
株式会社ファミリーマート
株式会社ファミリーマートは2030年までに2017年度対比30%のCO2排出量削減を目標に掲げ、物流配送におけるCO2削減を積極的に推進しています。
AIを活用した配送シミュレータによる配送コースの設定やクリーンディーゼル車両やFC(燃料電池)小型トラック、RD(リニューアブルディーゼル)を使用した環境配慮型配送車両の導入など多岐にわたる取り組みの推進により、2024年度の物流配送において排出されるCO2は、2017年度対比で12.8%削減となりました。
出典)
https://www.family.co.jp/company/news_releases/2025/20250605_01.html
GROUND株式会社・日本通運株式会社
GROUND株式会社は自律型協働ロボット(AMR)「PEER 100」をNIPPON EXPRESSホールディングス株式会社のグループ会社、日本通運株式会社に導入しました。「PEER」シリーズはSLAM技術を搭載しており、施設内の環境をリアルタイムで認識しながら最適なルートを選定し、自律走行します。また、Wi-Fi環境下で稼働し、タブレットやPCの専用インターフェースを通じて簡単に操作・管理も可能です。1回の充電で8~10時間の連続稼働ができる事も特徴です。
今回導入された「PEER 100」3台は、物流施設内のピッキング作業や工程間搬送を支援するAMRです。本プロジェクトでは、広い施設において、ステーションから出荷場所までの無人搬送を行うことで、スタッフの歩行距離を削減し、作業負担の軽減に貢献します。また、「PEER 100」を含むさまざまなソリューションを組み合わせることで、歩行が困難な方も施設内作業を行える環境を実現しました。
出典)
https://www.groundinc.co.jp/newsroom/pressrelease/20250325
アスクル株式会社
アスクル株式会社は、物流センターと補充倉庫間の商品輸送(横持ち)計画にAIを活用した需要予測モデルを導入し、全国の物流拠点で展開を開始しました。
このAI需要予測モデルは、物流センターとその近郊に位置する補充倉庫間での「いつ・どこからどこへ・何を・いくつ運ぶべきか」をAIが指示するものです。従来は担当者が経験や知見を基に手作業で計画を立てていましたが、AIの活用により予測精度が向上し、作業工数の削減にもつながりました。
導入により、ALP横浜センターにおいて商品横持ち指示の作成工数約75%減/日、入出荷作業約30%減/日、フォークリフト作業約15%減/日の実績を得ました。
出典)
サントリーロジスティクス株式会社と富士通株式会社の共同開発
物流業界初!サントリーロジスティクス株式会社と富士通株式会社と共同開発したフォークリフト操作のAI判定システムを導入しました。従来ヒトが眼で確認していたドライブレコーダー画像をAIが解析することにより、判定者毎の評価のバラツキを低減し、映像確認時間の大幅短縮に繋げています。またハンドル操作、指差呼称など、安全操作に必要な動作を可視化・評価することにより、乗務員の安全感度も上がり、事故の抑制に繋がっています。
出典)
https://www.suntorylogistics.co.jp/pdf/newsrelease202106.pdf
物流AI導入の課題と成功のポイント
物流業界におけるAI導入は、ドライバー不足やコスト増、業務の属人化といった課題に対する有効な打ち手として注目されています。しかし、導入がうまくいく企業もあれば、成果につながらないケースも少なくありません。
AIを活用した改革を確実に成果へとつなげるには、現場の実態と課題を正しく捉え、段階的かつ現実的に取り組むことが重要です。
ここでは、物流AI導入の際によく直面する課題と、それを乗り越えるための成功のポイントを紹介します。
1. データが揃っていない・整っていない
AI導入の出発点は「データ」ですが、現場での紙ベース管理や、システム間の分断により、十分な量と質のデータが揃っていない企業も多く見られます。
【成功のポイント】まずはWMSやTMSといった基幹システムの整備・連携を進め、入力ルールや形式を標準化することから始めましょう。
2. 現場とシステム部門の連携が取れていない
AIは現場業務を支援するツールである一方、導入・運用は情報システム部門や外部ベンダーの手に委ねられがちです。その結果、現場にフィットしない仕組みとなり、形骸化するリスクも。
【成功のポイント】AI導入は「現場巻き込み型」で進めるのが鉄則。現場の声を反映した要件設計や、実証実験(PoC)を通じたフィードバックサイクルが鍵を握ります。
3. 小さく始めて、大きく育てる
AI導入というと大掛かりな改革をイメージしがちですが、一気に全体最適を狙うと時間もコストもかさみ、途中で頓挫する例も少なくありません。
【成功のポイント】 まずは「特定拠点の配車最適化」「ピッキングのAI支援」など、効果が見えやすい単位でスモールスタートを切るのが賢明です。
4. 導入後の運用フェーズで止まる
AIを導入しても、活用が現場で定着しなければ意味がありません。入力や操作が煩雑だったり、成果が見えにくいと、利用率が下がる傾向にあります。
【成功のポイント】操作の簡便さ、活用教育、社内マニュアル、サポート体制など、「使われる仕組みづくり」にも注力しましょう。
5. ROI(投資対効果)が不明確
AIは決して安い投資ではないため、「コスト削減にどのくらい寄与するか」が事前に見えにくいと、社内説得も進みません。
【成功のポイント】導入前に現状の業務工数・コストを見える化し、試験導入による効果を数値で可視化する「実証→評価→拡張」のサイクルが必要です。
今後の物流AI活用の展望と企業の取るべきアクション
AIの導入は一部の先進企業だけの話、そんな時代はもう終わりつつあります。配送ルートの最適化、倉庫内作業の効率化、需要予測の精度向上など、物流業務とAIの親和性は非常に高く、2025年以降の業界では、AI活用の有無が競争力の差を左右すると言っても過言ではありません。これから物流企業が押さえるべきAI活用の展望と、特に中小企業に向けた現実的なアクションについて解説します。
2025年以降の物流業界に求められるAI戦略
少子高齢化と人手不足、そして「2024年問題」に象徴される労働規制強化の波は、今後も物流業界に大きな影響を与え続けます。こうした背景から、省人化と効率化の両立が不可欠なテーマとなっており、AIはその中心に位置づけられています。
2025年以降は、単なるコストカットや自動化ではなく、「判断」「最適化」「予測」に強みを持つAIの活用が求められます。配車計画の高度化、在庫の動的管理、さらには顧客需要の先読みなど、データをもとに現場の意思決定を支援するAIの存在感はますます大きくなるでしょう。
中小物流企業でも導入可能なAIツールとは?
「うちには予算も人材もないからAIは無理」そんな声もよく聞かれますが、近年は低コスト・ノーコードで始められるAIツールも続々登場しています。以下はその一例です。
画像解析AI(ピッキング支援など)
倉庫内の作業品質をAIで監視・支援するツール。カメラとソフトの組み合わせで導入しやすく、誤出荷防止やトレーニングにも効果的です。
チャットボット+生成AI
作業マニュアルや日報の作成支援に活用。文章作成の手間を軽減し、現場の負担を減らします。
これらは初期投資が少なく、部分的な導入から始められる点が特徴。外部の専門家やベンダーと連携すれば、専門知識がなくても運用は十分に可能です。
シュミレーターサービス(ADT)
「ADT」とはアイディオットデジタルツインのことで、物流に関わる在庫管理や配送などのデータをリアルタイムで可視化・分析するシミュレーターです。このツールは、数十種類のデータセットを集約し、物流業務の最適化と効率化を支援します。膨大なデータを用いて行うため、限りなく現実に近いシミュレーションをすることができます。
「ADT」では、可視化、シミュレーション、物理空間の実装が可能です。「ADT」を利用し、物流での自動化をシミュレーションし、車両情報の可視化や人員のシミュレーションなどにより、いきなり行う危険性を減らし、スムーズな物流自動化に踏み出すことができます。
お問い合わせはこちら
まとめ
本記事では、物流業界で進むAIの導入と、その具体的な活用領域や成功事例、導入時の課題、今後の展望までを幅広く解説しました。人手不足やコスト高騰といった課題に直面するなか、AIは単なる自動化ツールではなく、配車・倉庫・在庫・人員などあらゆる物流プロセスの「判断」や「最適化」に貢献する存在へと進化しています。今後、AIの活用が物流の効率と競争力の鍵を握ることは間違いありません。小さな一歩から導入を始めることが、変革への第一歩になります。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。