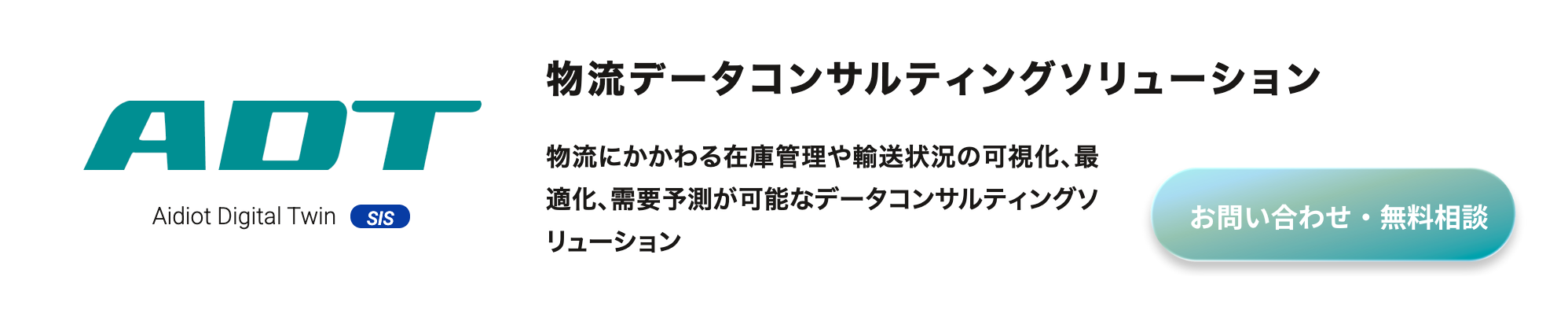物流拠点のあり方は、業務効率や顧客満足に直結する重要な戦略要素です。人手不足や配送コストの上昇、納期短縮のニーズが高まる中、従来の拠点配置や在庫の持ち方を見直す企業が増えています。
拠点の場所や数をどう設計するかはもちろん、在庫をどう分散させ、輸配送の流れをどう最適化するかが鍵となります。本記事では、エリア戦略・在庫分散・輸配送の視点から、物流拠点を選定・再編する際の考え方と実践のポイントをわかりやすく解説します。
なぜ今、物流拠点の再配置が注目されているのか?
企業の競争力を左右する物流戦略。その中でも、拠点の配置はコスト・納期・在庫回転率などに大きな影響を与える重要な要素です。
昨今の外部環境の変化により、これまでの物流ネットワークでは対応しきれない課題が表面化しており、拠点再配置の必要性が高まっています。以下では、具体的にどのような背景から再配置が求められているのかを整理します。
2024年問題・人手不足の影響
働き方改革関連法によるトラックドライバーの時間外労働の上限規制(年960時間)「2024年問題」によって、長距離輸送を中心に物流網の見直しが進んでいます。
とくに片道500kmを超えるような中長距離輸送では、1日での配送が難しくなり、分断やリレー輸送、中継拠点の設置といった対応が求められています。
加えて、慢性的な人手不足も依然として解消されておらず、少ないリソースで効率的に配送するための仕組みづくりが急務となっています。物流拠点の配置を見直すことは、労働力の有効活用と安定的な配送体制の構築につながります。
▼あわせて読みたい!
EC需要の増加と消費地近接ニーズ
EC市場の拡大により、消費者の求める配送スピードと利便性は年々高まっています。「翌日配送」「当日配送」への対応は、もはや選ばれるブランドの前提条件となりつつあります。
こうした背景のもと、従来の幹線輸送主体のモデルから、消費地に近い場所に在庫を持つ「ラストワンマイル対応型」の物流拠点が注目されています。小口多頻度化する配送に対応するには、拠点の細分化や中間拠点の強化が現実的な選択肢になります。
▼あわせて読みたい!
物流コストの高騰とその背景
燃料費の上昇、労務費の増加、運送会社からの運賃見直し要請など、物流コスト全体が上昇傾向にあります。とくに直近では、ドライバー不足による配車の難しさから、条件によっては従来よりも大幅に高い運賃を提示されるケースも見られます。
こうしたコスト上昇に対応するためには、拠点配置や在庫の持ち方を含めた物流全体の見直しが不可欠です。物理的な距離だけでなく、輸送ルートの組み立てや在庫補充のタイミングも含めて再設計することが、コスト抑制とサービス水準維持の両立につながります。
物流拠点設計・再配置の主な目的とは?
物流拠点の配置は、単なる「物の置き場所」を決める作業ではありません。リードタイム、コスト、在庫精度、そしてリスク対応力といった、企業活動全体に関わる重要な戦略項目です。
単に拠点数を増減するだけでなく、「どこに、何の目的で配置するか」を明確にすることが、物流機能全体のパフォーマンスを左右します。ここでは、物流拠点設計・再配置における主な目的を4つに整理し、それぞれの考え方を解説します。
リードタイムの短縮
顧客のニーズが高度化・即時化する中で、リードタイムの短縮は競争力の源泉となります。
特にECや小売業においては、翌日配送・当日配送が当たり前になりつつあり、これに応えるには配送拠点を消費地近くに設けることが不可欠です。
拠点を都市圏に分散配置することで、配送距離を短縮し、出荷から納品までのスピードを大幅に向上させることが可能になります。また、納品時間帯の指定にも柔軟に対応できるようになり、顧客満足の向上にもつながります。
輸送コストの最適化
長距離輸送に頼りすぎると、燃料費・人件費・高速道路料金など、さまざまなコストが積み上がっていきます。
物流拠点の配置を見直すことで、幹線輸送とエリア配送のバランスを調整し、より効率的な輸送ルートを組むことが可能になります。
たとえば、主要取引先の集中するエリアに中継拠点を設ければ、1回あたりの配送件数や積載率を向上させることができ、結果的にコストの最適化と業務の安定化が図れます。
BCP(事業継続計画)対応
BCP(事業継続計画)対応とは、自然災害や事故、感染症の流行、システム障害など、突発的な事態が発生した際でも、企業が事業をできるだけ止めず、あるいは速やかに復旧させるための準備や体制を整えることを指します。
災害や事故など、突発的なトラブルに備える意味でも、物流拠点の再配置は有効な手段です。
1拠点依存のリスクを回避し、複数拠点で分散管理することで、万が一の停止時にもバックアップ体制を構築できます。
BCP対応としては、代替輸送ルートの確保、複数の仕入れ・販売チャネルへの対応力強化なども併せて検討が必要です。物流機能の“冗長性”を持たせることは、企業全体のレジリエンス向上につながります。
在庫管理の最適化
物流拠点の設計は、在庫の持ち方にも大きく関係します。
エリアごとに適切な在庫量を分散して持つことで、欠品や過剰在庫のリスクを抑え、倉庫の稼働効率も高めることが可能です。
さらに、TMS(輸配送管理システム)やWMS(倉庫管理システム)との連携により、拠点間での在庫融通や、リアルタイムの在庫可視化を実現するケースも増えています。在庫管理と拠点戦略を一体で考えることが、今後ますます重要になっていくでしょう。
物流拠点を最適化するためのステップ
やみくもに拠点を増減したり、他社事例をそのまま参考にしてもうまく機能するとは限りません。自社の物流特性や事業の方向性に応じて、段階的に最適化を進めることが求められます。ここでは、物流拠点の最適化を進めるうえで基本となる4つのステップを紹介します。
1.現状分析:物流KPI・データの収集
最初に必要なのは、現状の把握です。
拠点ごとの在庫回転率、出荷件数、配送リードタイム、輸送距離、積載率などの物流KPIをもとに、自社の物流がどこでコストを生んでいるのか、どこにボトルネックがあるのかを明確にします。
過去のデータや出荷実績に加え、季節波動や顧客別の配送傾向なども加味しながら、全体像を把握することが重要です。この分析が、以降の意思決定の土台になります。
2.シミュレーション:拠点数・立地のパターン比較
現状の課題が整理できたら、次は将来を見据えたシミュレーションを行います。
拠点数を増やす、減らす、あるいは立地を変更するなど、複数のパターンを設計し、それぞれがコストやサービスレベルに与える影響を比較検討します。
配送リードタイムや幹線輸送の所要時間、保管スペースの確保、採用可能な人材層など、立地によって得られる効果と制約は大きく異なります。物流システムの導入有無や、TMS・WMSとの連携を前提にした運用設計も、この段階で検討します。
3.再配置・移転計画の策定
シミュレーション結果に基づき、最適な拠点構成を定めたら、次は具体的な再配置・移転計画の策定に入ります。
新設・移転・統廃合などの方針に加え、予算、スケジュール、人員配置、既存拠点との業務切替計画などを細かく整理します。
あわせて、既存の業務委託先や物流パートナーとの契約条件の見直しも必要になる場合があります。実行フェーズに移る前に、関係各所と合意形成を図ることが重要です。
4.運用・評価フェーズへの移行
拠点の再配置を実行した後も、計画通りに機能しているかを継続的に評価していくことが欠かせません。
KPIをもとに運用状況をモニタリングし、想定していた効果が得られているか、追加の改善が必要かを見極めていきます。
また、運用を通じて新たに見えてくる課題もあります。拠点戦略は一度決めて終わりではなく、事業環境や顧客ニーズの変化に応じて見直し続ける“動的な設計”であることを前提に取り組むことが重要です。
拠点設計に使える最新テクノロジーとは?
物流拠点の見直しや再配置は、従来であれば経験や勘に頼る場面も少なくありませんでした。
しかし現在では、シミュレーション精度の向上や情報連携の高度化を支える最新テクノロジーの登場により、より根拠のある拠点設計が可能になっています。
ここでは、拠点戦略の精度とスピードを高めるうえで有効な3つの技術をご紹介します。
物流デジタルツイン
物流デジタルツインとは、現実の物流ネットワークを仮想空間上に再現し、拠点配置や輸配送ルート、倉庫内オペレーションなどをリアルに可視化・検証できる技術です。
たとえば「関東と関西にもう1拠点ずつ追加した場合、コストと納期はどう変化するのか」「繁忙期の物量を今の体制でさばけるか」といったシナリオを、現実に近い形で事前に確認できます。
現場への影響を最小限に抑えながら、複数パターンの仮説検証ができるため、拠点設計の意思決定を大きくサポートしてくれます。
アイディオットでは「ADT」という物流デジタルツインを提供しています。「ADT」とはアイディオットデジタルツインのことで、物流に関わる在庫管理や配送などのデータをリアルタイムで可視化・分析するシミュレーターです。このツールは、数十種類のデータセットを集約し、物流業務の最適化と効率化を支援します。膨大なデータを用いて行うため、限りなく現実に近いシミュレーションをすることができます。
「ADT」では、可視化、シミュレーション、物理空間の実装が可能です。「ADT」を利用し、物流での自動化をシミュレーションし、車両情報の可視化や人員のシミュレーションなどにより、いきなり行う危険性を減らし、スムーズな物流自動化に踏み出すことができます。
TMS/WMSとの連携
拠点設計は単体で完結するものではなく、輸配送や倉庫業務との整合性があってこそ実効性を持ちます。
TMS(輸配送管理システム)やWMS(倉庫管理システム)と連携させることで、リアルタイムの物量データや車両の稼働状況、庫内作業の処理能力を踏まえた現実的な設計が可能になります。
たとえば、出荷頻度の高い商品(品番やアイテム単位)の分布状況や、拠点間の在庫移動回数をTMSで分析することで、適切な拠点間連携や在庫配置の設計につながります。
物流業務全体をひとつのフローとして捉える視点が、テクノロジー活用のカギとなります。
需要予測AIによる在庫配置最適化
エリアごとの需要変動に対応するには、精度の高い予測に基づいた在庫配置が欠かせません。
近年は、過去の販売データやキャンペーン、天候、商圏特性など複数の要素をもとに、AIが需要を予測する技術が実用段階に入っています。
この需要予測に基づき、どの拠点にどの程度の在庫を置くべきかを最適化することで、欠品リスクの低減と在庫コストのバランスをとることが可能になります。
特に品目数が多く、リードタイムの短縮が求められる業態においては、こうしたツールの導入が戦略面でも大きな武器になります。
拠点再配置のタイミングでやるべきこと
物流拠点の再配置、成功のカギを握るのは、初期段階での情報整理とシミュレーション、そして投資対効果の冷静な見極めです。ここでは、拠点再配置を検討する際に、企業として押さえておくべき基本的な4つのステップを解説します。
商圏分析/配送分析/在庫分析の3点セット
拠点の移転や新設を検討する際は、まず現状を多角的に把握することが不可欠です。
「どのエリアに顧客が集中しているか(商圏分析)」「どこから出荷・配送しているか、何に時間やコストがかかっているか(配送分析)」「在庫の動きと保管効率にムダはないか(在庫分析)」といった3点を軸に、課題と改善余地を可視化していきます。
これらの分析をもとに、拠点設計の方向性と優先順位を整理することが、的確な判断につながります。
配置パターンのシミュレーション
分析結果を踏まえて、次に行うべきは複数パターンによる配置のシミュレーションです。
「拠点を1つ減らすとどうなるか」「東西に1拠点ずつ追加した場合の効果は?」「一極集中と分散のどちらが適しているか」など、異なる構成案を比較することで、最も効果的な配置を見つけやすくなります。
納品リードタイムや積載率、作業負荷、庫内滞留などの変化も合わせて検討しながら、全体最適を意識した判断が求められます。
移転コスト・ROI(投資対効果)の試算
拠点の移転には、施設費用、什器やシステムの再構築、教育・引越しに関するコストなど、さまざまな費用が発生します。
これに対して、拠点配置の変更によって得られる効果(配送距離短縮、在庫回転率改善、人件費の最適化など)を定量的に見積もることで、ROI(投資対効果)の試算が可能になります。
短期的な支出に目を奪われず、3年後、5年後といった中長期視点で採算がとれるかを検討することが、判断の精度を高めるポイントです。
拠点変更に伴うKPIの再設計
拠点が変われば、現場の運用や評価指標も見直す必要があります。
たとえば、「出荷リードタイム」「庫内作業の生産性」「在庫日数」「トラック稼働率」など、現場で日々確認すべきKPIは、配置変更後の運用に即した内容へと再設計することが大切です。
KPIの見直しは、業務の再スタートを明確にし、関係者の意識をそろえるうえでも効果があります。拠点再配置を単なる「場所の移動」で終わらせないためにも、運用面での定義づけが欠かせません。
物流拠点再配置で競争力を高めるポイントまとめ
物流拠点の再配置は、単に倉庫やセンターを移転・増設するという話にとどまりません。市場の変化や顧客ニーズ、社内の事業構造に合わせて物流体制を見直すことは、企業全体の競争力に直結する重要な取り組みです。
ここでは、拠点の見直しを通じて業務効率の向上やコスト最適化を実現するために、特に押さえておきたい5つの視点を整理しています。
市場・顧客ニーズに近い場所への配置
納品リードタイムや柔軟な配送対応が求められる今、拠点の立地は顧客との距離を意識して選定することが重要です。
消費地や主要な取引先エリアの近くに拠点を構えることで、配送のスピード・精度が向上し、サービスレベル全体が高まります。
特にECや日配品の取り扱いが多い業種では、都市圏におけるラストワンマイル対応力が、顧客満足に直結します。
在庫の分散と集約のバランス最適化
在庫を分散させればリードタイムは短縮されますが、在庫量が増えすぎると管理コストが膨らみます。一方、在庫を一極集中させると効率は上がるものの、配送面での柔軟性が失われるリスクがあります。
重要なのは、商流・物量・出荷頻度に応じて、分散と集約のバランスを見極めることです。在庫の持ち方を再設計することは、拠点配置と密接に関係しており、両者を一体で考える必要があります。
輸配送コストの削減
物流拠点の再配置は、輸配送コストの削減にも直結します。
輸送距離や配送ルートを見直すことで、燃料費や高速代、人件費の最適化が図れます。また、積載率の向上や幹線輸送とエリア配送の役割分担を明確にすることでも、コスト効率が大きく改善されます。
特に近年は、運賃上昇が企業の収益を圧迫する要因となっており、輸配送設計の見直しは避けて通れない課題です。
物流DXとの連携
物流拠点の最適化は、デジタル技術との連携によってさらに高い効果を発揮します。
TMS(輸配送管理システム)、WMS(倉庫管理システム)、需要予測AIなどのツールを活用することで、現場の実態を把握し、データに基づいた判断が可能になります。
また、拠点の再配置を機に業務フローやオペレーションを見直すことで、DXの導入効果を最大限に高めることができます。
BCP(事業継続計画)への対応
災害や障害発生時に業務を止めないためには、物流機能の分散とバックアップ体制の構築が不可欠です。
拠点が1か所に集中していると、万一の事態で出荷が完全に止まるリスクがあります。複数拠点による相互補完体制を整えることで、安定供給体制の構築と企業の信頼確保につながります。
BCP対応はコスト要因ではなく、取引先との関係維持・ブランド価値の維持という観点でも、重要な要素となっています。
データから未来を予測するサービス「ADT」で物流自動化を実現!
「ADT」とはアイディオットデジタルツインのことで、物流に関わる在庫管理や配送などのデータをリアルタイムで可視化・分析するシミュレーターです。このツールは、数十種類のデータセットを集約し、物流業務の最適化と効率化を支援します。膨大なデータを用いて行うため、限りなく現実に近いシミュレーションをすることができます。
「ADT」では、可視化、シミュレーション、物理空間の実装が可能です。「ADT」を利用し、物流での自動化をシミュレーションし、車両情報の可視化や人員のシミュレーションなどにより、いきなり行う危険性を減らし、スムーズな物流自動化に踏み出すことができます。
お問い合わせはこちら
まとめ
本記事では、物流拠点の再配置に注目が集まる背景と、エリア戦略・在庫分散・輸配送設計を見直す際のポイントについて解説しました。顧客ニーズの多様化や人手不足、物流コストの上昇といった環境の変化に対応するためには、現状の体制を前提とせず、拠点の役割や配置をゼロベースで考える視点が重要です。市場との距離、在庫の持ち方、コストとのバランス、そしてBCP対応までを含めて戦略的に設計することで、物流は企業の競争力を高める力になります。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。