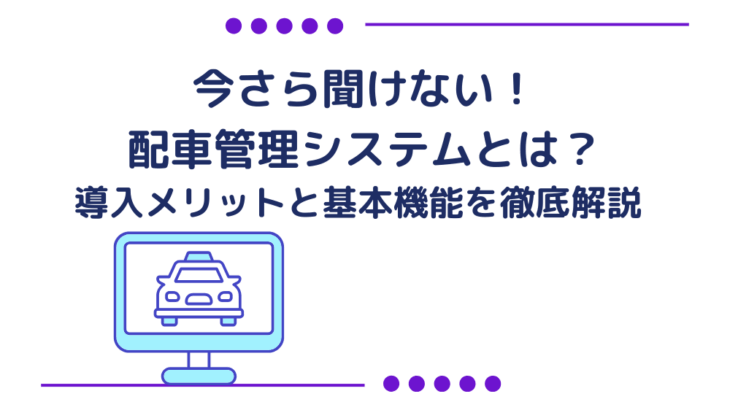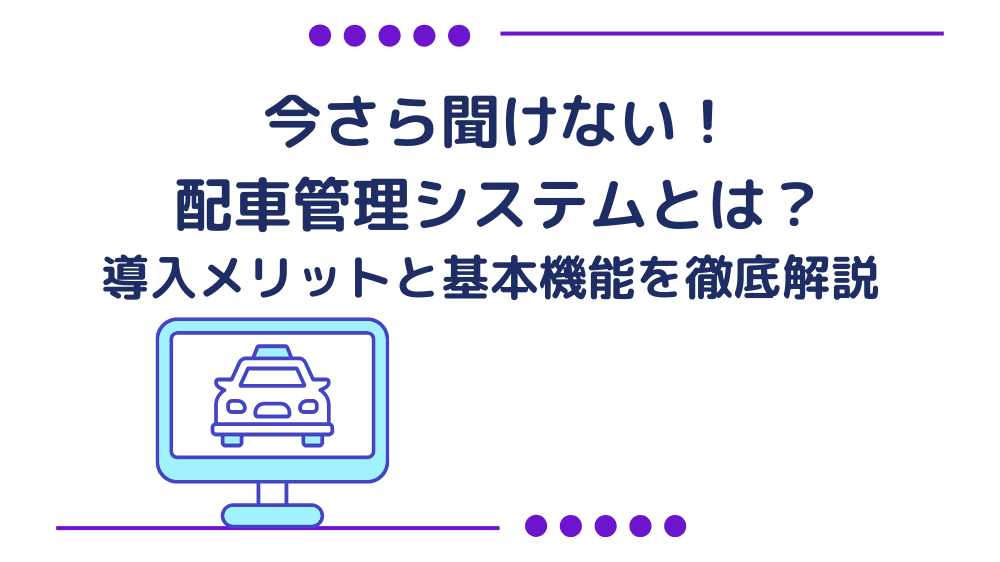
ドライバー不足や2024年問題への対応が急がれる中、物流現場の効率化を支える手段として「配車管理システム」への注目が高まっています。従来は担当者の経験や勘に頼っていた配車業務も、今やデジタル化によって最適化が可能な時代に入りました。
本記事では、配車管理システムの基本的な仕組みから、導入による業務効率・コスト削減・人手不足対策といったメリット、そして実際にどんな機能が使えるのかまで、現場視点でわかりやすく解説します。
配車管理システムとは?
配車管理システムは、トラックやドライバーの配車や運行計画を効率よく組むためのITツールです。出荷情報、車両の空き状況、ドライバーの勤務時間、配送先の場所や時間指定など、複雑な条件をもとに最適な配車プランを自動で作成できます。
従来のように紙や電話、表計算ソフトで調整していた配車業務をデジタル化することで、作業時間の短縮やミスの防止、属人化の解消につながります。また、リアルタイムの位置情報や運行状況を把握できる機能もあり、急な変更にも柔軟に対応できます。特に人手不足や2024年問題を見据え、効率的かつ持続可能な運行管理が求められる今、導入の必要性が高まっているシステムです。
なぜ今、配車業務のデジタル化が必要なのか?背景と業界課題
近年、物流業界では「デジタル化」が急速に注目されています。背景には、業界全体が抱える慢性的な課題に加え、2024年問題や人手不足などの構造的変化があります。ここでは、配車業務のデジタル化がなぜ今求められているのか、その理由を整理してご紹介します。
担い手不足と属人化の限界
ベテラン配車担当者の経験と勘に依存した業務が多く、属人化が進んでいる現場では、担当者の不在がそのまま業務停止につながるリスクがあります。人材の高齢化や後継者不足も深刻で、再現性のある“仕組み”への転換が求められています。
2024年問題による配車の難易度上昇
トラックドライバーの時間外労働に上限規制(年960時間)が設けられることで、今まで通っていたルートや運行スケジュールが組めなくなる場面も増えます。より複雑な条件をもとに配車するには、従来の手作業では対応が難しく、デジタルによる効率的な判断が不可欠です。
▼あわせて読みたい!
業務負荷の増大とヒューマンエラー
毎日の案件変動に対応しながら、車両・人員・積載条件など多くの要素を手計算で調整する作業は、非常に煩雑でミスも起こりやすいのが現実です。デジタル化によって負荷の軽減と精度向上が期待できます。
配車管理システムでできること
配車管理システムは、単なる運行スケジュールの作成ツールではありません。ドライバーや車両の稼働状況、荷物情報、交通条件など、さまざまな要素を踏まえて、日々の配車業務をより効率的に、かつ柔軟に運用するための仕組みです。
ここでは、配車管理システムを導入すると具体的に何ができるのか、その主な機能をご紹介します。
最適な配車計画の自動作成
配車管理システムの中核機能ともいえるのが、自動配車です。システムは、出荷件数、配送先の地理的条件、車両の大きさ・積載制限、ドライバーの拘束時間、休憩時間の法令制限など、複数の条件を同時に加味して最適なルート・配車割り当てを算出します。
これにより、車両の無駄な走行や積載率の低下を防ぎつつ、ドライバーの労働時間にも配慮した配車が可能となります。
運行状況のリアルタイム把握
各車両にGPSやドライバー用アプリを導入すれば、車両の位置・停止時間・走行速度などをリアルタイムで把握できます。交通渋滞や天候の影響によって遅延が発生した場合も、即座に状況を把握し、関係者への共有や次善の対応が可能です。また、荷主や納品先に正確な到着予定を伝えられるため、クレーム対応や連絡の手間も減ります。可視化が進むことで、現場のストレスも軽減されます。
配送業務の見える化と分析
日々の運行実績がデータとして蓄積されることで、定量的な分析が可能になります。具体的には、車両ごとの走行距離や積載率、ドライバーごとの待機時間、遅延発生率、繁忙時間帯の傾向など、あらゆる指標を可視化できる為、改善すべき配送ルートの見直しや、荷待ちが頻発する納品先への対応方針など、課題発見と対策立案がスムーズになります。
各種帳票の自動作成
運行管理では、日報・配送報告書・請求明細など、数多くの帳票が必要になります。配車管理システムを導入すれば、配車データと連動した帳票が自動作成でき、手入力の手間やミスを大幅に削減できます。月次集計や請求処理も自動で反映できるため、経理や営業部門との連携もスムーズになります。結果として、事務スタッフの負担軽減と業務スピードの向上が期待できます。
導入による主なメリット
配車業務は、物流現場において毎日発生する重要なオペレーションのひとつです。ここでは、配車管理システムを導入することで得られる主なメリットを紹介します。
配車業務の属人化を解消できる
従来の配車業務は、経験豊富な担当者のノウハウに大きく依存しており、情報の属人化が課題でした。
配車管理システムを導入することで、車両の稼働状況やドライバーのスケジュール、配送ルートなどの情報がすべてデジタルで記録・共有され、誰でも同じ水準で判断・対応ができる環境が整います。その為、担当者の退職や異動があっても、業務が止まることなく安定した運用が継続できます。
業務効率とスピードが向上する
配車担当者は日々、複数の案件を短時間で調整しなければなりません。システムを活用すれば、配送条件や積載量、到着時刻の制約など複雑な情報を一括で処理し、最適なルートと人員配置を瞬時に導き出せます。これまで数時間かかっていた作業が数十分で済むようになり、急な変更にも柔軟に対応可能です。結果として、業務時間の短縮とともに、人的ミスの防止にもつながります。
コスト削減と利益率の改善が期待できる
非効率なルートや空車走行の多発は、物流コストに直結します。配車管理システムは、複数案件の組み合わせを最適化することで、積載率を最大限に引き上げ、回送の削減を実現します。例えば、同一エリアの納品先をまとめて効率化すれば、1台あたりの配送効率が大きく改善されます。また、燃料費や拘束時間の削減にもつながり、全体の収益性向上に寄与します。
ドライバーの働きやすさが向上する
ドライバー不足が深刻化する中で、職場環境の改善は企業の大きな課題です。配車システムを使えば、長時間拘束や不公平な配車が発生しにくくなり、適正な運行計画のもとで働くことができます。待機時間の削減や、休憩・労働時間のバランスも取りやすくなるため、現場の満足度が向上します。結果として離職率の低下や新規採用の促進といった好循環が生まれます。
顧客満足度が向上する
システムにより納品予定や配送進捗がリアルタイムで共有されるため、急な遅延やトラブル時にもスムーズな対応が可能になります。問い合わせへの回答精度が上がり、顧客への信頼感が高まります。また、着荷時間の精度が向上すれば、受け入れ側の業務も効率化され、物流全体の品質が上がります。こうした積み重ねが、他社との差別化と長期的な取引継続の要因となります。
実際の導入事例から学ぶ!配車システム活用事例
NECソリューションイノベータ株式会社のULTRAFIX/TMSを導入した株式会社シーエナジーの事例
株式会社シーエナジー社は配車システムをエクセルで管理していましたが、属人的判断に限界が生じ2012年に「ULTRAFIX」を導入しました。2021年4月にはAI機能も追加し配送計画自動化をさらに進化させました。AI機能を追加したことで業務時間を44%削減することができました。これにより生み出された余剰時間を使ってお客様のもとに伺い、お話を伺う中でニーズを細やかに吸い上げ、より的確なサポートが行えるようになっています。
出典)
NECソリューションイノベータ株式会社のULTRAFIX/TMSを導入したJFE商事鋼管管材株式会社の事例
JFE商事鋼管管材株式会社は、配車業務の属人化と輸送効率の課題を抱えており、NECの輸配送管理システム「ULTRAFIX/TMS」を導入し、2024年3月に本格運用を開始しました。
導入から半年の時点で、配車業務の標準化と可視化が進み、配車担当者の属人的な業務をシステム化。さらに、これまで11台で運用していたトラックを9台に削減でき、輸送効率が約20%向上しました。属人化の解消、業務の効率化、車両稼働の最適化を実現しています。
出典)
https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ss/logistics/products/tms/case/jfe-shoji-kkt/
今後の展望〜AI・IoTと連携する配車の未来〜
配車管理システムは、今後さらに進化していきます。その鍵を握るのがAI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)との連携です。これまで人手と経験に頼っていた業務を、より正確かつ柔軟に、自動で処理できるようになることで、物流全体のパフォーマンスを大きく向上させる可能性を秘めています。ここでは、今後注目される技術的な展開と、それによって実現する未来像についてご紹介します。
AIによる配車最適化の高度化
現在も一部で導入が進んでいるAIによる自動配車機能は、今後さらに進化し、リアルタイムの道路状況、天候、交通量などの情報を踏まえた高度な判断が可能になります。従来の「効率的なルート選定」から一歩進み、「予測にもとづいたプロアクティブな配車」へと変化していきます。
IoTによる車両・ドライバー情報のリアルタイム収集
車載デバイスやセンサーによって、車両の位置情報だけでなく、ドライバーの体調、走行中の挙動、荷台の温度なども取得できるようになり、安全管理や品質管理の精度が大幅に向上し、より細かな判断が現場レベルで可能になります。
自動運転・MaaSとの連携
将来的には、自動運転技術やMaaS(Mobility as a Service)との連携も視野に入ってきます。たとえば、決まった区間での無人配送や、地域内のラストワンマイル輸送を自動車両が担うケースも登場しつつあります。配車管理システムは、これらのモビリティと連動し、人的リソース不足を補う存在へと進化していきます。
データ連携によるエコシステムの構築
配車データがTMS、WMS、需要予測システムなどと連携することで、物流全体がシームレスにつながる「エコシステム」が形成されます。これにより、全体最適を実現しやすくなり、効率性だけでなく環境配慮やサステナビリティの視点でも競争力を高めることが可能になります。
まとめ
本記事では、配車管理システムの基本的な仕組みから、導入によるメリット、具体的な機能、そして今後の展望までを解説しました。人手に頼っていた配車業務を標準化・効率化し、コスト削減やドライバーの負担軽減につなげられる点は、多くの企業にとって大きな魅力です。
加えて、AIやIoTとの連携が進めば、さらなる精度やスピードの向上も期待できます。配車の見直しは、物流全体の最適化にも直結します。これを機に、自社の業務を見直してみてはいかがでしょうか。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。