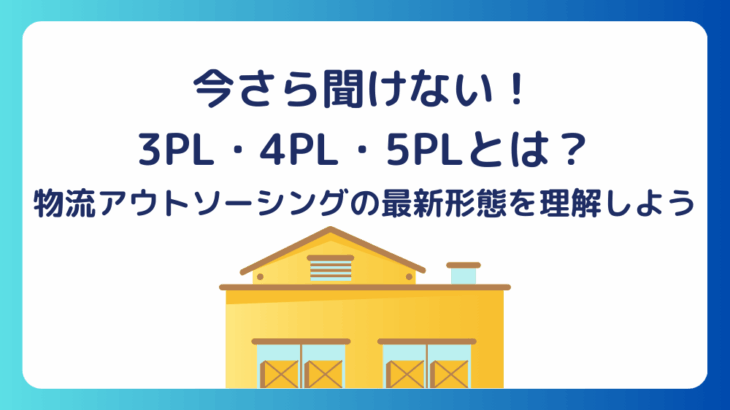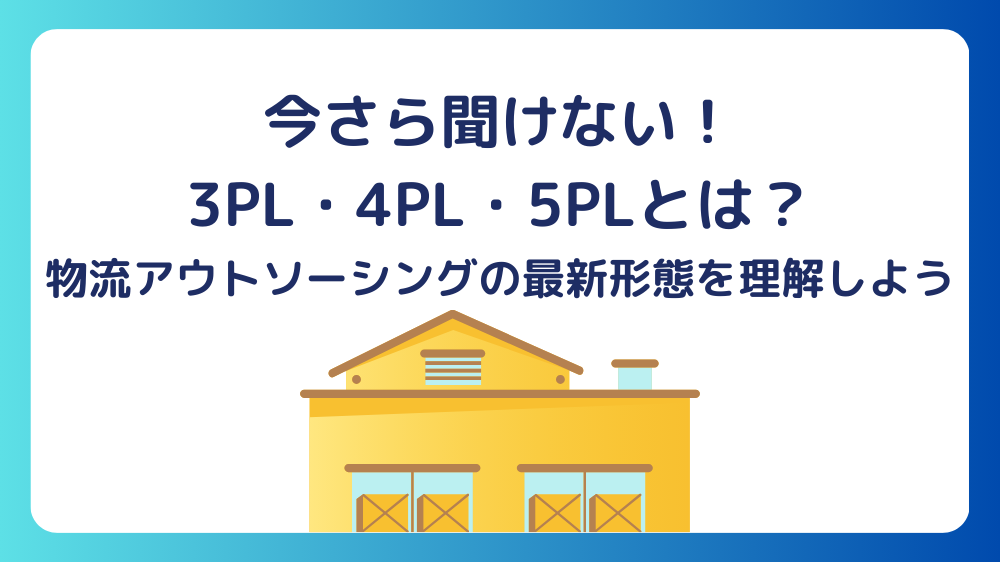
はじめに
物流における「PL(Party Logistics)」とは、物流の主体がどの立場にあるかを示す概念です。
物流業務の外部委託・分業の形態を「何次(○PL)」として分類しています。数字が上がるほど戦略性・統合性・IT化レベルが高くなります。
物流業務の範囲や委託の度合いに応じて、1PLから5PLまでの分類があり、企業がどの形態を採用するかによって、物流の効率やコストが大きく変わります。
▼あわせて読みたい!
物流サービスは“アウトソーシング”から“戦略パートナー”の時代へ
物流業界は今、大きな変革の時代を迎えています。かつては単なる「運ぶ」だけだった物流サービスが、今や企業の競争力を支える「戦略パートナー」としての役割を担うようになっています。配送や保管だけでなく、在庫管理、注文処理、さらには物流戦略の立案まで、物流のアウトソーシングは多様化・高度化しています。
本記事では、3PLから5PLまでの違いと、それぞれの特徴、導入メリットをわかりやすく解説します。
3PL・4PL・5PLとは何か?
3PL(物流の実務を委託するパートナー)
3PLは、企業が物流業務全般を専門業者にアウトソーシングする形態です。倉庫管理、配送手配、在庫管理など、物流に関するオペレーションを一括して外部業者に委託し、効率化を図ります。
特徴
一括管理:倉庫から配送までの流れを一社が管理。
コスト削減:自社で物流設備や人員を持つ必要がなくなる。
柔軟対応:繁忙期などに合わせた柔軟な対応が可能。
4PL(物流の総合プロデューサー)
4PLは、物流の設計・管理全体を担う形態です。3PL業者を統括し、物流全体を最適化するための計画・実行を行います。企業は物流戦略の立案や最適化を4PL業者に任せ、効率化を追求します。
特徴
物流全体のコントロール:複数の3PL業者を統括し、戦略的に管理。
コストとパフォーマンスの最適化:物流プロセス全体を分析し、最適化。
デジタル化対応:リアルタイムでのデータ管理や分析が可能。
5PL(物流の未来型プラットフォーム)
5PLは、複数の企業・業界を統合した、ITベースの最適化・自動化を主導するモデルです。AIやIoT、ブロックチェーンを活用し、サプライチェーン全体をデジタルで管理します。これにより、リアルタイムでの在庫管理、配送ルートの最適化、需要予測が可能になります。
特徴
完全なデジタル管理:物流データをリアルタイムで分析。
自律的最適化:AIによる需要予測や配送計画の自動化。
サプライチェーン全体の可視化:全ての物流プロセスが一元管理。
それぞれの機能解説・機能比較表
| 分類 | 3PL (Third Party Logistics) | 4PL (Fourth Party Logistics) | 5PL (Fifth Party Logistics) |
| 基本機能 | – 倉庫管理
– 配送手配 – 在庫管理 – 返品対応 |
– 3PLの統括管理
– 物流戦略立案 – データ管理 – コスト最適化 |
– AI・IoT活用
– 需要予測の自動化 – サプライチェーン全体管理 – 自動化技術の導入 |
| データ活用 | 各3PL事業者のシステムを使用 | 各3PLデータを統合・最適化 | AI・ビッグデータで自動化 |
| 対応範囲 | 国内・国外の物流業務 | 国際物流、マルチチャネル対応 | グローバルサプライチェーン |
| コスト管理 | 3PL事業者ごとに契約 | 4PLがコスト交渉を一括管理 | AIが自動でコスト最適化 |
| 導入例 | EC企業が配送を3PLに委託 | 多国籍企業が物流統括を4PLに委託 | ECプラットフォームがリアルタイム配送最適化を5PLに委託 |
なぜ4PL・5PLが注目されているのか
3PLからさらに進化した4PLや5PLが注目を集めています。では、なぜこの4PL・5PLが注目されているのでしょうか?物流業界の構造変化・経営課題・テクノロジーの進展という3つの観点から、詳しく解説します。
物流業務の複雑化と“部分最適”の限界
3PLは、主に「運ぶ・保管する」など物流実務の外注に特化しています。しかし近年は、ECの急拡大により、小口・多頻度配送が主流になり、また、サプライチェーンの複雑化により、複数拠点・複数事業所をまたぐ管理が必要になってきています。
部分的に外注するだけでは、全体の最適化ができないことから、物流全体の設計・管理まで任せられる「4PL」へのニーズが増加しています。
物流人材・ドライバーの深刻な不足
2024年問題によるドライバー不足や、倉庫人材の確保難、担当者依存の「経験と勘」の業務から脱却したいニーズなど、属人化の排除と「自動で動く物流」の仕組みが求められており、人的リソースではなく「設計・統合・最適化」で回す物流として、4PL・5PLが期待されています。
SCM全体の最適化への移行
多くの企業が、物流を「単なるコスト」ではなく「競争力の源泉」と考えるようになっています。「在庫を減らす」「納期を短縮する」「CO₂排出を抑える」などの戦略課題があり、調達・製造・販売をつなぐSCM(サプライチェーンマネジメント)最適化が最重要テーマで、4PLはSCMを俯瞰し、5PLはデータを用いてその最適化を自動化することから注目されています。
AI・IoTなどのテクノロジー活用による差別化
5PLでは、AI・IoT・クラウド・ロボティクスといった技術を駆使して、需要予測 × 動的配車の自動化(AI)、倉庫作業の自律ロボット制御(IoT+RL)、リアルタイム在庫と配送状況の可視化(クラウドTMS/WMS)といった高度な管理が可能です。
5PLは物流を「人が動かすもの」から「データで動かすもの」に変えることが可能です。
企業間連携(水平・垂直)の加速とプラットフォーム化の流れ
昨今、物流業界では、競合企業同士が積載率向上のために共同配送をしたり、物流インフラを複数企業で共用したりといった産業の壁を超えた連携(異業種混載など)が加速しています。
単独の物流業者では設計できないネットワークが必要になってきており、中立的立場で設計できる4PLや、全体最適を図れる5PLが重宝される傾向にあります。
それぞれのメリット・デメリットとは?
物流アウトソーシングは、企業にとって効率化とコスト削減の鍵ですが、3PL・4PL・5PLにはそれぞれメリットとデメリットがあります。自社の物流戦略に合わせて、最適なモデルを選ぶことが重要です。
3PL
メリット
コスト削減: 自社で物流設備や人材を持たずに済み、運営コストを大幅に削減できます。
物流の専門性活用: 専門の物流業者が管理するため、効率的かつスピーディーな配送が実現。また、物流業務の外注により自社のリソースをコア業務に集中できます。
柔軟な対応: 需要変動や配送エリアの拡大にも対応可能で、成長企業に向いています。
デメリット
物流戦略のコントロールが難しい: 外部委託のため、サービス品質や対応速度に制約があります。
情報共有の遅れ: 自社の在庫状況や配送状況をリアルタイムで把握しにくい場合があります。
長期契約リスク: 変更が難しい契約を結ぶと、ニーズの変化に柔軟に対応できません。
4PL
メリット
サプライチェーン全体を一括管理: 複数の物流業者を統合し、戦略的に物流を最適化。
コスト最適化: 複数の業者を統一管理し、余計なコストを削減できます。
データドリブンな運用: 物流データをリアルタイムで収集し、最適化に役立てます。
デメリット
初期導入コストが高い: 戦略設計やシステム導入にコストがかかる場合があります。
柔軟性に欠けることも: 特定業者への依存度が高くなると、業務変更が難しくなる場合があります。
情報の透明性が求められる: 複数の業者との情報共有やデータの一元化が不可欠です。
5PL
メリット
AI・IoTでデジタル化: 最新技術を駆使し、在庫・配送の自動化が可能。
グローバル対応: 国際物流も一括管理し、複雑な関税処理や輸送計画も支援。
複数企業の統合管理: 共同配送や共同倉庫など、複数企業間での効率化が可能。
デメリット
導入のハードルが高い: 高度なシステム構築や運用ノウハウが必要。
依存度が高い: プロバイダーの技術や運用力に強く依存するため、選定が重要です。
データセキュリティのリスク: デジタル化により、情報漏洩やサイバー攻撃のリスクも高まります。
どの業態・フェーズにどのPLが向いている?
物流アウトソーシングは、企業の成長フェーズや事業内容によって最適な形が異なります。3PL、4PL、5PLのそれぞれの特性を理解し、自社の状況に最も適したモデルを選ぶことが、効率的な物流運営のカギとなります。ここでは業態や成長フェーズごとに、どのPLが最適かを解説します。
3PLが向いている企業
・スタートアップ企業や中小企業
物流に関するリソースやノウハウが不足している企業には3PLが最適です。自社で倉庫や配送車両を持たず、物流業務を一括して専門企業に委託できます。これにより、コストを抑えつつ、配送品質を確保できます。
・急成長中の企業
ECサイトやD2Cブランドなど、短期間で急成長を遂げる企業も3PLが向いています。繁忙期のオーダー増加やキャンペーン時の対応も、3PL業者のキャパシティに依存できるため、柔軟な対応が可能です。
▶ 例:小売・アパレル、食品メーカー、スタートアップ企業
4PLが向いている企業
・複数の物流拠点を持つ中堅企業
複数拠点間での配送管理や在庫管理が煩雑になる企業には、4PLが最適です。4PLは単に物流を委託するだけでなく、複数の物流業者を統合管理し、効率化を図ります。
・サプライチェーン全体を効率化したい企業
調達から配送までの全体を見渡し、最適な物流戦略を構築する4PLは、供給網の複雑な製造業や流通業に効果的です。企業は物流の指揮をプロに任せ、コア業務に集中できます。
▶ 例:製造業(自動車、家電)、大手小売チェーン、グローバル企業
5PLが向いている企業
・グローバル展開を視野に入れた大企業
海外拠点を持つ企業や国際輸送を頻繁に行う企業は、5PLのメリットを最大限に享受できます。AIやIoTを活用したリアルタイムのデータ分析により、グローバルサプライチェーンの最適化が可能です。
・ デジタル化を積極的に推進する企業
5PLはデジタル技術を駆使し、リアルタイムのデータに基づいた意思決定を支援します。自動化された在庫管理や配送計画により、人手をかけずに物流業務を効率化できます。
▶ 例:大手総合商社、グローバルEC企業、製薬・医薬品企業
まとめ
本記事では、物流アウトソーシングの最新トレンドである3PL・4PL・5PLについて、その違いとメリット、そして企業ごとに最適な選択肢を解説しました。
3PLはコスト削減と業務効率化を重視したアウトソーシング手法で、スタートアップや中小企業に最適です。
一方、4PLはサプライチェーン全体を俯瞰し、複数の物流業者を統合管理するため、製造業や大手流通業に向いています。
そして、5PLはデジタル技術を活用し、データドリブンな最適化が可能な最先端モデル。国際展開を目指す企業やデジタル化を進める企業に理想的です。
自社の規模、事業内容、成長フェーズに合わせて適切なPLを選択し、戦略的な物流パートナーシップを構築することが、これからの競争力向上につながります。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。