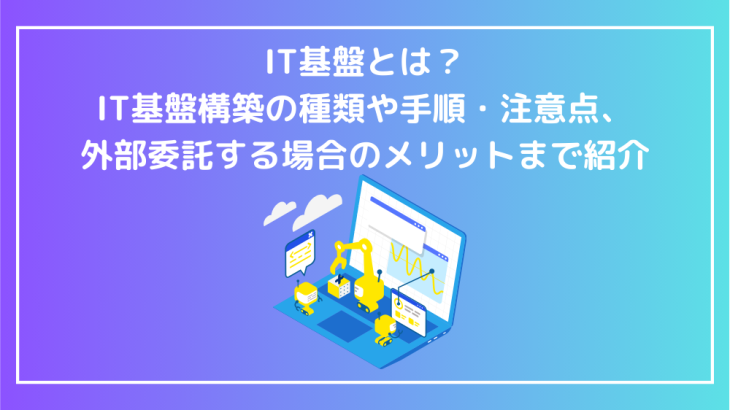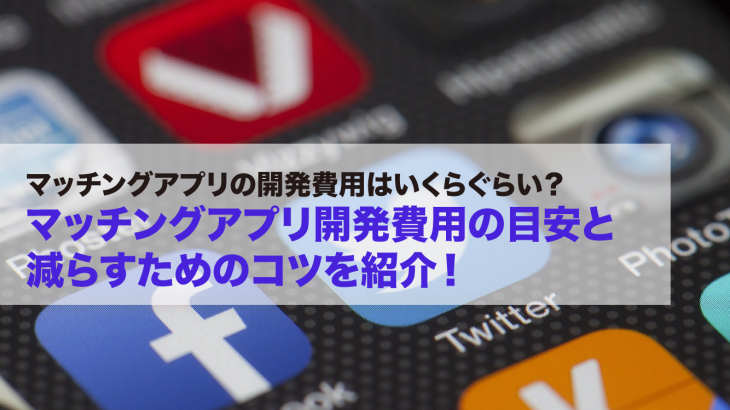クラウドシステムとは
ふだんの生活でスマートフォンやパソコンを使っていると目にする「クラウド」。実際に利用の経験がある方も多いのではないでしょうか?
クラウドシステムとは、「提供会社が構築するシステムをインターネット上で利用できるサービス」です。
ソフトウェアやサーバが手持ちのコンピューターに入っていなくても、レンタル料を支払い、インターネット環境があれば使用できるのが特徴です。
身近にあるものでは、例えばApple社のiCloudがあります。iCloudは、iPhoneやiPadで撮影した写真などのデータを自動的にインターネットを経由してサーバーに保存するクラウドサービスです。必要に応じて閲覧や編集ができます。
他にもGmailやオンラインゲームなどがあげられ、身近でも活用されています。
クラウドシステムの基礎知識
ここではクラウドシステムについてもう少し深く知るために必要な基礎知識をお伝えしていきます。
パッケージシステムを利用する仕組み
クラウドでは、次の2つがセットの「パッケージシステム」を使用します。
①アプリケーション
②データベース
アプリケーション
利用者の目的に応じて作られたプログラムです。パソコンやスマホにインストールして使用します。
例として、表計算ソフトや文章作成ソフトなどがあげられます。
データベース
一定の形式(管理・分析・検索するために最適な形式)で整理された情報の集まりのことです。
例として、名簿や電話帳などの個人情報、商品の管理などの情報などがあげられます。
クラウドシステムの利用者は、ほとんどの場合、これらのアプリケーションとデータベースを合わせて使います。
アプリケーションは情報処理装置(パソコンやスマートフォン)にインストールして使用します。インターネットを介してサーバにあるデータベースから情報を参照し、パッケージシステムを使用します。
システムの所有者
所有元が「利用者か、提供者か」によって会計処理が異なります。
・利用者が所有する場合
パッケージシステムやサーバーを自社運用するオンプレミス型(オンプレ型)の場合、利用者が管理する施設に機器を設置して運用します。
パッケージシステムとサーバーを自社で購入するため自社の資産、会計上も資産となります。
・提供者が所有する場合
クラウドシステムはパッケージシステムとサーバーをインターネットを経由して使用するため、購入は不要であり、使う間の利用料を払います。
提供者の所有で、自社の資産とはなりません。
しかし、全ての利用者がこれにあてはまるわけではありません。なかには、パッケージシステム、サーバーのどちらか一方だけをクラウドで使うケースがあります。次項ではその分類についてご紹介します。
クラウドでできる主な業務とは
クラウドでできる主な業務には、以下のようなものが挙げられます。
データストレージとバックアップ
クラウドサービスは、データの保存とバックアップを効率的に行うことができます。これにより、オンプレミスのハードウェアに依存せずに、大量のデータを安全に保管し、災害時のデータ復旧も容易になります。
例: Amazon S3、Google Cloud Storage、Microsoft Azure Blob Storage
リモートデスクトップと仮想ワークスペース
クラウドを利用して、リモートデスクトップや仮想ワークスペースを提供することで、従業員がどこからでも業務を遂行できる環境を構築できます。
例: Amazon WorkSpaces、Microsoft Windows Virtual Desktop、Google Cloud Virtual Desktops
ソフトウェア開発とデプロイ
クラウドプラットフォームは、アプリケーションの開発、テスト、デプロイを効率的に行うための環境を提供します。開発者はリソースを迅速にスケールアップ・ダウンできるため、柔軟性が向上します。
例: AWS Elastic Beanstalk、Google App Engine、Microsoft Azure DevOps
コミュニケーションとコラボレーションツール
クラウドベースのツールを使って、チームのコミュニケーションとコラボレーションを強化できます。これには、ビデオ会議、チャット、ドキュメント共有などが含まれます。
例:Microsoft Teams、Google Workspace、Slack
カスタマーリレーションシップマネジメント(CRM)
クラウドベースのCRMシステムは、顧客データの管理と分析を効率化し、営業活動の最適化やマーケティングキャンペーンの効果測定を支援します。
例:Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365
エンタープライズリソースプランニング(ERP)
クラウドベースのERPシステムは、企業の資源を一元管理し、業務プロセスの効率化を図ります。これにより、在庫管理、会計、人事などの業務を統合的に管理できます。
例:SAP S/4HANA Cloud、Oracle ERP Cloud、Microsoft Dynamics 365
これらの業務はクラウドの活用により効率化され、企業の柔軟性と競争力を向上させることが期待されます。
クラウドサービスの分類
クラウド業者が「何を提供するか」によって3つの種類にわけられます。
・SaaS(サース)Software as a Service
・PaaS(パース)Platform as a Service
・IaaS(イアース)Infrastructure as a Service
ここでは3種類の紹介をしていきます。
SaaS(パッケージシステム一体型)
SaaSは、インターネットを通じてソフトウェアアプリケーションを提供するサービスです。ユーザーはブラウザを通じてアプリケーションにアクセスし、利用します。
インターネット接続さえあれば、どこからでも利用可能で、サブスクリプションモデルで提供されることが多く、初期費用が不要で、ソフトウェアのアップデートやメンテナンスが不要な点が特徴です。
例:
Google Workspace: オフィスツール(Gmail、Google Docs、Google Driveなど)。
Microsoft 365: オフィスソフトウェア(Word、Excel、Outlookなど)。
Salesforce: CRM(顧客関係管理)ツール
PaaS(サーバ+開発環境提供型)
PaaSは、アプリケーションの開発、テスト、デプロイ、管理を行うためのプラットフォームを提供します。開発者は、インフラの管理から解放され、アプリケーションの開発に集中できます。
開発ツール、データベース、ミドルウェアが統合された環境を提供し、スケーリング、バックアップ、セキュリティが自動化され、インフラ管理の負担が軽減される点が特徴です。
例:
Google App Engine: アプリケーションのスケーリングと管理。
Microsoft Azure App Services: WebアプリケーションとAPIのホスティング。
Heroku: 簡単なデプロイとスケーリング。
IaaS(サーバ環境提供型)
IaaSは、仮想化されたコンピューティングリソース(仮想マシン、ストレージ、ネットワーク)を提供するサービスです。ユーザーは、物理的なハードウェアを所有することなく、必要なリソースをオンデマンドで利用できます。
必要に応じてリソースをスケーリング可能な柔軟性が特徴で、使用した分だけ支払う従量課金制で、ユーザーはオペレーティングシステムやアプリケーションの管理を担当します。
例:
Amazon Web Services (AWS) EC2: 仮想サーバーの提供。
Microsoft Azure Virtual Machines: 仮想マシンのホスティング。
Google Cloud Compute Engine: 高性能なコンピューティングリソースの提供。
これらのクラウドサービスは、それぞれ異なるニーズに対応するために設計されており、企業や個人が柔軟に選択することができます。
クラウドシステムの導入費用
クラウドシステム導入の費用は、使用するリソースの種類と量、稼働時間、データ量と転送頻度などによって様々ですが、ここでは、クラウドシステム導入に関連する主要な費用項目について解説します。
初期設定費用
アーキテクチャ設計:クラウドインフラの設計と計画。
データ移行:既存のシステムからクラウドへのデータ移行費用。
コンサルティング:クラウド導入のための専門コンサルティングサービス。
運用費用
サブスクリプション料金:クラウドプロバイダーのサービス使用料(※IaaS、PaaS、SaaSの各モデルに応じて異なる)。
ストレージコスト:データ保存のための料金。
データ転送費用:データの出入りに伴う転送費用
管理・メンテナンス費用
システム監視:24時間体制の監視と管理費用。
セキュリティ対策:セキュリティソリューションの費用。
アップデートとパッチ適用:システム更新とパッチ適用の費用。
クラウドサービスは安さだけでなく、コストパフォーマンスに優れているかが重要です。また、使用するリソースの種類と量、稼働時間、データ量と転送頻度などによっても変わってきますので、必要な機能を満たすクラウドサービスをいくつかピックアップし、コストを比較したり、プロバイダーの公式料金計算ツールやコンサルティングサービスを活用すると良いでしょう。
クラウドシステム利用時の会計処理
自社でソフトウエア・ハードウエアを用意し、システムを構築・運用する「オンプレミス型」では、パッケージシステムとサーバーを自社で購入します。そのため自社の資産となり、会計上でも固定資産として計上する必要があります。
クラウドシステムを利用した場合、設備を保有しているのは利用者ではなく、サービス提供者です。クラウドシステムの場合は、その利用形態によって、会計処理も変わってきます。
利用形態は3通りが考えられます。
パッケージシステム一括購入の場合
【資産】
・購入した「パッケージシステム」は利用者の所有する資産取得になるため、固定資産として会計処理されます。
・導入に必要な「作業料」や「カスタマイズ費用」も取得価格に含めることが実務指針に示されています。
・「ソフトウェア」を無形固定資産として計上する場合は、減価償却の耐用年数を5年以内にすることとされています。
【費用】
・「サーバーの月額利用料」、「導入時の操作指導料」は費用として計上します。
パッケージシステムをリース購入する場合
【費用】
・パッケージシステムのリース購入は、リース会社からの資産の借用となります。そのため資産計上は不要であり、「リース料」は費用として計上します。「カスタマイズ」や「設定作業」に伴う料金を含めてリース料金とする場合があります。
・「導入時の操作指導料」、「サーバ使用料」は費用として計上します。
クラウド業者のパッケージシステムを利用する場合
【資産】
・クラウド業者のパッケージシステム所有となりますので、資産計上は不要です。ただし、「カスタマイズ」を行った場合の費用、それに伴う「設定作業料」は利用者の資産として計上できます。
【費用】
・クラウドサービスの設備を保有しているのはサービス提供者ですので、「クラウドサービス利用料」は費用として計上します。
・「導入時の操作指導料」、「サーバの利用料」は費用として計上します。
まとめ
クラウドシステムはサービスの提供形態によって、カスタマイズ性やシステム構築の有無などの特徴が変わってきます。 また、パッケージシステムを購入するか、クラウド利用するかによってシステムの所有者も変わり、会計処理も異なってきます。 それぞれの企業の特徴に合ったクラウドサービスの選択をすることで、管理負担の軽減や業務の効率化につなげることができます。
アイディオットでは、「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行っています。国内最大級の導入実績!新規事業でマッチングサービス立ち上げならアイディオットへご相談ください。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。