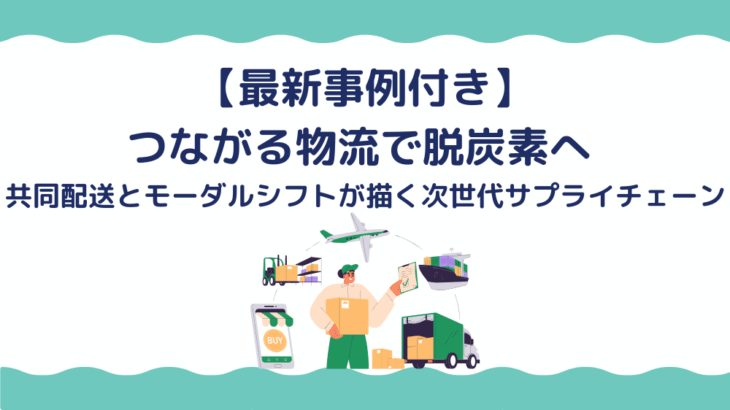脱炭素社会の実現に向け、物流分野にも構造的な変革が求められています。
その中でも、共同配送による積載効率の最大化と、モーダルシフトによる幹線輸送の低炭素化は、現実的かつ即効性のあるアプローチとして注目を集めています。
さらに、こうした取り組みを持続的に拡大する鍵を握るのが、フィジカルインターネットの発想と物流標準化の推進です。
本稿では、企業の枠を超えて「つながる物流」を実現するための実践的な視点から、脱炭素化の道筋を探ります。
はじめに ― 脱炭素要請と物流危機
物流業界にとって避けられない課題となっているのが「脱炭素対応」と「持続可能な輸送力の確保」です。燃料費や人件費の上昇、そして2026年問題に代表される輸送力不足は、従来の輸配送モデルを根本から見直す転機を迫っています。その解決策として注目を集めているのが「共同配送」と「モーダルシフト」です。本記事では、これらの施策についてとなぜ今必要とされ、どのように企業の競争力やサステナビリティ経営につながるのかを具体的に解説します。
Scope3削減の重要性
企業の温室効果ガス排出削減において注目されるのが「Scope3(サプライチェーン全体の間接排出)」です。多くの業種において、物流はScope3排出量の大部分を占めています。つまり、輸配送や倉庫運営でのCO₂削減は、単なるコスト管理の範囲を超え、投資家や消費者からの信頼を得るための経営課題と直結しています。荷主企業が自ら物流データを可視化し、排出削減のロードマップを描くことは、サステナビリティ経営の基盤強化に欠かせません。
▼あわせて読みたい!
2026年輸送力不足と環境対応の二重課題
2024年問題で表面化したドライバー不足は、2026年にかけてさらに深刻化すると見込まれています。労働時間規制の強化により輸送キャパシティは縮小し、輸送枠の取り合いと運賃高騰が常態化する可能性があります。
同時に、ESGやScope3対応の観点から「環境に優しい物流」の実現も求められており、輸送効率化と低炭素化を両立する施策が急務です。共同配送やモーダルシフトといった取り組みは、この二重課題を同時に解決するための具体的な答えとして注目されています。
共同配送 ― 積載率向上とCO₂削減の切り札
共同配送の基本仕組みとメリット
共同配送とは、複数の会社や業者が、各自の荷物をまとめて1台のトラックに積み、一緒に運んで同じ配送先に荷物を届ける仕組みのことです。
主なメリットは下記が挙げられます。
- 積載率向上による効率化
従来の「半分しか積んでいない状態で走る」無駄をなくし、トラック1台あたりの輸送効率を最大化できます。 - コスト削減
配送コストを参加企業間で分担することで、輸送費を抑制できます。運賃の高止まりが続く中で有効な対策です。 - CO₂排出削減
走行台数や走行距離が減ることで、温室効果ガスの排出削減に直結します。Scope3削減の取り組みとしても有効です。 - 輸送力確保
ドライバー不足が進む中で、効率的に配送枠を確保できる点も大きな魅力です。
▼あわせて読みたい!
事例1:ロート製薬、ミルボン、Haleonジャパンの共同配送
ロート製薬株式会社、株式会社ミルボンとHaleonジャパン株式会社は、持続可能なサプライチェーン構築を目的とした物流効率化の取り組みとして、東陽倉庫株式会社の協力のもと、3社における共同配送を2025年8月より開始しました。
パレットサイズ、輸送量、製品安全の問題など、各社の様々な制約条件をクリアするため、共同配送に適した製品選定、積載技術の検証、品質テストを実施。製造拠点と倉庫間をリレー方式で繋ぐことで、積載効率の最大化、ドライバースイッチ等、長距離輸送でも過負荷なく運行できる体制を整えました。
【具体的な効果】※週1回 共同配送を実施した場合
・積載率 :13.7%向上(平均66.5%→75.6%)
・輸送効率 :トラック102台/年(67.1%)削減
・総合輸送距離 : 15,428km/年(38.6%)削減
・CO₂削減量:13.3t-CO₂/年(32.8%)削減
上記輸送効率化において18.4%コスト削減および1運行単価19.2%改善。相互扶助並びにドライバーの雇用環境改善に寄与
今後は月1便で実施している本スキームを、週1便へ増便することで、定期化・安定運用を図るとともに、本取り組みにより得た成功事例やノウハウを活かし協力企業を増やすことで拠点拡大を目指し、またタイムスケジュールの自動化など物流DXを推進し、積載率の最適化や省人化のさらなる推進を図りますとしています。
出典)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000485.000044879.html
事例2:F-LINE ― 食品メーカー6社による共同配送会社
味の素株式会社、ハウス食品グループ本社株式会社、カゴメ株式会社 KAGOME CO.,LTD.、株式会社日清製粉ウェルナ、日清オイリオグループ株式会社、株式会社 Mizkan Holdingsが出資するF-LINE株式会社は2025年8月28日、9月から北海道の共同配送で最適な輸送手段を組み合わせる「モーダルコンビネーション」に試験的に取り組むと発表しました。トラック運転手不足に対応し、環境負荷低減にもつなげ、札幌市から帯広市の幹線輸送で、二酸化炭素(CO2)排出量の約43%の削減を見込んでいます。
札幌市にある拠点から帯広市の中継拠点までのトラック輸送を鉄道で代替し、そこから納品先への配送はトラックを使い、モーダルコンビネーションの実用性を総合的に評価します。
食品メーカー6社とF-LINE株式会社は、北海道で2016年から共同配送を始め、23年に札幌市と北広島市の2カ所だった保管・配送拠点を札幌市内の1カ所にして効率化しました。共同配送の納品先の8割が札幌都市圏に集中しており、残りの2割は各地方に分散しています。
出典)
https://news.ajinomoto.co.jp/2025/08/2025_08_28_02.pdf
低炭素化
モーダルシフトの特徴と効果
脱炭素社会の実現に向けて、物流業界では「モーダルシフト」が再び注目を集めています。トラック輸送に依存してきた幹線輸送を、鉄道や船舶といった環境負荷の少ない手段へ切り替えることで、CO₂排出量を大幅に削減できる取り組みで、単なる環境対応にとどまらず、ドライバー不足や輸送効率の改善にも寄与する“構造改革”のひとつとして、多くの企業が導入を進めています。
主なメリットは下記が挙げられます。
- 幹線輸送のCO₂排出を大幅削減
鉄道や船舶は、同じ輸送量でもトラックに比べてCO₂排出量が約1/5~1/10に抑えられるとされています。とくに長距離輸送ではその効果が顕著で、環境負荷低減に直結します。近年では、カーボンニュートラル経営の一環として「Scope3排出量削減」の施策に組み込む企業も増えています。 - ドライバー不足への対応策として有効
モーダルシフトは、人手不足対策としても効果的です。長距離を鉄道やフェリーに任せることで、ドライバーの拘束時間を短縮し、働き方改革にも貢献します。たとえば、関西~関東間の輸送をトラックから鉄道コンテナに切り替えることで、ドライバーは「最寄駅までの短距離運行」のみで済むようになります。 - コストと安定性の両立
一見するとモーダルシフトはコスト増の印象を持たれがちですが、燃料高騰や高速料金の上昇を考慮すると、中長期的にはコスト安定化につながります。天候や交通渋滞の影響を受けにくく、安定したリードタイムを確保できる点も大きなメリットです。 - 共同輸送とのシナジー効果
さらに、モーダルシフトは共同配送と組み合わせることで効果が倍増します。複数企業が貨物をまとめて鉄道やフェリーに載せることで、積載率を高め、輸送効率を一層引き上げることが可能です。
事例1:ビール4社の海上モーダルシフト
2017年9月にアサヒビール株式会社、キリンビール株式会社、サッポロビール株式会社、サントリービール株式会社は物流部門での環境負荷の低減および長距離トラック輸送の削減によるドライバー不足への対処を目的に、共同物流を行うことで合意しました。
2025年には澁澤倉庫株式会社と大王海運株式会社を主体に関東から関西までトラックで直送していた商品を、いったん千葉港に集約してRORO船で大阪港まで輸送し大阪港から各拠点に陸送を行いました。その結果、CO2排出削減量:1,648.7t(59.3%) 、ドライバー運転時間省力化:3,793時間(77.5%)削減されました。
出典)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000172834.pdf
https://www.shibusawa.co.jp/sustainability/environment/
https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2017/0516_04.html
事例2:森永乳業株式会社×日本通運株式会社×日本貨物鉄道株式会社×日本石油輸送株式会社
森永乳業株式会社、日本通運株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本石油輸送株式会社は、流動食モーダルシフト推進協議会を結成し、31フィートスーパーURコンテナを活用した鉄道によるラウンド輸送を7月1日より開始しました。なお、往路復路ともに同じ荷主(森永乳業)による31フィートスーパーURコンテナ※2を活用したラウンド輸送は日本初の取組みになります。
森永乳業の物流において、特に東北地区発着の広域輸送ルートでは、トラックドライバー不足が顕著であり「運べないリスク」が高まっていました。一方で、現行の鉄道コンテナを活用したラウンド輸送については、往復荷の確保が難しく、往路と復路で異なる荷主を探すことにも労力を費やしていました。
このたび、4社でコンソーシアムを結成し、森永乳業専用の31フィートスーパーURコンテナを導入し、神戸と盛岡・仙台の間のうち、百済・大阪貨物ターミナル駅(大阪府大阪市)から仙台貨物ターミナル駅(宮城県仙台市)の固定ルートで往復利用することで、これまでの課題を解決することができ、また、環境面でもCO₂排出量を約72%削減、年間排出量約184tの抑制を見込んでいます。
出典)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001293.000021580.html
フィジカルインターネットと標準化の役割
“つながる物流”の鍵を握るフィジカルインターネット
フィジカルインターネットは、インターネットの仕組みを物流に応用し、モノの移動をネットワーク全体で最適化するという新しい発想です。
情報通信の世界では、データが標準化されたパケットとしてネットワークを自在に流通します。同様に、物流の世界でも標準化されたコンテナやパレット単位で貨物を共有インフラ上に流通させる。これがフィジカルインターネットの基本理念です。
この発想が進めば、輸送手段や倉庫、荷主が異なっても、同じ標準のもとでスムーズに接続・連携が可能になります。結果として、
・積載率の最大化
・中継拠点や車両の共用によるコスト削減
・輸送距離・待機時間の削減によるCO₂排出抑制
といった成果が期待されます。
▼あわせて読みたい!
標準化こそが「共有」の前提条件
フィジカルインターネットのような、ネットワーク型物流を成立させるには、「標準化」が不可欠です。
現在の物流現場では、パレットサイズ、積付け仕様、伝票情報、入出荷データのフォーマットなどが企業ごとに異なっており、共同化やモーダルシフトの障壁になっています。
例えば、欧州ではEURパレット(1200mm×800mm)のように共通規格が浸透しており、荷役機器や倉庫システムもそれを前提に設計されています。これに対して日本では、業界や地域ごとに規格が分かれ、物流の“分断”が温存されているのが実情です。
標準化は単なる技術的統一ではなく、企業間で物流資源を共有し、ネットワーク全体で効率を上げるための共通言語といえます。
データ連携とデジタル基盤の整備
フィジカルインターネットの実現には、データ標準化と相互運用性の確保も欠かせません。
国土交通省が推進する「物流情報標準ガイドライン」は、その基盤づくりの一環です。
ガイドラインでは、広範囲でのデータ連携などによる物流の効率化・生産性向上のために必要なデータ項目の標準形式等が定められています。
具体的には、以下の3つの標準を定義しています。
物流業務プロセス:共同輸送、共同保管、検品レス、バース予約を行う際の、運送計画や集荷、出庫、配送といった物流プロセスの流れやルール。
物流メッセージ:運送計画や集荷、入出庫、配達といった物流プロセスで用いるメッセージ(複数のデータ項目で構成された物流情報)のルール。
物流共有マスタ:物流メッセージ標準を採用する各業界システムがマスタ整備をする際の指針。
また、物流データの共有・分析を支える共通API、データプラットフォーム、ブロックチェーン技術なども注目されています。
こうした技術基盤が整えば、車両の稼働状況や倉庫の空き情報をリアルタイムに共有し、輸送マッチングを自動化することも可能になります。これは、共同配送の高度化や幹線輸送の最適化に直結します。
参考)物流情報標準ガイドライン
企業が今すぐ取るべきアクション
物流コストの上昇と輸送力不足が続く中で、荷主企業には“待ちの姿勢”ではなく、能動的な改革が求められています。特に2026年4月に施行される改正物流効率化法や環境対応など外部要因が一気に加速するなか、今からの準備が数年後の企業競争力を左右します。ここでは、すぐに着手できる3つの具体的なアクションを紹介します。
自社の物流データを可視化・分析
第一歩は、自社物流の現状を「見える化」することです。輸送ルート、積載率、CO₂排出量、倉庫稼働率などのデータを集約・分析することで、どの部分に無駄や偏りがあるかを定量的に把握できます。
最近では、輸送管理システム(TMS)や倉庫管理システム(WMS)にCO₂排出量を自動算出する機能を組み込む企業も増えており、可視化が進めば、共同配送やモーダルシフトに適した区間の特定や、他社との連携提案の根拠づくりにもつながります。
他社・業界団体との共同化可能性を検討
データ分析の次は、「どこと組めば相乗効果が出るか」を見極める段階です。同一エリアに配送先を持つ企業、同じ業界で非競合の商品を扱う企業など、“敵ではなく仲間になれる”相手を探すことが重要です。
近年は、商工会議所や業界団体、自治体が共同配送プラットフォームの形成を支援する動きも活発化しています。自社単独では解決できない物流課題も、地域単位・業界単位の共創によって、効率と環境の両立が可能になります。
環境負荷の定量化と脱炭素KPIの設定
「環境対応」は、定性的な表現だけでは社内外に伝わりません。物流由来のCO₂排出量を定量化し、2030年や2050年に向けた中期的なKPIを設定することが必要です。
たとえば、「2030年までに物流CO₂排出量を20%削減」「主要幹線区間の30%をモーダルシフト化」「自社便の積載率を平均80%以上に維持」 といった数値目標を掲げることで、社内の意識と投資判断が変わります。
また、これらのKPIはESG評価やサステナビリティレポートでも重要な指標になります。
取引先や協力会社を巻き込んだサプライチェーン全体での脱炭素化も欠かせません。自社だけで削減努力をしても、サプライチェーン全体のCO₂排出量が減らなければ意味がないのです。
そのためには、環境負荷を共有する仕組みと協働のルールが必要です。共通の目標と仕組みを持つ“グリーン・パートナーシップ”の形成も効果的です。
まとめ
物流業界は今、かつてない転換期にあります。ドライバー不足、燃料高騰、環境対応。これらの課題を同時に乗り越えるには、従来の発想を超えた「協働」が欠かせません。その中核にあるのが、今回ご紹介した共同配送とモーダルシフトです。
共同配送+モーダルシフト=物流危機の突破口
企業同士が垣根を越えて配送を共有し、さらに鉄道や海運などのモーダルシフトを組み合わせることで、積載効率を高めながらCO₂排出を大幅に削減できるため、輸送力不足への対策と環境対応を同時に実現でき、結果として持続可能な物流ネットワークを構築できます。
ESG対応・コスト削減・競争力強化の同時実現
共同配送やモーダルシフトは、単なる“コスト対策”ではなく、経営の持続可能性を高める戦略でもあります。CO₂削減はESG経営の重要指標となり、効率化によるコスト削減は利益率の改善につながります。さらに、安定的な輸送力を確保できれば、納期遵守率の向上など、取引先からの信頼性強化にもつながります。物流の未来を動かすのは「単独最適」ではなく「共創最適」です。いまこそ、業界全体が手を取り合い、持続可能なサプライチェーンの再設計に踏み出す時です。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。