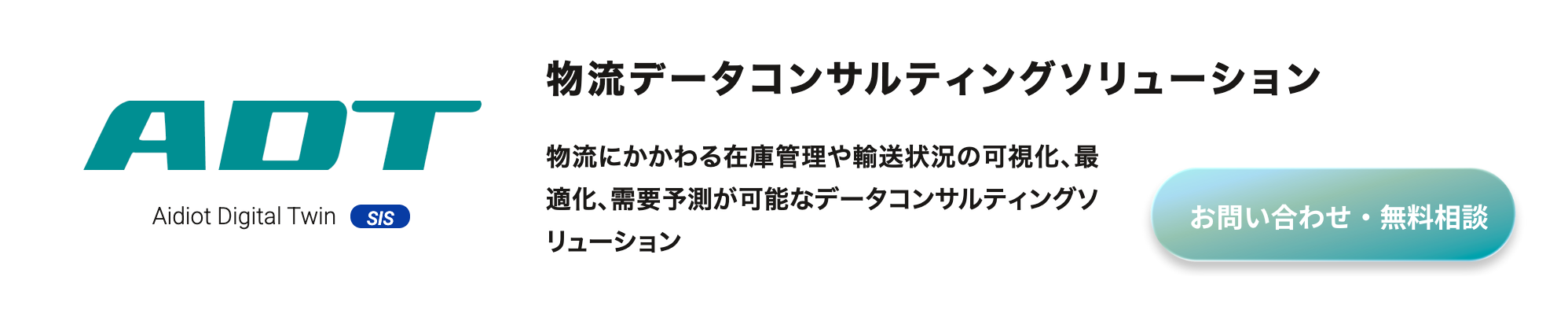物流コストは企業経営において避けて通れない課題ですが、近年は「下げたくても下がらない」という声が増えています。その背景には、燃料費や人件費の上昇といった直接的な要因だけでなく、2024年問題を経て本格化する2026年問題によるドライバー不足や労働規制の影響、再配達やラストワンマイルの非効率といった構造的な要因が複雑に絡み合っています。
本記事では、2025年時点の物流コスト動向を整理し、荷主企業が取るべき実践的な対策をわかりやすく解説していきます。
物流コストとは?基礎から理解する
物流コストは、企業活動の中で製品や商品を「生産地から消費者の手元に届ける」ために発生する費用の総称です。単に「運賃」だけでなく、倉庫での保管や荷役作業、人件費、在庫を持つことによる資金コストまで幅広く含まれるのが特徴です。
物流コストの内訳
物流コストは大きく分けて以下のような要素で構成されます。
1.輸送費
商品の移動にかかる費用で、トラック・鉄道・航空・海上輸送などの手段によって変動します。運賃や燃料費、高速道路料金、ドライバーの人件費もここに含まれます。燃料費や人件費の影響を受けやすく、コストの大部分を占めることが多いです。
2.保管費
倉庫や物流センターでの保管にかかる費用。スペースの賃料、光熱費、管理システムの運用費などが含まれます。長期保管が必要な場合、コストが増加します。
3.荷役費
倉庫内での積み下ろし、ピッキング、仕分けなどにかかる費用で、フォークリフト・自動搬送ロボットの運用費や、作業員の人件費もここに含まれます。自動仕分けシステム導入やフォークリフトの自動化により削減できる可能性があります。
4.梱包、包装費
梱包費は、商品を安全に配送するためのパッケージングにかかる費用で、ダンボール・緩衝材の購入費や、大量の商品を効率的に輸送・保管するためのパレット費用、包装作業の人件費が含まれます。
5.流通加工費
流通加工とは、商品を消費者向けにカスタマイズする作業で発生する費用で、ラベル貼り・値札付け、商品の組み立てやギフト包装、出荷前の検品作業などが含まれます。
6.情報システム費
物流システムの運用や、在庫管理にかかる人件費やITシステムの費用が含まれます。倉庫管理システム(WMS)や、輸送管理システム(TMS)EDI(電子データ交換)などがあります。
物流コストを正しく把握し、最適化することで、企業はコスト削減の正しい対策を取ることが可能です。
▼あわせて読みたい
物流コストを取り巻く最新動向
物流を巡る環境はここ数年で大きく変化し、企業の収益構造や競争力を左右する要因となっています。単純な効率化では吸収できない「構造的なコスト上昇」が進んでおり、その背景を理解しなければ適切な対策は打てません。ここでは、物流コスト上昇の主要な要因を整理しながら、今なぜ物流戦略が経営課題に直結しているのかを解説します。
運賃値上げの背景 ― ドライバー不足と2024年問題
トラックドライバーの高齢化と人材不足は深刻です。2024年4月から施行された働き方改革関連法により、トラックドライバーに時間外労働の上限(年間960時間)が適用されました。長時間労働に依存したこれまでの輸送モデルは維持できなくなった結果、輸送キャパシティが縮小し、運賃の値上げ圧力が高まっています。
▼あわせて読みたい
燃料費・人件費の上昇
世界的なエネルギー価格の変動と、人件費の上昇がダブルで企業の物流費を押し上げています。燃料費は直接的に輸送コストを増加させるだけでなく、倉庫の電力・冷暖房費などにも波及します。
また、物流業界では慢性的な人手不足が続いており、ドライバーだけでなく倉庫作業員の確保も難しくなっています。その結果、人件費の上昇圧力が強まり、単価が上がるだけでなく、採用・教育・定着のための投資コストも増加しています。
輸送力不足による「枠の取り合い」と料金上昇
物流業界でいう「枠」とは、トラックやドライバーが使える配送の時間や車両のキャパシティを指します。
例えば、1日で100台のトラックしか稼働できないのに、120社から配送依頼が来たらどうなるでしょうか?
このとき、依頼をした企業同士で「どの会社がその100台を使えるか」を争うことになります。これが「枠の取り合い」です。
特に繁忙期には、輸送力が需要を満たせず「枠の取り合い」が発生しています。結果として、一部の荷主は通常より高い運賃を支払ってでも輸送枠を確保せざるを得ない状況になります。今後は輸送能力の制約が常態化し、運賃の高止まりが続くと予想されています。
2025年以降の物流コスト見通し
物流コストの上昇は2024年問題をきっかけに表面化しましたが、2025年以降はさらに“構造的な課題”として定着していくと考えられます。
ドライバー不足や規制強化だけでなく、エネルギー価格の不安定化や人件費の高止まりといった外部要因も重なり、企業にとって物流コストは避けられない経営課題になりつつあります。ここでは、最新の試算や市場動向を踏まえ、今後の見通しを整理してみましょう。
国の試算が示す「輸送力14%不足」の現実
国土交通省は「持続可能な物流の実現に向けた検討会」において、2026年度には国内のトラック輸送力が約14%不足するとの試算を示しています。これは単なるコスト上昇にとどまらず、需給の逼迫によって運賃が高騰し、さらに物理的に「荷物が運べない」というリスクが現実のものとなる可能性を意味します。
荷主企業にとっては、納期遅延や欠品による販売機会の損失、さらにはサプライチェーンの分断といった深刻な影響が避けられません。
出典)持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめ
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001626756.pdf
中長期的に物流費が下がりにくい構造的理由
物流コストが今後も下がりにくい背景には、いくつかの構造的な要因があります。
・労働力不足と人件費上昇
ドライバーの高齢化が進み、新規人材の確保も困難になっています。さらに2024年問題で象徴されるように労働時間規制が強化されたことで、1人あたりの稼働時間が減少し、輸送力の制約が強まっています。こうした人材面の制約は人件費の上昇につながり、結果として物流コストを押し上げています。実際、日本ロジスティクスシステム協会の「第24回 物流コスト調査報告書」(2025年4月)によれば、売上高に占める物流コスト比率は2023年度から上昇傾向にあり、2024年度には5.44%と過去最高水準を記録しました。
・燃料・エネルギー価格の不安定化
原油価格の高止まりや為替変動による燃料費の上昇が、直接的に輸送コストへ反映されています。また、環境対応の一環としてEVや水素車へのシフトが進みつつありますが、当面は車両更新に伴う初期投資が短期的なコスト負担となります。
・物流施設や不動産コストの増加
都市部を中心に倉庫需要が高まっており、JLLの「日本の物流施設市場レポート」では、賃料上昇が続いていることが報告されています。これにより、保管コストが上昇し、物流コスト全体を押し上げています。
・ESGや脱炭素対応による投資負担
Scope3排出量削減を求められるなか、企業はモーダルシフトや共同配送、省エネ倉庫の導入など、環境負荷低減の取り組みを加速させています。しかし、これらの施策は短期的には投資負担となり、物流コスト増加の要因となっています。
荷主企業に迫るコスト転嫁と価格競争リスク
・物流事業者からの運賃改定や取引条件の見直し要請
物流事業者からの運賃改定や取引条件の見直し要請は一層強まると見込まれます。背景にあるのは、人件費や燃料費、施設コストの上昇であり、物流事業者がこれらのコスト増を内部で吸収しきれなくなっている結果、荷主企業への価格転嫁圧力が高まっています。
さらに、国土交通省が進める「物流効率化法」の改正により、従来は物流事業者に任されていた効率化の責任が、荷主にも明確に課せられるようになりました。これにより、荷主側も運賃や条件交渉を避けることは難しくなっています。
・価格競争力の低下や顧客離れのリスク
輸送コストの上昇分を商品価格に反映せざるを得ない局面も増えるでしょう。しかし、これはそのまま価格競争力の低下や顧客離れのリスクにつながります。消費者や取引先がコスト上昇を受け入れられない場合、他社にシェアを奪われる可能性が高まるのです。
・契約条件の見直し
契約条件の見直しも避けては通れません。納品リードタイムの延長や時間指定の緩和、荷待ち条件の是正といった調整が求められる場面が増えていきます。こうした取り組みを進めるうえでは、荷主と物流事業者の協働が不可欠です。一方的な負担の押し付けではなく、双方が持続可能な仕組みを構築することが、コスト上昇を吸収しながら競争力を維持する鍵となります。
物流コスト上昇が企業経営に与えるインパクト
近年の物流コストの上昇は、単なる経費の増大にとどまらず、企業経営の根幹を揺るがす要因になっています。輸送費・人件費・エネルギー価格の高止まりはもちろん、2026年問題を背景に輸送力不足も深刻化。これにより、利益構造や供給体制、さらには企業のサステナビリティ戦略にまで影響が及んでいます。ここでは、経営への具体的なインパクトを整理してみましょう。
利益率の圧迫と価格転嫁の難しさ
物流コストの増加は、製造・流通企業にとって直接的に利益率を削る要因です。運賃や倉庫費用が上がっても、すべてを商品価格に転嫁できるわけではありません。特に競争の激しい市場では「値上げ=顧客離れ」のリスクを抱えるため、価格転嫁は難しく、結果として企業内部でコストを吸収せざるを得なくなります。この構造的圧迫が、中長期的な収益性に影を落としています。
納期遅延・欠品による売上損失リスク
物流のひっ迫は、単なるコスト増にとどまらず、納期遅延や欠品発生につながります。ドライバー不足や輸送枠の取り合いにより、必要な時に商品が届かない事態が発生すれば、直接的な売上損失だけでなく、顧客からの信頼低下にも直結します。BtoB取引では契約違反リスク、BtoCでは口コミやリピート率低下といった副次的な影響も無視できません。
ESG・Scope 3対応との関連
さらに注目すべきは、物流コストの上昇がESGやScope 3対応とも密接に結びついている点です。効率の悪い輸送や在庫過多は、余計なCO₂排出を招き、ESG評価を下げるリスクにつながります。一方で、輸配送効率化や在庫の最適化は、コスト削減と同時にScope 3削減の実績にもつながり、持続的成長を目指す企業にとっては経営戦略上の必須課題となっています。
荷主企業が今すぐ取るべき対策
物流コストの上昇と輸送力不足が重なるいま、荷主企業には待ったなしの対応が求められています。単純なコスト削減では限界があり、サプライチェーン全体を見直す「戦略的改善」が必須です。ここでは、すぐに取り組むべき4つの対策を整理します。
積載率・待機時間など輸配送KPIの可視化
輸送力不足の時代において、まず着手すべきは現状把握です。特に 積載率や待機時間といった輸配送のKPIを数値化し、ボトルネックを特定することが重要です。
積載率が低い場合 → 共同配送や貨物シェアリングで改善余地がある
待機時間が長い場合 → 荷役体制や納品予約システムの導入で短縮可能
「感覚的な管理」から「データに基づく管理」へシフトすることで、改善の優先順位を明確にできます。
共同配送・モーダルシフトによる効率化
自社単独での輸配送には限界があります。他社と共同配送を行えば積載率を高められ、コストも分担可能。さらに、鉄道やフェリーを組み合わせるモーダルシフトを取り入れれば、長距離輸送の効率化とCO₂排出削減を両立できます。輸送枠不足の中では、いかにリソースをシェアし合うかが鍵となります。
在庫戦略・拠点再配置による物流負荷の平準化
需要変動が大きい中で、在庫を一点集中させるのはリスクです。需要地に近い拠点に在庫を分散配置することで、配送距離を短縮しつつ欠品リスクも低減できます。拠点再配置は大きな投資を伴いますが、中長期的には物流負荷を平準化し、持続的なコスト削減に直結します。
物流DXによるコスト構造改革
短期的なコスト削減だけでなく、構造的に強い物流体制を築くためにはDXが不可欠です。
・AIによる配車・ルート最適化 → 輸送効率を高め燃料・人件費を削減
・IoTによるリアルタイムモニタリング → 積載率・稼働率の改善
・倉庫自動化・ロボティクス → 荷役の効率化、人材不足リスクの緩和
こうしたテクノロジーの導入は初期投資が必要ですが、中長期的には物流コストを吸収する競争力の源泉となります。特に、リアルタイムデータをもとにした意思決定は、コスト削減だけでなくサービス品質の維持にもつながります。
まとめ|待っていても物流コストは下がらない
本記事では、2025年以降の物流コストが下がりにくい背景と、その構造的な理由について解説しました。
ドライバー不足や規制強化、燃料費や人件費の上昇、さらには輸送力不足による「枠の取り合い」など、複数の要因が複雑に絡み合っているため、コストは自然に下がるどころか、むしろ高止まりする傾向にあります。
こうした状況下で、企業が取るべき姿勢は「待つ」ことではなく「動く」ことです。輸配送の効率化や共同配送、在庫戦略や拠点再配置といった施策を通じて、コストを戦略的にコントロールする必要があります。また、物流DXの活用によって、データに基づいた意思決定やリアルタイムな最適化を進めることも欠かせません。
物流は単なるコスト要素ではなく、企業の競争力そのものを左右する戦略領域です。待っていても状況は改善しません。CLOを中心に経営全体で取り組むことで、持続可能なサプライチェーンと安定した企業経営を実現することができるでしょう。
データから未来を予測するサービス「ADT」で物流自動化を実現!
「ADT」とはアイディオットデジタルツインのことで、物流に関わる在庫管理や配送などのデータをリアルタイムで可視化・分析するシミュレーターです。このツールは、数十種類のデータセットを集約し、物流業務の最適化と効率化を支援します。膨大なデータを用いて行うため、限りなく現実に近いシミュレーションをすることができます。
「ADT」では、可視化、シミュレーション、物理空間の実装が可能です。「ADT」を利用し、物流での自動化をシミュレーションし、車両情報の可視化や人員のシミュレーションなどにより、いきなり行う危険性を減らし、スムーズな物流自動化に踏み出すことができます。
お問い合わせはこちら