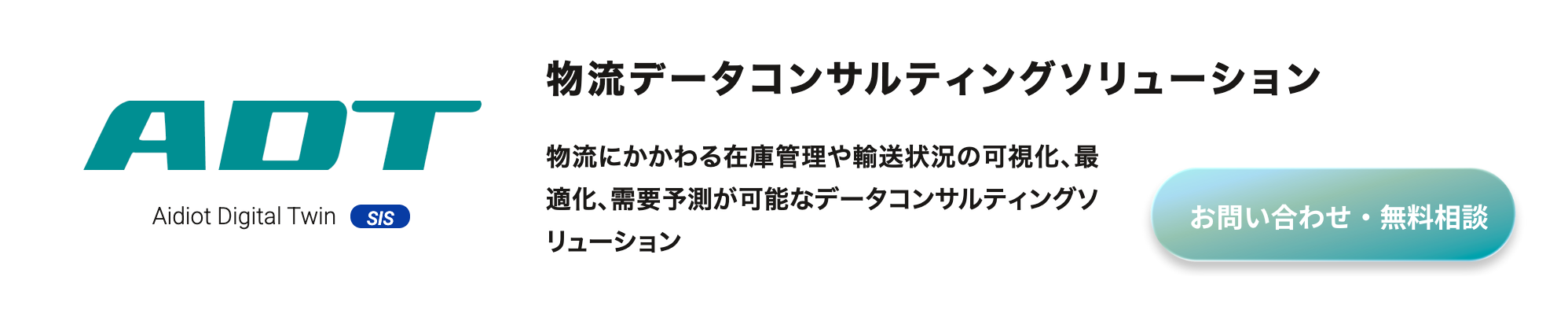はじめに
「2024年問題」は、物流業界に大きなインパクトを与えました。しかし、それは終点ではなく、むしろ始まりにすぎません。ドライバー不足は解消されず、輸送力不足は今後さらに深刻化し、国の試算では 2026年度には約14%の輸送力が不足 すると見込まれています。いわゆる「物流危機2026」です。
この流れの中で、荷主企業にとって見過ごせないのが 物流改正法です。改正法では、単に物流事業者に任せるのではなく、荷主も協力して積載率向上や待機時間削減に取り組む責任 が明確化されました。つまり、物流効率化は「選択肢」ではなく「義務」となりつつあります。
もし対応が遅れれば、「納期遅延や欠品による顧客離れ」「輸送コスト急騰による利益圧迫」「サプライチェーン断絶による事業リスク」といった事態が現実のものとなります。
本記事では、なぜ物流改革が進まないのかを整理しつつ、物流改正法が荷主企業に突きつける新たな義務と責任を解説します。そして、企業が今すぐ取り組むべき具体的な対処法をご紹介します。
2024年問題は「始まり」にすぎない
2024年4月、トラックドライバーの時間外労働時間が「年間960時間」に制限されました。これは物流業界にとって大きな転換点であり、輸送力が1〜2割減少すると言われています。すでに「希望通りの出荷枠が取れない」「納期調整を余儀なくされる」といった影響が現場で出始めています。
しかし、この「2024年問題」は終点ではありません。むしろ本当の危機の入口に過ぎないのです。
ドライバー不足は解決していない
若手のなり手不足と高齢化で、トラックドライバー人口は年々減少。2024年の規制は、それをさらに加速させる要因に。
輸送力不足は今後さらに拡大
国土交通省・経産省の試算では、2026年度には約14%の輸送能力不足が発生すると予測されています。
荷主企業にしわ寄せが直撃
希望する便が確保できない、物流コストが高騰する、納期を守れない。こうしたリスクは事業継続そのものを揺るがしかねません。
つまり、2024年問題は「物流危機2026」へとつながるプロローグにすぎないのです。
▼あわせて読みたい!
物流危機が企業経営に与えるインパクト
物流危機は、単なる現場の輸送課題にとどまりません。企業の売上・利益・信用・持続可能性を揺るがす重大な経営リスクです。ここでは、具体的にどのような影響が生じるのかを見ていきましょう。
納期遅延と取引先からの信頼低下
輸送枠が確保できず納期が守れない場合、直接的に顧客満足度が下がります。特にBtoB取引では「安定供給」が契約条件に組み込まれているケースも多く、繰り返し遅延が発生すれば取引先からの信用失墜 → 取引縮小や契約解除に発展しかねません。
物流コスト高騰による利益圧迫
ドライバー不足や燃料価格上昇に伴い、今後も運賃は上昇基調にあります。さらに輸送力が限られる中で「高い料金でも輸送枠を確保する」動きが強まれば、物流費は企業の経営を圧迫する固定費として重くのしかかります。
販売価格への転嫁が難しい業種では、利益率低下 → 収益構造の悪化につながります。
在庫リスクとサプライチェーン不安定化
輸送の遅延を恐れて在庫を積み増すと、保管コストや廃棄リスクが拡大します。逆に在庫を絞りすぎると、配送遅延による欠品・販売機会損失を招きます。
結果として、サプライチェーン全体の安定性が揺らぎ、BCP(事業継続計画)にも支障をきたします。
ESG・Scope 3対応への悪影響
物流効率が低下すれば、CO₂排出量は増加します。企業の温室効果ガス排出量の大半を占めるのはScope 3(サプライチェーン全体)であり、効率化を怠ることは、脱炭素経営の遅れ=企業価値の毀損につながります。
取引先や投資家からの評価にも直結するため、物流危機はESG経営の重要課題でもあるのです。
以上のように、物流危機は、多方面で経営に打撃を与えます。
つまり、「モノが運べない」という状況は単なる物流部門の問題ではなく、企業全体の競争力に直結するリスクなのです。
物流改正法が迫る新たな義務と責任
2023年に改正された物流改正法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律)は、これまでの法制度の中でも大きな転換点です。従来は物流事業者に対して効率化の努力義務が求められていましたが、今回の改正では荷主企業も含めたサプライチェーン全体の協働が強く打ち出されました。
積載率向上と待機時間削減の義務化
物流改正法では、トラック輸送の効率化を目的に、以下のような取り組みが求められています。
・積載率の向上:共同配送、積み合わせ輸送などを通じ、空車走行や低積載率を減らす。
・待機時間の削減:荷待ち・荷役時間を短縮し、ドライバーの労働環境を改善。
これらはもはや「任意の改善」ではなく、国が数値目標を掲げて推進する政策課題となっています。
荷主に課される協力責任
改正法の重要なポイントは、荷主企業も効率化に協力する義務が明確化されたことです。
具体的には、
・不合理な発注や過剰な納品頻度の是正
・荷待ち・荷役作業の削減に向けた出荷体制の改善
・配送効率化に資する情報提供(在庫情報や出荷計画の共有)
といった行動が荷主に求められています。
つまり、物流事業者に「効率化を任せる」だけではなく、荷主側が社内オペレーションや商慣習を見直すことが不可欠になっています。
KPI可視化と法令遵守の関係
法令対応を形式的に済ませるのではなく、実態を数値で把握し、改善を証明できることが今後重要になります。
「積載率」「待機時間」「CO₂排出量(Scope 3算定にも直結)」
これらのKPIを可視化し、定期的にモニタリングすることで、法令遵守の裏付けとなるだけでなく、社内外に対して「効率化に取り組んでいる」ことを示す証拠にもなります。
物流改正法は、荷主企業にとって、「物流は委託先の課題」ではなく「自社の責任」であることを突きつけています。
「積載率向上」「待機時間削減」「KPI可視化」
これらを進めることは、単なる法対応にとどまらず、サプライチェーン全体の競争力を高める取り組みでもあります。
▼あわせて読みたい!
なぜ物流改革が進まないのか
物流の効率化や改革が必要であることは、多くの企業が理解しています。それにもかかわらず、大きな進展が見られないのはなぜでしょうか。背景には、複数の要因が絡み合っています。
荷主と物流事業者の温度差
荷主は「輸送力不足=経営リスク」として危機感を抱いています。一方で物流事業者は「人手不足や日々の配送維持」で精一杯であり、長期的な視点に立ちにくいのが実情です。この危機感と現場課題のギャップが、改革の議論をかみ合わせにくくしています。
短期コスト優先で投資が先送りされる構造
物流改革には、TMS(輸配送管理システム)やWMS(倉庫管理システム)、自動化設備など一定の投資が必要です。しかし荷主は「物流コストの削減」を優先し、物流事業者は「投資余力が乏しい」ため、短期的なコスト負担を嫌って先送りされがちです。結果として、必要性は理解していても改革が具体化しません。
データ不足・可視化の遅れ
積載率や待機時間といったKPIは、現場にデータが偏在しています。荷主は全体像を把握できず、物流事業者も情報共有に十分な仕組みを持たない場合が多いのが現状です。データに基づいた議論ができないため、改革の根拠や効果測定が不十分になり、取り組みが進みません。
サプライチェーン全体での合意形成の難しさ
効率化のためには、複数の荷主や物流事業者、さらには倉庫業者が協力する必要があります。しかし「誰がコストを負担するのか」「どこがメリットを享受するのか」で利害が衝突しやすく、全体最適の取り組みが実現しにくいのが実態です。
人材・リソース不足
物流事業者では改革を推進する人材が不足しており、現場は日々の配送維持で手一杯です。荷主側も物流専門部門が小さい企業が多く、戦略的に物流をマネジメントする人材が不足しています。結果として「やるべきことは分かっているが、動かせる人がいない」という状況に陥っています。
以上のように、物流改革が進まないのは、様々な構造的な要因が絡み合っているためです。この壁を越えるには、データに基づく共通認識の形成、荷主・物流事業者の協働、そして長期的視点での投資判断が欠かせません。
企業が今すぐ取るべき対処法
物流危機は避けられない将来ではなく、すでに進行中の現実です。荷主企業は「物流は委託すれば済むこと」ではなく「経営課題」と捉え、直ちに行動を起こす必要があります。以下では、すぐに着手すべき具体的な対処法を整理します。
積載率・待機時間のKPI可視化
輸送効率の改善は、現状を「見える化」することから始まります。
・IoTセンサーやGPSで車両・積載状況を把握
・TMS(輸配送管理システム)で運行データを集約
・BIツールで積載率や待機時間をダッシュボード表
可視化は改善の出発点であり、物流改正法への対応にも直結します。
▼あわせて読みたい!
共同配送・モーダルシフトの推進
自社単独では輸送効率に限界があります。
・近隣企業や同業他社と連携した共同配送
・トラック依存を減らすモーダルシフト(鉄道・船舶利用)
を進めることで、輸送力不足を補い、CO₂削減にもつながります。
▼あわせて読みたい!
在庫戦略・拠点再配置の見直し
物流危機は在庫戦略そのものの見直しを迫ります。
・過剰在庫を防ぎつつ欠品リスクを抑える適正在庫の設計
・消費地に近い物流拠点の再配置
・発注ロットや納品頻度の調整による輸送負荷の平準化
サプライチェーン全体での最適化が不可欠です。
▼あわせて読みたい!
物流DXの活用
デジタル技術は、効率化と最適化の強力な武器です。
・AI需要予測で出荷波動を平準化
・自動配車システムで積載効率を最大化
・WMS(倉庫管理システム)と連携して在庫と輸配送を一体管理
DXは「物流部門の効率化」にとどまらず、経営全体の意思決定スピード向上にもつながります。
物流事業者とのパートナーシップ強化
短期的なコスト交渉だけでは、持続的な物流は成り立ちません。
・長期契約による安定的な輸送力確保
・改善プロジェクトを共同で推進
・データ共有による透明性のある協力関係
これらを築くことが、企業の「物流リスク耐性」を高めます。
企業が今すぐ取るべき対処法は、可視化(KPIの把握)、協働(共同配送・モーダルシフト)、最適化(在庫・拠点戦略)、DX活用(AI・TMS・WMS導入)、パートナーシップ(物流事業者との協力強化)という5つのステップに整理できます。
これは単なる「コスト削減策」ではなく、経営リスクの回避と競争力強化の両立に直結する戦略です。
データから未来を予測するサービス「ADT」で物流自動化を実現!
「ADT」とはアイディオットデジタルツインのことで、物流に関わる在庫管理や配送などのデータをリアルタイムで可視化・分析するシミュレーターです。このツールは、数十種類のデータセットを集約し、物流業務の最適化と効率化を支援します。膨大なデータを用いて行うため、限りなく現実に近いシミュレーションをすることができます。
「ADT」では、可視化、シミュレーション、物理空間の実装が可能です。「ADT」を利用し、物流での自動化をシミュレーションし、車両情報の可視化や人員のシミュレーションなどにより、いきなり行う危険性を減らし、スムーズな物流自動化に踏み出すことができます。
お問い合わせはこちら
まとめ〜物流危機をチャンスに変える発想〜
2024年問題を契機に始まった輸送力不足は、2026年以降さらに深刻化すると見込まれています。物流改正法によって荷主企業にも協力責任が明確に課され、物流はもはや「委託先任せ」で済む時代ではなくなりました。
一方で、この危機は単なるリスクにとどまりません。取り組み次第で、企業にとって大きな成長機会へと変えることができます。
・効率化によるコスト競争力の強化
積載率向上や待機時間削減は、直接的なコスト削減につながります。物流効率が高い企業は、それ自体が競争優位の源泉になります。
・脱炭素・ESG経営との相乗効果
共同配送やモーダルシフトはCO₂削減効果を持ち、Scope 3対応として投資家や取引先からの評価を高めます。物流効率化は「環境対応」と「事業成長」を両立させる手段でもあります。
・データ活用による経営高度化
KPIを可視化し、サプライチェーン全体を最適化する仕組みは、経営の意思決定を迅速かつ的確にします。物流DXは単なる現場改善にとどまらず、企業全体の競争力を底上げします。
物流危機は確かに避けがたい現実ですが、それを「守りの負担」と見るか、「攻めの戦略」と見るかで、未来は大きく変わります。今こそ、荷主企業は物流を「外注コスト」ではなく、経営戦略の中核として再定義する必要があります。
その第一歩は、現状を見える化し、物流パートナーと協働することから始まります。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。