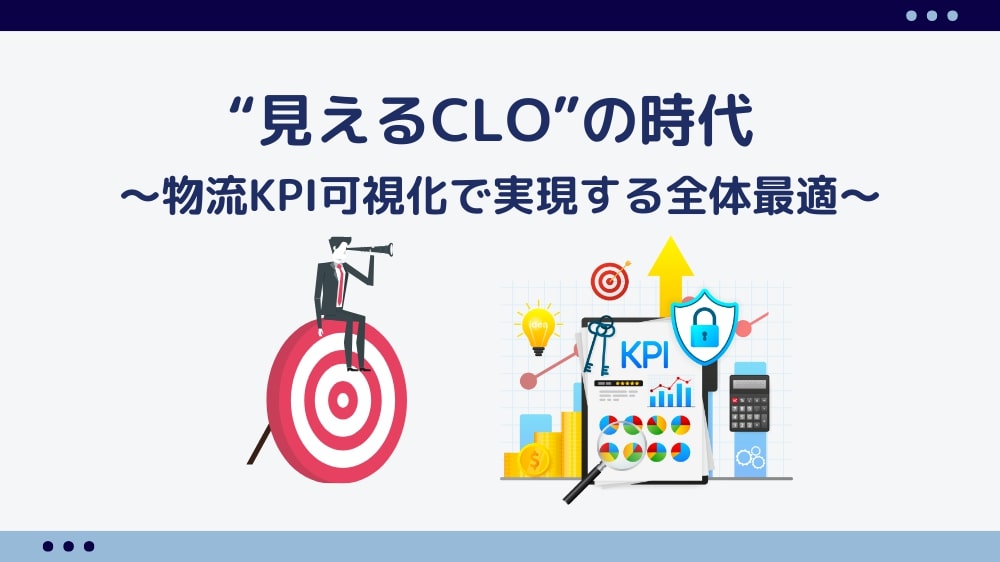
「物流は見えているか?」――2026年問題を目前に、CLO(Chief Logistics Officer)に突きつけられているのはこの問いです。ドライバー不足、輸送コスト高騰、脱炭素のプレッシャー。もはや勘や経験だけでは、複雑化したサプライチェーンをコントロールできません。
今、注目を集めているのが物流KPIの可視化。配送リードタイム、在庫回転率、納期遵守率、CO₂排出量といった指標を“見える化”し、リアルタイムで意思決定につなげることで、企業は初めて「部分最適」から「全体最適」へと舵を切ることができます。
本記事では、CLOがどのようにして“見えるCLO”へと進化し、物流危機をチャンスへ変えているのかを探っていきます。
▼CLOについてはこちらをチェック
CLOが管理すべき物流KPIとは
物流現場には数多くのKPIが存在しますが、CLOが特に注目すべきは「全体最適」に直結する指標です。中でも積載率・荷待ち時間・荷役時間の3つは、サプライチェーン全体の効率化を測るうえで欠かせません。
1. 積載率
積載率は、トラックやコンテナといった輸送リソースをどれだけ有効活用できているかを示す指標です。積載率が低ければ、それだけ空気を運ぶことになり、コストとCO₂排出が増加します。逆に高積載を実現すれば、輸送効率の改善・コスト削減・環境負荷低減の三拍子を同時に達成可能です。CLOにとっては「積載率をどの水準で維持すべきか」を経営課題として設定することが重要です。
▼あわせて読みたい!
2. 荷待ち時間
トラックドライバーが工場や倉庫で待機する時間は、労働生産性を直接的に下げる要因です。2024年問題によりドライバーの労働時間規制が強化された今、荷待ち削減は輸送キャパシティ確保の生命線といえます。可視化されたデータをもとに「どの拠点で、どの時間帯に、どれだけ待機が発生しているか」を把握することは、現場改善にとどまらず、取引先との交渉材料にもなります。
▼あわせて読みたい!
3. 荷役時間
荷役時間は積み下ろし作業の効率を示すKPIです。作業に時間がかかれば、その分トラックの回転率が下がり、輸送全体のスループットが低下します。倉庫内の動線設計や設備投資、さらにはデジタルツインを活用したシミュレーションによって改善が可能です。CLOは荷役時間を「ボトルネックの見える化」指標として捉え、全体最適の観点から改善に取り組むべきでしょう。
▼あわせて読みたい!
KPI可視化のメリット
物流現場のKPIを可視化することは、単なる“数字管理”にとどまりません。CLOが全体最適を実現するうえで、次のような具体的な効果を生み出します。
1. 現場の改善ポイントを即時発見
従来は、荷待ちや荷役に関するデータを集計するのに数日かかり、その間に改善機会を逃してしまうケースも少なくありませんでした。可視化されたダッシュボードがあれば、
「どの拠点で積載率が低いのか」
「どの時間帯に荷待ちが発生しているのか」
をリアルタイムで把握可能です。これにより、現場責任者は即座に人員配置を見直し、CLOは経営レベルでのリソース最適化判断を下せます。
2. 荷主と物流事業者間の情報ギャップ解消
荷主と物流事業者の間では、「なぜ遅延が発生したのか」「どのコストが増えているのか」といった点で認識がずれることがあります。KPIを共通指標として可視化することで、“共通言語”に基づいた対話が可能になります。
3. 改善施策の効果検証を迅速化
施策を実行した後の効果検証も、KPIの可視化によって飛躍的にスピードアップします。豊田通商では、トラック予約システム導入後に「待機時間が60分から20分に短縮」したことをデータで即座に確認でき、追加拠点への展開判断が迅速に行われました。
改善活動が“トライ&エラー”ではなく“データドリブンのPDCA”に進化することは、CLOの戦略立案に直結します。
可視化を成功させる3つの条件
KPI可視化の取り組みは、単にダッシュボードを導入すれば成果が出るわけではありません。CLOが全体最適を実現するためには、以下の3つの条件を満たすことが不可欠です。
1. 物流情報標準ガイドラインに準拠したデータ連携
拠点や取引先ごとに異なるフォーマットのデータをつなぎ合わせるのでは、比較や統合ができず、可視化の効果は半減します。国交省が推進する「物流情報標準ガイドライン」に準拠することで、輸送計画・在庫データ・受発注情報を共通ルールで扱えるようになり、荷主と物流事業者の間で一貫したKPI管理が可能になります。実際に、大手メーカーや小売業では標準ガイドラインを踏まえたデータ連携基盤を整備し、共同輸送や在庫一元管理に活用しています。
2. リアルタイム性と自動更新
「昨日のデータ」ではなく「今この瞬間の状況」を捉えられるかが、CLOの意思決定を左右します。IoTやクラウド基盤を活用し、トラックの積載状況や荷待ち時間を自動更新する仕組みが整えば、現場の改善だけでなく、経営層が即時にシナリオを描くことが可能です。
3. 経営層・現場双方が理解できる指標表示
可視化ツールは「誰のためのものか」を意識しなければ形骸化します。経営層には投資対効果やCO₂削減効果を、現場には作業生産性や待機時間といったオペレーションに直結する指標を。それぞれが自分の言葉で理解できる形で表示することが重要です。
AI×可視化でCLOの業務はこう変わる
KPI可視化の次なる進化は、AIとの融合です。AIは膨大なデータをもとにパターンを学習し、従来は人間の経験に依存していた意思決定を「自動化」または「高度化」します。CLOの業務は、AI×可視化によって以下のように変革していきます。
1. 改善シナリオの自動生成
従来の改善活動は、現場の経験や試行錯誤に基づいて行われてきました。AIを活用すれば、「荷待ち時間を30%削減するにはどの施策が有効か」といった改善シナリオを自動で提示できます。例えば、需要予測と出荷調整をAIが自動提案し、輸送コストを削減することが可能になります。
CLOは結果を評価・選択する立場にシフトし、現場のトライ&エラーにかかる時間と負担を大幅に削減できます。
2. 配車・拠点配置の最適化
配車や拠点配置は物流コストとサービスレベルを左右する最重要テーマです。AIはリアルタイムの受注データや交通情報をもとに、最適なルートや拠点間のバランスを導き出します。CLOは、従来の“手作業での最適化”から“AIによる戦略設計の監督”へと役割が進化していきます。
3. CO₂削減効果のシミュレーション
サステナビリティ経営において、CO₂削減は避けて通れません。AIとデジタルツインを連携させれば、「もし共同配送を実施したらCO₂排出量は何%減るのか」といったシミュレーションが可能になります。
CLOは、改善の成果を「環境指標」として定量化し、経営層や投資家に示すことができるようになります。
データから未来を予測するサービス「ADT」で物流自動化を実現!
「ADT」とはアイディオットデジタルツインのことで、物流に関わる在庫管理や配送などのデータをリアルタイムで可視化・分析するシミュレーターです。このツールは、数十種類のデータセットを集約し、物流業務の最適化と効率化を支援します。膨大なデータを用いて行うため、限りなく現実に近いシミュレーションをすることができます。
「ADT」では、可視化、シミュレーション、物理空間の実装が可能です。「ADT」を利用し、物流での自動化をシミュレーションし、車両情報の可視化や人員のシミュレーションなどにより、いきなり行う危険性を減らし、スムーズな物流自動化に踏み出すことができます。
お問い合わせはこちら
まとめ〜見える化はCLOの最強武器〜
物流クライシスが目前に迫るなか、CLOに求められるのは「全体最適を描く力」です。その羅針盤となるのが、物流KPIの見える化です。
積載率、荷待ち時間、荷役時間といった基本KPIを起点に、改善の芽を即座に見つける。荷主と物流事業者の認識ギャップを埋め、共通言語で議論を進める。さらにAIを組み合わせることで、改善シナリオの自動生成やCO₂削減シミュレーションまで可能になる。
可視化は、単なるダッシュボードではありません。CLOが経営と現場をつなぎ、企業の競争力を根底から高めるための“最強武器”です。数字を見て終わるのではなく、数字を未来の戦略に変える。その時、CLOは物流危機を乗り越えるだけでなく、企業の成長をリードする存在となるでしょう。

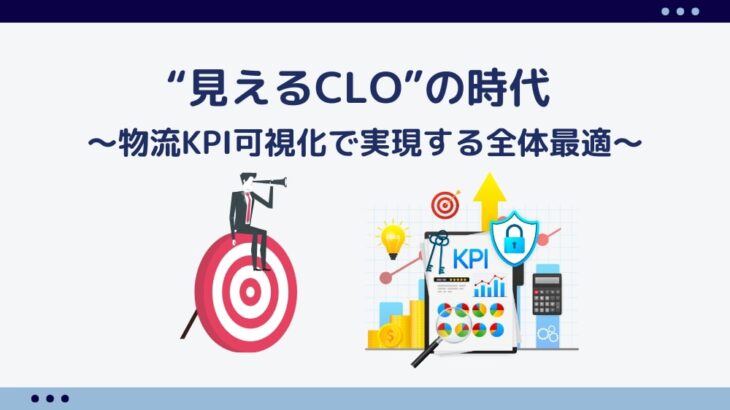

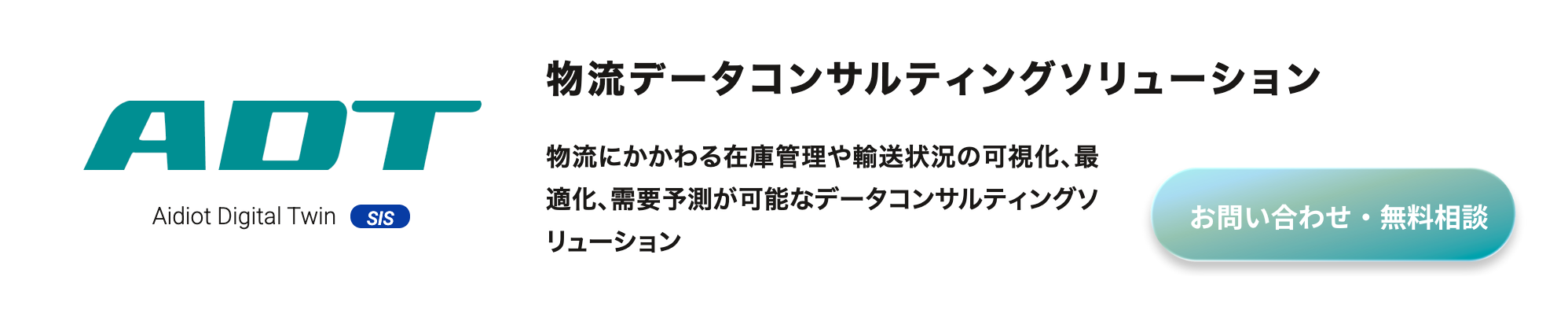

 Aidiot編集部
Aidiot編集部





