 労働時間規制や燃料費高騰、ドライバー不足など、物流現場を取り巻く課題は年々深刻化しています。2026年問題を見据えれば、部分的な効率化ではもはや間に合わず、サプライチェーン全体を視野に入れた抜本的な変革が急務です。特に、物流戦略を統括するCLOには、デジタル技術を武器にした「物流DX」の推進が求められます。
労働時間規制や燃料費高騰、ドライバー不足など、物流現場を取り巻く課題は年々深刻化しています。2026年問題を見据えれば、部分的な効率化ではもはや間に合わず、サプライチェーン全体を視野に入れた抜本的な変革が急務です。特に、物流戦略を統括するCLOには、デジタル技術を武器にした「物流DX」の推進が求められます。
本記事では、CLOが着手すべき3つの改革について、実行のポイントや期待できる効果を具体的に解説します。効率化と競争力強化を同時に実現するための道筋を、今こそ描き直すときです。
はじめに
CLOは企業における物流・サプライチェーン全体の戦略と実行を統括する最高責任者のことを指します。
2024年5月に改正された「物流効率化法」により、2026年4月からは、一定規模以上の荷主企業がCLOを選任することが義務付けられました。
ここで重要になるのが、物流戦略の中枢を担うCLOの視点改革です。現場の効率化にとどまらず、経営全体を俯瞰して意思決定を行うリーダーシップが求められています。
▼あわせて読みたい!
物流の限界が迫る今、CLOに問われる“3つの視点改革”とは
2026年問題と物流の構造的ひっ迫
2026年問題は、特定荷主に対する物流効率化の義務化であり、荷主企業の物流管理体制や業務プロセスの見直しが求められます。2026年には都市部配送の集中や再配達の増加といった既存の課題と結びつき、「運べない」リスクが急増します。単にトラックを増やす、倉庫を建てるといった対症療法では、根本的な解決は望めません。
単なるデジタル化では不十分、全体最適が鍵
WMS(倉庫管理システム)やTMS(輸配送管理システム)、そして配送ルートのAI最適化など、現場業務の効率化を狙ったデジタル施策は確かに成果を生みます。しかし、それらはあくまで“部分最適”の域を出ません。現場単位の改善だけでは、輸送コストが下がっても在庫コストが跳ね上がる、拠点効率が上がってもリードタイムが延びるなど、別の箇所で歪みが生じやすくなります。
全体最適とは、輸送・在庫・拠点・人員・発注量といった複数の要素を、企業全体のサプライチェーン戦略として再設計することです。
例えば、配送ルートを短縮するために拠点を新設する場合、その立地は輸送効率だけでなく、在庫回転率やBCP(事業継続計画)、将来の需要変動まで踏まえて決定する必要があります。
CLOの役割は「現場管理」から「経営戦略」へ
これまで多くの企業では、CLOは倉庫や輸配送の現場オペレーションを円滑に回す責任者としての色合いが強く、経営会議では“コスト報告”が主な役割というケースも少なくありませんでした。ですが、2026年問題をはじめとする構造的な物流危機を前に、企業競争力を維持するにはこの位置づけを大きく変える必要があります。
これからのCLOに必要な役割は、調達・営業・IT・財務と横断的に連携し、サプライチェーン全体を俯瞰した意思決定を担うことです。例えば、営業と連動して需要変動に即応できる在庫戦略を組み立てたり、IT部門と協力してWMS/TMSやAI分析基盤を全社最適で導入したり、財務とともに物流投資のROIを定量的に示し、経営判断を後押しすることが求められます。
第1の改革:拠点改革
市場の変化や人手不足、配送制約の強化によって、これまでの物流拠点のあり方は限界を迎えています。単に「倉庫を増やす」「拠点を減らす」といった単発施策では、もはや持続的な改善は見込めません。DXが進む今こそ、拠点の立地・役割・連携を戦略的に見直す“拠点改革”がCLOに求められています。ここでは、最適立地の考え方から拠点配置の判断軸、そして庫内業務の高度化まで、実践的な視点で整理します。
DX時代の“最適立地”とは何か
最適立地は「安い土地」や「既存拠点の延長線」で決めるものではありません。
輸送距離・時間:主要需要地までのアクセスの速さと安定性
労働力確保:人材市場の規模と採用競争の状況
BCP(事業継続計画):自然災害や交通障害への耐性
需要変動対応力:シーズナリティや販促期への柔軟性
これらを総合評価し、WMSや需要予測AIによるシミュレーションを活用することで、事業成長とコスト効率を両立できる立地を導き出します。
集約 vs 分散の意思決定基準
集約型は在庫集約や輸送効率向上に強みがありますが、災害時の供給リスクや一極集中による負荷増が懸念されます。
分散型は災害リスク分散やリードタイム短縮で有利ですが、拠点間の調整や在庫過多に注意が必要です。
意思決定の軸は、
1.リードタイム許容範囲
2.需要変動の特性(地域性・季節性)
3.リスク発生時の影響範囲
4.在庫・輸送コストのトータルバランス
以上の4つです。経営戦略と照らし合わせた「将来像」も視野に入れることが重要です。
庫内業務の可視化と連携強化(WMS・IoT活用)
立地や拠点数を最適化しても、庫内作業が属人化していては効果が限定的です。
・WMS導入で入出庫・在庫状況・作業進捗をリアルタイムに把握
・IoT活用で作業負荷や設備稼働状況を可視化
・データ共有で他拠点のベストプラクティスを横展開
これにより、拠点間の連携が強化され、全体最適なオペレーションが実現します。
▼あわせて読みたい!
第2の改革:在庫改革
需要変動の激化やサプライチェーンの複雑化により、在庫は「多ければ安心、少なければ効率的」という単純な話では済まなくなっています。過剰在庫は保管費や廃棄ロスを押し上げ、一方で欠品は売上機会を失い顧客満足度を下げます。
CLOが向き合うべきは、この“持たないリスク”と“過剰のコスト”の狭間で、在庫を常に最適な水準に保つための改革です。ここでは、その実践的アプローチを3つの観点から整理します。
在庫のブラックボックスを可視化する
多くの企業では、「どこに」「何が」「どれだけ」あるのかがリアルタイムでわからない状態が続いています。例えば、A倉庫にはあるはずの商品が実際には足りなかったり、逆にB倉庫に大量に眠っていたり──こうした在庫の“見えない”状態を「ブラックボックス化」と呼びます。
WMS(倉庫管理システム)や在庫可視化ツールを導入し、すべての拠点の在庫データを一元化します。リアルタイムで在庫数や所在、動きがわかれば、補充や移動の判断が即座にでき、余分な在庫や欠品のリスクを大幅に減らせます。
データに基づく「在庫配置戦略」
在庫の配置は、単に全体量を増減するだけでは不十分です。大切なのは、「どの拠点に」「どの商品を」「何日分」置くかを、数字とデータを根拠にして決めることです。
1.需要の集中度
地域別・季節別・キャンペーン時期ごとの需要変動を把握します。たとえば、夏に売れる飲料を寒冷地に多く置いても回転率は落ちます。
2.サービスレベル
「どこまで欠品を許容するか」「納期は何日以内か」といった条件を明確にします。これによって、安全在庫の基準が決まります。
3.輸送コストとのトレードオフ
在庫を分散させれば納期は短縮できますが、輸送コストが上がることも。逆に拠点を集約するとコストは下がる一方、配送リードタイムが延びる可能性があります。
これらの要素を分析し、「過剰在庫によるムダ」と「欠品による販売機会損失」の両方を防ぐ配置計画を作ることが目的です。数値化された配置戦略があれば、状況の変化にも迅速に対応でき、在庫コストを最適化できます。
需要予測・自動補充・多拠点在庫の統合管理
在庫改革を継続的に機能させるには、自動化と統合管理が不可欠です。
需要予測AI:過去データと外部要因(天候・イベント)を加味して精度を向上
自動補充システム:設定した在庫水準を下回ると自動発注
多拠点統合管理:全拠点の在庫を仮想的に一体化し、最適拠点から出荷
これらにより、在庫の偏在や“売れる場所に商品がない”という機会損失を減らすことができます。
第3の改革:輸配送改革
トラックドライバー不足や燃料高騰、荷量の波動化により、輸配送の「実車率70%」はもはや限界値に近づいています。空車や部分積載が続けば、コストは右肩上がりで利益を圧迫し続けます。これからのCLOに求められるのは、既存の運び方を前提に改善するのではなく、データ・ネットワーク・パートナーシップを活かして新しい“動かし方”を設計することです。
配送データとAIルート最適化
ルート設定や配送順序の最適化は、もはや勘や経験だけでは限界です。GPSや配送実績データを蓄積し、AIがリアルタイムで交通状況・積載率・納品時間を考慮して最適ルートを提案する仕組みが不可欠です。これにより、同じ車両・同じ人員でも走行距離を減らし、燃料と時間の両方を削減できます。
共同配送・混載・マッチングの高度化
単独配送からの脱却は、今後の標準戦略です。複数企業での共同配送や異業種間の混載便は、積載率向上と環境負荷低減の両立が可能です。さらに、AIマッチングプラットフォームを使えば、リアルタイムで“空きスペース”と“積みたい荷物”を結びつけ、空車回送をほぼゼロに近づけることも可能です。
物流会社との共創モデル構築(Win-Win発注)
発注者と物流会社の関係を「単なる委託」から「共創」へと変えることも重要です。配送効率や積載率の改善に伴うコスト削減を成果配分型でシェアする契約や、長期的な物量保証による安定稼働支援など、双方にメリットがあるスキームを設計することで、パートナーシップが強固になります。
全体最適こそがCLOの仕事
物流コストの高騰や人手不足、需要変動の激化。こうした環境下で、CLOに求められる役割はかつてないほど大きくなっています。現場の改善や一部工程の効率化だけでは、企業全体の競争力を守れない時代です。
必要なのは、サプライチェーン全体を俯瞰し、輸送・在庫・拠点・情報の流れを一体として設計し直す「全体最適」の視点。コスト削減とサービス品質の両立はもちろん、企業戦略に直結する物流をどう作り上げるか。その舵取りこそが、今のCLOの核心的な仕事です。
部分最適の落とし穴を知る
部署や拠点単位での効率化は、一見成果が出やすく見えますが、全体では逆効果になることがあります。例えば、配送コスト削減のために拠点を集約すると、納期が延びて販売機会を失う可能性があります。CLOは、全体視点での「影響範囲」を見抜き、単発の施策がどこに波及するかを読み解く力が必要です。
サプライチェーン全体のKPIを設計する
在庫回転率や実車率といった指標だけではなく、コスト・品質・納期を横断的に管理するKPI設計が不可欠です。部署ごとではなく、全社共通の指標を持つことで、部門間の最適化の衝突を防ぎ、意思決定のスピードも高まります。
データ連携基盤で意思決定を加速する
全体最適は、感覚や経験だけでは成立しません。WMS、TMS、ERP(企業資源計画)などのシステムを連携させ、リアルタイムで輸送・在庫・需要のデータを可視化することが重要です。これにより、需要変動やトラブル時にも迅速な判断が可能になります。
全社的な合意形成と文化づくり
全体最適の最大の壁は、部門間の利害調整です。CLOは調達・営業・製造・IT・財務といった部門と対等に対話し、「物流はコスト削減のためだけでなく価値を生み出す領域」という認識を共有する役割も担います。
おわりに
物流を取り巻く環境は、これまでの延長線上では通用しない局面に突入しています。単発の効率化や部分最適では、コスト上昇とサービス低下の悪循環を断ち切ることはできません。いま必要なのは、サプライチェーン全体を俯瞰し、状況の変化に即応できるリアルタイム意思決定の仕組みを持つこと。
DXは単なるツール導入ではなく、“戦略のスピードアップ”を実現するための基盤です。そして、その変革をリードできるのは、全体を見渡すCLOの役割に他なりません。
DXはツールでなく“戦略のスピードアップ”
WMSやTMS、AIルート最適化といった技術は、あくまで手段です。真の目的は、情報が部門をまたいで即座に共有され、変化に合わせて戦略を組み替えられる体制を作ること。データの一元化や可視化は、そのためのスタートラインに過ぎません。
CLO主導の変革で、サプライチェーンの競争力を高めよ
サプライチェーン全体を設計・統合できる視点を持つのはCLOです。調達・製造・営業・ITなど全社を巻き込み、コストだけでなく納期・品質・柔軟性を同時に高める設計が必要です。CLOが旗振り役となり、現場の改善と経営戦略をつなぐことで、物流は「守りのコスト」から「攻めの武器」へと変わります。
データから未来を予測するサービス「ADT」で物流自動化を実現!
「ADT」とはアイディオットデジタルツインのことで、物流に関わる在庫管理や配送などのデータをリアルタイムで可視化・分析するシミュレーターです。このツールは、数十種類のデータセットを集約し、物流業務の最適化と効率化を支援します。膨大なデータを用いて行うため、限りなく現実に近いシミュレーションをすることができます。
「ADT」では、可視化、シミュレーション、物理空間の実装が可能です。「ADT」を利用し、物流での自動化をシミュレーションし、車両情報の可視化や人員のシミュレーションなどにより、いきなり行う危険性を減らし、スムーズな物流自動化に踏み出すことができます。
お問い合わせはこちら
まとめ
本記事では、CLOが物流DXを進めるうえで取り組むべき3つの改革、拠点・在庫・輸配送について解説しました。
単なるデジタル化や部分最適ではなく、サプライチェーン全体を俯瞰し、リアルタイムで意思決定できる体制を構築することが鍵です。
これら3つの改革をCLOが主導し、現場と経営をつなぐ戦略的な意思決定を行うことで、物流はコストセンターから企業の競争力を支える武器へと進化します。



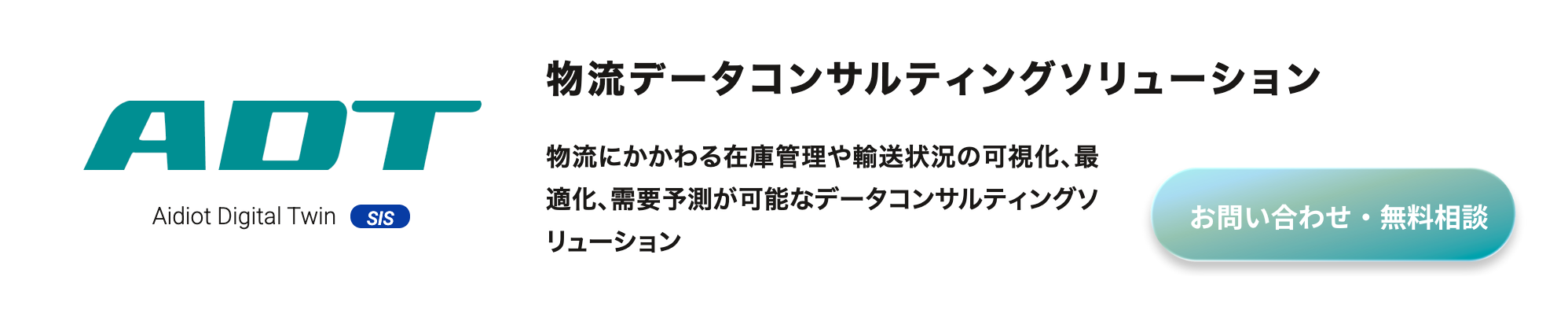

 Aidiot編集部
Aidiot編集部





