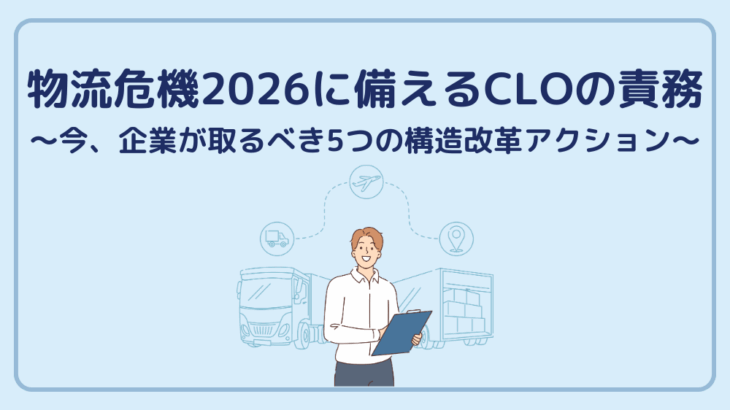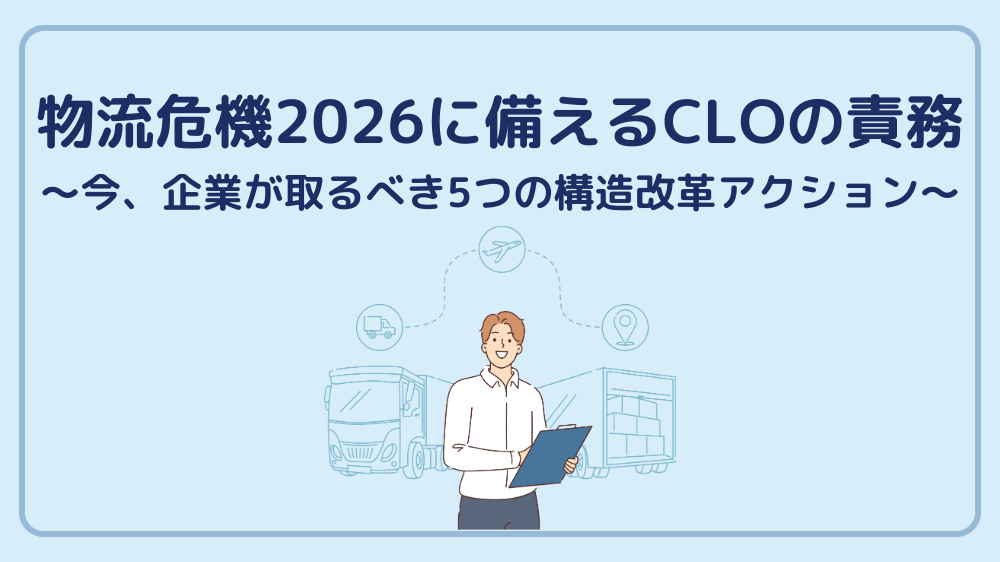
2024年問題を皮切りに、日本の物流は構造的な転換点に差し掛かっています。2026年にはさらなる深刻化が予想され、従来の延長線上では対応しきれない局面に突入する可能性があります。
こうしたなか、物流を経営戦略の中核に据えるべき役割として、CLO(Chief Logistics Officer)への期待が高まっています。CLOは企業における物流・サプライチェーン全体の戦略と実行を統括する最高責任者のことを指します。
2024年5月に改正された「物流効率化法」により、2026年4月からは、一定規模以上の荷主企業がCLOを選任することが義務付けられました。
本記事では、物流危機2026に向けてCLOが果たすべき責任と、今まさに企業が取り組むべき5つの構造改革アクションについて整理。単なるコスト管理にとどまらない、持続可能で競争力ある物流戦略のヒントをお届けします。
▼CLOについて詳しく解説!ホワイトペーパーを無料でダウンロード!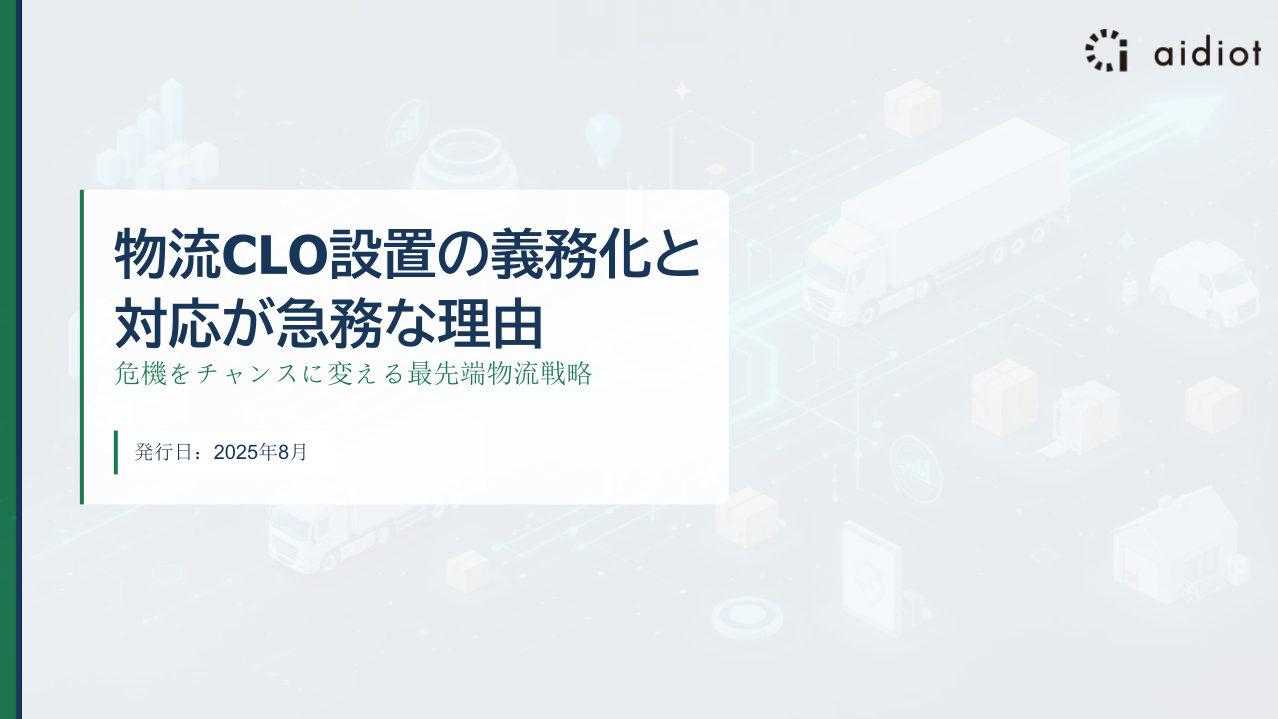
物流危機2026とは何か
▼物流の2026年問題についてはこちらをチェック
ドライバー不足・規制強化・都市集中など複合的要因の整理
2024年問題によって表面化したドライバーの時間外労働の規制(年960時間)は、その影響が年々強まり、2026年には物流業界の「供給力不足」が本格化すると予測されています。
ドライバー不足の原因として、トラックドライバーの高齢化による退職の増加と若年層の就業回避、労働時間規制による稼働制限、低賃金や過重労働の実態があります。
さらに、燃料費や人件費の上昇、都市部への配送集中による交通制約、再配達増加など、複数の要因が同時多発的に進行中です。一つひとつはすでに顕在化している課題ですが、2026年にはこれらが連鎖的に影響しあい、かつてない規模で物流全体の機能低下を引き起こす可能性があります。
物流問題が「現場の努力」ではなく「経営戦略」に移行している理由
これまでは、現場での運用改善や配車調整、倉庫レイアウトの見直しなどで対応できた部分も多くありました。しかし今や、「モノが運べない・届かない」事態が発生しかねない状況です。
調達・販売・在庫すべてに直結する物流問題は、サプライチェーン全体の最適化なしには解決できません。結果として、物流は現場対応の枠を超え、事業の存続に関わる「経営課題」として再定義されつつあります。
CLOというポジションの役割が再定義されつつある背景
こうした流れの中で、CLOの存在意義も変わりつつあります。従来の物流担当役員とは異なり、CLOは全社横断で物流を再構築する「戦略担当者」としての役割を担います。調達・販売・生産・DX・人材戦略まで、あらゆる部門と連携しながら、持続可能な物流体制を構築するリーダー。それが、今求められているCLOの姿です。
Action1|全社横断で物流KPIを可視化する仕組みの構築
物流の現場改善はこれまで現場主導で行われてきましたが、2026年以降の供給制約時代においては、全社的な視点で「物流を経営の指標」として捉え直す必要があります。その出発点が、KPI(重要業績評価指標)の可視化です。単なる業務データの収集にとどまらず、財務や営業、調達、ITといった各部門が連携して共通言語で物流の成果と課題を把握できる仕組みづくりが求められています。
財務・調達・営業・IT部門と連携した「共通指標」の設計
物流費だけを見ていては、全体最適は実現できません。例えば、調達部門は発注単位や納期から、営業は納品遅延リスクから、ITはデータ整備や連携性の観点から、それぞれ物流と密接に関係しています。CLOは、これらの部門と連携し、輸送コスト・在庫回転率・納品遵守率・積載率など、全社で意味のあるKPIを定義する役割を担います。
自社物流の弱点・機会を定量的に把握できる状態の確保
「どこがボトルネックになっているのか」「どのルートが非効率なのか」など、物流の現場感覚だけに頼らず、データとして定量的に示せる状態を整備することが、改善の出発点になります。週次・月次でのダッシュボード化や、異常値アラートの仕組みが有効です。
データ主導の意思決定基盤の整備
感覚や経験則に頼る配車や在庫判断は限界を迎えつつあります。蓄積された物流データを活用し、拠点の再配置や共同配送の導入可否といった中長期の経営判断まで、データに基づいて意思決定できる仕組みを整えることが、CLOの役割のひとつです。
Action2|中期視点での拠点・在庫再配置戦略の立案
物流を「現場任せ」にしていては、これからの変化に対応しきれません。供給制約が深刻化する2026年を見据え、今こそ中長期視点での拠点配置と在庫戦略の見直しが求められています。CLOには、短期のコスト削減ではなく、中期的な競争力強化の観点から、拠点と在庫をどう最適化するかの意思決定が求められます。
消費地近接型・中継拠点の設計とROI試算
都市部への配送集中が進むなかで、消費地に近い拠点配置や、中継輸送に対応した中間拠点の設計は、物流の安定供給に不可欠です。ただし、単に倉庫を増やせばよいわけではありません。初期投資・運用コスト・期待される配送品質改善を総合的に試算し、投資回収の見通しを立てたうえで判断する必要があります。
▼あわせて読みたい!
在庫コスト・配送品質の最適バランス設計
拠点の増加は在庫の分散につながり、コストが膨らむリスクもあります。一方で、納品リードタイムの短縮や欠品率の低下といった配送品質の向上も見込まれます。単なる一律の在庫削減ではなく、需要予測やSKU特性に応じて「どこに、どれだけ、何を持つか」を再設計することが、経営的なインパクトを大きく左右します。
サプライチェーン全体のレジリエンス確保
自然災害や突発的な需給変動が発生しても、柔軟に供給を継続できる体制。それが今、企業にとっての生命線となっています。複数拠点によるバックアップ体制や、BCP(事業継続計画)を踏まえたリスク分散型のネットワーク設計は、コストだけでなく「止まらない物流」を実現するための投資です。
▼あわせて読みたい!
Action3|BCPと委託先依存リスクを見直す「調達再設計」
サプライチェーンの脆弱性は、物流のボトルネックから顕在化します。特に2026年以降は、ドライバー不足や自然災害、地政学リスクが物流の“止まりやすさ”を増幅させ、調達戦略そのものの見直しが不可欠になります。CLOには、物流を「モノを運ぶ機能」から「経営を止めない機能」へと再定義する視点が求められます。
委託先・協力会社との相互補完関係の構築
特定の運送会社や倉庫事業者に依存しきった状態では、ひとたびトラブルが起きた際に業務が立ち行かなくなります。重要なのは「取引先を増やす」ことよりも、「お互いに支え合える関係性を築く」こと。日常的な情報共有や共同運行の検討など、パートナー企業との連携強化が供給の安定性を左右します。
災害・障害発生時の切替体制整備
BCP(事業継続計画)は、もはや製造や本社機能だけの話ではありません。主要な輸送ルートが寸断された場合の代替手段、倉庫が被災した際のバックアップ体制、配送遅延時の顧客対応プロセスなど、物流業務に特化したBCPの策定が求められます。緊急時に「誰が、何を、どう動くか」を可視化しておくことがカギです。
物流領域でも「単一調達」から「多元調達」への転換を
調達といえば仕入れ先の話になりがちですが、物流委託においても同様の集中リスクがあります。1社に頼り切る体制から脱却し、地域・規模・機能の異なる複数の物流パートナーと契約しておくことで、有事の際も代替運用がしやすくなります。価格競争力だけでなく、リスク分散性も含めて調達戦略を再設計すべきタイミングです。
Action4|物流業務の標準化・自動化を推進するオペレーション設計
人手不足と業務の複雑化が進むなかで、物流業務の「やり方」が属人的なままでは、持続的な運用が難しくなってきています。特に2026年問題が迫る今、誰がやっても同じ成果が出せる仕組み=標準化と、その仕組みを支える自動化が欠かせません。CLOには、現場任せにしないロジスティクス全体の設計力が求められています。
属人性の排除と平準化可能なプロセスの洗い出し
現場の担当者によって業務品質やスピードがバラつく状況では、組織としての対応力に限界があります。まず取り組むべきは、作業工程を細かく棚卸しし、「誰でも再現できる手順」を整理すること。マニュアル化や作業動画の活用も効果的です。現場にしか見えていなかった“暗黙知”を、会社の“仕組み”へ昇華させる視点が必要です。
WMS/TMSの再評価とデジタルツール導入による自動化余地の抽出
倉庫管理(WMS)や配車管理(TMS)といった既存システムを、これからはデータを活用して判断や指示のプロセス自体を自動化することが求められます。最新のクラウドツールやAI連携機能の導入によって、業務負荷を減らしながら精度を高める仕組みへと転換できます。
組織全体の運用能力を高めるリーダーシップの発揮
標準化や自動化を進めるうえで、最も大きな障壁は「変化への抵抗感」です。現場の理解と納得を得ながら進めるには、単なる施策ではなく「文化」として根づかせるリーダーシップが不可欠です。トップダウンとボトムアップの両輪で、オペレーションのあり方を組織全体で見直す姿勢が問われています。
Action5|社内意思決定構造の再構築と「物流に投資する文化」の醸成
どれだけ現場で優れた施策があっても、意思決定のテーブルに物流の議題が上がらなければ、実行には至りません。特に2026年問題のように、構造的で持続的な対策が求められる局面では、物流を「コストセンター」ではなく「戦略投資領域」として捉える経営の視点が不可欠です。CLOが企業の中で戦略的に機能するには、組織構造と意思決定プロセスの再設計が重要になります。
経営陣への危機意識共有と財務部門との連携
「物流の問題は現場の課題」と見なされていては、本質的な改善は進みません。CLOには、経営層に対して現状のリスクと今後の影響を、定量・定性の両面からわかりやすく伝える役割が求められます。また、財務部門と連携して、物流投資の意義や回収シナリオを説明することで、予算化のハードルを下げることができます。
短期コストと中長期価値のトレードオフ判断の場づくり
物流改善には、一定の初期コストが避けられません。しかし、それがドライバーの定着率向上やCO₂削減、BCP強化など中長期の企業価値につながる投資であれば、むしろ「守りの経営戦略」として捉えるべきです。現場・経営・財務が同じテーブルで議論できる場をつくることが、持続可能な意思決定の鍵となります。
CLOを核とした経営議題への格上げ
これからの企業経営において、物流は単なる「オペレーション」ではなく、「事業成長の前提条件」です。CLOはその最前線に立ち、経営戦略とオペレーションをつなぐ存在であるべきです。役員会や経営会議に物流視点が組み込まれるよう、CLO自身がアジェンダを構成する主体となることが求められます。
まとめ
本記事では、2026年に深刻化が予想される物流危機を前に、企業が取るべき5つの構造改革アクションをCLOの視点から解説しました。物流はもはや現場だけの課題ではなく、経営全体で取り組むべき戦略テーマです。KPIの可視化、拠点と在庫の再設計、調達リスクの見直し、業務の標準化・自動化、意思決定構造の再構築。これらはすべて、持続可能な物流体制の土台となる取り組みです。今こそ、企業としての覚悟が問われています。
▼CLOについて詳しく解説!ホワイトペーパーを無料でダウンロード!