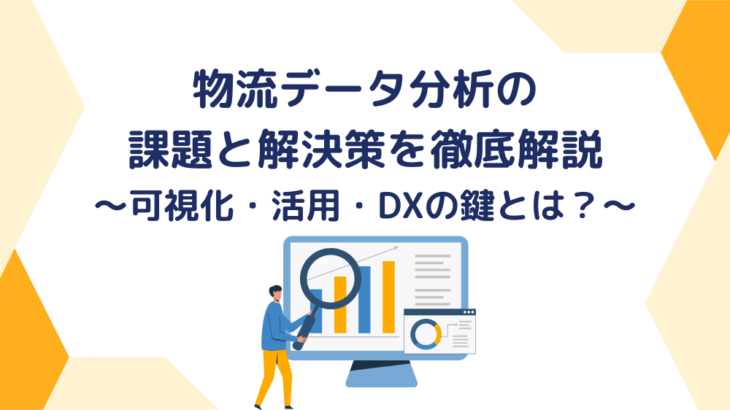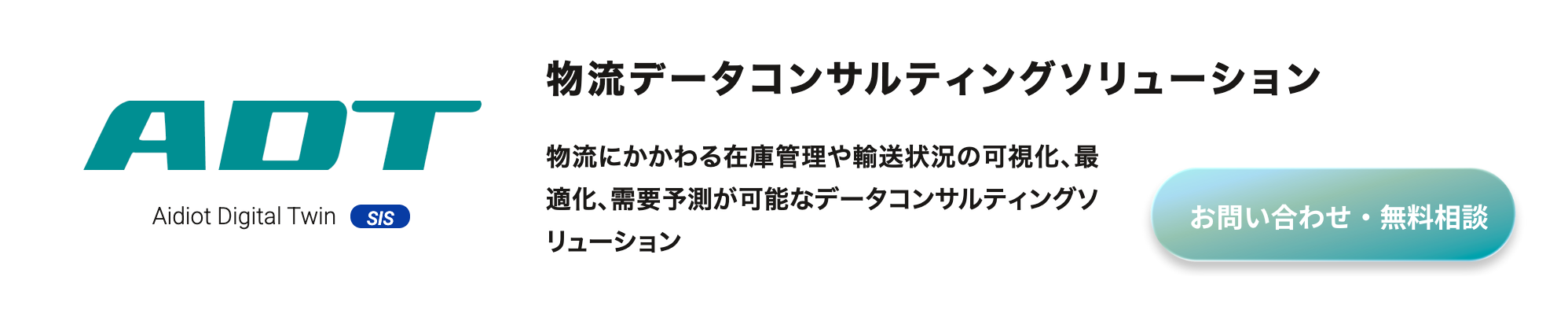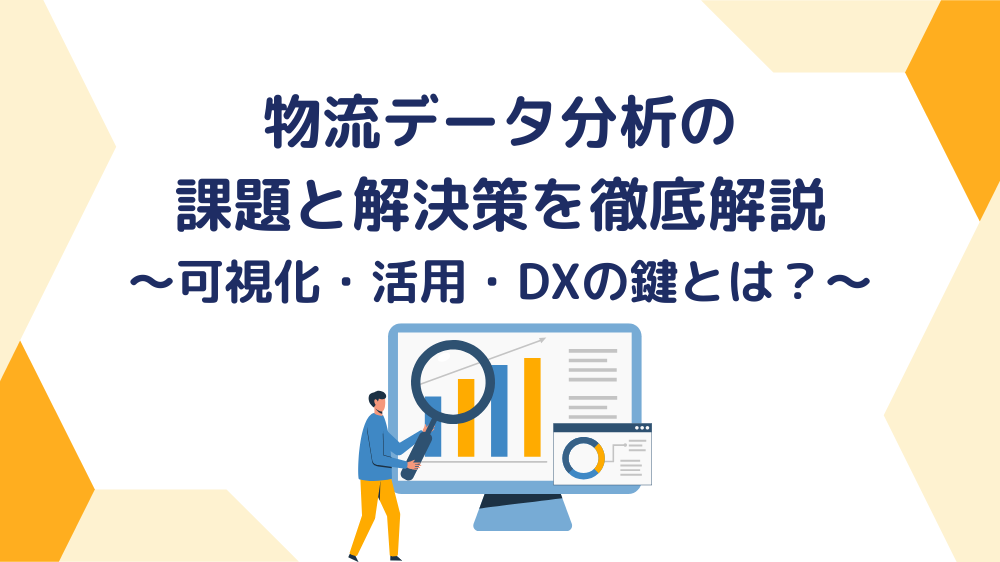
物流業務の改善やコスト最適化を進めるうえで、データ分析の重要性がこれまで以上に高まっています。しかし実際には、
「何を見ればよいのか分からない」
「データが分散して活用しきれない」
といった悩みを抱える現場も少なくありません。
せっかく収集しているデータも、分析や意思決定に活かせなければ宝の持ち腐れです。
本記事では、物流データ分析がうまく進まない背景を整理しながら、可視化や活用のポイント、DXにつなげるための実践的なアプローチまで詳しく解説します。
物流データ分析とは?
物流データ分析とは、物流の現場で日々発生するさまざまなデータを整理・分析し、業務の効率化やコスト削減につなげる取り組みのことです。
なぜ今「物流×データ分析」が重要なのか?
2024年問題や人手不足といった課題が広がる中で、「現状を正しく把握すること」は、対策の第一歩です。
荷量、車両の稼働状況、倉庫内の作業負荷、リードタイムのばらつきなど、物流にはさまざまな変動要因があります。
これらを数値で捉え、定量的に分析することで、ボトルネックの特定や改善策の優先順位づけが可能になります。属人的な判断では見逃されがちな問題にも、データなら気づくことができます。
可視化・最適化・省人化にどうつながるか
データ分析の第一段階は「見える化」です。たとえば、どの拠点で荷待ちが多いのか、どの時間帯に車両が集中しているのかを把握するだけでも、業務改善の糸口になります。
次に「最適化」です。配送ルートの無駄を削ったり、作業スケジュールを平準化したりといった判断に、データが活かされます。そして、こうした最適化が進めば、作業のムリ・ムダが減り、省人化や自動化の設計も現実的になります。
特にゼロタッチ物流を目指す場合、センサーや機器から得られる情報をどう整理し、業務設計に活かすかが大きな鍵となります。
▼あわせて読みたい!
物流データ分析でよくある課題
物流の効率化や省人化を進めるうえで「データ活用の重要性」は広く認識されていますが、いざ実務に落とし込もうとすると、多くの企業が似たような壁に直面します。単にツールを導入するだけでは、分析も改善も思うように進まないのが現実です。
ここでは、現場でよく聞かれる4つの課題を整理し、それぞれの背景を掘り下げてみましょう。
データが集まらない(分散・紙・手作業)
「そもそもデータが揃わない」これは多くの現場で最初にぶつかる課題です。拠点ごとに管理方法がバラバラだったり、紙の伝票や手書きの記録が残っていたりと、情報が散在・非構造化されているケースは珍しくありません。
まずは、どの情報をどこから集めるのかを明確にし、入力や収集の仕組みを整えることがスタートラインです。
分析できない(ツール不足・スキル不足)
データは集めたものの、分析に活かせていないという声もよく聞かれます。表計算ソフトでの処理に限界があり、BIツールや分析用システムが導入されていない、あるいは使いこなせる人材が不足している、といった要因が背景にあります。
難しい分析を一気に目指すのではなく、まずは業務に直結する指標に絞り、シンプルな可視化から始めるのが現実的な一歩です。
分析しても活かせない
分析結果が出ても、それが現場の業務改善に結びつかない。これは意思決定プロセスや組織体制の問題に起因することが多い課題です。
改善提案が部門ごとに止まり、全体最適につながらなかったり、分析担当と現場の間で目的や言語が噛み合わなかったりと、データが“使われない”状態が生まれやすくなります。
システムが連携しない
物流の各業務で別々のシステムが稼働している企業では、それらの連携が課題になります。
TMS(輸配送管理)、WMS(倉庫管理)、販売管理などのデータが個別に存在しており、リアルタイム連携ができなければ、全体の見える化や効率化が進みません。結果として、部分最適にとどまり、分析結果が断片的になりがちです。
課題を解決するための実践策
物流データ分析を業務改善やコスト最適化につなげるためには、単にデータを集めるだけでなく、現場で「活かせる」仕組みが欠かせません。
ここでは、分析精度を高め、日常業務に根付かせるための具体的なアプローチを4つの視点から解説します。
データの一元管理とリアルタイム可視化の仕組み作り
物流の各工程で発生するデータを、TMS(輸配送管理)やWMS(倉庫管理)などのシステム間でつなぎ、リアルタイムに可視化できる環境を整えることが第一歩です。
散在している情報を一か所にまとめ、誰でも同じ画面で状況を確認できる状態にすることで、業務判断のスピードと精度が大きく向上します。データの鮮度と整合性が、実効性のある分析を支えます。
BIツール・ダッシュボードの導入と活用教育
蓄積したデータを読み解くためには、BIツールやダッシュボードの活用が有効です。日別・週別の物量推移や遅延分析などを可視化することで、異常値や改善ポイントが見えるようになります。
同時に、現場スタッフが自らデータを扱えるよう、基本的な操作教育や活用目的の共有も重要です。使える環境と使える人をセットで整備していく必要があります。
KPI設計とPDCA運用による“使える分析”の推進
分析の成果を業務に活かすには、KPIを明確にし、継続的なPDCAサイクルをまわす仕組みが求められます。「車両積載率」「配送遅延率」「庫内作業生産性」など、定量的な指標を持つことで、改善の方向性が明確になります。
会議資料や報告書のための分析にとどまらず、現場の意思決定に直結する“使える分析”を実現することがゴールです。
外部パートナー・クラウドサービスとの連携強化
全ての仕組みを自社内で構築するのは現実的ではありません。クラウド型の可視化ツールやデータ連携プラットフォームを活用することで、スピーディかつ柔軟に体制を整えることができます。
また、BI構築やKPI設計の知見を持つ外部パートナーと連携することで、自社の強みを活かしたデータ活用が進みやすくなります。
データ分析によって実現できる物流改善の事例
配送ルートの最適化(走行距離と燃料コスト削減)
株式会社ファミリーマート
株式会社ファミリーマートは、2030年までに2017年度対比30%のCO2排出量削減を目標に掲げ、物流配送におけるCO2削減を積極的に推進しています。
2022年10月から弁当やサンドイッチなどの定温・チルド配送からAIを活用した配送シミュレータの運用を開始し、2023年10月からアイスクリームや冷凍食品などの冷凍配送、2024年6月から加工食品・ドライ飲料などの常温配送に導入し、店舗配送の最適化に繋げています。
効率的なルート設定によって配送コースや配送車両台数が約10%削減されるとともに、2017年度対比、走行距離で約5,300万キロ(約20%)を削減いたしました。
出典)
https://www.family.co.jp/company/news_releases/2025/20250605_01.html
・荷待ち・荷役時間の削減(ドライバー拘束時間の短縮)
大和ハウス工業株式会社とキヤノンマーケティングジャパン株式会社
大和ハウス工業株式会社とキヤノンマーケティングジャパン株式会社は物流施設におけるトラックドライバーの荷待ち・荷役時間を可視化し、改善を支援するシステムを開発。2024年11月より、大和ハウス工業株式会社が開発した複数の企業テナントが入居できる物流施設「DPL平塚」において、効果を検証するための実証実験を開始し、2025年4月以降、大和ハウス工業が展開する物流施設「DPL(ディーピーエル)」への本格導入を目指します。
このシステムでは、カメラが撮影する映像から物流事業者ごとにトラックを自動検知し、物流施設入場からバースへの移動、バースでの荷役作業、物流施設退場までの記録を自動で把握、蓄積します。
また、映像をキヤノンMJグループ独自の作業解析技術を用いることで、映像からドライバーの行動をAIが分析し、荷待ちや荷役の時間を計測します。これらのデータに基づき、トラックドライバーの時間を要した点について、動作分析により課題を把握することで、荷主事業者やテナント企業の物流効率化に向けた改善を支援します。
出典)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001159.000013943.html
データから未来を予測するサービス「ADT」で物流自動化を実現!
「ADT」とはアイディオットデジタルツインのことで、物流に関わる在庫管理や配送などのデータをリアルタイムで可視化・分析するシミュレーターです。このツールは、数十種類のデータセットを集約し、物流業務の最適化と効率化を支援します。膨大なデータを用いて行うため、限りなく現実に近いシミュレーションをすることができます。
「ADT」では、可視化、シミュレーション、物理空間の実装が可能です。「ADT」を利用し、物流での自動化をシミュレーションし、車両情報の可視化や人員のシミュレーションなどにより、いきなり行う危険性を減らし、スムーズな物流自動化に踏み出すことができます。
お問い合わせはこちら
まとめ
本記事では、「物流データ分析の課題と解決策」について、可視化・活用・DXを切り口に解説しました。多くの現場では、データが集まらない、活かせない、システムがつながらないといった壁に直面していますが、仕組みづくりやツールの活用、KPIの設計次第で改善は可能です。
リアルタイムの可視化や、分析結果を業務へつなげる工夫が、物流現場の生産性と柔軟性を高めます。まずは小さな改善から、データを“使える資産”へと変えていきましょう。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。