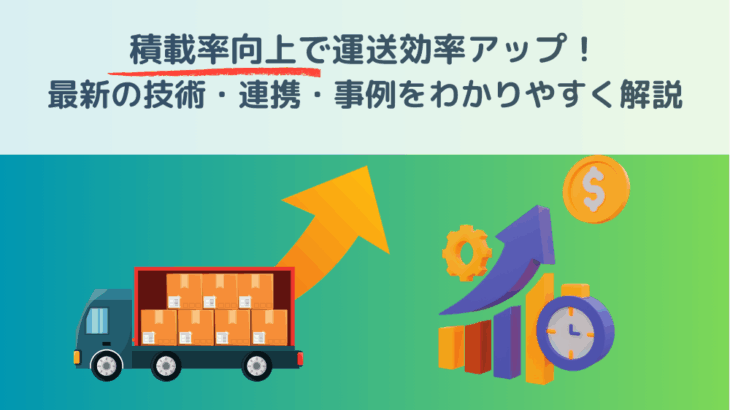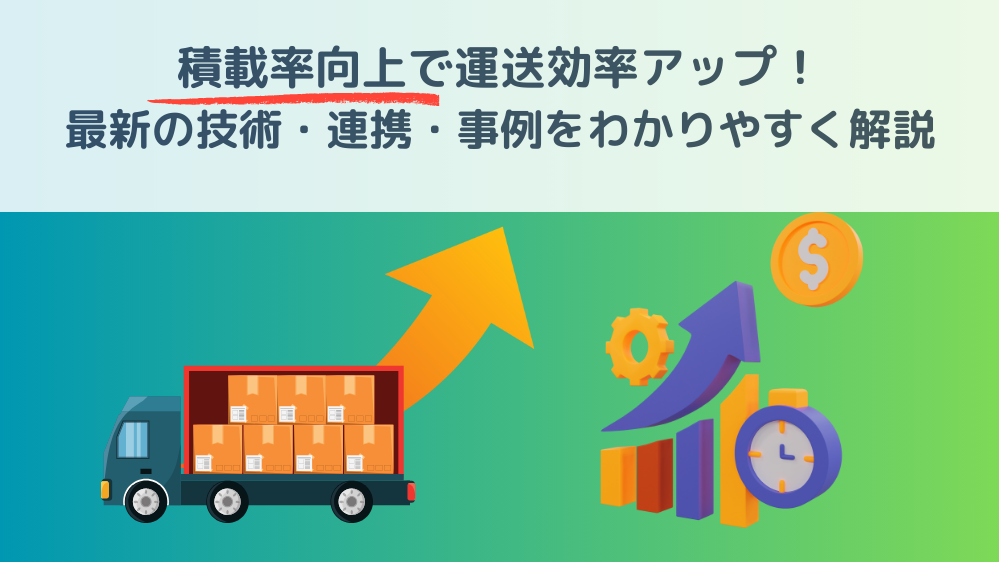
物流業界では、ドライバー不足やCO₂排出削減への対応など、輸送効率の改善が急務となっています。その中で注目されているのが、「積載率の向上」です。積載率とは、トラックなど輸送手段に対してどれだけの貨物が積まれているかを示す指標であり、輸送効率を左右する重要な要素です。
そもそも積載率とは?
積載率とは、トラックやコンテナなどの輸送手段において、積載可能な容量に対して実際に積み込まれた貨物の割合を示す指標です。一般的に、積載率が高いほど輸送効率が向上し、コスト削減や環境負荷の軽減につながります。
積載率の計算方法
積載率は以下の計算式で求められます。
積載率(%)=(実際の積載重量または積載容積 ÷ 最大積載可能重量または容積)×100
積載率の定義
積載率とは、主に以下の2つの観点で使われます。
重量積載率:積んでいる荷物の重量が、その車両の最大積載可能重量に対してどれくらいか(%)
容積積載率:荷室の容積に対して、どれだけ荷物が占めているか(%)
たとえば、10トンまで積めるトラックに5トンしか積んでいなければ、重量積載率は50%。積載率が低いままでは、車両も人手も燃料も“ムダ”が多くなってしまうため、効率化を図るうえでとても重要な指標となります。
日本の平均積載率と課題
国土交通省の資料によれば、2010年度以降、日本の貨物自動車の積載率は40%以下の低い水準で推移しています。これは、トラックの積載スペースの半分以上が空のまま走行していることを意味し、燃料コストや人件費の非効率化、CO₂排出の無駄にもつながっています。特に宅配便や短距離輸送では、荷物のサイズや集荷・配送時間の制約などもあり、「積みたくても積めない」状況が慢性化しています。
ドライバー不足が深刻化する中、1回の運行でできるだけ多くの荷物を運ぶ“積載効率の最大化”が、今や物流業界全体の急務といえるでしょう。
積載率の向上は、輸送能力の増加にも直結し、物流の持続的成長に寄与します 。このような背景から、積載率向上に向けた取り組みが求められています。
出典)
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001760824.pdf?utm_source=chatgpt.com
▼あわせて読みたい!
なぜ今、積載率の向上が求められているのか?
これまで物流業界では「早く・確実に届けること」が最優先とされてきましたが、いま最も注目されているキーワードのひとつが「積載率の向上」です。
背景には、単なる業務効率だけではない、社会全体の変化や課題があります。ここでは、なぜ今、積載率の改善が急務なのかを、4つの視点から整理して解説します。
「物流2024年問題」によるドライバー不足と労働時間規制
2024年4月から施行された働き方改革関連法により、トラックドライバーにも時間外労働の上限(年間960時間)が適用されました。これにより、1人のドライバーが1日に運べる荷物量が物理的に減少することになります。人手不足が深刻な中、「少ない回数でより多く運ぶ」ためには、トラック1台あたりの積載効率を最大化するしかないという現実的な課題が浮き彫りになっています。
燃料価格・輸送コストの上昇
原油価格の高騰や円安の影響により、軽油などの燃料費が上昇傾向にあります。また、車両コストや人件費、保険料などの固定費も上がっており、企業は輸送コストの見直しを迫られています。「1台で運べる量を増やす=1運行あたりのコストを下げる」という視点からも、積載率の改善は極めて有効な打ち手です。
環境負荷削減(CO₂排出量の削減)
運送に関わるCO₂排出量の削減は、サステナブル経営の重要なテーマとなっています。積載率が低い状態で走る車両が多ければ多いほど、ムダな走行と排出が積み重なることに。積載率を上げて1回あたりの運送効率を高めることは、温室効果ガスの排出削減にも直結し、環境負荷低減への具体的なアクションとして多くの企業で注目されています。
配送の多頻度化・小口化
EC需要の拡大や個人向け配送の増加により、以前よりも「少量を頻繁に届ける」配送形態が一般化しています。その一方で、トラックの積載スペースが埋まりきらないまま走行するケースも増えており、非効率な運行が常態化しつつあるのが現状です。この流れに対抗するには、荷物の混載や積み合わせ、拠点間の再配置などを通じた積載率の見直しが必要とされています。
積載率向上のための具体的な取り組み
積載率を上げるための方策は、単に「もっと荷物を詰め込もう」という発想では成り立ちません。
荷主企業同士の連携、テクノロジーの導入、物流全体の設計の見直しなど、複数の視点からアプローチする必要があります。ここでは、今注目されている積載率向上のための具体的な取り組みを5つご紹介します。
共同配送
異なる荷主企業の荷物を同じトラックでまとめて運ぶのが「共同配送」です。
納品先が同じエリア内に複数ある場合など、配送の効率を大きく改善できる仕組みとして、多くの企業で導入が進んでいます。かつては競合関係や情報共有の壁がありましたが、最近では物流専業の中立的な事業者が間に入ることで、マッチングが現実的に。コスト削減と環境負荷の両方にメリットがある点も大きな魅力です。
▼あわせて読みたい!
混載輸送の強化
小ロットの商品を別の荷物と積み合わせて運ぶのが混載輸送です。
特に宅配便やBtoCビジネスでは荷物が小型化しているため、1件の荷物だけではスペースを無駄にしがちです。仕分けや再配達の効率を踏まえた混載設計や、倉庫での事前マージなど、輸送だけでなく前後の工程も含めた見直しが求められています。
配送ルート・積載計画の最適化
TMS(配車・運行管理システム)やAIによるルート最適化は、積載率改善の“頭脳”部分を担う存在です。積み込む順序や走行ルートを考慮した最適な積載パターンを自動で提案することで、ドライバーの経験に頼らない計画が可能に。さらに、リアルタイムの交通情報や荷物状況を加味して再計算する仕組みも進化しており、「積んだ後の見直し」まで含めた柔軟な運用が実現できるようになっています。
▼あわせて読みたい!
帰り便・空車情報の活用
配送が終わったトラックが空のまま帰ってしまう空車回送は、積載効率の観点では最大のロス。これを防ぐために、帰り便を活用した荷物の積み合わせや、空車情報の共有プラットフォームの導入が進んでいます。物流企業や荷主がリアルタイムで情報を出し合うことで、「帰りにあわせて荷物を積む」流れがつくりやすくなり、稼働率の向上とコスト削減につながります。
パレットやコンテナの標準化・共通化
積載効率を上げるうえで見逃せないのが積載単位の整備です。企業ごとにサイズが異なるパレットやコンテナを使っていると、積み合わせやトラックへの配置に無駄が生じます。JIS規格などに沿った共通サイズのパレット・コンテナを利用することで、積載効率が大きく向上します。また、レンタルサービスや共同回収の仕組みも広がっており、標準化はサプライチェーン全体にとってのメリットにもなります。
▼あわせて読みたい!
企業による積載率向上の成功事例
コクヨサプライロジスティクス株式会社、アスクル株式会社の共同配送による積載率向上
コクヨサプライロジスティクス株式会社(KSL)は、アスクル株式会社と協力し、大阪から福岡への同一納品先への輸送を共同化する取り組みを実施しました。この取り組みは、2021年9月からの実証実験を経て、2022年10月より本格運用が開始されました。
具体的には、KSLの近畿IDCとアスクルの大阪DMCという近隣の物流拠点から、福岡市東区にあるASKUL Logi PARK 福岡への輸送をチャーター便で共同化しました。これにより、積載率が年間で9%向上し、CO₂排出量を13%削減する成果を上げました。また、共同輸送により荷受けの工数が短縮され、荷受けバースの占有時間も削減されるなど、副次的な効果も得られています。
出典)
https://www.kokuyo-supplylogistics.com/news/2023/09/post-5.html
豊田合成株式会社のAIとカメラによる積載量の自動把握
豊田合成株式会社は、2021年に人手不足への対応や環境負荷の低減などを目指した物流改善のプロジェクトを立ち上げました。2025年度中に荷物の積載率を現行の70%から85%に引き上げることを目標としています。
2023年にAIとカメラを活用した荷量算出システムを導入して荷量の把握・路線別荷量算出・最大積載量設定を自動化しました。トラック荷台を24時間撮影しAI解析することで、積載状況を100%把握できる仕組みを構築し低積載路線や便を即座に特定できるようになり、輸送体制の最適化が進みました。その結果、年間約9,400便の運行を削減し、CO₂排出量も約760トン削減。このシステムは、愛知県みよし市と一宮市の物流拠点で運用されています。
2024年にはスマートフォンのLiDARスキャナ(3Dセンサー)を活用した積載量算出システムを開発しました。データ処理がスマホ内で完結するため、手軽に持ち運び・導入できる点が特長です。今後は、豊田合成株式会社での輸送の残り4割を占める、物流拠点を経由しない納入ルートなどで活用を進める計画です。
出典)
https://www.toyoda-gosei.co.jp/seihin/technology/theme/logistics/?utm_source=chatgpt.com
佐川急便株式会社とパンメーカー4社(フジパン株式会社、株式会社リョーユーパン、株式会社フランソア、株式会社タカキベーカリー)と共同配送による積載率向上
2022年に佐川急便株式会社は九州エリアで、上記のパンメーカー4社と連携し、パン製品の共同配送を実施しました。これまで各社が個別に配送していたため、トラックの積載率が低いまま運行されるケースが多く、配送コストやドライバー不足が課題となっていました。
佐川急便株式会社は各工場を巡回し、商品を集荷する体制を整え各メーカーの商品を方面別に仕分け。複数メーカーの商品を組み合わせる取り組みをしました。
共同配送を実施した結果、車両台数を43台から22台に削減することに成功し積載率向上と配送効率の改善が実現しています。配送効率化により、配送コストや配車業務の削減に加え、配送車両台数の減少によるCO₂排出量の年間18.7%削減を実現しました。
出典)
積載率向上のメリットと導入時の注意点
積載率向上はメリットが大きい一方で、導入にはいくつか注意点も存在します。ここでは、押さえておきたいポイントを整理してご紹介します。
メリット
・コスト削減
積載率を高めることで、1台のトラックに積める荷物量が増えます。その結果、必要な車両台数や運行回数が減少し、燃料費、ドライバーの人件費、有料道路の通行料など、輸送にかかるさまざまなコストが削減されます。メンテナンス費用や車両保険料といった固定費の負担も軽減されるため、物流全体のコスト構造に大きなインパクトを与えることができます。
・ドライバー負担の軽減
効率的な積載と配送ができるようになると、1回あたりの配送量が増え、同じ時間内でより多くの成果を上げられるようになります。ドライバーの長時間労働の抑制や深夜・早朝運転の負担軽減が可能に。過酷な労働環境が改善されることで、ドライバーの離職率低下や新規採用のハードル緩和にもつながります。
・環境負荷の低減
積載率が低い状態で走るトラックが減れば、無駄な走行が削減され、トータルの走行距離が短縮されます。その結果、燃料消費量とCO₂排出量の大幅な削減が可能になります。
・輸送力の最大化
ドライバー不足が深刻化する中、これまで以上に「限られたリソースでいかに多く運ぶか」が問われています。積載効率を高めることで、同じ台数・同じ人数でも運べる荷物量が増加し、結果として輸送力全体の底上げにつながります。
導入時に注意すべきポイント
・荷物のサイズ・形状のばらつき
積載率向上を目指すうえで、荷物の「大きさ」「形状」がバラバラだと、トラック内で効率よくスペースを使えず、かえって作業が複雑になってしまいます。小さな箱から長尺物まで混在する場合、パズルのように最適な積み方を考えなければなりません。
この問題に対処するには、パレットやコンテナのサイズを標準化・共通化して、積み込みやすさを確保することが重要です。さらに、物流センターや工場側で荷姿統一ガイドラインを整備することで、現場の負担を事前に軽減することができます。
・過積載リスクへの対応
積載効率を重視するあまり、トラックの最大積載重量や積載容積を超えてしまうリスクにも注意が必要です。過積載は道路交通法違反となり、企業の信用問題にも直結します。
過積載を防ぐためには、積み込み前の重量チェックの徹底が不可欠です。最近では、積載量をリアルタイムで管理できる車両搭載型センサーや管理システムの導入も進んでおり、これらのツールを活用することで安全かつ確実な運用が可能になります。
・共同配送の調整コスト
複数企業で荷物をまとめて運ぶ「共同配送」は積載率向上の有効手段ですが、導入時には調整に大きな労力がかかることがあります。たとえば、納品先の営業時間の違い、納品条件、荷物の取り扱いルールの違いなど、細かい調整ポイントが数多く存在します。
このような場合には、物流専門のコーディネーターや中立的な物流会社に間に入ってもらい、調整を効率的に進めることが成功のカギになります。また、共同配送スタート前にルールを作成しておくこともスムーズな運用に役立ちます。
・現場のオペレーション負荷
積載率を最大化しようとすると、荷物の積み込み順や積み重ね方が複雑になり、現場の作業者にとって負担が増すリスクもあります。荷役時間の長期化やヒューマンエラーの発生にもつながりかねません。
それを防ぐには、事前に積み込み手順をマニュアル化することが重要です。また、積み方をシミュレーションする積載設計ソフトウェア(ロードプランナー)や、荷積みを支援するICTツールの活用によって、作業負荷を軽減しながら積載効率を高める工夫が求められます。
今後の展望と企業がとるべき次の一手
積載率向上への取り組みは、単なる物流効率化にとどまらず、これからのビジネス競争力を左右するテーマになりつつあります。燃料費高騰やドライバー不足、環境規制の強化など、物流を取り巻く課題は年々厳しさを増しています。これからの時代、積載率向上に成功するかどうかは、コスト競争力だけでなく、企業のサステナビリティそのものにも直結すると言えるでしょう。ここでは、今後の展望と企業が次に打つべき具体的なアクションについて整理します。
データ活用とAIによるさらなる最適化
これまで経験や勘に頼っていた配車・積載業務も、これからはデータとAIによる最適化が主流になっていきます。輸送量、荷姿、納品時間などの細かなデータをリアルタイムで収集・分析し、最適な積み方や配送ルートを提案するシステムの導入が急速に進むでしょう。 企業としては、IoTセンサーやTMS(輸配送管理システム)の活用を進め、データドリブンな物流運営への転換を早めることが重要です。
異業種・異業態との連携強化
単独企業で積載率を高めることには限界があります。今後は、異業種間・異業態間の共同配送や混載輸送といった、業界横断型の連携がますます重要になります。食品、日用品、工業製品など、カテゴリをまたいだ輸送ネットワークをどう構築できるかがカギです。そのためにも、オープンなパートナーシップ戦略を取り、共同輸送に柔軟に取り組める体制整備が求められます。
サステナビリティ視点での取り組み推進
積載率向上は、単なるコスト削減策ではありません。CO₂排出量削減や循環型社会づくりに貢献する、企業のESG活動の一環としても積極的に打ち出していくべきです。
「積載率○%向上=CO₂○%削減」というわかりやすい成果指標を設け、社内外に対してサステナブルな物流改革に取り組んでいることを積極的に発信することも、今後は欠かせない要素になります。
現場視点を重視したオペレーション改革
システムや連携だけでなく、実際に現場で積み込み・配送を行うドライバーや作業スタッフへの配慮も忘れてはなりません。作業負荷が高くなれば事故リスクや離職リスクも高まります。
現場の声を反映しながら、積載ルールや作業マニュアルをブラッシュアップし、誰もが無理なく実行できるオペレーションを作ることが、積載率向上の真の定着につながります。
まとめ
本記事では、積載率向上の重要性と、それに向けた最新技術や企業間連携の取り組み、導入時の注意点、そして今後の展望について解説しました。
ドライバー不足や燃料コストの高騰、環境対応といった物流業界の課題に対し、積載率向上はコスト削減だけでなく、輸送力強化やサステナビリティ推進にもつながる有効な施策です。企業が積極的にデータ活用や異業種連携を進め、現場とのバランスを取りながら取り組みを加速させることが、これからの物流改革のカギとなるでしょう。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。