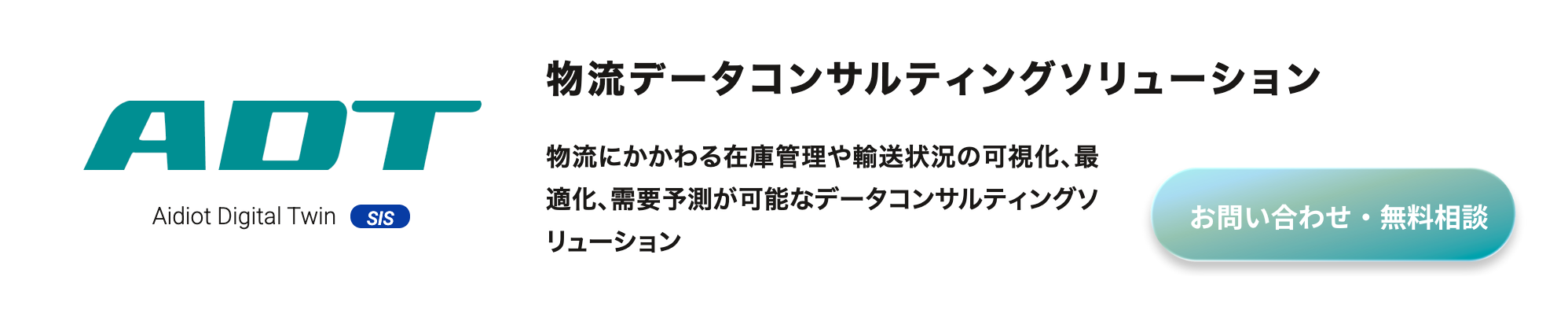はじめにーいま、なぜ積載効率改善なのか
物流現場では今、「荷主の選別」という言葉が現実味を帯びてきています。トラックドライバーの2024年問題を皮切りに、輸送力不足は深刻化しています。今までは「お願いすれば運んでもらえる」関係だった荷主と運送会社の力関係が、静かに反転し始めています。
本記事では、選ばれる荷主の共通点と、今日から取り組める積載効率改善策を紹介します。
2024年問題による輸送力不足
「2024年問題」とは、日本の物流業界が直面した大きな転換点を指します。2024年4月から施行された「働き方改革関連法」により、トラックドライバーの労働時間に上限が設けられ、残業時間は年間960時間までに制限されました。長時間労働が常態化していた運送業界では、輸送力の低下を招く要因となりました。加えて、ドライバーの高齢化も影響しています。
燃料高騰・CO₂排出削減圧力
燃料価格の上昇は、運送コストを直撃します。さらに、脱炭素社会の流れの中で、企業にはCO₂排出量の削減が強く求められています。トラック1台あたりの積載量を増やせば、同じ輸送量をより少ない車両・距離でまかなえるため、コストと環境負荷の双方を減らせます。積載効率の改善は、経営とサステナビリティを両立させるための最も現実的な解決策なのです。
空車回送の実態
多くの物流現場では、片道は満載でも帰りは空車というケースが少なくありません。これが“空車回送”と呼ばれる無駄な運行で、輸送コストの増加だけでなく、CO₂排出の大きな要因にもなっています。近年では、ラウンド輸送により、帰り便に荷物を載せる取り組みが進み始めました。空車を減らすことが、積載効率の改善とコスト削減の両立につながります。
▼あわせて読みたい!
空車の正体〜どこで発生しているのか〜
トラックが走っているのに、荷物を載せていない。そんな「空車」の存在は、物流現場では日常的に起きています。輸送コストの上昇やドライバー不足が深刻化する今、空車はもはや見過ごせない経営課題です。空車が生まれる理由は、業界構造や運用ルールに根づいた非効率が潜んでいます。
片方向偏重の輸送ルート
多くの企業が抱えるのが、「行きは満載、帰りは空車」という片道偏重の輸送ルートです。納品先が限られている、または特定エリアに集中している場合、帰りの荷を確保できず、どうしても空車で戻ることになります。特に地方への一方向輸送ではこの傾向が顕著です。結果として、燃料費や高速代、人件費といったコストだけが積み重なり、積載効率を大きく下げてしまいます。
発着時間ルールの硬直
もうひとつの要因は、発着時間の柔軟性がないことです。「午前中必着」「午後出荷厳守」といった商慣習が根強く、物流現場では同じ時間帯に車両が集中します。
その為、倉庫や配送センターでの待機が発生し、次の便への転換が遅れる悪循環を生みます。荷主や受け取り側が発着時間を少し緩和するだけでも、運行計画の自由度が増し、空車削減につながります。
荷待ち発生と帰り便の不一致
荷待ち時間も空車発生の温床です。荷積み・荷下ろしの順番待ちが長引くと、予定していた帰り便の荷を逃すことがあります。また、帰り便の出発地や時間が発着スケジュールと合わず、空のまま戻るケースも少なくありません。近年は、トラック予約システムや物流マッチングの導入によって、こうした不一致を減らす動きが広がっています。
積載効率改善に効く2大戦略
積載効率の改善は、いまや物流の現場だけでなく経営課題として注目されています。輸送力の不足、ドライバーの拘束時間制限、燃料費の高騰、脱炭素など、これらすべてに共通して効く打ち手が「1台のトラックでどれだけ無駄なく運べるか」です。そこで鍵となるのが、共同配送と貨物シェアリングという2つの考え方になります。
【共同配送】荷物×ルートの最適マッチング
共同配送とは、複数の企業が同じトラックで荷物を運ぶ仕組みです。業界や商品が違っても、配送先のエリアやルートが近ければ一緒に積むことができる可能性があります。1社単独では半分しか積めなかった車両を、満載に近い状態で走らせることができるのです。
共同配送は単なるコスト削減策にとどまらず、人手不足対策やESG対応という面でも効果を発揮します。今後はデータ分析を活用し、AIによる最適ルートマッチングが主流になっていくでしょう。
【貨物シェアリング】空きスペースを“流通させる”考え方
もうひとつ注目されているのが「貨物シェアリング」という考え方です。これは、事業者同士でトラックや倉庫の空きスペースをリアルタイムで共有・活用する仕組みのこと。空車回送や半端積みを減らし、より多くの荷物をより少ない車両で運ぶことを目指します。
近年では、オンラインプラットフォームを通じて「行きはA社の荷物、帰りはB社の荷物」といったマッチングが自動で成立するサービスも登場しています。これにより、従来は無駄だった空車の移動が、収益を生む運行に変わります。まさに、物流のシェアエコノミーです。
共同配送の成功事例
▼あわせて読みたい!
急成長中!貨物シェアリングの最新動向
事業者同士でトラックや倉庫の空きスペースをリアルタイムで共有・活用する貨物シェアリングの最新動向を紹介いたします。
空きスペースを資産に変える発想
従来、トラックの空き荷室や倉庫の空き棚は「もったいないけど仕方ない」ものでした。 しかし、貨物シェアリングの登場によって、これらの“空き”が収益化できる資産へと変わりつつあります。オンライン上で「空き情報」と「荷物情報」をマッチングさせることで、これまでムダになっていた区間やスペースが有効活用できるようになりました。
テクノロジーが支えるリアルタイムマッチング
貨物シェアリングを支えているのは、デジタル技術です。AIによってリアルタイムで最適マッチングや、GPSでの位置情報共有、積載率の自動可視化など、データを活用した仕組みが整いつつあります。
環境対応・コスト削減へのダブル効果
貨物シェアリングの導入は、経営と環境の両面で効果があります。
空車走行を減らすことで燃料費を抑え、CO₂排出も削減。実際に、年間で10〜20%の燃料費削減、CO₂排出量15%減を達成した企業も出ています。
また、荷主にとっても運賃の安定化やリードタイム短縮といったメリットがあり、持続的な物流基盤を構築する手段として注目が高まっています。
導入の壁と打開策
実際に導入しようとすると、課題が出てくるのが現実です。利害関係が複雑に絡み、各社の事情がぶつかります。システムや設備の問題よりも、むしろ「関係性の調整」こそが最大のハードルになっているのが現場の実情です。
ここでは、導入時に多くの企業が直面する3つの壁と、それを乗り越えるための現実的な打開策を整理します。
荷主間の利害調整
共同配送や貨物シェアリングの議論では、まず「どこが得をするのか」「どこが負担を負うのか」という不均衡が問題になります。距離・積載量・納品頻度が異なるため、費用や効果の分配が曖昧になりがちです。
打開策として有効なのが、“見える化”による合意形成です。運行データをもとに、台数削減やCO₂削減といった定量効果を共有し、参加企業全体の「総益」で議論をします。加えて、第三者(物流事業者やコンサルタント)が中立的な調整役を担うことで、交渉の摩擦を和らげることができます。数字と第三者の存在が、信頼の土台になります。
梱包サイズ・ラベル標準化
共同配送を効率化するうえで、見落とされがちなのが梱包形態やラベル表示の違いです。
同じパレットに積むにも、段ボールのサイズや積み方が違えば、積載効率が落ち、仕分けの手間が増える。これが現場では致命的なロスになります。
打開策はシンプルで、共通仕様のルールづくりです。サイズ・ラベル・バーコードなどを共通化すれば、倉庫・ドライバー双方の作業負荷が減り、結果的にリードタイム短縮とコスト削減につながります。
データ開示への心理的ハードル
データ連携は効率化の要ですが、「取引条件が知られるのでは」「他社に弱みを握られるのでは」という心理的抵抗が根強くあります。この壁を越えるには、信頼の設計が必要です。
たとえば、匿名化や暗号化によるデータ共有、アクセス範囲を制限した共同プラットフォームの利用など、安心して見せられる仕組みを整えることが重要です。加えて、最初から全情報を出すのではなく、部分的なデータ共有から始めるステップ方式が有効です。小さな成功体験の積み重ねが、企業間の信頼を育てていきます。
いますぐ始められるステップ
積載効率の改善は、誰もが「やらなきゃ」と思いつつも、最初の一歩でつまずきがちです。大がかりなシステム導入やデータ連携をいきなり始める必要はありません。まずは、自社の輸送を見える化し、身近なパートナーと小さく試すことが大切です。そこから確実に成果を積み重ねていくことが、持続可能な物流改革の近道です。
自社輸送の可視化(積載率/走行データ取得)
改善の出発点は、自社の現状を「数字で把握すること」です。トラックの積載率、稼働台数、走行距離、待機時間など、日々の輸送データを集めてみると、意外なムダが見えてきます。
最近では、GPSやデジタコ、運行管理アプリなどを活用することで、走行データをリアルタイムに取得・分析できる仕組みが整っています。
「感覚」で動かしていた運行を「データ」で管理できるようになれば、積載効率の低い便や空車回送がどこで発生しているか、一目で分かります。まずは見える化から始めましょう。
帰り便共有できる荷主候補の抽出
次のステップは、「誰と組むか」を考えることです。
同じエリアで納品・集荷を行っている企業、もしくは共通の配送ルートを持つ荷主を探すと、帰り便の共有や混載配送の可能性が見えてきます。業界が違っていても、条件、目的地、時間帯などが合えば、共同配送が成立します。
自社だけで完結させないという発想が、空車削減とコスト削減の第一歩になります。
小エリア共同配送からPoC
大規模な共同配送をいきなり立ち上げようとすると、調整やコストが大きな負担になります。
そこでおすすめなのが、小エリアから始めるPoCです。
たとえば、同じ工業団地内や隣接エリアの荷主同士で、一部のルートだけ共同配送を試すなど。この小さな実証で得られる“数字”は大きな意味を持ちます。台数削減率、CO₂削減量、作業時間短縮など実際の効果を可視化することで、社内やパートナー企業への説得力が格段に増します。
積載効率の改善や共同配送は、一気に変えるものではなく、小さく始めて広げる取り組みです。いまあるデータとネットワークを活かし、まずは始めることがこれからの時代に求められる持続可能な物流への最初の一歩です。
データから未来を予測するサービス「ADT」で物流自動化を実現!
「ADT」とはアイディオットデジタルツインのことで、物流に関わる在庫管理や配送などのデータをリアルタイムで可視化・分析するシミュレーターです。このツールは、数十種類のデータセットを集約し、物流業務の最適化と効率化を支援します。膨大なデータを用いて行うため、限りなく現実に近いシミュレーションをすることができます。
「ADT」では、可視化、シミュレーション、物理空間の実装が可能です。「ADT」を利用し、物流での自動化をシミュレーションし、車両情報の可視化や人員のシミュレーションなどにより、いきなり行う危険性を減らし、スムーズな物流自動化に踏み出すことができます。
お問い合わせはこちら
まとめ
積載効率の改善は、もはや物流部門だけの課題ではなく、企業競争力を左右する経営テーマへと進化しています。輸送力不足、コスト上昇、脱炭素の潮流が加速するなか、共同配送や貨物シェアリングは“選ばれる荷主”になるための実践的な解決策です。重要なのは、完璧を目指して立ち止まることではなく、小さな実証からデータを積み重ね、信頼ある連携を広げていくこと。荷主と物流事業者が互いに協力し合えば、空車という大きなムダは必ず削減できます。積載効率を高める取り組みこそが、持続可能な物流の未来を切り拓く最大の鍵となるのです。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。