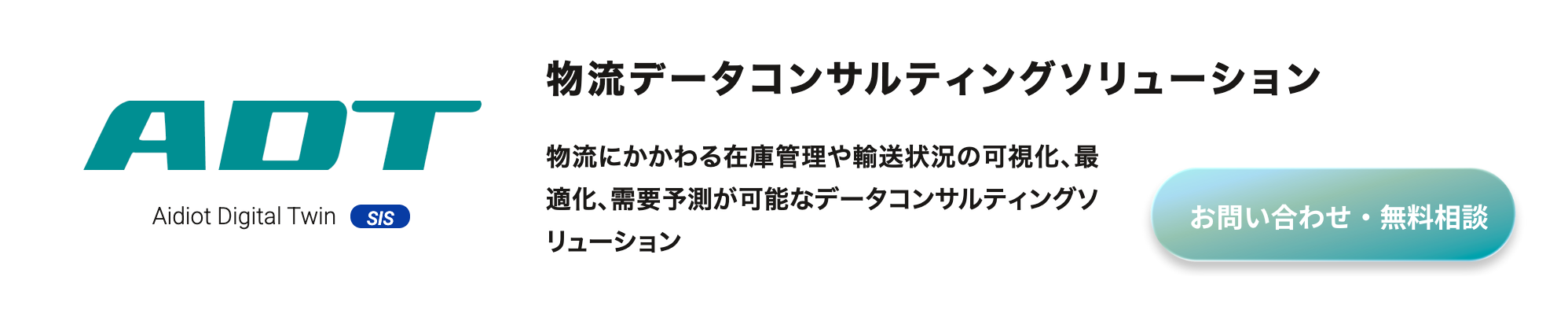はじめに
2025年、物流コストの上昇が止まりません。燃料・人件費の高騰、2024年問題によるドライバーの労働時間規制、再配達や都市部配送の増加といった課題が複雑に絡み合い、2026年には輸送力そのものが不足すると警鐘が鳴らされています。荷主企業にとって、物流はこれまで以上に「利益を左右する経営テーマ」へと変わりつつあります。
本記事では、CLOがこの難局をどう乗り越えるべきか。最新動向を踏まえながら、今日から着手できる実践的な戦略を紹介いたします。
▼物流コストとは?こちらもチェック
物流コスト高騰の背景 ― 3つの要因
物流コストが高騰してる原因は、一つの理由ではありません。労働規制、国際情勢、脱炭素など複数の課題が同時発生し、企業努力だけでは吸収しきれない状況になっています。ここでは、特に影響の大きい3つの要因を整理します。
①人手不足と2024年問題:拘束時間規制による輸送力低下
人手不足は、トラックドライバーの高齢化が影響しています。若い人材の参入が追いついていません。そこに2024年4月に働き方改革関連法が適用され、トラックドライバーの残業時間が年960時間に制限されたことが重なり、これまで長時間労働で支えてきた輸送力が大きく縮小しました。
結果として、稼働時間の制約により長距離輸送が成立しにくくなり、「運べる荷物そのものが減る」という本質的な課題が表面化しています。輸送力が不足すればするほど、限られた枠を確保するために運賃は上昇し、企業の物流コストを圧迫します。まさに、徹底した効率化でなんとか回っていた物流が、物理的な限界に突き当たっている状況です。
②燃料・エネルギー価格の上昇:国際情勢の影響
燃料やエネルギー価格の高騰は、物流コスト上昇の大きな要因のひとつです。グローバルな需給バランスの変化や、不透明な国際情勢が続く中、軽油価格は安定しにくい状況が続いています。物流は燃料への依存度が非常に高く、価格がわずかに上がるだけでも輸送コストを大きく押し上げます。
さらに、コスト増は輸送だけに留まりません。倉庫の冷暖房や冷凍・冷蔵設備を稼働させるための電力費も上昇し、庫内作業に必要なフォークリフトや車両の維持、タイヤやオイルなどの資材費にも影響が及んでいます。つまり、物流のあらゆるオペレーションにおいて、エネルギー価格の高止まりが継続的な負担となっているのです。
この状況が長期化するほど、単なる吸収努力では対応できず、コスト見直しと構造改革が不可避になっていきます。企業に求められるのは、「燃料を使わない選択肢をどう増やすか」という視点です。
③脱炭素・ESG要請:追加投資が必要になる一方で回収が課題
脱炭素の流れが世界的に加速し、企業にはCO₂排出削減の取り組みが強く求められるようになっています。物流領域はその中でも排出量の多くを占めるため、対策の優先順位は年々高まっています。しかし、この取り組みには避けられない現実があります。それは「投資が先行し、回収が後からついてくる」ということです。
EVトラックや水素車を導入すれば排出削減効果は大きいものの、車両価格は依然として高く、充電・水素ステーションなどのインフラ整備もままなりません。倉庫でも、省エネ設備・自動化システム・再エネ導入といった取り組みには初期コストが重くのしかかります。加えて、CO₂削減の成果は「もし対策をしなかった場合」と比較しなければ見えにくく、社内で投資価値を伝えるのが難しいという課題も付きまといます。
一方で、脱炭素はもはや“環境配慮”というレベルではなく、金融機関や取引先からの評価に直結する経営課題になりました。特にScope 3(サプライチェーン全体の間接排出)の削減要求は強まり、対応を後回しにするほど競争力は低下してしまいます。
CLOが注視すべき物流KPI
物流コスト上昇や輸送力不足が続くいま、CLOには「現状を可視化し、改善の打ち手を明確にする」役割が求められます。そのための軸となるのがKPIです。ここでは、特に注視すべき5つの指標を解説します。
①積載率
もっとも効果が出やすいKPIの一つが積載率です。積載率とは、トラックやコンテナなどの輸送手段において、積載可能な容量に対して実際に積み込まれた貨物の割合を示す指標です。
1%改善するだけでも輸送コストへの影響は大きくなります。積載率の向上には、AIやデータを使用した需要予測・共同配送・ルート最適化といったあらゆる施策があります。
物流効率化法では、物流効率化に向けた取組みを行うことで、積載率を全体の車両で44%に増加する目標を立てています。
▼あわせて読みたい!
②荷待ち時間
荷待ち時間とは、トラックドライバーが荷物の積み下ろしを待っている時間です。しばしば長時間に及びます。納品先の受け入れ態勢が整っておらず、現場でドライバーが順番待ちしている場合などが含まれます。
③荷役時間
荷役時間とは、物流の現場において「貨物の積み込み・積み下ろし・仕分け・運搬などの物理的な取り扱い作業全般を指します。
荷役時間は様々な原因で長時間に及んでしまうことが多いため、時間削減が求められています。荷役作業の標準化や事前予約・受付システムの利用で改善が可能です。
物流効率化法では、物流効率化に向けた取組みを行うことで、トラックドライバー1人当たり年間125時間の拘束時間の短縮(1運行の荷待ち時間・荷役等時間を2時間以内、1回の受渡しごとの荷待ち時間・荷役等時間を1時間以内にする )する目標を立てています。
▼あわせて読みたい!
④輸送コスト比率
輸送コスト比率とは、売上に対して輸送コストが占める割合を示す指標です。たとえば売上100億円に対して輸送費が10億円なら、輸送コスト比率は10%。
この数値が高いほど、物流が利益を圧迫していることを意味します。輸送コストは燃料価格の高騰や運賃改定など外部環境の影響を受けやすいため企業競争力とのバランスを見ながらコントロールする視点が求められます。
⑤CO₂排出量
CO₂排出量は、ESG経営における最重要指標のひとつです。
排出量の多くがScope 3となるため、企業単独では管理が難しい一方で、削減余地が大きい領域でもあります。
例えば、積載効率の改善や配送ルートの最適化、鉄道・船舶を活用するモーダルシフト、EV・水素トラックの導入など、物流改革で実施する施策はそのままCO₂削減効果に直結します。
事例に学ぶコスト削減の打ち手
豊通物流株式会社 豊田営業所:バース予約システムで待機時間60分→20分に短縮
豊通物流株式会社 豊田営業所は、バース予約システム「MOVO Berth」を導入し、トラックの待機時間削減と作業効率化を実現しました。
導入前は、早朝に車両が集中し、待機所とバース間の移動・連絡が煩雑だったため、入出荷双方の予約をデジタルで管理し、納品希望時間やバース計画を踏まえたスムーズな受付体制を構築しました。導入後、トラックの待機時間は平均60分から20分へと大幅短縮、さらに呼び出し業務(月900分相当)もゼロ化を達成しています。
出典)
https://hacobu.jp/case-study/1814/
株式会社NX総合研究所:共同配送化による物流コスト削減
株式会社NX総合研究所は、同業種に属するパソコン周辺機器メーカー2社様を対象に、共同配送を活用した物流効率化プロジェクトを実施しました。
本取り組みにより、物流コストの削減に加え、CO₂排出量を28%削減する成果を収めています。
当初、各社様では個別に納品、積載効率の低下や車両稼働の重複が課題でした。NX総合研究所では、詳細なデータ分析やヒアリング、現地視察を通じて改善ポイントを抽出し、まずは短期的な施策として貸切車両による合わせ積み配送を導入しました。
中長期的には、更なる運賃の削減、荷役作業の効率化を目指しています。
出典)
https://www.nx-soken.co.jp/topics/case-11
アサヒロジ株式会社:入庫・格納作業時間削減
アサヒロジ株式会社は、倉庫業H社様においてホーム下から荷役できる「水平流動ラック」を導入し、入出庫動線を再設計することで、現場の省力化と安全性向上、ならびに作業効率化を実現しました
入庫・格納作業時間を1日あたり約26時間削減(期間合計で▲37.3%)し、処理能力は624函/時間(2021年)→777函/時間(2022年)へ向上
さらに入庫車両の待機時間を毎月約30分削減し、2時間以上待機した車両の比率も約10%減少したとされています(計測期間:2022年1~3月)。
これらの成果は、荷役・荷待ち時間の短縮を通じて車両稼働や人件費の効率化に資する取り組みとして位置づけられます。
出典)
https://www.alogi.co.jp/case_study/h/
AIとデジタルツインで未来の最適化へ
物流業務は、長年「経験と勘」に支えられてきましたが、輸送力不足やコスト高騰が続く中、そのやり方では持続できません。
そこで注目されているのが AI×デジタルツインによる未来予測型の最適化です。
実際の物流をデジタル空間にそっくり再現し、「もしこうしたら?」を事前に検証しながら最適解を導き出します。
▼あわせて読みたい!
改善シナリオの自動生成
AIは、物流現場が抱える課題に対して、複数の改善シナリオを自動で提示できます。たとえば「積載率を2%高めたい」「荷待ち時間を30分短縮したい」といった目標を設定すると、AIは物量データや配送計画、過去の実績をもとに、どのような施策が最も効果を発揮するかを導き出します。
施策案は、荷役の動線を見直してフォークリフトの移動量を減らすことや、出荷時間をずらして混雑を避ける工夫、配送順序の変更による滞在時間短縮など、多岐にわたります。一つひとつは現場でも思いつく改善かもしれません。しかし、それらを同時に組み合わせ、全体最適となるパターンを数千通りも比較することは、人間では到底不可能です。
AIは、それぞれの施策を試した場合の積載率の改善幅、燃料コストの削減量、CO₂排出への影響などを事前に数値化して提示します。これにより、担当者はどの施策に投資すべきかを納得感を持って判断できます。
配車・拠点配置の最適化
AIは、車両やドライバーの稼働状況、道路の混雑情報、納品時間の制約など、数多くの条件を同時に考慮し、今この瞬間に最も効率のよい配車計画を導き出すことができます。従来は熟練担当者の経験に依存していた判断を、データに基づく最適解へと引き上げることで、日々の配送品質を安定させながら、輸送力の最大活用を実現します。
大きな効果を発揮するのが「拠点配置の見直し」です。物流ネットワークをデジタル上に再現し、倉庫の数や立地を変えた場合にどれだけ総輸送距離が減るのか、リードタイムが短縮できるのか、在庫日数や運行コストはどう動くのか。こうした影響を事前にシミュレーションできます。
CO₂削減効果のシミュレーション
脱炭素やESGへの対応が企業価値を左右する今、物流で実施する施策がどれだけ CO₂削減につながるのかを、事前に数値で示せることは大きな武器になります。AIとデジタルツインを活用すれば、モーダルシフトを行った場合の排出量削減効果や、積載率を改善した際にどれほど燃料使用量が減るのかといった相関を正確に算出できます。また、EVや水素トラックを導入した際の削減量と、そのためにかかる車両投資・充電設備費などの負担額を比較し、費用対効果まで提示することが可能です。
削減効果を数値で証明できるので、取締役会や荷主企業に対しても納得感のある説明ができ、投資決定のスピードが大幅に向上します。さらに、企業理念やサステナビリティ目標との整合性が明確になり、ESG評価の向上にも直結します。
お問い合わせはこちら
全体最適に向けたロードマップ
物流の改善を本当に成果の出る取り組みにするためには、「やみくもに効率化する」のではなく、段階を踏んで取り組むことが重要です。まずは現実を正しく把握し、小さな成功を積み上げ、最終的にサプライチェーン全体を変えていくことが重要です。
データ標準化とKPI可視化
最初のステップは、現状を正しく見ることです。
積載率、待機時間、輸送コスト比率など、共通の基準でKPIを整理し、データを一元管理します。現状とのギャップが具体的に見えるからこそ、改善の優先順位が明確になります。
拠点単位での改善施策実施
次に、現場で実際に成果が出る改善を行います。
バース予約による混雑解消、荷役作業の標準化、配車最適化による稼働率向上などです。
小さく始めて確実に成果を出し、その成功事例を横展開することで、現場の納得と経営のコミットが両立します。
サプライチェーン全体への展開
最後のステップは、組織をまたいだ全体最適です。
拠点間の在庫再配置や、中継輸送・共同配送の導入、DXによる一体運用など、企業全体の競争力を高める取り組みにシフトしていきます。
まとめ:物流コスト高騰はCLOのリーダーシップで乗り越える
本記事では、物流コスト高騰の背景と、CLOが取るべき戦略的な改善アプローチについて解説してきました。輸送力不足や燃料価格の上昇、脱炭素対応など、物流を取り巻く課題は待っていても解決しません。むしろ今後さらに、高止まりする構造が強まっていくとみられています。
そうした中で、重要になるのがCLOの存在です。物流を単なるコストではなく、企業競争力を左右する「戦略資産」として捉え、データに基づいた意思決定をリードできるかどうかが、成長の分岐点になります。
まずはKPIの可視化とデータ標準化から着手し、成功体験を拠点ごとに積み上げ、全体最適へと展開していきAIやデジタルツインをはじめとしたDXの力を活かすことで、未来を見据えた物流改革が動き出します。
データから未来を予測するサービス「ADT」で物流自動化を実現!
「ADT」とはアイディオットデジタルツインのことで、物流に関わる在庫管理や配送などのデータをリアルタイムで可視化・分析するシミュレーターです。このツールは、数十種類のデータセットを集約し、物流業務の最適化と効率化を支援します。膨大なデータを用いて行うため、限りなく現実に近いシミュレーションをすることができます。
「ADT」では、可視化、シミュレーション、物理空間の実装が可能です。「ADT」を利用し、物流での自動化をシミュレーションし、車両情報の可視化や人員のシミュレーションなどにより、いきなり行う危険性を減らし、スムーズな物流自動化に踏み出すことができます。
お問い合わせはこちら
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。