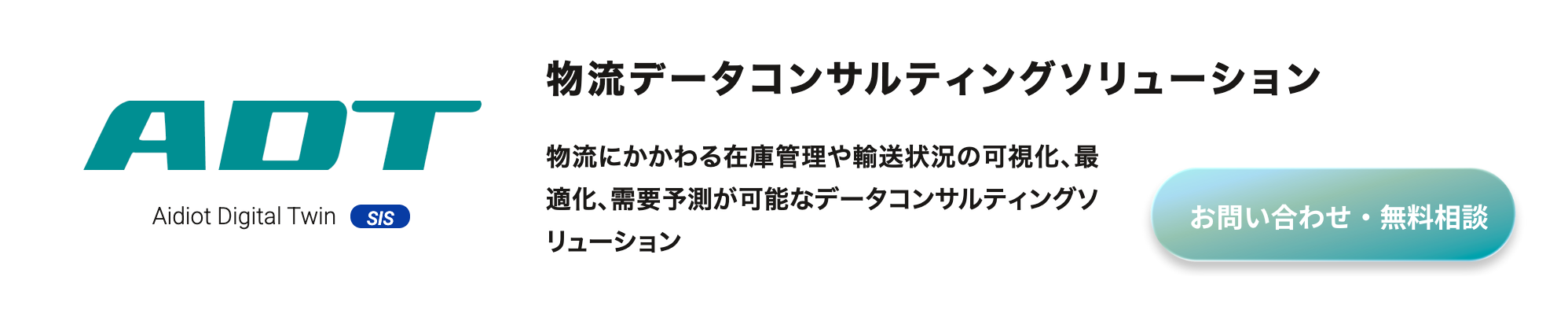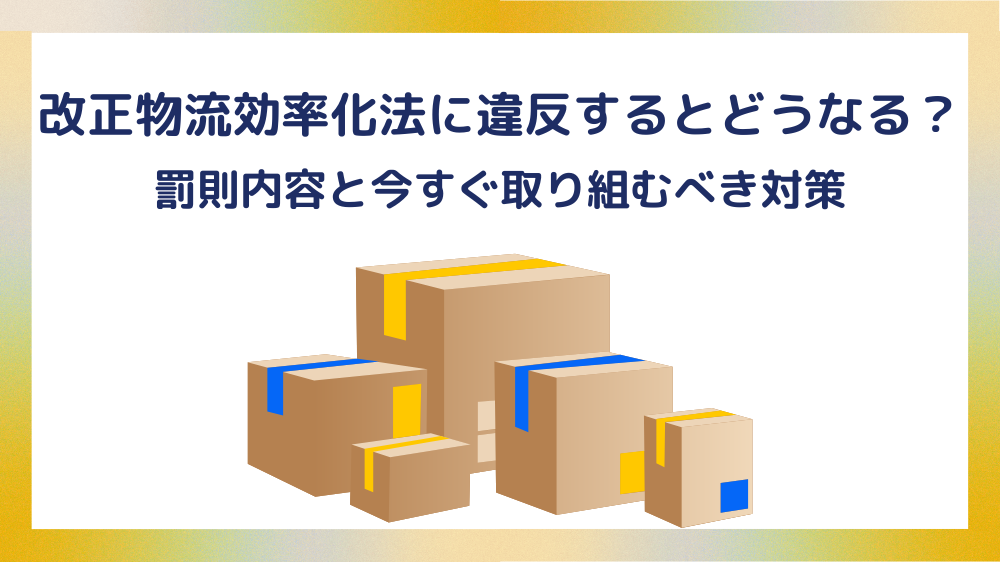
はじめに
2024年の法改正を受け、物流の「効率化」はもはや努力目標ではなく、法的責務となりつつあります。
改正物流効率化法(正式名称:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)は、荷主・物流事業者に対し、荷待ち時間の削減・荷役時間の短縮・積載効率の向上を義務化へと段階的に進めています。
本記事では、違反時の罰則内容と、企業が今すぐ着手すべき実務対応を整理します。
改正物流効率化法のポイントを再確認
改正物流効率化法とは
改正物流効率化法は、物流の生産性向上とカーボンニュートラル実現を目的に、2024年に国土交通省・経済産業省が共同で改正した制度です。
これまで努力義務だった取り組みを、2026年度以降、一定規模の企業には義務化・罰則付きで適用します。
▼あわせて読みたい!
施行スケジュール
施行スケジュールは次のとおりです。
2025年4月:努力義務の施行(全荷主・物流事業者対象)
2026年4月以降:特定事業者への義務化・罰則適用
特定事業者(大規模荷主・3PL・物流統括事業者など)には、
① 物流統括管理者(Chief Logistics Officer/CLO)の選任義務
② 中長期効率化計画の策定・報告義務
③ 国への定期報告・データ提出義務
が課されます。
違反時の罰則と行政対応
改正物流効率化法は「努力義務」から「実効性担保」へと踏み込んでいます。違反した場合、以下の行政処分や罰則が科される可能性があります。
| 違反内容 | 想定される処分・罰則 |
| 中長期計画・報告書の未提出 | 勧告 → 公表 → 命令 → 50万円以下の罰金 |
| CLO(物流統括管理者)の未選任 | 100万円以下の罰金、20万円以下の過料 |
| 虚偽報告・改ざん | 命令違反として100万円以下の罰金 |
| 勧告・命令への不履行 | 公表・命令違反罰則(100万円以下) |
| 立入検査拒否・妨害 | 50万円以下の罰金 |
さらに、「企業名の公表」が行われた場合、社会的信頼の失墜・取引停止など、企業の評判が悪化することによって生じる、信用の低下やブランド力の低下といったリスクが発生します。
行政指導による「指名停止」や「認定取消」もあり得るため、罰金以上にブランド毀損が深刻なリスクといえます。
荷主企業が取るべき3つの実務対策
①輸配送データの「可視化」とKPI管理
改正物流効率化法では、積載率や待機時間の改善などに荷主も主体的に取り組む責任が明確化されました。しかし、多くの企業では「どの地点で、どの程度非効率が生じているか」を把握できていないのが実情です。
国土交通省は今後、荷主・物流事業者双方からの定量的データ報告を求める方向を打ち出しており、データ可視化は法令対応・経営管理の両面で不可欠となります。
⚫︎何をすべきか
KPI設定の例:
積載率(%)・待機時間(分)・車両稼働率(%)・1輸送あたりCO₂排出量(kg)
データソース:
配送実績データ(TMS/WMS)・ドライバーアプリ・倉庫入出荷履歴
⚫︎どう進めるか
- 現状データの整備(「見える化できていない領域」を特定)
- 重要KPIの定義と目標値の設定
- 可視化ダッシュボードの構築(BI/SaaSツール活用)
- 月次モニタリングと改善施策のPDCA運用
②荷主・運送事業者の「協働体制」構築
従来は「荷主=発注者」「運送業者=受託者」という上下関係でしたが、改正法はこの構造を改め、「物流の適正化・効率化を協働で進める責務」を双方に課しています。
⚫︎何をすべきか
・発着時間・納品リードタイムの再設計
・複数荷主の共同配送・共同幹線輸送への参画
・鉄道・船舶を組み合わせたモーダルシフト検討
・配送条件(時間指定・ロット単位)の見直し
⚫︎どう進めるか
- パートナー運送会社とのKPI共有会議(月次)
- 共同配送・シェア便の経済効果をシミュレーション
- サプライヤー・顧客との発着スケジュール最適化協議
- モーダルシフト・中継拠点再構築の事業計画化
③「法令準拠+ESG対応」を統合した運用体制整備
法令対応だけでなく、物流は今やESG・サステナビリティ評価の対象です。Scope3(サプライチェーン全体)のCO₂排出量報告義務化が進む中、物流データは「規制対応」だけでなく企業価値を高める非財務情報としても扱われます。
⚫︎何をすべきか
・「法令遵守」「脱炭素」「労働環境」の三位一体での物流戦略策定
・改正物流効率化法と連動した社内ガバナンス体制の整備
・ESG報告書・統合報告書での物流関連KPI開示
⚫︎どう進めるか
- CLOやSCM統括部門を中心にESG連携を明確化
- CO₂排出量を可視化できるシステムの導入
- サプライヤーとの「グリーン物流協定」締結
- 国交省・環境省の補助制度・認定制度を活用
改正物流効率化法への対応は、単なる「罰則回避」ではなく、企業の持続可能性・競争力の基盤づくりです。
・データ可視化 → 客観的経営判断
・協働体制 → 輸送力・コストの安定確保
・ESG統合 → ブランド価値と取引信頼の強化
いま荷主企業に求められているのは、“守りの法令対応”から“攻めの物流経営”へ転換することです。
違反を避けるだけでなく、“選ばれる企業”へ
改正物流効率化法は「罰則法」ではなく、企業の競争力を再定義する分岐点です。荷主企業が法令順守と効率化を同時に進めることは、もはや社会的要請であると同時に、サプライチェーン全体から“選ばれる条件”となりつつあります。
法令順守が「取引条件化」する時代
2025年4月1日施行の改正法に基づき、国(国土交通省、経済産業省など)は、荷主・物流事業者が取り組むべき物流効率化の措置について判断基準を策定します。
国は、判断基準に基づいて事業者の取り組み状況を調査し、必要に応じて指導や助言を行います。指導に従わない悪質な事業者に対しては、その事実を公表することが可能となります。これにより、法令違反や不適切な取引を是正し、業界全体の健全化を図ります。
すでに大手メーカーや小売では、荷待ち時間の上限設定や、CO₂排出量・積載率データの報告義務化などを取引条件に組み込む動きが広がっています。つまり、物流の「適正化・見える化」に取り組む企業こそが、パートナー企業として“選ばれる存在”となるのです。
物流効率化がESG評価・企業ブランドに直結
ESG投資やサステナビリティ経営の文脈では、Scope3(サプライチェーンによる排出)の開示が国際的に求められています。
とくに製造・小売・商社など荷主企業は、物流を通じたCO₂削減や労働環境改善の取り組みをESGスコアやIR開示に直結させる動きが進んでいます。
物流の効率化は、単なるコスト削減ではなく、CO₂排出量削減による脱炭素貢献や、荷待ち・荷役削減による労働環境改善、共同配送による地域連携・社会価値創出といった複数の非財務価値を同時に実現します。
これらを“数字で語れる企業”が、投資家・顧客・パートナーからの信頼とブランド価値を獲得していくのです。
2026年を見据えた「CLO」の役割
今後、物流は経営の中核機能として位置づけられるでしょう。調達・生産・販売を横断して物流を統括し、サプライチェーン全体の最適化、脱炭素・人材戦略との統合、データガバナンスの確立を推進する役割を担うのが、CLO(Chief Logistics Officer)=物流最高責任者です。
CLOは単なるオペレーション管理者ではなく、経営戦略と社会的責任を結びつける“橋渡し役”。
物流の可視化・効率化・脱炭素を推進することで、企業の持続可能性を支える「戦略的ポジション」としての重要性が高まっています。
▼あわせて読みたい!
まとめ
改正物流効率化法は、物流を取り巻くルールを変えるだけでなく、企業のサプライチェーン戦略そのものを再設計するきっかけを与えています。
本記事で見てきたように、ポイントを正しく理解し、「理解」と「実務」のギャップを埋め、KPI設定や可視化、部門横断の仕組みを整え、さらに守りの対応を「攻め」の戦略へと転換すること。
これらのステップはすべて、CLOがリーダーシップを発揮することで初めて実現可能になります。
法令遵守を“義務”にとどめるか、“競争力強化の武器”に変えるか。その分岐点に立っているのが今の物流現場です。
2026年問題を目前に控えた今こそ、CLOは全社の羅針盤として、法対応を起点に物流改革を推進しなければなりません。「理解」を「実務」へ、そして「守り」を「攻め」へ──その一手をどう打つかが、これからの企業の成長を決定づけます。
データから未来を予測するサービス「ADT」で物流自動化を実現!
「ADT」とはアイディオットデジタルツインのことで、物流に関わる在庫管理や配送などのデータをリアルタイムで可視化・分析するシミュレーターです。このツールは、数十種類のデータセットを集約し、物流業務の最適化と効率化を支援します。膨大なデータを用いて行うため、限りなく現実に近いシミュレーションをすることができます。
「ADT」では、可視化、シミュレーション、物理空間の実装が可能です。「ADT」を利用し、物流での自動化をシミュレーションし、車両情報の可視化や人員のシミュレーションなどにより、いきなり行う危険性を減らし、スムーズな物流自動化に踏み出すことができます。
お問い合わせはこちら
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。