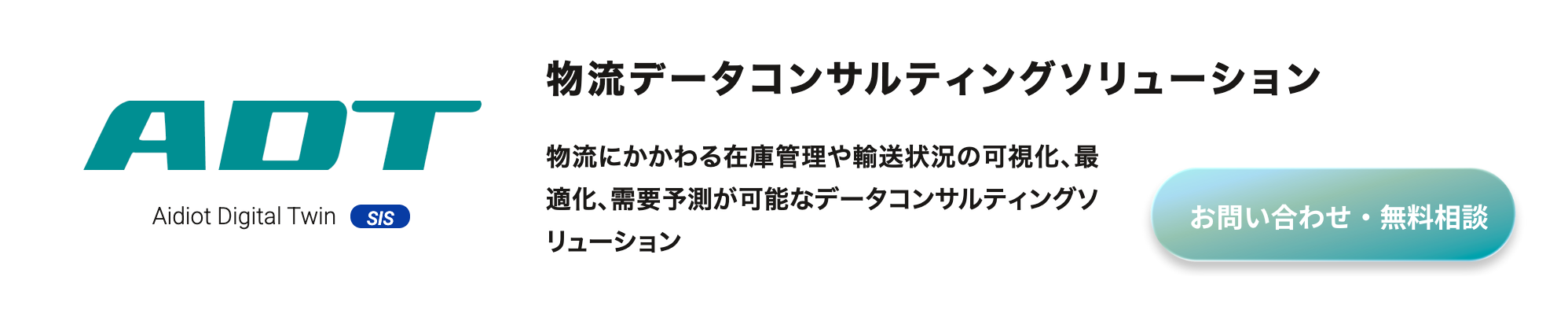はじめに
2024年問題を経て、いよいよ本格的に施行が進む「改正物流効率化法」。これまで物流効率化は運送会社や倉庫事業者の努力に委ねられるケースが多くありました。しかし改正後は、荷主にも荷待ち時間削減や発着時間の調整、積載効率向上に向けた取り組みといった新たな責任と義務が課され、企業全体で取り組むことが求められています。
とはいえ、法律を理解しただけでは不十分です。重要なのは「自社の現場にどう落とし込むか」。経営層からCLO、そして現場担当者までが一枚岩となり、法対応を単なる義務で終わらせず、コスト削減・ESG対応・競争力強化につなげることができるかどうかが問われています。
本記事では、改正法の要点を整理しながら、CLOが実際の現場オペレーションに落とし込むための実務的なアプローチを紹介します。
改正物流効率化法のポイントを再確認
荷主の新たな責任と義務
改正物流効率化法の大きな特徴は、荷主企業に明確な責任が課された点です。従来は「運ぶ側」に効率化の努力を依存していた構造から、荷待ち時間削減や発着時間の調整、積載効率向上に向けた取り組みを荷主自ら推進することが義務化されました。これにより、荷主は物流を「委託コスト」ではなく「経営課題」として捉える必要が出てきたのです。
物流事業者との協働
物流事業者との協働が必要な背景として、深刻なドライバー不足と労働時間規制(2024年問題)があります。これまでの「無理な発注を物流事業者が吸収する」仕組みは崩壊しつつあります。
さらに燃料費高騰や脱炭素対応のプレッシャーも加わり、荷主と物流事業者が共同で効率化を進めなければ、持続可能な輸送網を維持できない状況になっているのです。
具体的には、共同配送・モーダルシフト・標準化ガイドラインに沿ったデータ連携など、荷主と事業者が対等なパートナーとして改善を進めることが求められています。
▼あわせて読みたい!
なぜ「理解」と「実務」の間にギャップが生まれるのか
部門ごとの温度差
法改正の情報を把握しているのは経営企画や法務部門が中心であり、現場や営業部門には十分に伝わっていないケースが多くあります。結果として「知っている人」と「動くべき人」の間で温度差が生じ、実務への落とし込みが遅れます。
指標が共通化されていない
改正法では「荷待ち時間の削減」「積載効率の向上」といった方向性は示されていても、具体的なKPIや測定方法は各社任せです。現場では「どの数字を追えばいいのか」が不明確になり、取り組みが形骸化してしまうリスクがあります。
投資対効果が見えにくい
システム導入やデータ整備には一定のコストがかかります。しかし「どれくらい待機時間が減り、何円分の輸送コストに直結するのか」が可視化されないと、経営層の意思決定が進まず、現場改善が後回しになりがちです。
荷主と物流事業者の利害調整
荷主は「コスト削減」、物流事業者は「労働環境改善」と、優先順位が異なることがあります。この利害のズレが解消されない限り、協働の仕組みが形式的になり、実務が進みにくいのです。
CLO必見!具体施策への落とし込みの考え方
KPI設定【積載率、待機時間、CO₂排出量】
まず必要なのは、物流効率を測る共通の物差し=KPIを明確にすることです。積載率や待機時間といったオペレーション指標は、直接コストに結びつきます。またCO₂排出量は、サステナビリティ経営に不可欠な要素であり、ESG報告や取引先からの要請にも対応できます。CLOは「何を改善すべきか」を数字で定義し、全社に共有することがスタートラインです。
データ収集と可視化
KPIを設定しても、データがなければ改善はできません。そこで重要なのが、以下のような現場からデータを集め、可視化する仕組みです。
・待機時間:バース入構から作業開始までの時間をデジタル記録
・積載率:車両ごとの積載実績をシステムで管理
・CO₂排出量:輸送距離や燃料消費量を自動集計
サプライチェーン全体を見渡す視点
物流効率化は一企業の努力だけでは限界があります。CLOは、調達・製造・販売を含むサプライチェーン全体を見渡し、最適化を設計する立場にあります。
例えば、営業部門の発注リードタイムを調整することで待機時間を削減できるケースや、共同配送・モーダルシフトによりCO₂とコストを同時に削減できるケースがあります。
部分最適から全体最適へ。その視点を持ち、荷主と物流事業者の協働を前提に仕組み化していくことが、改正物流効率化法を「義務」から「戦略」へと変えるカギとなります。
現場で実践されている取り組み事例
【物流拠点統合・共同配送】アークスグループ
同社は、アークスグループ内での物流拠点統合・配送共同化を可能とするべく、物量平準化、物流資材標準化、中央コントロール機能の設置等、サプライチェーンにかかるオペレーション・リソース全体を改革しました。
従来、グループ内の各チェーンでは、商圏の重複する札幌近郊においても、個別の物流網で運営をしていました。物流リソースの不足に対処するべく、2017年度よりグループ全体での物流改革に着手。2021年4月より、グループ2社の物流拠点統合と共同配送化を開始しました。
物流拠点統合・共同配送化と同時に、配送ルートも最適化し、必要車両数の削減を実現し、また拠点の大規模化により、機械化・自動化が可能になりました。その結果、物流センターの運用効率化を実現したとともに、サプライチェーンの川 上・川下にも効率化効果が波及しました。
拠点の統合・機械化を可能にした背景には、納品リードタイムの延長による物量平準化、物流資材の標準化を行ったことが挙げられ、平準化・標準化により、自動化の投資額を最小化し、然るべき投資対効果を確保しています。また、共同配送の運営を円滑化すべく、各チェーンの代表者・3PLと共同で、配送計画の中央コントロール機能を設置しました。
出典)
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/distribution_industry/pdf/003_07_00.pdf
【共同輸配送】YKK AP株式会社、大王製紙株式会社、北陸コカ・コーラボトリング株式会社
YKK AP株式会社と大王製紙株式会社、北陸コカ・コーラボトリング株式会社は、8月より、異業種3社で商品輸送の効率化に向けた共同輸送を開始しました。
これまで各社の工場から商品が届けられる先まで、片荷輸送(全ての輸送は往路のみ実車、復路は空車)で運行していましたが、大王製紙の物流グループ会社であるダイオーロジスティクス株式会社が各社の輸送を一括で行い、各社の輸送拠点を繋ぐ運行ルートにしたことで空車での輸送距離を縮め、実車率を向上させました。
本取り組みで、CO2排出量では年間71.6トン(34%)、トラックドライバーの運転時間においては年間1,992時間(43%)の削減を見込んでいます。なお、本取り組みは、国土交通省が募集する令和7年度物流効率化法に基づく総合効率化計画の認定及びモーダルシフト等推進事業の認定を受けました。
出典)
https://www.ykkapglobal.com/ja/newsroom/releases/20250904
【船舶モーダルシフト】鈴与株式会社、クレシア物流株式会社、鈴与カーゴネット株式会社
鈴与株式会社、日本製紙クレシア株式会社、クレシア物流株式会社、鈴与カーゴネット株式会社で構成されたクレシア物流モーダルシフト推進協議会では、千葉県から福岡県への輸送において、従来は大型車による長距離運転輸送を行っていましたが、トレーラーへと輸送形態を変換、さらに東京-博多間のRO-RO船を活用しました。
これにより、CO2年間排出量を約48.8t(34%)削減、ドライバーの運転時間を年間1,766時間(90.2%)削減することができました。
出典)
https://www.suzuyo.co.jp/news/notice/2024103101.html
【航空と新幹線のモーダルシフト】鹿児島県、北九州市、広島県、九州旅客鉄道株式会社、ヤマト運輸株式会社
鹿児島県、北九州市、広島県、九州旅客鉄道株式会社、ヤマト運輸株式会社で構成された効率的な航空輸送の構築と推進協議会は、航空輸送(旅客・貨物機)を活用した幹線輸送と域内輸送(例:鹿児島 ~福岡)のモーダルシフトの実現を目指し、リードタイムとコスト検証を行い、また航空や新幹線利用へのモーダルシフトを促進するためにも輸送に関わるオペレーションの効率化も同時に検証していくとしています。
航空輸送、新幹線輸送を利用することにより品質向上、幹線における1日以上のリードタイム短縮と輸送コスト5%以上の削減を目指します。航空輸送の利用促進をすることで、安定的な輸送の確保と自治体や他物流会社と協業し、官民一体となって日本国の物流構築・維持へ貢献できるとし、スピード輸送による保冷輸送の構築ができることにより新たな販路拡大へ繋げることができるのではないかという見解を見せています。
出典)
https://cxhub.jp/regional-modal-shift/pdf/kagoshima_fukuoka_hiroshima.pdf
法令対応を「守り」から「攻め」へ変えるには
CLOの役割は「法令遵守の監視者」ではなく、法対応をきっかけに物流を経営戦略へ組み込む推進者です。守りの取り組みを“攻めの武器”に変えられるかどうかが、2026年を乗り越える鍵となります。
改正物流効率化法は荷主や物流事業者に新たな責任を課す一方、それをただの「コンプライアンス対応」として受け止めると、コスト負担や業務増加だけが残ってしまいます。CLOがまず押さえるべきは、法対応を最低限で終わらせず、経営価値に変える視点です。
待機時間や積載率、CO₂排出量といった法令対応で求められるKPIは、同時に経営の改善指標でもあります。
・待機時間削減 → ドライバー稼働率向上、コスト削減
・積載率改善 → 配送効率UP、CO₂削減
・CO₂削減量 → ESGスコア向上、取引先評価改善
CLOはこれらを「経営言語」に翻訳し、法令対応の延長線上で投資効果を示すことができます。
また、物流効率化は環境負荷低減とも直結しています。モーダルシフトや共同配送の取り組みを進めれば、法令遵守に加えて「脱炭素に積極的な企業」というブランド価値を獲得できます。CLOがリードすれば、調達や販売にも好影響を与えられるでしょう。
データから未来を予測するサービス「ADT」で物流自動化を実現!
「ADT」とはアイディオットデジタルツインのことで、物流に関わる在庫管理や配送などのデータをリアルタイムで可視化・分析するシミュレーターです。このツールは、数十種類のデータセットを集約し、物流業務の最適化と効率化を支援します。膨大なデータを用いて行うため、限りなく現実に近いシミュレーションをすることができます。
「ADT」では、可視化、シミュレーション、物理空間の実装が可能です。「ADT」を利用し、物流での自動化をシミュレーションし、車両情報の可視化や人員のシミュレーションなどにより、いきなり行う危険性を減らし、スムーズな物流自動化に踏み出すことができます。
お問い合わせはこちら
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。