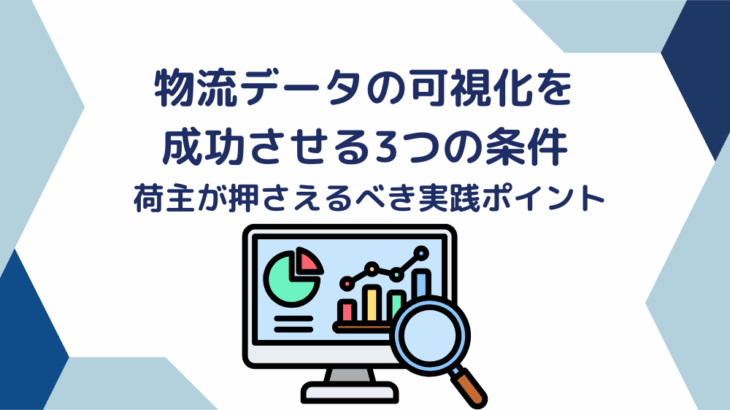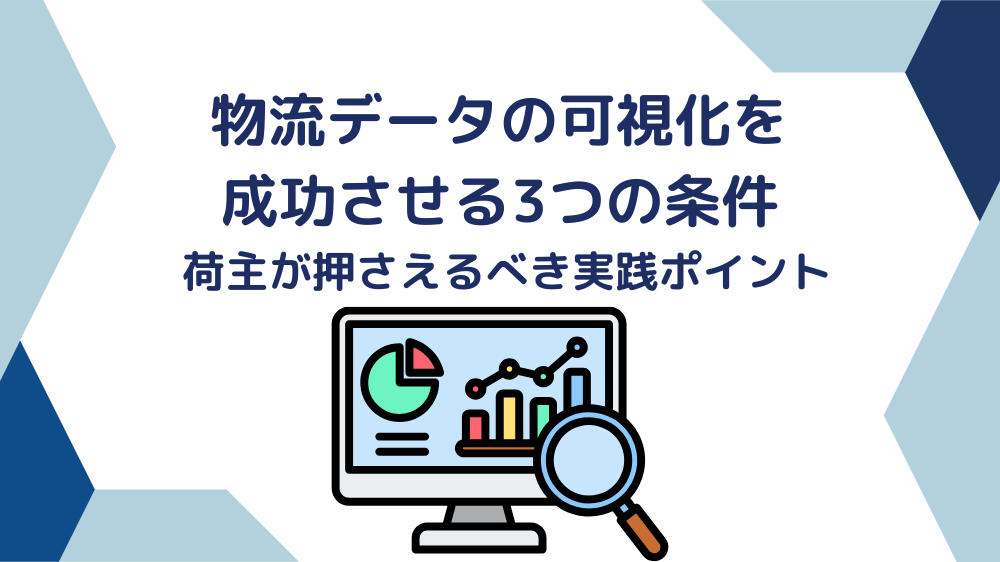
はじめに
「積載率や待機時間を“見える化”したのに、思ったほど成果が出ない」そんな声をよく耳にします。
物流データの可視化は、2024年問題や物流改正法への対応、さらにはScope 3削減など企業経営に直結するテーマです。しかし「見える化」だけでは改善につながらず、形骸化してしまうケースも少なくありません。
では、物流データの可視化を本当に成果へ結びつけるにはどうすればよいのでしょうか。鍵となるのが 「3つの成功条件」 です。
なぜ物流データの可視化は失敗しがちなのか
物流DXの第一歩として多くの企業が取り組む「データの可視化」。積載率や待機時間、配送コストなどを数値化して見える化することは確かに重要です。しかし実際には「ダッシュボードを作っただけでは現場改善につながらない」「部門ごとに数値が合わず混乱する」といった失敗例も少なくありません。なぜ可視化がうまく機能しないのか、その背景を整理してみましょう。
データがバラバラで正確性に欠ける
物流データは輸配送管理システム(TMS)、倉庫管理システム(WMS)、受発注システムなど、複数のシステムに分散しています。部門ごとに入力ルールが異なれば、同じ「積載率」でも計算式が違うケースもあります。その結果、データを統合しても数字が合わず、信頼できない「見せかけのKPI」となってしまうのです。可視化以前に、データ収集と整備の仕組みづくりが不可欠です。
現場と経営の視点が一致していない
経営層は「物流コスト削減」や「ESG対応」などのマクロ視点を重視する一方、現場では「積み残しを防ぐ」「納品時間を守る」といった目の前の課題が優先されます。このギャップを埋めないまま可視化を進めると、現場は「意味のない数字を見せられている」と感じ、改善活動が定着しません。KPIは全社の戦略と現場の実務を橋渡しできる設計であることが重要です。
「見える化」で満足して改善につながらない
データをダッシュボードに並べただけでは、単なる“現状確認ツール”に終わってしまいます。たとえば積載率が80%と分かっても、「なぜ20%が空いているのか」「どこを改善すべきか」が分からなければ意味がありません。可視化のゴールは「行動を変えること」。分析→施策立案→効果検証というサイクルに落とし込まなければ、可視化は“飾り物”で終わってしまいます。
物流データ可視化を成功させる3つの条件
物流の現場では「積載率が低い」「待機時間が長い」といった課題が日常的に語られます。しかし、感覚や経験に頼るだけでは改善の糸口をつかみにくく、データの可視化が必須となります。ただし、ダッシュボードを作れば自動的に成果が出るわけではありません。数字を“現場の行動”や“経営の意思決定”につなげるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。ここでは、その核心となる3つの条件を整理します。
条件1:正確で一元化されたデータ収集
最初の条件は「データの正確性と一元管理」です。現場ごとに異なる管理方法やシステムを使っていると、同じKPIでも算出方法が違い、比較ができません。TMS(輸配送管理システム)、WMS(倉庫管理システム)、IoTセンサーやデジタコのデータを統合し、「どの数字を見ても同じ意味を持つ」状態を作ることが出発点です。
条件2:データをリアルタイムで収集・自動更新する仕組みを持つ
Excelによる手作業集計では、可視化に遅延が生じ、改善サイクルを回せません。リアルタイムでデータを収集・更新する仕組みを導入することで、待機時間の削減や稼働効率の改善につながります。効率化の成果は「スピード」に比例します。
条件3:関係者間での共有と共通認識
せっかく正しいデータが揃っても、それを現場と経営層が別々に見ているだけでは改善につながりません。重要なのは、同じ指標を全員が同じ意味で理解し、共通の目標に基づいて動けることです。たとえば「積載率85%を目指す」という目標を営業・配車・倉庫が共有していれば、部門間の協力が進みやすくなります。
可視化で広がる可能性 ― 成功企業の事例から学ぶ
事例1:Nippon Express(NX) ― データ基盤による需給予測と人員配置最適化
日本最大の総合物流企業である Nippon Express(NXグループ)は、2020年の中期経営計画で「データドリブン経営」を掲げ、「NX Data Station」というデータ分析基盤の開発。NX Data Stationの特徴は大きく三つあります。第一に、各事業(海運、航空、自動車、鉄道、倉庫)が別々に保持しているデータを横断的に集約できる点。第二に、システムにないオフサイトデータやSaaSからのダウンロードなど、手持ちのデータも柔軟に取り込める点。そして第三に、ダッシュボードによる可視化、機械学習による需要予測、生成AIの活用など、総合的なデータ活用環境を提供している点です。
24時間稼働の大型倉庫では、需要変動に対応できず、人員配置や輸送計画に非効率が生じる課題がありました。この課題に対して、NX Data Station では、WMS(在庫管理システム)からの入出庫データ、キャンペーン情報、天候データなどを組み合わせた需要予測を実施し、結果、需給予測精度の向上、人員配置最適化、意思決定スピードが改善しました。
出典)
事例2:ニチレイロジグループ(ロジスティクス・ネットワーク)・株式会社デルソーレ
食品製造・外食向けを手掛ける株式会社デルソーレでは、点数の多い商品(約800点)を扱っており、全国納品の物流拠点ネットワークが複雑化していました。特に、拠点の保管スペース逼迫・長期在庫の滞留・パレット積載効率の低さが物流コスト・効率を圧迫している課題がありました。
取り組み内容
在庫可視化と報告体制の構築
・入庫から60日・90日以上滞留在庫をリスト化し定期的に報告
・受払実績データを日々可視化・営業部門へ共有
→長期在庫を明らかにし、営業も在庫実態を認知できる体制に
パレット積載率の改善
・倉庫でのパレット積載状況を写真撮影などで可視化
・商品ケース・梱包仕様の見直しによる形状・サイズ最適化
・梱包材料削減の工夫も併用
導入効果・成果
・長期在庫滞留を改善 → 在庫量を約3割削減
・パレットあたりの積載量向上 → 保管効率・輸配送効率の改善
・梱包材料削減・CO₂削減など環境面への効果も見られた
出典)
https://logisticsnetwork.nichirei-logi.co.jp/solution/case01/
事例3:大和ハウス工業株式会社・キヤノンマーケティングジャパン株式会社
大和ハウス工業株式会社とキヤノンマーケティングジャパン株式会社は、物流施設におけるトラックドライバーの荷待ち・荷役時間を可視化し、改善を支援するシステムを開発しました。2024年11月1日より、大和ハウス工業が開発したマルチテナント型物流施設「DPL平塚」において、当システムの効果を検証するための実証実験を開始。2025年4月以降、大和ハウス工業が展開する物流施設「DPL(ディーピーエル)」への本格導入を目指します。
本システムは、カメラ映像とAI解析を活用し、トラックの入退場からバース移動、荷役作業までを自動で検知・記録します。ドライバーの行動を分析して荷待ち・荷役時間を計測し、課題を特定。これにより荷主やテナントの物流効率化を支援し、物流施設を「保管拠点」から「効率化を実現する拠点」へ進化させ、2024年問題への対応を目指します。
出典)
https://corporate.jp.canon/newsrelease/2024/pr-0909
可視化の先に広がる物流の未来像
物流の可視化はゴールではなく、あくまで出発点です。積載率や待機時間といったKPIを「見える化」できた先には、さらに高度な予測や全体最適の仕組みが広がっています。ここでは、可視化の先にどのような未来像が見えてくるのかを整理します。
需要予測と在庫最適化の高度化
単に「今の状態」を把握するだけでなく、AIや機械学習を活用することで、需要を先読みし、在庫配置を最適化する仕組みが可能になります。販促や季節要因を取り入れた需要予測に基づき、どの拠点にどの商品を置くべきかを自動で提案する。これにより欠品リスクと過剰在庫の両方を防ぎ、コスト削減と顧客満足を同時に実現できます。
ESG・Scope 3開示対応の強化
物流データの可視化は、環境負荷の把握と開示にも直結します。積載率や輸送手段ごとのCO₂排出量を定量的に示せれば、ESG経営やScope 3(サプライチェーン全体での温室効果ガス排出)の開示に活用可能です。単なる「法令対応」にとどまらず、企業価値を高めるサステナビリティ戦略の一環として、データ活用の重要性はますます高まっていきます。
サプライチェーン全体の統合マネジメントへ
輸送・在庫・拠点のデータを統合し、リアルタイムで全体を俯瞰できれば、サプライチェーン全体を一つの仕組みとして最適化できます。たとえば、輸送遅延の予兆を検知して在庫再配置を即時に判断する、需要急増に備えて代替ルートをシミュレーションするといった対応が可能に。現場単位での改善から、企業全体、さらには業界全体の協調的なマネジメントへと進化するのが、可視化の次なるステージです。
まとめ ― データは「見える化」から「成果化」へ
本記事では、物流におけるデータ活用の課題と、可視化を成功させるための条件、さらにその先に広がる未来像について解説しました。積載率や待機時間といったKPIを「見える化」することは重要な第一歩ですが、それだけで終わってしまえば、単なる数値管理にとどまります。
本当に求められているのは、可視化によって得られたデータをもとに改善を重ね、コスト削減・生産性向上・サステナビリティ評価の強化といった具体的な「成果」へと結びつけることです。データは使われて初めて価値を生み出します。これからのCLOや物流責任者には、部分最適ではなく全体最適の視点で、可視化を経営成果に変える取り組みが求められています。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。