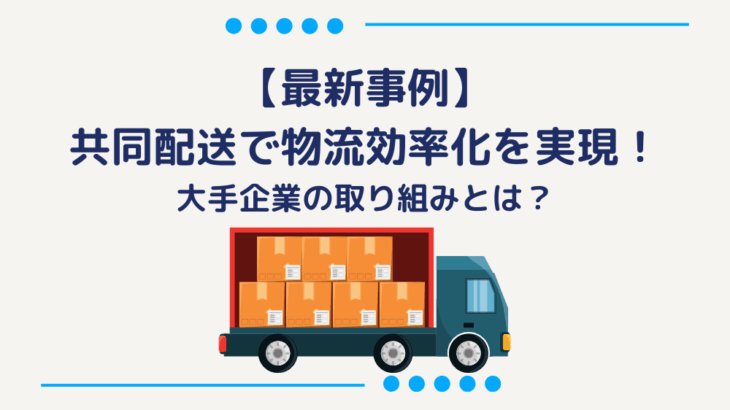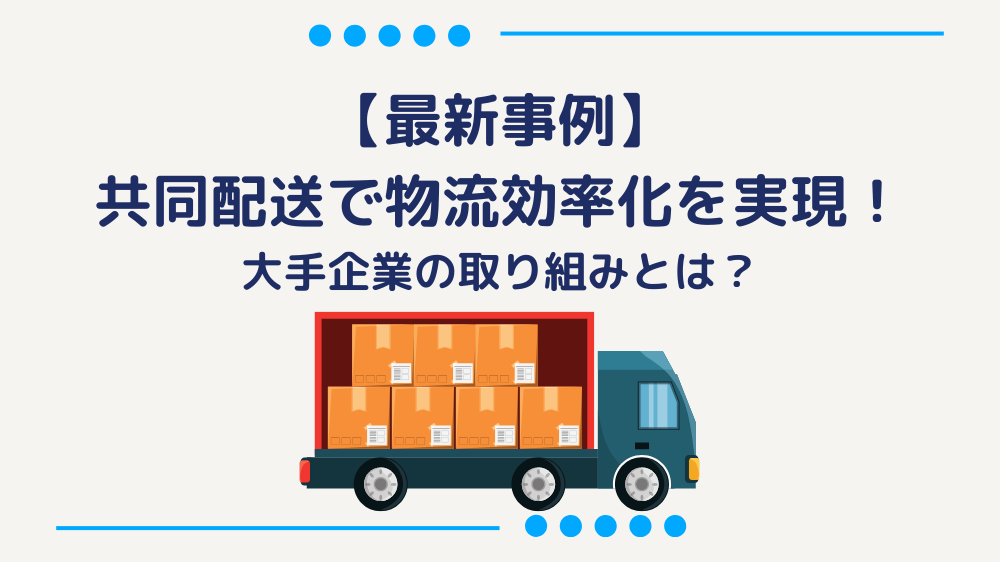
はじめに
物流業界はいま、人手不足・コスト高騰・環境負荷の増大といった「三重苦」に直面しています。特に2024年問題以降は輸送力不足が深刻化し、従来の個別配送モデルだけでは持続的な運営が難しい状況にあります。
こうした課題を打破するカギとして注目を集めているのが 「共同配送」 です。複数の企業が配送網や車両をシェアすることで、積載率を高め、コスト削減とCO₂削減を同時に実現できる手法です。
本記事では、【最新事例】として大手企業が取り組む共同配送の実践を取り上げ、共同配送の定義や仕組み、共同配送がもたらす波及効果などについて詳しく解説します。
物流効率化が求められる背景
物流業界はいま、大きな転換点に立たされています。コスト削減と効率化は長年のテーマでしたが、近年はそれが“選択肢”ではなく“必須課題”となりつつあります。その背景には、人材不足や規制強化、そして社会全体を揺るがす構造的な要因があります。ここでは、その主な理由を整理してみましょう。
ドライバー不足や物流コスト高騰
物流の最大の課題はドライバー不足です。高齢化が進む一方で若手の担い手は増えず、輸送力そのものが縮小傾向にあります。さらに燃料費や人件費の上昇が重なり、物流コスト全体を押し上げています。
結果として、輸送枠を確保するために高額な運賃を支払わざるを得ないケースも増え、荷主企業にとって経営を直撃する要因となっています。
▼あわせて読みたい!
物流危機2026に向けた構造的課題
物流危機2026年は、2026年4月に施行される改正物流効率化法により、特定荷主に新たな義務が課される2026年問題のことを指します。
2026年には「供給力不足」が深刻化すると予測されています。ドライバーの高齢化と後継不足などの人材構造、規制強化による供給力制約、都市部への配送集中、再配達増加などの都市構造と消費行動の変化、インフラ・投資負担の偏在などの構造的課題があります。これらの課題は「現場努力」だけでは解決できず、経営戦略レベルでの対応が必須となっています。
▼物流危機2026についてはこちらをチェック
なぜ「積載率」改善が重要なのか
効率化の最前線にあるのが積載率の改善です。トラック1台あたりの積載効率が低ければ、同じ荷物を運ぶのにより多くの車両と人員が必要になります。逆に、積載率を高めれば輸送コストを抑えるだけでなく、ドライバー不足の中でも限られたリソースを最大限に活かすことができます。また、積載率向上はCO₂排出削減にもつながり、ESGやScope 3対応といった企業のサステナビリティ戦略とも直結するテーマです。
▼あわせて読みたい!
共同配送とは?
物流の現場では、ドライバー不足やコスト高騰、環境負荷低減の要請など、複合的な課題が山積しています。その中で注目されているのが「共同配送」です。これは複数の企業が協力し合って配送をまとめることで、効率と持続可能性を両立させる取り組みです。単なるコスト削減にとどまらず、安定的な輸送力確保やサステナビリティの観点からも期待が高まっています。
▼あわせて読みたい!
定義と仕組み
共同配送とは、複数の会社や業者が、各自の荷物をまとめて1台のトラックに積み、一緒に運んで同じ配送先に荷物を届ける仕組みのことです。
例えば、同じエリアに配送する複数のメーカーや小売業者の商品を一台のトラックに積み合わせ、効率的に配送することが可能になります。
単独配送との違い
単独配送では、自社の商品を自社のトラックや委託便で運ぶため、積載率が低い場合でもフルコストを負担しなければなりません。一方、共同配送では複数社でコストを分担し、効率的に配送網を活用できます。これにより、空車率や部分積載といった無駄が大幅に削減されます。
期待される効果
コスト削減
積載率を高め、無駄な回送や空車を減らすことで、輸送コストを抑制できます。
環境負荷低減
車両の稼働台数を減らせるため、CO₂排出削減や渋滞緩和にもつながります。
安定輸送力の確保
ドライバー不足の中でも、リソースをシェアすることで安定的な輸送力を確保できます。特に繁忙期や突発的な需要増に強い仕組みといえます。
国内の共同配送最新事例
食品大手5社が出資するF-LINE株式会社の共同配送
味の素株式会社、ハウス食品グループ本社株式会社、カゴメ株式会社 KAGOME CO.,LTD.、株式会社日清製粉ウェルナ、日清オイリオグループ株式会社、株式会社 Mizkan Holdingsが出資するF-LINE株式会社は2025年8月28日、9月から北海道の共同配送で最適な輸送手段を組み合わせる「モーダルコンビネーション」に試験的に取り組むと発表しました。トラック運転手不足に対応し、環境負荷低減にもつなげ、札幌市から帯広市の幹線輸送で、二酸化炭素(CO2)排出量の約43%の削減を見込んでいます。
札幌市にある拠点から帯広市の中継拠点までのトラック輸送を鉄道で代替し、そこから納品先への配送はトラックを使い、モーダルコンビネーションの実用性を総合的に評価します。
食品メーカー6社とF-LINE株式会社は、北海道で2016年から共同配送を始め、23年に札幌市と北広島市の2カ所だった保管・配送拠点を札幌市内の1カ所にして効率化しました。共同配送の納品先の8割が札幌都市圏に集中しており、残りの2割は各地方に分散しています。
出典)
https://news.ajinomoto.co.jp/2025/08/2025_08_28_02.pdf
住友林業株式会社の住宅資材の共同配送
住友林業株式会社は2025年8月4日、完全子会社のホームエコ・ロジスティクス株式会社が戸建て住宅などの建設現場へ住宅資材を共同配送するサービスを提供すると発表しました。2024年1月より首都圏一都三県を対象にサービスを開始し8月1日から関西京阪神地区でもサービスを始めました。ホームエコ・ロジスティクスは建材流通業者から住宅資材の配送を受注し、配送センターから各納品現場までの配送業務を担います。
配送センターは首都圏一都三県の11カ所、関西京阪地区の2カ所に設置。輸送距離が短くなるよう配送センターを半径10~20㎞の範囲内に配置し、各納品現場への配送時間の短縮や急な資材変更、追加配送等のニーズに対応、トラックの稼働率も高めます。商物分離を徹底し、異なる仕入れ先の住宅資材を混載する共同配送で配送サービスを効率化します。
本サービスは工期に応じた物流計画に基づき、配送センターで住宅資材を集約し共同配送することで、従来と比較し配送便を約60%削減。納品現場の荷受け負担を軽減し、配送コストも約10%削減できますとしています。
出典)
https://sfc.jp/information/news/2025/2025-08-04.html
東ソー株式会社 Tosoh Corporation、三井化学株式会社 、三菱ケミカルグループ株式会社が実証実験化学品を鉄道で共同輸送
2025年7月に3社は、各社の異なる化学品を共同で鉄道輸送する実証実験を始めると発表しました。東海と中国地区のコンビナート間の物流を共同化し、二酸化炭素(CO2)排出量の削減やトラック運転手の労働時間を短縮する。実証期間は8月から2026年1月を予定しています。
実証では月に1〜2便の共同配送を計画し、従来は各社がトラックを使って輸送していました。積載量の大きい31フィートコンテナを使い、名古屋貨物ターミナル駅(名古屋市)と広島貨物ターミナル駅(広島市)、大竹駅(広島県大竹市)間を鉄道で輸送し、各社のコンビナートがある地域まではトラックでそれぞれが配送します。
2023年に経済産業省が主導する「フィジカルインターネット実現会議」に化学品のワーキンググループが設置され、約80の企業や団体が参加しており、2024年には参加団体のうち5社が、トラックによる共同配送を実証し、CO2排出量を28%削減、トラックの積載率も69%から89%に改善しています。
出典)
https://www.tosoh.co.jp/news/release/2025/20250729.html
株式会社ブルボンと岩塚製菓株式会社が連結トラック共同配送の本運行を開始
2025年7月17日、株式会社ブルボンと岩塚製菓株式会社はトラック2台分の荷物を運べる「ダブル連結トラック」を使った共同配送の本運行を開始した。新潟県長岡市にある物流会社の拠点から週2〜3便、埼玉県内にあるブルボンと岩塚製菓のそれぞれの物流拠点まで運ぶ。商品を共同配送することで、トラック運転手不足への対応と運行時の二酸化炭素の排出削減などにつなげる。
使用する連結トラックは全長25メートル。前方のコンテナに温度管理が必要なブルボンの商品、後方コンテナに岩塚製菓の商品を積載する。運ぶ商品は限定せず、そのときの需要に合わせて変更していく。埼玉からの帰りの便でも菓子などを積み、新潟まで戻ってくる。両社は2024年11月から連結トラックによる試験運行を開始し、本運行に向けての準備を進めていた。
出典)
共同配送がもたらす波及効果
ドライバー不足や輸送コストの上昇が続くなか、共同配送は単なる効率化の枠を超えて、社会全体に大きなインパクトを与える取り組みとして注目されています。コスト削減に加え、環境負荷の低減やESG対応、さらには業界の標準化を後押しするなど、長期的に持続可能な物流インフラを支える基盤となりつつあります。
CO₂排出削減による環境貢献
複数の荷主が一台のトラックを共有することで、必要な車両台数が減り、燃料消費やCO₂排出量を抑えられます。これは環境規制が強まる現代において、企業にとって社会的責任を果たす重要な手段となります。特に都市部での渋滞緩和や騒音低減など、地域社会への副次的なメリットも見逃せません。
ESG・サステナビリティへの対応
投資家や取引先から「持続可能な経営姿勢」が求められる中、共同配送はESG(環境・社会・ガバナンス)の観点でも評価されやすい取り組みです。輸送効率化によるCO₂削減は環境評価に直結し、協働体制の構築は「社会」や「ガバナンス」面での強みを示せます。結果として、企業ブランドの向上や取引先からの信頼獲得にもつながります。
業界全体での標準化・共通基盤づくり
共同配送の普及は、物流業界全体での標準化や共通基盤づくりを加速させます。これまで企業ごとに異なっていた配送ルールや運用が、協働を通じて整理・統一されることで、業界の効率性が底上げされます。また、データ共有やITシステム連携が進むことで、より柔軟でレジリエントなサプライチェーンが実現します。
共同配送を成功させるポイント
共同配送は物流効率化の切り札として注目されていますが、実際に導入・運用するにはいくつかの壁があります。単に「荷物をまとめて運ぶ」だけでは長続きせず、荷主同士の信頼関係や情報共有の仕組みが不可欠です。ここでは、共同配送を成功に導くための具体的なポイントを整理します。
競合企業間の信頼関係とルールづくり
共同配送は、しばしば競合関係にある企業同士が同じトラックや倉庫を利用する仕組みです。そのため、情報の扱いや責任範囲を明確にするルールづくりが重要です。荷物の優先順位や積載方法、コスト分担の仕組みをあらかじめ合意しておくことで、不要なトラブルを避け、持続可能な協働体制を築けます。
データ共有やITシステムの整備
配送スケジュールや積載状況をリアルタイムで把握できなければ、共同配送の効果は半減します。TMS(輸配送管理システム)やWMS(倉庫管理システム)といったツールを通じて、荷主間でのデータ共有を標準化することが求められます。特にAPIやEDIを活用したシステム連携は、情報の遅延や齟齬を防ぎ、安定した運用につながります。
小規模から始めるパイロット導入の有効性
共同配送は最初から大規模に展開すると調整が複雑になり、失敗リスクが高まります。まずは一部の地域や商品カテゴリに限定してパイロット導入を行い、実績や課題を共有しながら仕組みをブラッシュアップしていくことが有効です。小規模からのスタートで得られる成功体験が、社内外の理解を促進し、本格導入への足がかりとなります。
まとめ ― 協働が拓く物流の未来
物流業界はいま、大きな転換点にあります。ドライバー不足やコスト高騰といった構造的課題を前に、「自社だけで効率化を追求する」アプローチでは限界が見えてきました。そこで注目されているのが、「共同配送」をはじめとする協働の取り組みです。
「競争」から「協創」へ
これまで荷主企業や物流会社は、効率やコストをめぐって互いに競争してきました。しかし、輸送力不足や環境規制といった社会的課題を解決するには、リソースをシェアし合う「協創」の発想が不可欠です。協働することで、積載率の向上や待機時間削減といった成果はもちろん、持続可能な物流モデルを築くことができます。
大手企業の事例に学ぶ共同配送の可能性
今回ご紹介したように、すでに複数の企業が共同配送を実践しています。競合同士であっても輸送ルートを統合し、積載効率を高めることでコスト削減とCO₂排出削減を同時に実現している事例が出始めています。こうした実例は、他業界や中堅・中小企業にとっても参考となるはずです。
物流効率化に向けた次のアクション
今後、企業が取り組むべきは「小さく試す」ことです。特定のエリアや商品カテゴリーでパイロット共同配送を始め、実績を積み重ねながら仕組みを拡張することが成功の近道となります。同時に、データ共有やITシステム連携といった基盤整備を進めることで、協働を持続可能な形にできます。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。