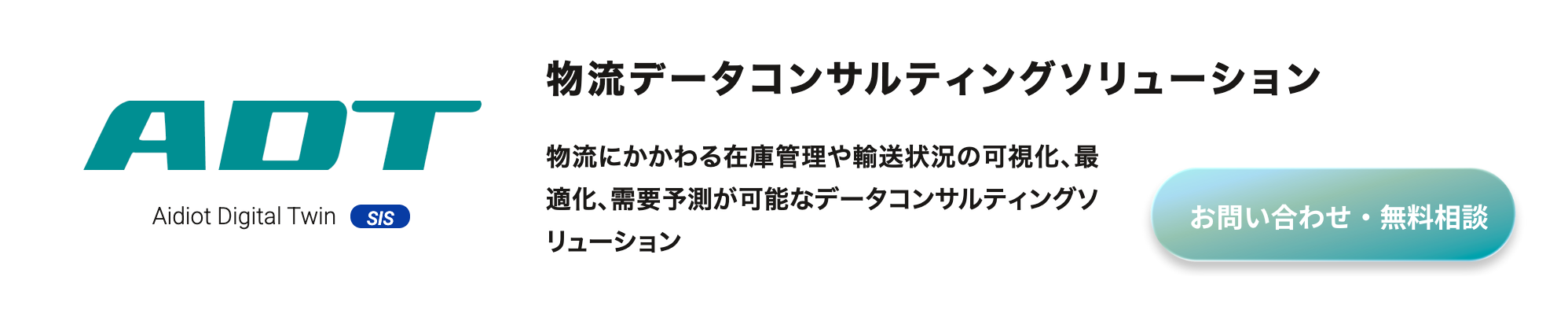働き方改革関連法によるトラックドライバーの時間外労働の上限規制(年960時間)「2024年問題」に続き、2026年4月には改正物流効率化法(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」の改正)が控えており、荷主企業の物流管理体制や業務プロセスの見直しが求められます。
特に「積載率の向上」と「待機時間の削減」は、コスト削減と法令遵守の両立に欠かせないKPIです。
しかし現状では、データが分散し、現場ごとに異なる管理方法が使われているため、正確な可視化や改善につなげられていない企業も少なくありません。
本記事では、CLOをはじめとする物流責任者が押さえておくべき実践的な改善アプローチを解説します。
なぜ積載状況や待機時間のKPI可視化が重要なのか
物流現場では「感覚的に非効率だ」とわかっていても、数字として根拠を持てないケースが多くあります。積載率や待機時間といったKPIを可視化することで、初めて改善の余地を明確にし、関係者を巻き込んだ改革が可能になります。では具体的に、なぜ今これらの指標を見える化することが重要なのかを整理してみましょう。
物流改正法で求められる荷主・物流の協働
2026年4月に施行される改正物流効率化法では、荷主に対しても待機時間削減や積載率向上への責務が求められます。そのためには物流会社だけでなく、荷主企業が主体的にKPIを把握し、改善に取り組む必要があります。数値を共有することが、両者の信頼関係と協働の前提条件になるのです。
▼改正物流効率化法とは?
物流コスト削減と効率化への直結
積載率が低ければ、同じ輸送量でもトラック台数が増え、燃料・人件費・高速料金がかさみます。逆に待機時間が長ければ、ドライバーの拘束時間が増え、稼働効率が低下します。KPIとして数値を把握することで、非効率の「見える化」とコスト削減のシナリオ策定が可能になります。
ドライバー不足・2024年問題への対応
2024年から時間外労働規制(年960時間)が適用され、長時間労働に頼る輸送体制は成り立たなくなりました。ドライバー一人あたりの生産性を上げるには、積載率向上と待機時間短縮が欠かせません。KPI可視化は、限られた労働力で最大の輸送力を確保するための基盤です。
ESG・Scope 3対応としてのニーズ
積載率の低さや過度な待機は、無駄なCO₂排出の要因になります。Scope 3対応を進める企業にとって、KPIの可視化は環境負荷を定量的に把握し、改善アクションにつなげる必須プロセスです。コスト削減とサステナビリティ対応を同時に進められる点でも意義があります。
物流改正法とKPI可視化の関係
物流の効率化を「現場の工夫」だけに任せる時代は終わりました。改正物流効率化法では、荷主企業にも積載率や待機時間改善に向けた責任が課されます。
つまり、これまで運送会社任せにされがちだった領域に、荷主自らが数値を把握・改善する体制が求められるのです。そのカギを握るのが「KPIの可視化」です。
改正法が掲げる「積載効率向上」と「待機時間削減」
改正法の大きなポイントは、輸送効率を高めるための「積載率向上」と、ドライバーの労働環境改善につながる「待機時間削減」です。
従来は荷主の要望優先で出荷調整が行われ、積載率の低下や長時間待機が常態化していました。今後はこれらが“法令遵守”の対象となり、改善の取り組みは企業の義務になります。
荷主に求められるデータ提供と協力義務
改正法では、荷主企業に対しても輸送実態のデータ提供や、物流事業者との協力が求められます。
積載率や荷待ち時間を正確に測定し、その結果を元に共同配送や出荷調整を行うといった取り組みです。これまで「物流は委託先に任せるもの」と考えていた企業にとって、大きなパラダイムシフトとなります。
法対応に向けたKPIモニタリングの重要性
法改正への対応で最も重要なのは、KPIの定期的なモニタリング体制を整えることです。積載率・待機時間をリアルタイムで把握しなければ、改善アクションをタイムリーに打つことはできません。WMSやTMSといったシステムを活用し、物流事業者との間でデータを共有できる仕組みを整えることが、法対応と同時に競争力強化にも直結します。
データ収集のための要素技術
物流の効率化や法改正対応のためには、「現場の見える化」が欠かせません。その出発点となるのがデータ収集です。これまでは紙や人手による記録が中心でしたが、今ではIoTやセンサー技術の進化により、自動的かつリアルタイムでデータを収集する仕組みが整いつつあります。ここでは、代表的な技術を整理します。
IoTセンサーやGPSによる車両・荷物追跡
トラックやコンテナに取り付けたGPSやIoTセンサーを活用することで、車両の位置情報や積載状況をリアルタイムに把握できます。温度・湿度などの環境データも取得可能で、食品や医薬品の輸送において品質管理にも役立ちます。これにより「どこに・何を運んでいるか」を即座に確認でき、輸送効率の改善やトレーサビリティ強化につながります。
デジタコ・ドラレコ連動による運行データ取得
デジタルタコグラフ(デジタコ)は速度や走行距離、時間などをデジタルデータとして記録し、法令遵守や安全運転管理に直結します。さらに、ドライブレコーダーと連動させれば急ブレーキや事故リスクの把握も可能になるため組み合わせることで、運行効率の評価やドライバーの働き方改善に役立つ精緻なデータが得られます。
RFID・バーコードでの積み込み/荷役の記録
倉庫や積み込み現場では、RFIDタグやバーコードが活躍します。商品やパレットごとにタグを付与し、スキャナーやセンサーで読み取れば、積み込みや荷役の記録を瞬時にデータ化できます。人手の記録ミスを防げるだけでなく、積載率の分析や荷待ち時間削減の根拠データとして活用できるのが強みです。
データ統合・処理を支える要素技術【データの一元化】
物流KPIの改善や法改正対応を進めるうえで重要なのは、「バラバラに存在するデータをどう一元化するか」です。車両運行データ、倉庫の在庫情報、荷主との取引データなどが分断されていては、現場改善も経営判断も属人的にとどまってしまいます。ここでは、データ統合を可能にする代表的な技術を解説します。
TMS(輸配送管理システム)による配車・積載率管理
TMSはトラックの稼働状況や配車計画を管理する基盤です。車両やドライバーの稼働状況、積載量、配送ルートをリアルタイムで把握でき、積載率や空車率の改善に直結します。手作業や勘に頼った配車業務を脱却し、データ主導で最適化できるのが大きな強みです。輸送効率化とコスト削減の“起点”になる仕組みといえます。
▼TMSとは?
WMS(倉庫管理システム)との連携による出荷データ統合
倉庫の在庫・出荷データを管理するWMSとTMSを連携させることで、輸配送と庫内業務をシームレスにつなげられます。たとえば、出荷データが自動的にTMSへ連携されれば、倉庫側の在庫情報と運送計画が一致し、余計な待機時間を削減できます。庫内作業と輸配送を一体で管理することで、サプライチェーン全体の効率化が可能になります。
▼WMSとは?
EDI・API連携による荷主・物流間の情報共有
荷主と物流会社の間で必要なデータをやり取りする仕組みがEDI(電子データ交換)です。従来は限定的なフォーマットでのやり取りが多かったものの、近年はAPIによる柔軟なデータ連携が進み、リアルタイムでの情報共有が可能になっています。発注・出荷・納品データをシームレスにつなぐことで、ミスを防ぎ、リードタイムの短縮や在庫の適正化にもつながります。
分析・可視化のための要素技術【データの見える化】
物流DXを本当に機能させるには、データを集めるだけでなく、それを「見える化」して意思決定につなげる仕組みが欠かせません。輸配送の稼働率、在庫の過不足、待機時間などを正確に把握できれば、改善の余地をピンポイントで特定できます。ここでは、分析・可視化を支える代表的な技術を紹介します。
BIツールやダッシュボードによるリアルタイム可視化
Excelや紙の帳票に頼った集計では、現場の状況をタイムリーに把握できません。BIツール(会社の中にあるさまざまなデータをまとめて、グラフや表などで見える化してくれるソフトウェア)やダッシュボードを導入することで、積載率や配送進捗、庫内の稼働率などをリアルタイムに確認可能になります。
例えば、地域別の輸送効率や時間帯ごとの待機状況をグラフ化すれば、現場改善の優先順位を直感的に判断できます。
AIによる需要予測と配車最適化アルゴリズム
従来は担当者の経験や勘に依存していた需要予測や配車計画も、AIの活用で大きく進化しています。過去の出荷データ、季節要因、販促スケジュールなどをAIが学習し、需要を精度高く予測しそれを基に最適な配車を自動で計算することで、空車率を減らしつつ、ドライバーの拘束時間も短縮できます。「欠品リスクを抑えながらコスト削減」を両立することが可能になります。
KPI可視化によって得られるメリット
物流の改善は「勘や経験」だけでは限界があります。データを基準に状況を把握し、問題を可視化することで、初めて現場と経営が同じ目線で改善に動けます。特に積載率や待機時間といったKPIの可視化は、コスト削減から労務改善、法令対応まで幅広い効果をもたらします。ここでは、その具体的なメリットを整理します。
積載率向上による輸送コスト削減
トラックが「どれだけ効率よく荷物を運んでいるか」を示す積載率は、輸送コストに直結します。可視化することで「どの便で空きスペースが多いか」が一目で分かり、積み合わせ改善や共同配送の検討が可能になります。結果として、同じ輸送量でも必要な車両台数を減らし、燃料費や人件費を抑制できるのです。
▼あわせて読みたい!
待機時間削減による労働生産性向上
荷積み・荷下ろし時の待機は、ドライバーの大きな負担であり、労働時間規制が強まる中で見過ごせない課題です。待機時間をKPIとして可視化すれば、どの拠点・どの時間帯に無駄が集中しているのかを特定できます。それにより、入出荷スケジュールの調整や庫内作業の平準化を進められ、ドライバーの拘束時間短縮と現場全体の効率化が実現します。
▼あわせて読みたい!
法令遵守とサステナビリティ評価の向上
2024年問題や2026年問題を背景に、物流の効率化は単なるコスト削減にとどまらず「企業の責務」として問われています。積載率や待機時間を可視化・改善することは、働き方改革関連法や物流改正法への対応を支えるだけでなく、ESG経営やScope3削減の観点からも評価されます。効率的な輸送はCO₂削減にも直結し、持続可能なサプライチェーン構築に欠かせない要素です。
まとめ|物流改正法を追い風にKPI可視化を進める
物流改正法の施行を前に、積載率や待機時間といったKPIの可視化は“義務的対応”にとどまりません。本記事では、データ収集から可視化までの仕組みづくりと、それを活かした全体最適の考え方について解説しました。最後に改めて重要なポイントを整理します。
データ収集・統合・可視化の三層構造がカギ
KPI可視化を進めるには、
①まず現場でのデータ収集(IoT・センサー・GPSなど)から始まり
②それをTMSやWMSに統合
③最後にBIツールやダッシュボードで可視化
この三層構造が必要です。この流れが整って初めて、数値に基づく改善アクションが動き出します。
法対応をきっかけに全体最適を目指す
法改正により、荷主と物流事業者の双方が協力して積載率向上や待機時間削減に取り組むことが求められます。これは「守りの義務」ではなく、在庫・輸送・拠点を含めたサプライチェーン全体の最適化へとつながる“攻めのチャンス”でもあります。可視化したKPIを共有し、経営レベルで意思決定に活かすことで、コスト削減だけでなく持続可能な物流基盤の強化へと発展させることができます。
データから未来を予測するサービス「ADT」で物流自動化を実現!
「ADT」とはアイディオットデジタルツインのことで、物流に関わる在庫管理や配送などのデータをリアルタイムで可視化・分析するシミュレーターです。このツールは、数十種類のデータセットを集約し、物流業務の最適化と効率化を支援します。膨大なデータを用いて行うため、限りなく現実に近いシミュレーションをすることができます。
「ADT」では、可視化、シミュレーション、物理空間の実装が可能です。「ADT」を利用し、物流での自動化をシミュレーションし、車両情報の可視化や人員のシミュレーションなどにより、いきなり行う危険性を減らし、スムーズな物流自動化に踏み出すことができます。
お問い合わせはこちら