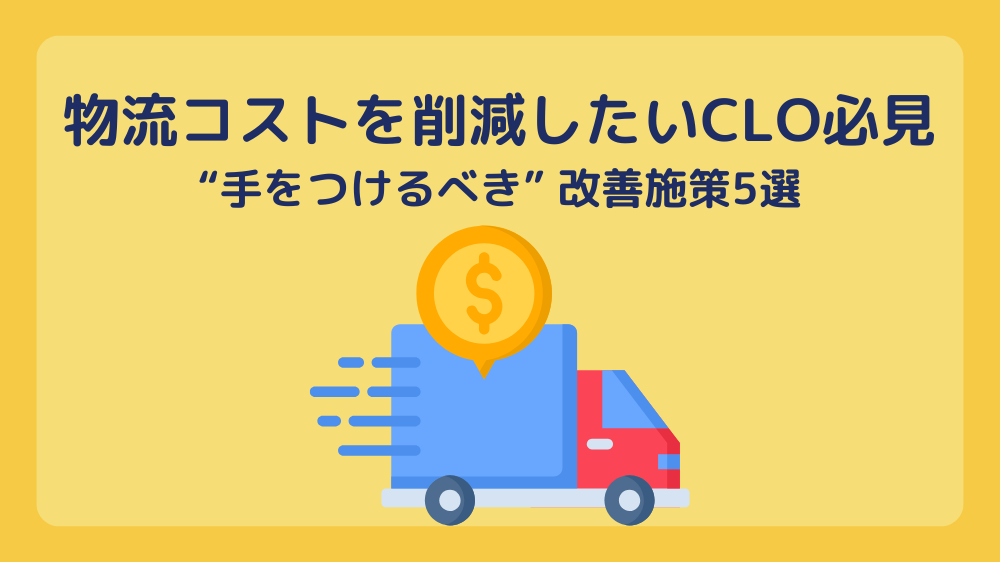
燃料費や人件費の高騰、ドライバー不足、拠点運営コストの増加など、CLOを悩ませる要因は年々積み重なっています。
現場では日々改善の工夫が行われていますが、それだけでは限界が見え始め、今や経営レベルでの戦略的なコスト削減が求められる時代です。
本記事では、数ある施策の中から「すぐに着手でき、効果が大きい」改善策を厳選してご紹介します。短期的な経費削減と中長期の成長基盤づくりを両立させたいCLOにとって、必ず押さえておきたい内容です。
▼CLOについてはこちらをチェック
物流コストが年々上昇…なぜいま“戦略的削減”が必要なのか
物流コストの上昇は、もはや一時的な現象ではありません。燃料価格の高止まり、人件費の増加、環境対応や規制強化による追加投資…。加えて2024年の働き方改革関連法によるドライバーの時間外労働規制が始まり、2026年にはその影響が本格化すると予測されています。これまで現場の工夫で吸収できていた負担も限界に近づき、企業の収益を圧迫する“構造的な課題”へと変化しています。いま求められるのは、単なる経費削減ではなく、長期的な競争力を見据えた「戦略的なコスト削減」です。
物流費の上昇要因と2026年問題
近年、物流コストは右肩上がりで上昇を続けています。その背景には、燃料価格の高止まりや人件費の上昇、環境対応への投資増加など複数の要因が絡み合っています。特に注目すべきは「2026年問題」です。
▼物流の2026年問題についてはこちらをチェック
単なる「コストカット」では逆効果な時代に突入
こうした状況で、値引き交渉や単発のコスト削減に頼るのはリスクが高まります。短期的には支出を抑えられても、取引先の離反や物流品質の低下につながり、結果的に収益やブランド価値を損なう可能性があります。
必要なのは、輸送ルートの最適化、共同配送や中継拠点の活用、在庫配置の見直しといった全体最適を視野に入れた“戦略的削減”です。コスト削減を単なる防御策ではなく、競争優位を築くための攻めの経営戦略として位置づけることが、2026年問題を乗り越える鍵となります。
CLOが押さえるべき「物流コスト削減の基本構造」とは?
物流コスト削減を経営課題として掲げても、「どこから手をつけるべきか」が見えなければ、的外れな施策に終わるリスクがあります。特にCLOや物流責任者にとって重要なのは、コストの全体像を正しく把握し、削減余地の大きい部分を見極めること。そのためには、まず物流コストの内訳と構造を理解し、自社のコストがどこに偏っているのかを“見える化”することが出発点です。
物流コストの内訳(輸送・保管・荷役・在庫・管理)
1.輸送コスト
商品の移動にかかる費用で、トラック・鉄道・航空・海上輸送などの手段によって変動します。運賃や燃料費、高速道路料金、ドライバーの人件費もここに含まれます。燃料費や人件費の影響を受けやすく、コストの大部分を占めることが多いです。
2.保管コスト
倉庫や物流センターでの保管にかかる費用。スペースの賃料、光熱費、管理システムの運用費などが含まれます。長期保管が必要な場合、コストが増加します。
3.荷役コスト
倉庫内での積み下ろし、ピッキング、仕分けなどにかかる費用で、フォークリフト・自動搬送ロボットの運用費や、作業員の人件費もここに含まれます。自動仕分けシステム導入やフォークリフトの自動化により削減できる可能性があります。
4.在庫コスト
在庫を持つことで発生する資金の固定化や、劣化・廃棄リスクのコスト。過剰在庫だけでなく、欠品による販売機会損失も含めて考える必要があります。
5.管理コスト
物流全体を運営・監督するための費用。システム利用料や管理部門の人件費、監査やコンプライアンス対応もここに含まれます。
▼あわせて読みたい!
削減対象の“見える化”が第一歩
全体の数字を把握せずに削減を進めると、影響度の小さい部分に手を入れて労力ばかりかかるケースがあります。まずは、部門別・工程別のコストを分解し、グラフやダッシュボードで可視化することが肝心です。これにより、重点的に取り組むべき領域が明確になり、関係部門との合意形成もスムーズになります。
物流コスト削減施策ランキング【優先度順トップ5】
物流コストの上昇が止まらない中、経営層や物流責任者にとって「どの施策から着手すべきか」を明確にすることは急務です。燃料費や人件費の高騰、2026年問題など、環境は年々厳しくなる一方で場当たり的なコストカットでは効果が薄く、むしろ現場負担やサービス低下を招く恐れがあります。本ランキングでは、複数企業の事例や効果の大きさをもとに、優先度の高い施策を5つ厳選。即効性と持続性の両方を兼ね備えた改善アプローチを解説します。
1.輸送効率の改善(積載率・配送ルート最適化)
輸送費は物流コストの中で最大の割合を占めます。積載率を高めることで、同じ輸送回数でもより多くの荷物を運べ、1個あたりの輸送コストが低下します。
また、配送ルートの最適化によって走行距離や空車時間を削減でき、燃料費・ドライバー拘束時間の削減にも直結します。TMS(輸配送管理システム)の活用やデータ分析によるルート再設計が効果的です。
▼あわせて読みたい!
2.在庫適正化による保管費の圧縮
過剰在庫は倉庫スペースの圧迫や保管費増大、さらには廃棄リスクを招きます。需要予測や販売データの活用により、適正在庫水準を維持すれば、倉庫の稼働効率を高められます。WMS(倉庫管理システム)でリアルタイムに在庫を把握し、棚卸しや補充も計画的に行うことがポイントです。
3.拠点再配置による移動距離の短縮
物流拠点の立地は輸送コストに直結します。消費地に近い場所へ拠点を移す「消費地近接型」や、中継拠点を活用したラストワンマイル短縮によって、輸送距離を減らし燃料費を削減できます。中長期的には固定費の見直しも可能になり、BCP(事業継続計画)の観点からも有効です。
▼あわせて読みたい!
4.倉庫内オペレーションの自動化・省人化
ピッキングや仕分けなど、人手に依存しやすい倉庫作業を自動化すれば、人件費削減だけでなく作業スピード・精度も向上します。AGV(無人搬送車)やロボットピッキング、音声認識システムなど、段階的に導入できる省人化ソリューションが増えています。
5.共同配送やモーダルシフトの活用
複数企業で配送を共同化すれば、積載率を高めつつ空車回送を減らせます。また、鉄道や船舶など環境負荷の低い輸送手段へのモーダルシフトは、CO₂削減とコスト低減を同時に実現可能。補助金や制度支援を活用すれば導入ハードルも下がります。
▼あわせて読みたい!
“削減しすぎて失敗”しないためのCLOの注意点とは?
物流コスト削減は避けて通れない経営課題ですが、「削りすぎ」は新たな損失を生むリスクをはらんでいます。過度な人員削減や設備縮小によって、納期遅延や品質低下、事故リスクの増加が起きれば、短期的なコスト削減は長期的な損失へと変わります。
CLOには、コストと品質・納期・安全を天秤にかけ、最適解を導き出すバランス感覚が求められます。削減策を進める上で特に注意すべきポイントを解説します。
品質・納期・安全のバランスをどう取るか
物流は単に「安く運ぶ」だけではなく、「安全に、期限通り、品質を保って運ぶ」ことが前提です。
配送ルートを短縮しても積み込み作業の時間が圧迫されれば破損や誤配送のリスクが高まります。ドライバーの勤務時間を無理に圧縮すれば、安全面のリスクや離職率の上昇につながることに。コスト削減の検討時には、サービスレベルや安全指標を同時にモニタリングし、バランスを欠かさない仕組みが重要です。
KPI設計と現場巻き込みが成否を分ける
数字だけを追う削減策は現場の反発や形骸化を招きます。CLOは財務指標だけでなく、納期遵守率、誤配送率、クレーム件数、労災発生件数などを含めた複合的なKPIを設計し、改善の指針にする必要があります。
そして、現場が「なぜこの削減が必要か」を理解し、主体的に動ける状態を作ることが不可欠です。会議室だけで決めるのではなく、現場ヒアリングや小規模トライアルを経て施策を浸透させることが、持続的な改善につながります。
物流コスト削減は「順番」と「設計」がすべて
物流コスト削減は、闇雲に着手しても成果は長続きしません。削減幅だけを追い求めると、サービス低下や現場の疲弊を招き、結果的に逆効果になるケースも少なくありません。CLOに求められるのは「何から、どの順番で、どの範囲まで削減するか」を描く設計力です。全体像を見据えたうえで優先順位を決め、短期施策と中長期戦略を組み合わせることで、持続的なコスト最適化が可能になります。
部分最適ではなく、全体設計がCLOの役割
輸送費、保管費、在庫コスト、荷役費、管理費──物流コストの内訳は複数に分かれています。それぞれ単独で削減することは可能ですが、全体のバランスを崩せば別の項目のコストが跳ね上がることも。CLOは財務・調達・営業・IT部門と連携し、各コストの相互関係を把握しながら“全体最適”を図る設計図を描く必要があります。
早期に手をつけるべき分野と中長期戦略の分け方
短期的には、積載率向上や配送ルートの見直しなど、即効性のある施策から着手します。一方、中長期的には拠点再配置、在庫最適化、モーダルシフトなど、時間と投資を要する構造改革を計画的に進めることが重要です。
ここでポイントとなるのは「短期で得た削減効果を中長期投資の原資に回す」という循環づくりです。これにより、単なるコストカットではなく、競争力強化につながる“戦略的削減”が実現します。
まとめ
本記事では、物流コスト削減に向けた優先度の高い施策を解説しました。輸送効率の改善や在庫適正化といった即効性のある取り組みから、拠点再配置や倉庫の自動化、さらには共同配送・モーダルシフトまで、短期と中長期の施策を組み合わせることで、持続的なコスト最適化が可能になります。
重要なのは、削減幅だけを追うのではなく、品質・納期・安全とのバランスを保ちながら、全体最適を意識することです。CLOとしては、社内外の関係者を巻き込み、数値に基づいたKPI設定と進捗管理を行うことが成功の鍵になります。コスト削減は単なる経費圧縮ではなく、競争力を高めるための戦略的投資と捉え、計画的に進めることが求められます。

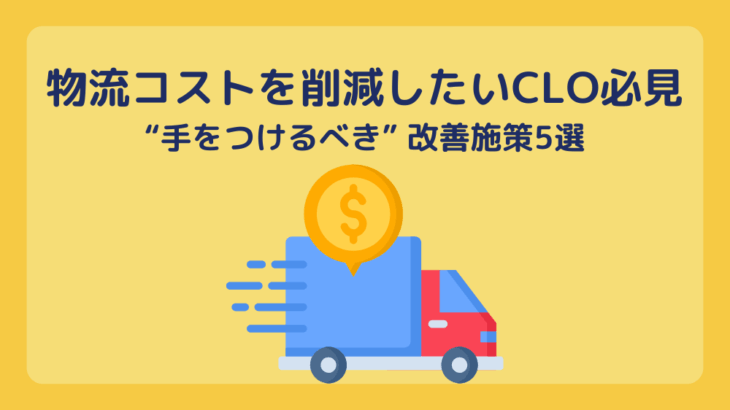


 Aidiot編集部
Aidiot編集部





