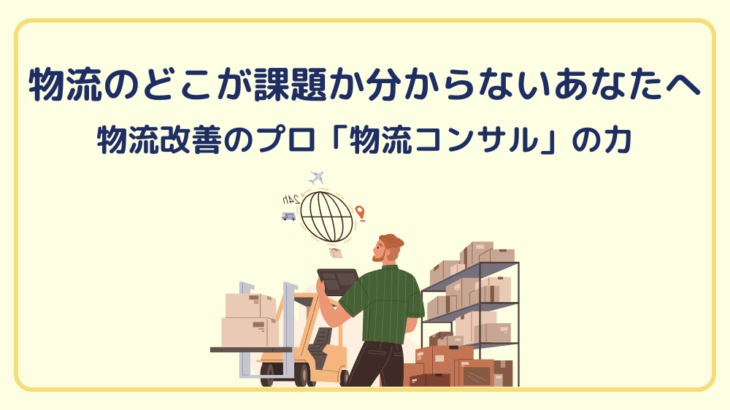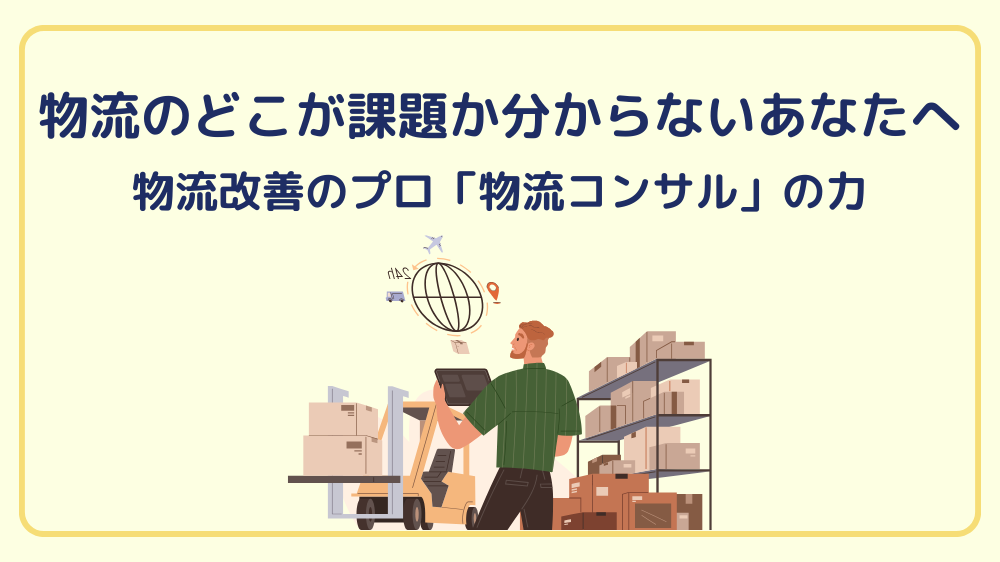
「物流を改善したいけれど、どこに問題があるのか分からない」そんな声が今、多くの企業から上がっています。輸送コストの高騰、納期遅延、在庫過多や人手不足など、物流の課題は複雑に絡み合い、現場では本質的な原因を特定するのが難しくなっています。そんな中、注目を集めているのが物流コンサルタントの存在です。物流のプロが、データと現場の両面からボトルネックを明らかにし、具体的な改善策を提示します。
この記事では、物流コンサルが果たす役割や導入のメリット、実際の成功事例までを詳しく解説します。
物流改善が必要な理由と、現場でよくある悩みとは
配送遅延や再配達の増加
「納品が間に合わない」「再配達が常態化している」といった声は少なくありません。これらは単なる運用の問題ではなく、配送計画や積載率、顧客とのコミュニケーションの仕組みに根本的な課題が潜んでいる可能性があります。
倉庫内作業の非効率化
ピッキング動線の無駄や棚配置の不適切さ、WMS(倉庫管理システム)の機能を十分に活かせていない運用によって、作業時間の増加やヒューマンエラーによる誤出荷が発生し、倉庫全体の生産性を著しく低下させている可能性があります。
コストが下がらない
燃料費・人件費の上昇に加え、積載率の低さや非効率なルート設計、過剰な在庫・保管スペースの維持など、見えにくいムダがコストを押し上げており、全体最適の視点での物流費の再設計が求められています。
物流コンサルタントとは何か?
物流に課題を感じていても、「どこから手をつければいいのか分からない」という企業は少なくありません。そんなときに力を発揮するのが「物流コンサルタント」です。単なるアドバイザーではなく、物流戦略の立案から現場改善、ツール導入までを一気通貫でサポートしてくれる存在です。
物流戦略設計/現場分析/業務改善/ツール導入まで対応
物流コンサルタントは、まず企業の現状をヒアリングし、物流全体の可視化・分析からスタートします。拠点配置や輸送ルートの最適化、倉庫内作業の見直し、WMSやTMSなどシステムの導入支援まで幅広く対応。単なる部分最適ではなく、全体最適を見据えた改善提案が強みです。
物流会社ではなく「荷主側の立場」で設計・交渉も代行
荷主企業にとって重要なのは「利益に直結する物流」です。物流コンサルタントは中立的な立場で荷主側に立ち、輸送会社や倉庫業者との条件交渉、契約見直しなども代行してくれます。これにより、コストダウンとサービス品質の両立が可能になります。
システムや現場との橋渡しも可能
現場作業者とIT部門、それぞれの言語や関心が違うことで改善が進まないケースもあります。物流コンサルタントは、現場の運用実態を理解したうえで、最適なシステム設計を提案します。現場とシステムの橋渡し役として、スムーズな業務変革を支えます。
物流コンサルタントは単なるアドバイザーではなく、以下のような実行型のパートナーです。
「どこに課題があるか分からない」状態から、「何を変えれば、どう改善できるか」が明確になり、「現場・経営両面での物流最適化」が実現できます。
物流改善はどこから着手すべきか?
「物流コストが高い気がする」「現場が忙しそうだけど、どこを直せばいいのかわからない」そう感じたとき、まず取り組むべきは現状の見える化です。勘や経験に頼るのではなく、データと事実をもとに改善点を明らかにすることが、無駄のない改革への第一歩になります。
「見える化」から始めるべき理由
物流改善の成功は、現状を正確に把握できているかどうかで決まります。どこにコストがかかっているのか、どの工程に時間がかかっているのかが分からなければ、改善策も的外れになってしまうからです。まずは数値で現場を“見える化”することが、改善活動の起点となります。
ABC分析/配送ルート分析/作業工数の棚卸が第一歩
たとえば、商品の出荷頻度と利益率を分類する「ABC分析」で、重点管理すべきアイテムが明確になります。さらに、配送ルートの実態を地図上で可視化することで、無駄な運行や積載の偏りに気づけることも。倉庫内作業では、作業別の時間と人員配置を洗い出すことで、非効率な工程が浮き彫りになります。
課題の優先順位付けと改善インパクトの試算
課題が見えてきたら、「どこから直すか」の優先順位を決めましょう。改善にかかるコストと、得られる効果(時間短縮・コスト削減など)を試算し、「投資対効果」が高い領域から着手することが、限られたリソースで成果を最大化するコツです。いきなり全体を変えるのではなく、スモールスタートで確実に改善する道筋を描くことが大切です。
段階的に改善→効果検証→展開する(PDCA)
物流改善は「一発勝負」ではなく、小さく試し→検証→展開するプロセスが重要です。
スモールスタート例:
・1拠点だけでWMS導入 → 効果確認後に全社展開
・一部エリアでルート最適化 → 全国配送に広げる
・一商品カテゴリで在庫適正化 → 他カテゴリに応用
物流コンサルを入れると何が変わる?
「改善が必要なのは分かっている。でも、社内ではどこがボトルネックなのかはっきり見えない」「改革に取り組もうとすると、現場とぶつかってしまう」そんな悩みを抱える企業が、次の一手として選ぶのが物流コンサルです。単なるアドバイザーではなく、物流全体を見渡し、実行支援まで伴走します。どのような役割を果たすのかを見ていきましょう。
ムダを「見える化」して、具体的な削減ポイントを示す
物流の現場には、「いつの間にか定着したムダ」が多く潜んでいます。物流コンサルは、データ分析や現場ヒアリングを通じて、そのムダを可視化し、数字で改善余地を提示します。たとえば、「このルートを変更すれば月100万円のコスト削減が可能」「この作業工程の重複をなくせば1日1時間の短縮になる」など、具体的な改善ポイントが明確になります。
属人化・ブラックボックス化を解消し、標準化が進む
例えば、ベテラン社員の「勘と経験」に頼っていた作業が、WMS導入でマニュアル化され、誰でもミスなく処理できるようになるなど、作業のルールや手順が個人に依存していた場合、作業標準書やKPIの設計を通じて、誰でも安定した作業ができる体制が整います。また、教育や業務引き継ぎもスムーズになり、人材リスクが下がります。
経営戦略に直結する“攻めの物流”が実現する
物流は単なるコストセンターではなく、差別化要因・顧客体験の起点にもなります。
例えば、配送リードタイムの短縮で顧客満足度向上させたり、在庫最適化で資金繰りを改善させたりなど、物流コンサルは、販売戦略・SCM・ESG視点も含めた提案が可能です。
物流コンサルタントは現場に入り、改善計画を策定・実行し、成果につなげる“実行支援型パートナー”です。課題が複雑なほど、その効果が大きく実感できるでしょう。
物流コンサルを活用した企業の成功事例
株式会社ベスト・ロジスティクス・パートナーズ(略称:BLP)「菓子メーカーにおける資材品管理の改善」
株式会社ベスト・ロジスティクス・パートナーズ(略称:BLP)は、菓子メーカーの「課題の見える化がしたい、既存センターを改善したい」という課題に対して資材品エリアに在庫ロケーション管理を導入し、「脱属人化」を実現しました。これは、物流センターで培われた在庫管理ノウハウを活用したものです。
実施前は20名×2.5時間×3日=150人時を要していましたが、実施後は13名×2.5時間×1日=32.5人時となりました。
出典)
https://www.blp-corp.com/case/consulting/?utm_source=chatgpt.com
SGシステム株式会社×両備ホールディングス株式会社
SGシステム株式会社は運行管理、労務・勤怠管理、給与管理と連動するクラウド型テレマティクスサービスを両備ホールディングス株式会社に導入して業務システムを改善しました。
「輸送車両の運行データをリアルタイムで把握し、日報作成・給与管理と連携させて作業効率を高めたい。」という課題に対して、労務管理の処理時間短縮、車両動態の見える化によりサービス向上が実現、乗務員の遵法意識の向上の効果を出しました。
出典)
https://www.sg-systems.co.jp/casestudy/ryobitransport/
船井総研ロジ株式会社「アパレル商品の共同配送事例」
船井総研ロジ株式会社は3PL事業者として、アパレルメーカー2社とパートナー会社で共同配送を行いました。
導入前の「路線会社からの値上げ」「共同配送を構築する為の出荷個数の不足」「出荷個数制限が生じ、安定した配送網が構築できていない」という課題に対して、納品先の選定、集荷時間、納品時間などのスキームを構築して共同配送を行いました。結果、各社運送費の削減、安定した配送網の構築を実現することができました。
出典)
https://www.f-logi.com/ninushi/case/kyoudouhaiso-2/
物流改善に取り組む企業が今後目指すべき方向性
企業が物流改善に取り組む際、見直すべきは単なる作業手順やコストの数字だけではありません。物流は今や「企業価値を左右する戦略領域」とも言われ、視点の転換が求められています。ここでは、これからの企業が物流戦略をどう進化させていくべきか、3つの視点から掘り下げます。
部分最適から“全体最適”への視点転換
これまでは、ピッキングの効率化や配送費の削減といった個別の改善が中心でしたが、今後はサプライチェーン全体を俯瞰した「全体最適」が鍵になります。たとえば、製造・販売・在庫・輸送を分断せず、横断的に連携させることで、無駄を削減しながらも柔軟な対応が可能になります。
単なるコスト削減ではなく、「競争力を生む物流」へ
安く・早く届けるだけでは、差別化にはつながりません。重要なのは、「どうすれば顧客に選ばれる物流になるか」という視点。納品精度やリードタイム短縮など、物流品質の向上がそのままブランド価値につながる時代です。
物流コンサルタントとの協業が、組織の思考も変える
外部の物流コンサルタントは、仕組みの改善だけでなく、社内の「当たり前」に疑問を投げかける存在でもあります。現場の声と経営判断をつなぐファシリテーターとして、改革のきっかけを生む役割を果たすのです。結果的に、物流を企業の強みに変える意識が育ちます。
まとめ
本記事では、物流現場が抱える課題の代表例と、その解決に力を発揮する「物流コンサルタント」の役割について解説しました。
倉庫作業の非効率、配送ルートのムダ、コスト高止まりといった問題は、多くの企業で共通する悩みです。
しかし、現場に入り込み、客観的かつ実務に即した改善策を提案・伴走してくれる物流コンサルを活用することで、課題の見える化から解決まで一気通貫で進めることが可能になります。単なるコスト削減ではなく、「経営に貢献する物流」を実現するためにも、外部の知見を取り入れる選択肢を、ぜひ前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。