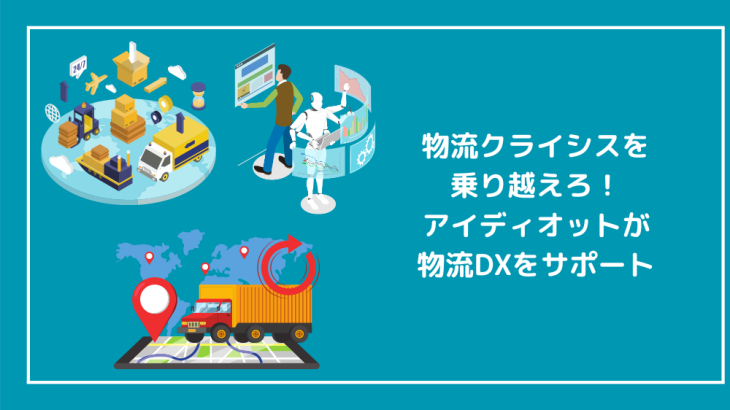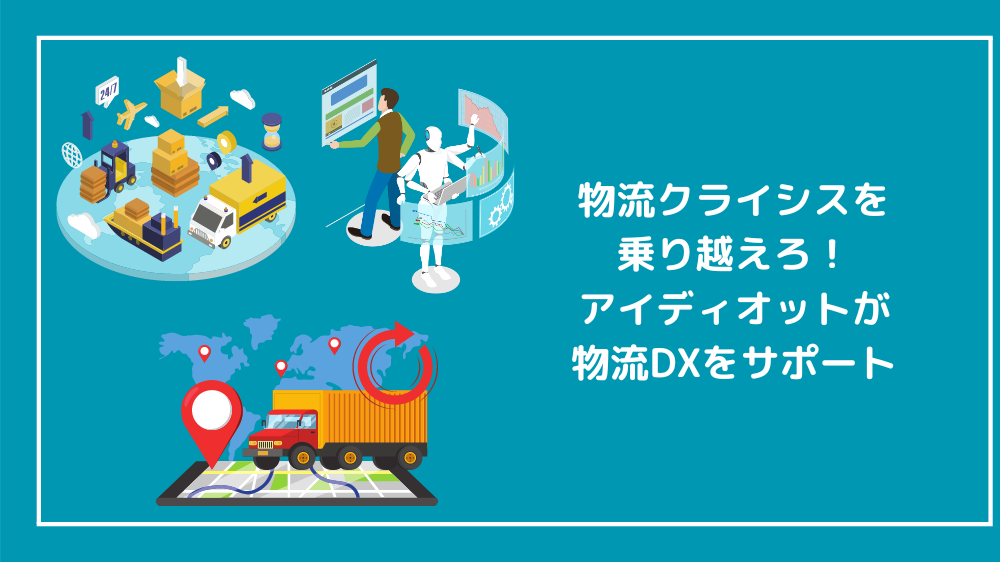
サプライチェーンのDX支援についてはコチラから
製造者から消費者へ物を届ける重要なインフラといえる物流ですが、ECサイト利用などによる荷物取扱量の急増に対して、物流のキャパシティーが追い付かなくなることから「物流クライシス(危機)」が叫ばれています。「物流クライシス」と呼ばれる現象が続いており、特に2024年にはその深刻度が増すとされています。この物流クライシスは、2024年問題やEC市場の急拡大、ドライバー不足など、多くの要因が重なって発生しています。
物流クライシスには複数の要因があり、それらを解決しないことには確実に状況は悪化するばかりです。しかしながら、物流業界の改革は容易なことではありません。新たな技術やシステムの導入には多大なコストがかかるため、多くの企業が取り組みに踏み切ることができない状況が続きます。
「物流クライシス」がもたらす影響は、物流業界に限定されず、私たちの生活にも深刻な影響を与える可能性があり、深刻な社会課題として認識され始めております。この記事では物流クライシスといわれる状況について、その原因や起こりうる問題点を踏まえながら、解決に必要なことを解説いたします。
物流業界が直面する「物流クライシス」とは何か?
「このままではモノが運べなくなる」――。
「物流クライシス」とは、物流業界が抱える人手不足やコスト増、非効率な構造などによって、物流サービスの持続が困難になる深刻な危機的状況のことを指します。とくに日本では、2024年問題(時間外労働の上限規制)をきっかけに、この言葉が一気に広まりました。
背景にある3つの要因
①ドライバーの人手不足
ドライバーは、若手の担い手が少なく、平均年齢は年々上昇しています。(40代後半~50代)また、2024年からトラックドライバーの時間外労働規制が年間960時間までと強化され、人手不足はますます深刻化しています。その結果、「働ける時間が減る=運べる量が減る」事態になっています。
②ラストワンマイルの過重負担
ECの拡大で個人宅配が急増し、再配達率が依然高い状態が続いており、効率の悪い「1件ずつ配送」がドライバーに重くのしかかっています。小口多頻度・即日配送のニーズに、現場が追いつけない状況です。
③非効率な物流構造と荷主依存
短納期・分納・夜間搬入など、荷主主導の無理な納品条件に加え、荷待ち時間や積み下ろし作業など、「運んでない時間」にも人件費がかかっております。ドライバーの負担が増え、離職につながり、その結果人手不足という悪循環になってしまっています。
物流クライシスによる影響とは?想定ケースについて
物流クライシスによる影響として考えられる代表的なケースとしては、以下のようなことが考えられます。
配送コストが上昇する
物流クライシスが発生した場合、物流ネットワークの混乱によって配送コストが上昇する可能性があります。例えば、製品の輸送経路が変更、移動距離が極端に増えた場合、燃料費や人件費などのコストの増加が考えられます。また、製品の輸送が遅れた場合、代替手段での輸送が必要になる場合もあります。これらの追加コストが物流企業にかかることで、配送コストの上昇が避けられません。結果的に、消費者は製品の価格上昇を経験することがあります。特に、海外からの輸入品や遠隔地からの輸送が多い商品には、配送コストの急上昇が予想されます。
配達時間遅れ・時間指定の不可などサービスレベルの低下
物流ネットワークが混乱し配達時間の遅れや既存サービスの担保が困難になる可能性が高いです。例えば、交通規制や天災などの理由により、製品の輸送が遅れた場合、約束した配達時間を守れなくなるケースも想定されます。また、製品の在庫不足などにより、注文から配達までの時間が従来よりも長くなる場合もあります。これらの問題が物流企業に起こると、顧客満足度の低下や販売不振などの経済的損失を招くことが予想されます。特に、オンラインショッピングが一般化した現在、顧客に迅速なサービスを提供することが求められているため、配達時間の遅延などの問題が起こると、消費者に多大な不満を与えることが予想されます。
食品・日用品・医薬品などの品不足が起こる可能性がある
食品や日用品、医薬品などは私たちの生活に欠かせないものであり、一時的な在庫切れがあるだけでも私たちの生活に大きな影響を与える可能性があります。物流クライシスが発生した場合、物流ネットワークの混乱によって生産地からの製品の輸送が滞るケースは容易に想定できます。また、国境を超えた輸送には通関手続きが必要であり、混雑によって物流がストップする可能性があります。これらの要因により、食品や日用品、医薬品などが供給不足に陥る可能性があります。さらに、輸送遅延によって製品の鮮度が損なわれる可能性もあります。例えば、冷凍食品の場合、一時的な輸送遅延でも鮮度が損なわれることがあります。私たちは、普段当たり前に利用している商品がなくなってしまうことで、不安やストレスを感じる可能性が考えられます。
物流サービスの「当たり前」が見直される時代へ
これまで消費者にとって当たり前だった「即日配送」「送料無料」「再配達」といったサービスが、物流クライシスの深刻化により見直されつつあります。その背景には、深刻なドライバー不足や2024年問題による労働時間の制約、物流コストの上昇があり、従来の水準を維持することが困難になってきているのです。今後は、以下のような変化が現実のものとなる可能性があります。
・即日配送ではなく、数日〜1週間の配送猶予
・「送料無料」ではなく、送料が明示される課金モデルの導入
・再配達の回数制限や、有料化による無駄な配送の抑制
・配送日時指定の制限や廃止によって、効率優先のルート配送へ移行
つまり、消費者にとって「注文すればすぐ届く」「送料は払わなくていい」「何度でも届けてくれる」といった常識が、今後は通用しなくなるかもしれません。“届いて当たり前”の時代は終わりを迎えようとしているのです。
大企業も物流クライシスに陥っている?事例詳細を解説
Amazonの事例:佐川急便の撤退・ヤマト運輸は当日配送を中止
物流クライシスの事例として世間の注目を集めたのがAmazonと物流を巡る騒動です。Amazonはマーケットプレイスを除く全商品の通常配送料を完全無料化や、当日配送地域の拡大など、利用者サービスの向上を行っています。しかしこれらの負担はAmazonだけではなく配送業者も大きく被ることを前提にしたものでした。
佐川急便はAmazonの配送を一手に引き受けていましたが、利用者サービス向上のしわ寄せから売上の急増とは裏腹に、単価の低下による利益率低下と人手不足による現場の疲弊に直面していました。再三に渡り、佐川急便はAmazonへ値上げ交渉を行っていましたがそれも決裂し、2013年Amazonから撤退する決断を下しました。佐川急便の物流クライシスととも言えるでしょう。
その後はヤマト運輸がAmazonの配送を引き受けましたが、過度の要求により現場は疲弊しているという話が頻繁に上がっておりました。現に、2020年11月、ヤマト運輸は、大型個人向け配送サービスであるAmazonの「Prime Now」の当日配送から撤退すると発表しました。これは、ヤマト運輸の配達体制が維持できなくなったためで、同サービスを手がける倉庫・物流会社との交渉が決裂したことが理由とされています。今後も、Amazonの当日配送サービスの利用者は他の配送会社を利用することになり当日配送にかかるコストが上昇する可能性があります。また、ヤマト運輸は他の配送業者が新規参入することで競争が激化し、経営環境が悪化することも懸念されています。
佐川急便は運送賃上げ、ドライバー不足が懸念
続いての事例も佐川急便になります。佐川急便は、物流クライシス・2024年問題に向けた準備として、2021年11月に一部の運賃を値上げすることを発表しました。
さらに、2023年4月にも、持続可能な物流インフラの維持と品質の向上を目的に、宅配便などの運賃の値上げを発表しました。パートナー企業との取引単価の見直しや、燃料補助金の支給、従業員の処遇改善などを実施してきましたが、現在においても、エネルギーや施設・車両等の価格高騰および労働コストの上昇や、労働環境改善、顧客ニーズに対応したサービス品質の維持・向上、省人化や業務効率化に向けた施設およびDXへの設備投資など、これまで以上に厳しさが増しており、長期的かつ継続的な対応が求められています、としています。
楽天は自前配送からの撤退
「楽天の自前配送からの撤退」というニュースが2020年に報じられました。これは、楽天が自社で行っていた配送業務を、順次委託先の業者に切り替えることを決めたというものです。この決定には、当時既に深刻な人手不足に直面していた物流業界の現状が大きく関係しています。
楽天は、自社配送を含めた配送業務の一部を佐川急便や日本郵便、西濃運輸などの他社に委託することで、配送ネットワークの拡大と、配送品質の向上を目指すとしています。また、この撤退により楽天は配送業務に関連する人件費などのコスト削減を図ることができると期待が高まっています。
しかしながら、今後の物流業界においては、楽天を含む多くの企業が同じように委託先に頼らざるを得ない状況に陥る可能性があります。そのため、適切な委託先の選定や、配送ネットワークの最適化が求められるでしょう。
今からでも遅くない!物流クライシスを解決するための対策
物流クライシスへの対応は、もはや物流業界だけの問題ではなく、企業・社会全体で取り組むべき構造的課題となっています。
ここでは、企業や自治体、消費者も含めた具体的な対策・社会的な動きについてわかりやすく解説します。
共同配送・異業種混載による輸送の効率化
課題:トラックの積載率が低く、非効率
- 荷主ごとに個別に配送 → 空車が多く、ドライバー負担も増加
- 小口多頻度配送の増加により、非効率なルート運行が常態化
対応策:
・異業種間でトラックをシェアする「共同配送」「混載便」の拡大
・地域ごとの共同物流拠点の整備
▼あわせて読みたい!
モーダルシフトによる長距離輸送の見直し
課題:長距離トラック輸送にドライバーが確保できない労働環境改善のための対策
対応策:
・鉄道や船舶に切り替える「モーダルシフト」の推進
・長距離を鉄道、短距離をトラックで分担することで、ドライバーの労働時間を短縮
▼あわせて読みたい!
デジタル化・物流DXによる可視化と最適化
課題:アナログ作業・属人化で管理が非効率
対応策:
・配車システム、ルート最適化AI、動態管理ツールの導入
・倉庫・車両のIoT化や業務データのリアルタイム可視化
消費者の理解と行動変容
課題:「即日配送・送料無料」が当然という認識が根強い
対応策:
・再配達の削減、配送猶予の容認、エコ配送の選択など
・宅配ボックス・置き配・ピックアップ拠点(PUDOステーション等)の活用
行政・政策支援の強化
主な取り組み:
・物流効率化法(改正物流総合効率化法)の制定
・GX(グリーントランスフォーメーション)補助金によるEV・モーダルシフト支援
・「特定荷主制度」など、荷主側の責任明確化と行動促進
▼あわせて読みたい!
物流クライシスは“個社努力”だけでは解決できません。
これからは、企業横断・業界連携・社会理解を軸に、「持続可能な物流エコシステム」の構築が問われています。
デジタルツインで物流クライシスを乗り越える!アイディオットが物流DXをサポート
物流クライシスと叫ばれる一方で、配送センターでドライバーに無駄な待機時間が発生したり、トラック積載率が41%程度であったり、業界として非効率的があるとの指摘もされています。中小配送業者では未だに電話とファックス、そして手作業や勘に頼る業務が多く、それらの解決も物流クライシスの解決に必要です。このように物流業界には様々な課題がありますが、DX・データ活用やデジタルツインといったテクノロジーの導入によってこれらの課題解決が期待されています。
物流業界においてもデジタル化の波はすでに到来しています。物流現場では、データの取り扱いを含めた効率化が進んでおり、物流の可視化、自動化、最適化などの課題を解決するために、AIやIoTなどの先端技術の活用が求められています。また、大量のデータをもとに分析を行い、より効率的なルートや配送スケジュールを作成することで、配送時間の短縮やコスト削減を図ることができます。
さらに、デジタルツインの導入も有望です。デジタルツインとは、物理的なオブジェクトやプロセスに対し、それに対応する仮想的なモデルを作成し、現実と仮想を統合することで、現場の課題解決に役立てる技術です。物流業界においては、トラックや倉庫などの設備をデジタルツインで表現することで、物理的な現場と同時に仮想的な現場を可視化することができ、物流の可視化や分析に役立てることができます。
戦略立案から実行支援まで可能なAidiot
Aidiot(アイディオット)は「BtoB領域の脳と心臓になる」というミッションを掲げるIT企業で、AIやデータといったテクノロジーを駆使して、時代の最先端を行くサステイナブルな形でのデジタル戦略をクライアントに提案しています。
物流の効率化のためシステム導入を検討するとき、どのように問題解決を考えるべきか、そのスタートで躓きがちですが、自社の解決すべきポイントから戦略を立て、実際に現場に落とし込み運用するまで任せられる信頼性が何より重要となります。
そのワンセットを任せられるのがアイディオットです。
まとめ
すでに進行している物流クライシスですが、運送量の増加は止められないことから、根本的な解決は運送の効率化・最適化を進めながら、業務環境を改善し物流を魅力的な業界にしていく必要があります。そのためには「人である必要のない業務」を洗い出し、システム化による運送業務の効率化は欠かせない取り組みです。それを乗り越えた先には、まだ伸びていく市場が待っています。
物流業界のデジタル化の加速、物流クライシスを打破するためにも、先ずは日常生活を見直してみませんか? 物流業界のデジタルトランスフォーメーションを実現するための相談や支援が必要であれば、「アイディオット」がお手伝いします。我々の技術とノウハウで、業務の最適化と効率化を実現し、未来の物流業界を共に築いていきましょう。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。