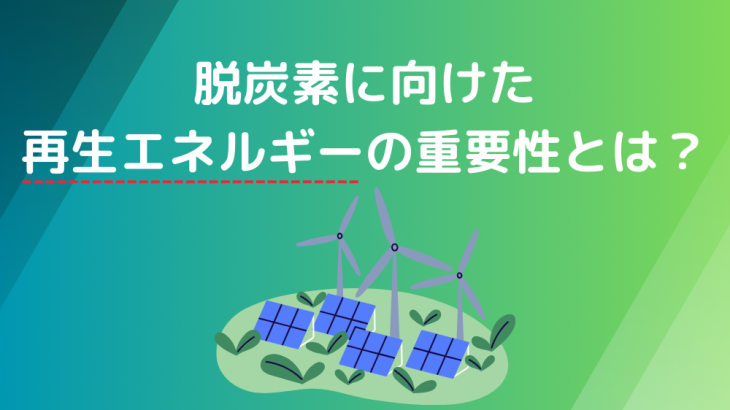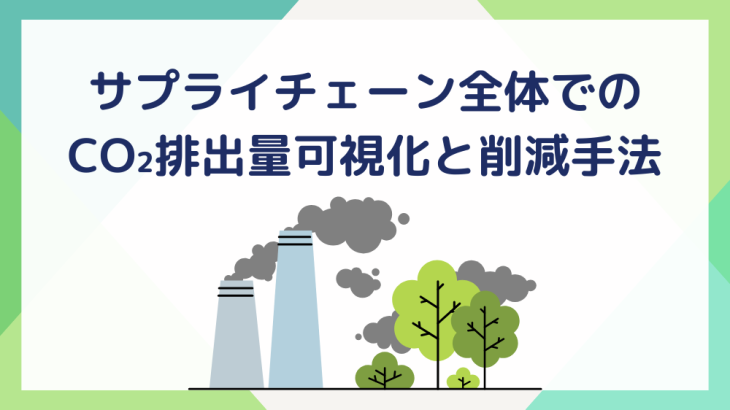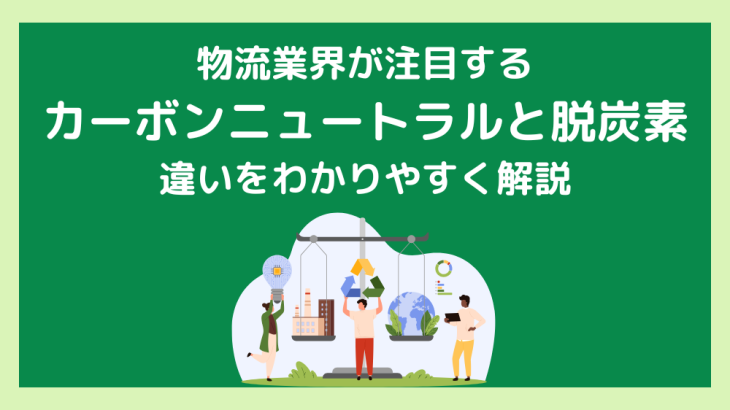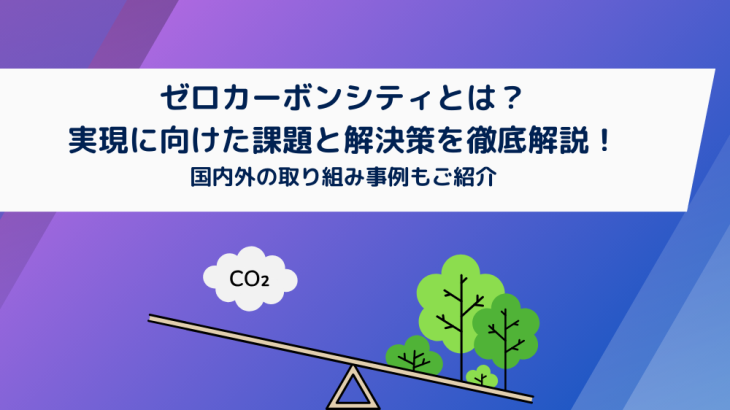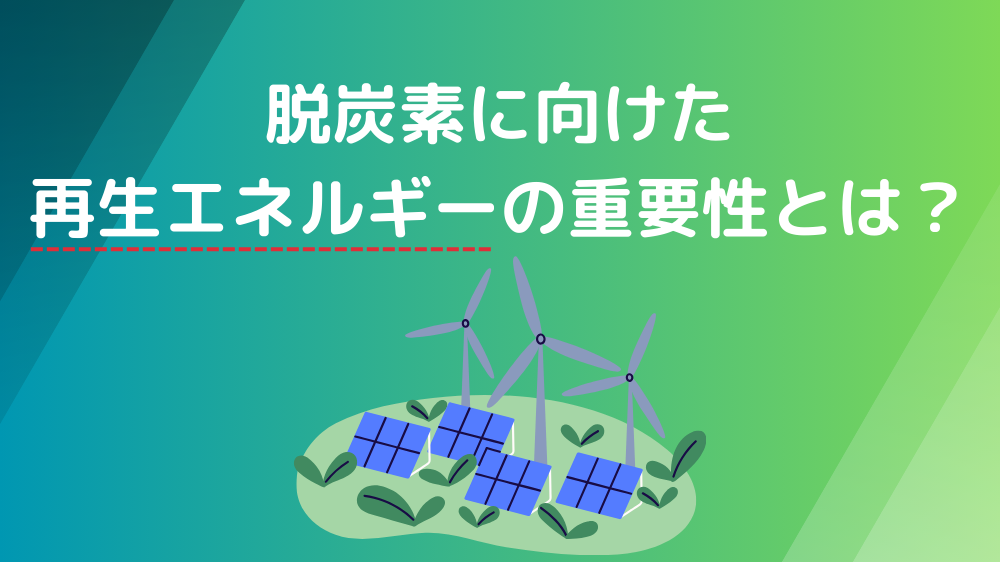
脱炭素社会の実現へ〜再生可能エネルギーの役割とは?〜
脱炭素社会を目指す上で、再生可能エネルギーは欠かせない存在です。再生可能エネルギーとは、太陽光や風力、地熱など、自然由来のエネルギーを利用して発電する仕組みで、化石燃料に頼らないため、CO₂排出を大幅に削減できます。
現在、多くの企業がこの再生可能エネルギーを活用した取り組みを進めています。
工場や物流倉庫の屋根に太陽光パネルを設置し、自社で必要な電力を賄うだけでなく、余剰電力を地域社会に供給するケースが増えています。
また、再生可能エネルギーで電力を供給することで、製品の「環境価値」を高め、消費者や取引先からの信頼を獲得する動きも見られます。
再生可能エネルギーの導入は環境だけでなく、コスト削減や競争力強化にもつながる取り組みです。地球規模の課題である脱炭素化に向けて、再生可能エネルギーの役割はますます大きくなるでしょう。これからの未来を支える重要な選択肢として注目されています。
再生可能エネルギーが注目される背景
地球温暖化や気候変動が深刻化する中、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが世界中で加速しています。その中でも、再生可能エネルギーは脱炭素社会を目指す重要な手段として注目されています。以下に、再生可能エネルギーが注目される理由を具体的にご紹介します。
気候変動への対応
化石燃料(石炭、石油、天然ガス)の燃焼によるCO₂排出が、地球温暖化の主因とされています。再生可能エネルギーは、発電時にCO₂をほとんど排出しないため、脱炭素社会の実現に不可欠な手段です。
また、2015年に採択されたパリ協定では、温暖化を産業革命以前から2℃以内、さらに努力目標として1.5℃以内に抑えることを掲げられており、多くの国が再生可能エネルギーの拡大を進める政策を採用しています。
持続可能なエネルギー供給
太陽光や風力、水力など、自然由来のエネルギーは無尽蔵で枯渇しません。持続可能なエネルギー源として、次世代にわたって安定した供給が期待されています。
エネルギー安全保障の強化
国内で再生可能エネルギーを生産すれば、エネルギーの輸入依存を減らし、価格変動や供給リスクへの耐性を高めることができます。特に、エネルギー自給率の向上が課題となっている国において重要視されています。
技術革新とコストの低下
再生可能エネルギーに関連する、太陽光発電パネル、風力タービン、蓄電池などの技術は急速に進化しており、効率が向上しています。
特に太陽光や風力発電のコストはここ数十年で大幅に低下し、化石燃料と同等、またはそれ以下のコストで発電可能となっています。
持続可能な開発目標(SDGs)の達成
国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)のうち、「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」(目標7)や「気候変動に具体的な対策を」(目標13)は、再生可能エネルギーの普及が重要な役割を果たします。
社会的な支持と企業価値の向上
再生可能エネルギーの利用は、環境に配慮する姿勢を示すもので、企業や自治体は社会的信頼を得るとともに、持続可能なビジネスモデルの構築につながります。
再生可能エネルギーが注目される背景には、気候変動対策、資源の有限性、技術革新、エネルギー安全保障など多岐にわたる要因があります。このような背景を受けて、再生可能エネルギーの利用拡大が世界的な優先課題となっています。
再生可能エネルギーの導入がもたらすメリット
再生可能エネルギーの導入は、脱炭素社会を目指す上で多くのメリットをもたらします。その主なポイントを見ていきましょう。
環境へのメリット
・温室効果ガスの削減
再生可能エネルギーは、化石燃料を使用せず、太陽光や風力など自然由来のエネルギーを活用するため、CO₂の排出を大幅に抑えることが可能で、気候変動対策として、脱炭素社会の実現に寄与します。
・資源の持続可能な利用
太陽光、風力、水力などは枯渇しないエネルギー源であり、次世代への環境負荷を抑えられます。
経済的なメリット
・エネルギーコストの安定化
化石燃料は価格が市場の変動や地政学的なリスクに左右されますが、再生可能エネルギーはこうした影響を受けにくく、エネルギーコストの安定化につながります。
・エネルギーコストの長期的な削減
技術の進化により、再生可能エネルギーの発電コストは年々下がっています。初期投資は必要ですが、長期的にはエネルギーの自給自足が進み、輸入燃料のコスト削減にもつながります。
社会的なメリット
・地域活性化
再生可能エネルギー施設(風力発電所、バイオマスプラントなど)は地方に設置されることが多く、地域経済の活性化につながります。
・健康リスクの低減
再生可能エネルギーの利用は、大気汚染の原因となる化石燃料の使用を減らし、住民の健康リスクを低減します。
・エネルギーへのアクセス向上
電力網が未発達な地域でも、小規模な太陽光発電や風力発電を利用することで、安定した電力供給が可能です。
技術革新の促進
再生可能エネルギーの導入にはAIやIoT、蓄電池技術などが組み合わされ、エネルギー効率や管理が大幅に向上します。
これは、新しいビジネスモデルや技術開発を生む土台となります。
国際的な信頼性の向上
再生可能エネルギーを推進することは、パリ協定やSDGs(持続可能な開発目標)への貢献として国際社会からの評価を高め、環境先進国としての地位を確立できます。
再生可能エネルギーの導入は、環境負荷を削減し、経済の安定化と成長を促進するだけでなく、地域社会やエネルギー安全保障にも多大なメリットをもたらします。これからの持続可能な社会を築くための重要な柱として、さらなる普及が期待されています。
国内外の導入事例から学ぶ、再生可能エネルギーの現状
福島県「福島イノベーション・コースト構想」
東日本大震災後、福島県では再生可能エネルギーを地域の復興の柱として推進し、広大な土地を活用し、大規模な太陽光発電や風力発電の導入を進めています。
福島再生可能エネルギー研究所(FREA)を中心に、水素エネルギーの研究開発を実施し、再生可能エネルギーによる電力で地域の自立を目指します。
出典)
神奈川県藤沢市「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン(Fujisawa SST)」
『Fujisawaサスティナブル・スマートタウン(Fujisawa SST)』は、先進的な取り組みを進めるパートナー企業と藤沢市の官民一体の共同プロジェクトです。広さ約19haの街の中に、住宅地区(低層・中高層)、生活支援地区、福祉・健康・教育地区が配置され、約1,000世帯の入居を予定しており、各住戸には、太陽光発電システムとリチウムイオン蓄電池に加え、エネファーム、HEMSなどが備えられており、道路沿いに設置したコミュニティソーラー出力100kWと、街区全体で再生可能エネルギー利用率30%以上、CO2排出量70%削減(1990年比)を目指しています。
出典)
兵庫県豊岡市「営農型太陽光発電」
兵庫県豊岡市では、水稲栽培と太陽光発電を組み合わせた「営農型太陽光発電モデル」を導入しました。農業と再生可能エネルギーを両立させることで、地域内の電力地産地消を進め、自治体と連携した普及が実現しています。
発電設備は35kWの出力で遮光率30%。余剰電力を新電力会社に供給し、売電収入で事業性を確保しました。また、モデル事業として営農型太陽光発電の普及につなげるため、地域の関心と理解を高めるために勉強会を開催し、説明で課題解決を図った。
この事業では国の補助金を活用し、調査から設備導入までスムーズに進行し、自治体が電力を購入する仕組みを構築し、安定した運営が可能になりました。
出典)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/guide/pdf/jirei_01.pdf
ハウステンボス株式会社
ハウステンボス株式会社では、太陽光発電と農業を融合した自家消費型の観光農園事業を展開しています。約2,300㎡の敷地に設置した100kWの太陽光パネルで発電し、園内の電力を自家消費するとともに、ブルーベリーを栽培して園内レストランで提供しています。
当初、発電効率向上のため床面に反射シートを敷設しましたが、藻の付着や維持コスト増や観光施設としての見た目の悪化が問題になりました。そこで反射シートを撤去し、天井に反射ネットを張ることで発電量を維持しつつ効率的な運用が可能となり、課題を解決しています。
出典)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/guide/pdf/jirei_02.pdf
株式会社太陽住建
株式会社太陽住建は、環境省の補助事業のもとで令和元年9月から横浜市の老人福祉施設「和みの園」(福祉避難所指定)の屋根に自家消費型太陽光発電設備(26.4kW)を設置し稼働を開始しています。
取り組みとしては、福祉避難所職員が発災時に機器を適切に操作できるよう、パワーコンディショナーや蓄電池の操作方法を記載したマニュアルを作成や、災害時に施設の加入者やその家族が必要な電気(通信手段など)を利用できるよう、設備を避難者やその家族に開放したり横浜型リビングラボと連携し、福祉避難所の自家消費推進を通じて災害に強い街づくりを推進しています。
本事業のノウハウを活用し、空き家を防災拠点として活用する取り組みを町内会と協力して進める計画も策定しています。
出典)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/guide/pdf/jirei_10.pdf
再生可能エネルギー導入の課題とその解決策
再生可能エネルギーは、地球温暖化や気候変動対策として重要な役割を果たしています。しかし、導入にはいくつかの課題も存在し、それを解決する具体的な取り組みが求められています。主な課題とその解決策をご紹介いたします。
初期コストの負担
太陽光パネルや風力タービンの設置には高額な初期投資が必要で、中小規模の事業者にはハードルが高いです。
解決策: 国や自治体の補助金制度や税制優遇を活用することで、初期費用の負担を軽減可能です。PPA(電力購入契約)モデルの活用で導入コストを抑えることができます。
天候や立地による制約
太陽光や風力は天候や地域特性に左右され、安定した発電が難しい場合があります。
解決策: 蓄電池を併用することで発電量の変動を緩和し、複数のエネルギー源を組み合わせた分散型エネルギーシステムの導入が効果的です。
運用・保守の難しさ
設備の劣化や故障により、安定的な運用が課題となる場合があります。
解決策: 定期的なメンテナンスや遠隔監視システムの導入により、トラブルを未然に防ぐ仕組みを整備します。
脱炭素社会におけるエネルギーの未来像とは
脱炭素社会の実現に向けて、エネルギーは大きな転換期を迎えています。これまでの化石燃料中心のエネルギー供給から、再生可能エネルギーを基盤とした持続可能な仕組みに移行しようとしています。この未来像を以下にわかりやすく解説します。
再生可能エネルギーが主役
技術革新によりコストが低下し、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーが化石燃料と同等かそれ以下のコストで提供可能になり、大規模なメガソーラーやオフショア(洋上)風力発電の導入が進行中です。
地域特性を活かした地熱発電や水力発電などの再生可能エネルギーの導入が進み、地方経済の活性化にも貢献します。特に地熱発電は火山帯を持つ日本において注目されるエネルギー源となります。
エネルギーの分散化と地域化
地域ごとにエネルギーを生産・消費する「分散型エネルギーシステム」が普及し、中央集約型の大規模発電から、自宅や地域での太陽光パネル、蓄電池などを活用する小規模システムへの移行が進むでしょう。
また、地域で生産した再生可能エネルギーを地域内で利用する仕組みが拡大し、地域主導のエネルギー事業(地域電力会社)も増加中です。
デジタル技術との融合
電力網がデジタル技術で最適化され、需要と供給をリアルタイムで調整します。天候依存などの再生可能エネルギーの不安定さを補うため、AIやIoTを活用した効率的なエネルギー管理が進むでしょう。
蓄電技術の進化
再生可能エネルギーの不安定性を補うため、大容量蓄電池が普及し、自宅用蓄電池、電気自動車(EV)のバッテリーを活用した「V2G(Vehicle-to-Grid)」が進化中。
また、余剰電力で水を電気分解して作られるグリーン水素が注目されており、発電だけでなく、産業用燃料や輸送分野でも活用が期待されています。
脱炭素化を支える輸送の変革
電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)が普及し、輸送分野の脱炭素化を推進し、物流においても電動トラックやドローンの活用が進むでしょう。
また、トラック輸送から鉄道や船舶輸送へのモーダルシフトが推進され、再生可能エネルギーを活用した電動化が進むでしょう。
持続可能な社会構築への影響
エネルギー転換は、SDGsの「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」(SDGs目標7)、「気候変動への対策」(目標13)に直接貢献します。
また、再生可能エネルギーの普及は、新たな産業や雇用を生み出しながら、環境負荷を低減します。
脱炭素社会のエネルギーの未来像は、再生可能エネルギーを基盤とし、デジタル技術や蓄電技術の活用による効率化が進むことが特徴です。
分散型エネルギーシステムの普及や水素エネルギーの活用により、地域経済の活性化やエネルギー自給率の向上が期待されています。この未来像を実現するためには、技術革新だけでなく、政策や社会全体の協力が不可欠です。
まとめ
脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの活用は欠かせない鍵となります。太陽光や風力、水素エネルギーといったクリーンエネルギーは、環境負荷を減らすだけでなく、地域の特性を活かしたエネルギー自給自足の仕組みを構築する可能性を秘めています。
一方で、コストや技術面、地域住民の理解など、導入における課題も存在しますが、国や自治体の補助金制度、技術革新、そして私たち一人ひとりの意識改革によって、これらの課題を乗り越えることができます。
再生可能エネルギーの推進は、地球環境を守り、次世代へ持続可能な社会をつなぐ大切な取り組みです。一人ひとりがこの重要性を理解し、行動を起こすことで、脱炭素社会への道を切り開いていきましょう。
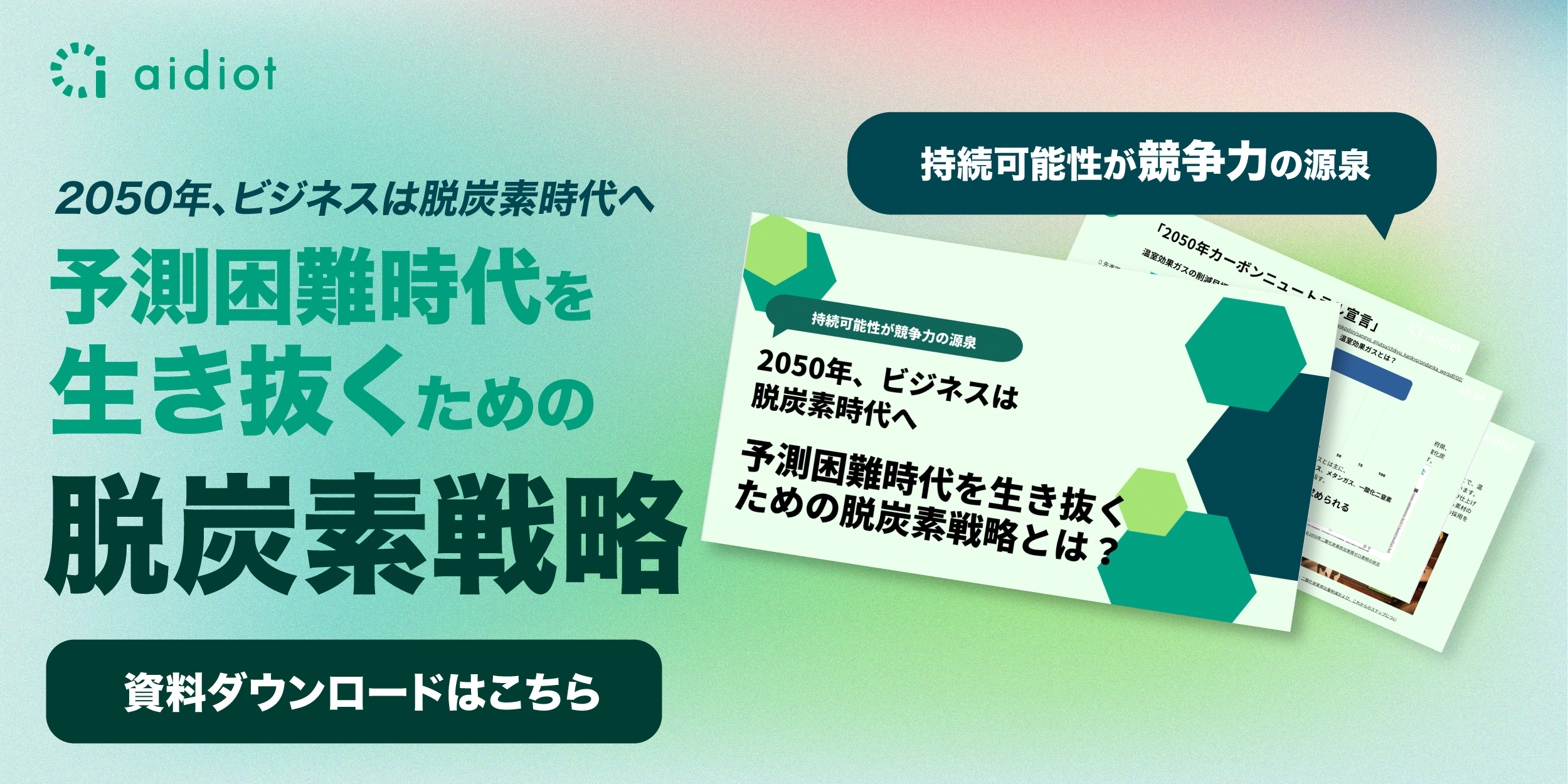
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。