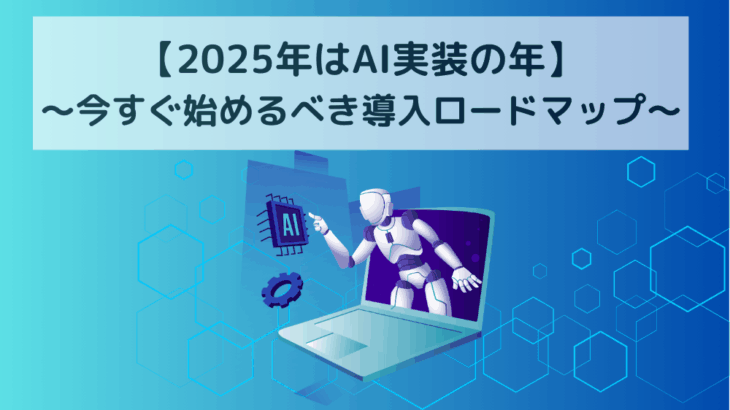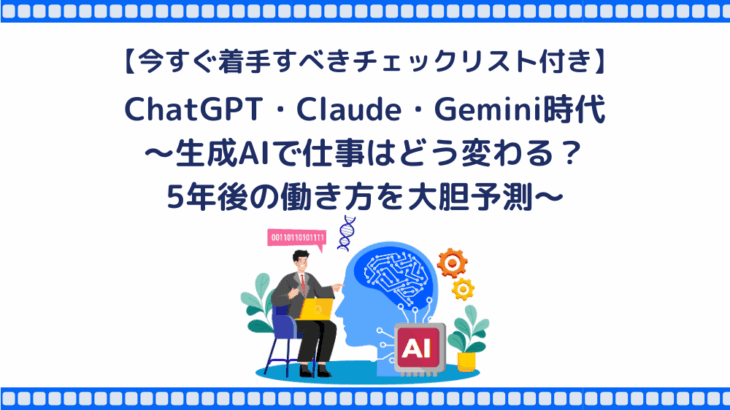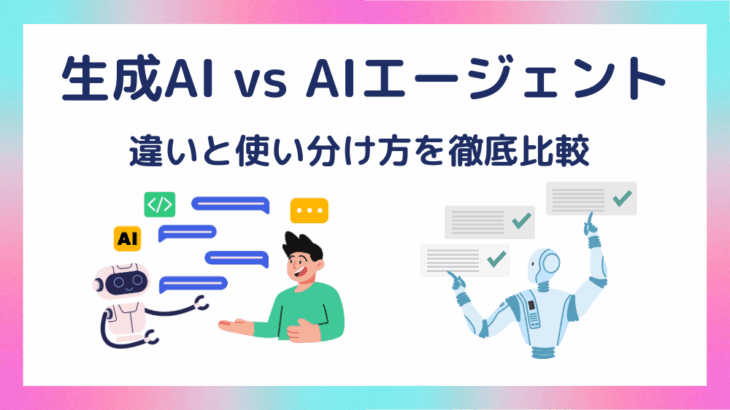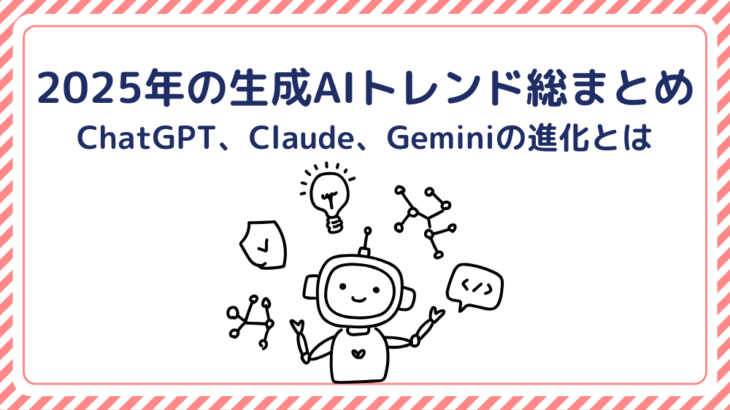物流業界では、AIの活用が“実験段階”から“実務の中核”へと急速に移行しています。中でも注目されているのが、需要予測と配送最適化におけるAIアルゴリズムの進化です。
これまで経験や勘に頼っていた需要変動の読み取りやルート設計が、AIによって高精度にシミュレーションできるようになり、在庫の最適配置や積載率の向上、CO₂排出削減など、企業の利益と環境の両立を支える基盤となりつつあります。
しかし、「AIがどう判断しているのか」「どのような仕組みで最適化されているのか」は意外と知られていません。本記事では、AIアルゴリズムの基本構造の解説、需要予測・配送最適化の裏側で何が起きているのかをご紹介いたします。
- 1. はじめに ― なぜ物流にAIアルゴリズムが必要なのか
- 2. AIアルゴリズムの基本を知る
- 2.1. AIと従来型システムの違い
- 2.2. 物流で活用される代表的なアルゴリズム
- 2.2.1. (1)時系列予測(ARIMA・LSTMなど)
- 2.2.2. (2)数理最適化(線形計画法・整数計画法)
- 2.2.3. (1)Dijkstra法(ダイクストラ法)
- 2.2.4. (2)A*(Aスター)アルゴリズム
- 2.2.5. (3)巡回セールスマン問題(TSP:Traveling Salesman Problem)
- 2.2.6. (1)クラシックVRP(基本モデル)
- 2.2.7. (2)時間窓付きVRP(VRPTW)
- 2.2.8. (3)多拠点・共同配送型VRP
- 2.2.9. (1)スロット配置最適化(Storage Location Assignment)
- 2.2.10. (2)ピッキング経路最適化
- 3. 需要予測アルゴリズムのしくみ
- 4. 配送最適化アルゴリズムのしくみ
- 5. 実際の導入事例
- 6. 導入の課題と注意点
- 7. まとめ
はじめに ― なぜ物流にAIアルゴリズムが必要なのか
物流の現場は、転換期を迎えています。人手不足、労働規制の強化、コスト上昇、そして顧客の多様化するニーズなどの課題が同時に押し寄せる中で、従来の「人と経験に頼るオペレーション」では、持続的な運営が難しくなりつつあります。こうした背景のもと、AIアルゴリズムを活用した物流改革が急速に注目を集めています。
2026年に迫る輸送力不足
2024年問題によってドライバーの時間外労働時間に年960時間の上限が設けられた結果、輸送力の確保はかつてないほど厳しい状況にあります。また、国土交通省の試算では、2026年には国内のトラックの輸送力が約14%不足すると予測されています。
出典)持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめ
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001626756.pdf
単にトラックや人員を増やすことでは対応しきれず、「限られたリソースをどう効率よく動かすか」が最大の課題になっています。ここでAIアルゴリズムが力を発揮します。配送ルートの最適化、積載率の最大化、渋滞予測やリードタイムの短縮など、人の勘や経験では不可能なレベルの最適化を瞬時に実現できるのです。
物流コスト上昇と顧客ニーズの多様化
さらに企業を悩ませるのが、燃料費や人件費の高騰です。加えて、EC市場の拡大により「翌日配送」「再配達」「小口多頻度配送」が常態化し、物流負荷は増加の一途をたどっています。
一方で、顧客はスピードだけでなく、時間指定や指定場所受け取り(宅配ボックス・コンビニ受け取り・ロッカー受け取りなど)、配送状態の可視化・通知など柔軟な配送選択も求めるようになりました。
上記のような条件を満たすには、従来のシステムやマニュアル対応では限界があります。
AIアルゴリズムによるデータ分析と自動最適化こそが、コスト抑制とサービス品質向上を両立させる鍵となるのです。
AIアルゴリズムの基本を知る
AIが物流の現場に広がる今、「アルゴリズム」という言葉を耳にする機会が増えています。しかし、実際にどのように機能し、従来のシステムと何が違うのかを理解している人はまだ多くありません。
AIアルゴリズムは単なる「自動化ツール」ではなく、データから学び、現場ごとに最適な判断を導くための仕組みです。ここでは、AIと従来型システムの違い、そして物流分野で活躍している代表的なアルゴリズムについて整理します。
AIと従来型システムの違い
従来の物流システムは、あらかじめ人が設定したルールや条件に基づいて動作していました。たとえば「出荷数が一定以上なら追加便を手配する」といった“決められた判断”しかできません。
一方AIアルゴリズムは、過去のデータやリアルタイム情報から学習し、AI自ら判断を最適化する点が大きな違いです。
天候・交通・需要変動など、変数の多い現実の物流環境において、AIはルールを超えた柔軟な対応を可能にします。つまり、AIは「決められたことをこなす存在」から「より良い方法を見つけ出す存在」へと進化しているのです。
物流で活用される代表的なアルゴリズム
AIアルゴリズムは、物流のあらゆる領域で活用が進んでいます。
◾️需給予測・在庫最適化
過去の販売データや季節要因をもとに、出荷量や在庫の最適数を自動で算出します。
(1)時系列予測(ARIMA・LSTMなど)
需要変動を予測し、過剰在庫・欠品を防ぐ。
最近ではディープラーニング(LSTM, Transformer)が精度向上を支えています。
(2)数理最適化(線形計画法・整数計画法)
コスト最小化やサービスレベル最大化を目的に、在庫配置・補充頻度・拠点配置を最適化します。
◾️配送ルート最適化
渋滞・配送時間・積載率などを総合的に分析し、最短かつ効率的なルートを導き出します。
(1)Dijkstra法(ダイクストラ法)
最短経路探索の基本アルゴリズム。一地点から他の全地点への最短経路を求めることができ、地図アプリや配送ルート探索の基礎に使われます。
(2)A*(Aスター)アルゴリズム
Dijkstra法にヒューリスティック(推定値)を加えた改良版で、探索範囲を効率的に絞り込み、リアルタイム経路検索や動的ルート更新に活用されています。
(3)巡回セールスマン問題(TSP:Traveling Salesman Problem)
「複数の配送先を最短で巡る経路」を求める典型問題。厳密解の計算は難しいため、現実の物流ではヒューリスティック法(近似解法)が多用されます。
代表例:貪欲法(Greedy Algorithm)、焼きなまし法(Simulated Annealing)、遺伝的アルゴリズム(Genetic Algorithm)
これらは配送ルート自動生成・ドライバー配車最適化システムに組み込まれています。
◾️配車・車両割り当て
TSPを拡張し、「複数車両が複数の配送先を担当する」現実的な問題に対応したものです。
(1)クラシックVRP(基本モデル)
総走行距離を最小化する配車パターンを求めます。制約条件(積載量・配送時間・ドライバー労働時間など)を組み込むことも可能です。
(2)時間窓付きVRP(VRPTW)
配送先ごとに「何時から何時の間に届けるか」という時間制約を考慮。宅配やコンビニ配送など、ラストワンマイル物流でよく使われます。
(3)多拠点・共同配送型VRP
複数拠点・複数荷主が参加する共同配送に対応。アルゴリズム的には「クラスタリング(k-meansなど)+経路最適化」を組み合わせて、積載率と距離のバランスを取ります。
◾️倉庫内最適化
庫内作業の効率化に使われるアルゴリズム群です。
(1)スロット配置最適化(Storage Location Assignment)
商品の出荷頻度・重量・関連性を分析し、ピッキング動線を最小化する棚配置を決定します。
代表的手法:クラスタリング分析、線形計画法、遺伝的アルゴリズム
(2)ピッキング経路最適化
作業者やロボットの移動距離を最小化。
Dijkstra法やA*アルゴリズムの応用に加え、AIによるダイナミックルート生成が実用化されています。
◾️AI×リアルタイム最適化
近年では、AIと従来の数理最適化を組み合わせた「ハイブリッド最適化」が主流です。
・機械学習が需要変動や交通状況を予測
・数理最適化が現場の意思決定を自動化
・強化学習(Reinforcement Learning)が配送順序や再配車を動的に最適化
これにより、「常に変動する現場条件に適応する物流最適化」が現実化しています。
需要予測アルゴリズムのしくみ
需要の変動が激しい現代の物流において、「どれだけ在庫を持ち、いつ補充するか」を正確に判断することは経営効率を大きく左右します。
物流では、「いつ・どこで・どれだけ売れるか」を予測できれば、
・在庫を持ちすぎない(コスト削減)
・欠品を防ぐ(販売機会損失の回避)
・最適な輸配送計画を立てられる(効率化)
という効果が得られます。
この“未来の需要”をデータから予測するのが、需要予測アルゴリズムです。
これは過去のデータや外部環境の変化をもとに、将来の需要を数値で見通す仕組みです。勘や経験ではなく、データに基づいた判断が求められる今、需要予測はサプライチェーン最適化の出発点といえるでしょう。
時系列データと機械学習
需要予測の基礎となるのが「時系列データ」です。過去の販売量や出荷量、在庫推移などの時間軸に沿ったデータを分析し、そこから未来の動きを推定します。
近年では、機械学習モデル(例えばLSTMやXGBoostなど)がこれを高精度に処理します。単純な平均値や移動平均に頼らず、トレンドや変化のパターンを“学習”して未来を予測できるようになりました。これにより、需要の急変や異常値にも柔軟に対応可能です。
季節性・トレンド・外部要因を考慮する方法
需要は常に一定ではなく、「季節」「イベント」「天候」「経済動向」といった外的要因にも大きく影響を受けます。たとえば飲料やアイスは気温、暖房機器は冬季需要などが明確です。
AIアルゴリズムはこれらの要素を多変量データとして取り込み、単なる過去の延長ではなく“文脈を理解した予測”を行います。加えて、SNSの話題や広告キャンペーン、競合の価格変動といった非構造データを組み合わせることで、より現実に即した精度の高い見通しが可能になります。
在庫最適化や発注計画への応用
需要予測アルゴリズムの成果は、実際の業務にどう活かすかで真価が決まります。具体的には、在庫量の適正化や自動発注システムへの連携です。予測データをもとに「どの商品を、どの拠点に、いつまでに補充すべきか」を自動で算出し、過剰在庫や欠品のリスクを最小化します。
結果として、倉庫の保管コストや輸送費の削減に加え、サービスレベルの向上にもつながります。AIによる需要予測は、もはや単なる分析ではなく、経営の意思決定を支えるインフラへと進化しているのです。
配送最適化アルゴリズムのしくみ
ルート最適化の基本(巡回セールスマン問題など)
配送最適化の根幹にあるのが「どの順番で配送すれば最短距離・最短時間で回れるか」というルート設計です。これは「巡回セールスマン問題(TSP:Travelling Salesman Problem)」として知られており、数多くの拠点を効率的に回るための最短経路を導き出す課題です。
AIアルゴリズムは、地図情報・距離・道路状況などをもとに膨大な組み合わせを計算し、最も効率的なルートを瞬時に導き出します。従来の人の勘や経験に頼ったルート設計とは異なり、データに基づいた客観的な最適解を提供できるのが特徴です。
配車計画と制約条件(車両数・時間指定・積載量)
実際の物流現場では、単に距離が短いだけでは最適とは言えません。車両の台数、積載可能重量、配送先ごとの時間指定、ドライバーの勤務時間など、複数の制約を同時に考慮する必要があります。
AIはこれらを「制約条件」として入力し、最も現実的で効率的な配車計画を自動生成します。例えば、あるルートは距離が短くても渋滞が多い場合は避け、別の車両に割り当てるなど、現場目線の最適化を実現できるのが大きな強みです。
リアルタイム最適化(渋滞・気象データの反映)
AIによる配送最適化の進化は、事前計画にとどまりません。リアルタイムでの最適化も可能です。GPSや交通情報API、気象データなどを取り込み、渋滞や事故、天候変化が起きた際に即座にルートを再計算します。
これにより、突発的なトラブルにも柔軟に対応でき、遅延リスクの低減やドライバーの稼働効率改善につながります。今後は、AIが状況を先読みして動的にルートを調整する「予測型ロジスティクス」が、物流の新しいスタンダードになっていくでしょう。
実際の導入事例
大手小売での需要予測導入事例
株式会社ファミリーマート
株式会社ファミリーマートはAIを活用した新たな発注システム「AIレコメンド発注」を2025年6月末から全国500店舗にて運用を開始しました。「AIレコメンド発注」は、膨大なデータを分析・学習することで、各店舗におむすびや弁当、サンドイッチなどの最適な発注数を自動で推奨します。これにより、店舗の業務効率化に加え、品揃えの最適化と販売機会の最大化を目指します。
「AIレコメンド発注」の主な特長
・高精度な販売予測
AIが過去1年間の販売実績、店舗周辺の通行量(時間帯別、性別、年代別)、気象データ(気温、湿度、降水量、日照量など)、カレンダー情報(祝日など)といった多岐にわたる膨大なデータを分析・学習し、日別・便別・単品別に最適な販売予測数を算出します。これにより、発注担当者の経験では予測することができない変化も捉え、高精度な推奨値を提供します。
・売場ボリュームの自動調整とフードロス対策
販売予測数に加え、販売機会ロスを防ぐために、次の納品までの在庫の繰り越し分を考慮した「売場ボリュームを保つ数」を自動で算出・加算します。これにより、適切な商品陳列量を維持し、販売機会の最大化を図ります。また、これまで過剰な発注において発生していた廃棄ロスを適正化し、フードロス対策にも繋げていきます。
出典)
https://www.family.co.jp/company/news_releases/2025/20250710_01.html?utm_source=chatgpt.com
株式会社セブン&アイ・ホールディングス
株式会社セブン&アイ・ホールディングスは2018年春より、発注業務におけるAI活用に向け、一部の店舗にて実証実験を開始しました。その成果を踏まえて、2020年9月1日、AIを使った発注提案システムを、イトーヨーカドー全136店舗に導入しました。
商品の価格や、気温・降水確率などの天候与件、曜日による特性といった基本情報をAIが分析し、最適な販売予測数を提案します。発注数量の確定は発注担当者が行う仕組みで、対象となる商品は、カップ麺や菓子などの加工食品、冷凍食品、アイス、牛乳など計約8000品目に上ります。
AIを活用したことにより、日中の補充が最低限で済み、営業時間中に品切れになる頻度も減り、また担当者が発注作業にかける時間もAI導入以前に比べて平均約3割短縮したりと成果が出ています。
出典)
https://www.7andi.com/group/challenge/16862/1.html
・運送会社におけるAI配車システム事例
アルフレッサ株式会社とヤマト運輸株式会社のAI配車計画システム
アルフレッサホールディングス株式会社傘下のアルフレッサ株式会社とヤマトホールディングス株式会社傘下のヤマト運輸株式会社は2020年7月21日に「ヘルスケア商品」の共同配送スキームの構築に向けた業務提携を発表しました。第一弾として、ビッグデータとAIを活用して、顧客毎に日々の配送業務量を予測する配送業務量予測システムと適正な配車を行う配車計画システムを開発し、このたび導入を開始します。
配車計画システムは配送業務量予測システムで得られた情報(注文数、配送発生確率、納品時の滞在時間など)を基に配車計画を自動的に作成します。これまでにヤマト運輸が蓄積した物流や配車に関するノウハウに加え、渋滞などの道路情報を活用することで、効率的かつ安定的な配車計画を作成することができます。また配送の業務量が多い時には、ヤマトグループの保有する配送リソースも機動的に活用することが可能であり、これまで以上に安定した配送を行うことができます。
出典)
https://www.yamato-hd.co.jp/news/2021/newsrelease_20210803_1.html?utm_source=chatgpt.com
佐川急便株式会社とグーグル・クラウド・ジャパン合同会社のAIを活用した業務の効率化
2024年10月佐川急便株式会社とグーグル・クラウド・ジャパン合同会社は、DXを活用した総合物流機能の強化に向けた戦略的パートナーシップ協定を締結しました。
佐川急便株式会社が有する配送のデジタル基盤をもとにGoogle CloudやGoogle Maps Platformを活用することで、AIによる集配エリアの最適化や過去のデータに基づく将来の集配予測、必要な人員リソースの適正化の検討を行います。また、トライアルで導入したDXを通じて、総配達時間の短縮や車両台数の削減を検証し、効率的な配達ルートに変更したことによるCO2排出量の削減効果を確認していきます。
出典)
https://www2.sagawa-exp.co.jp/newsrelease/detail/2024/1024_2327.html?utm_source=chatgpt.com
導入の課題と注意点
AIやデータ分析を物流や配車最適化などの業務に導入する際、多くの企業が「期待した効果を得られない」「運用が定着しない」といった課題に直面します。
その原因の多くは、システムそのものではなく、導入前後の設計と運用の準備不足にあります。ここでは、AI・データ活用を成功させるうえで避けて通れないデータ整備のハードルとROI(投資対効果)の見極めについて整理します。
データ収集と整備のハードル
AI活用の前提となるのは、正確で一貫性のあるデータです。しかし、実際には「現場と本社でフォーマットが違う」「手入力や紙ベースの情報が多い」など、データの収集・整備に多くの時間と労力がかかります。
特に物流現場では、車両の位置情報、積載率、待機時間などのデータがバラバラに管理されているケースも多く、AIに学習させるための素材をそろえることが最大の壁になります。
導入前に、どのデータをどの頻度で収集し、どのように統合するか、このプロセスを設計しておくことが、プロジェクト成功の第一歩です。
ROI(投資対効果)の見極め
AI導入は“高コスト・高リターン”になりがちです。初期投資だけでなく、運用・保守・データ更新といった継続的コストも発生します。そのため、単に「AIを入れること」が目的化してしまうと、費用対効果が見えづらくなります。
ROIを見極めるには、「どの指標をどれだけ改善したいのか」を数値で明確にすることが重要です。たとえば「配車業務の工数を30%削減」「積載率を5ポイント向上」など、具体的なKPIを設定し、段階的に成果を検証する仕組みを整えることで、導入効果を可視化しやすくなります。
まとめ
本記事では、物流業界で注目が高まるAIアルゴリズムの基本構造と活用の仕組みについて解説しました。AIはこれまで人の経験や勘に頼っていた「需要予測」や「配送計画」をデータに基づいて最適化し、精度の高い意思決定を支える存在へと進化しています。
これらの技術は、単に効率化を目的とするだけでなく、ドライバー不足や環境負荷の低減といった社会課題の解決にもつながっています。
今後、AIは個別の業務支援にとどまらず、サプライチェーン全体を見渡した最適化へと進化していくでしょう。物流現場のリアルなデータをどう活かすかが、企業の競争力を左右する大きな鍵となります。