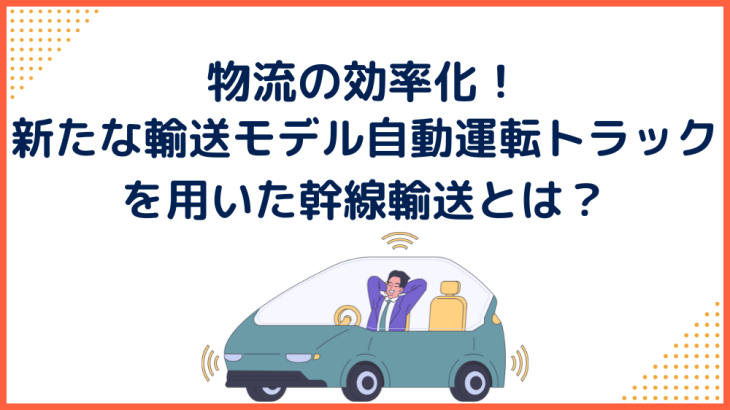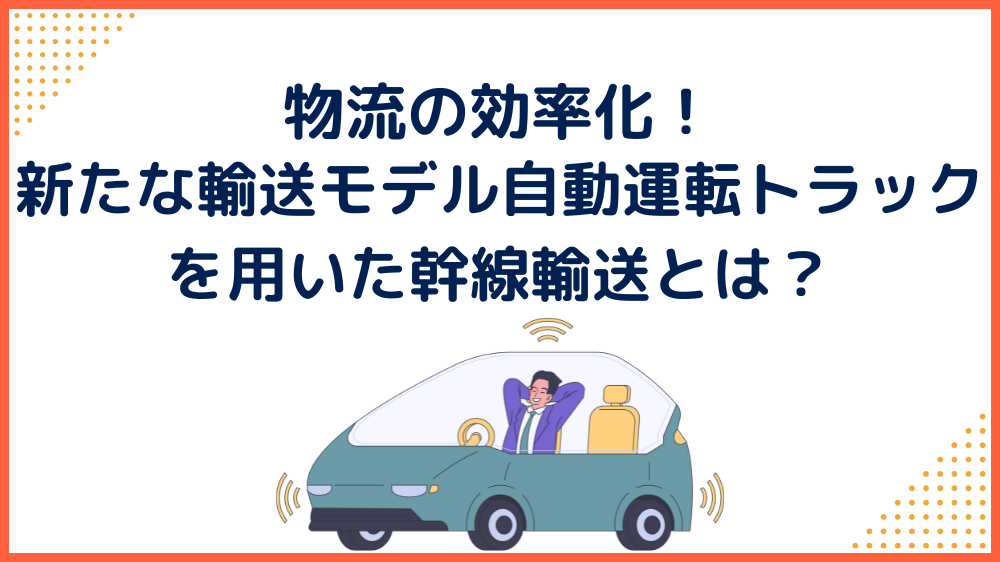
自動運転トラックとは?
自動運転トラックは、車両に搭載されたセンサーやカメラ、GPS、レーダーなどのデバイスを活用して動作します。これらの装置が周囲の状況をリアルタイムで把握し、高精度な地図情報(HDマップ)を参照しながら、自動的に最適な走行ルートや運転操作を判断します。また、高速道路などの決まったルートを運行する「幹線輸送」に適しており、長時間の運転が可能でドライバーの負担軽減や労働力不足の解消に役立つと期待されています。
自動運転トラックの技術的特徴
・センサー技術
カメラやライダー(LIDAR)、レーダーを組み合わせて周囲の状況をリアルタイムで検知し、安全な運行を支援する。
・高精度地図(HDマップ)
詳細な道路情報をもとに、トラックの現在位置を正確に把握しながらルートを設定します。
・AIアルゴリズム
速度調整や車間距離の管理を自動化し、交通状況に応じた判断を可能にします。
・通信技術(V2X)
車両間やインフラとの通信を行い、渋滞情報や緊急時の連携をスムーズにします。
自動運転トラックの技術レベル
自動運転には レベル0~5 の段階がありますが、幹線輸送では主に レベル3(特定条件下での自動運転)やレベル4(無人運行可能) の導入が進められています。
・レベル3:ドライバーは乗車しているが、高速道路など特定の環境下ではシステムが運転を担う
・レベル4:限定されたエリアや条件下では、完全な自動運転が可能
現在の実証実験では、高速道路や特定ルートでの 隊列走行(複数のトラックが自動制御で連なって走行) などが進められています。
幹線輸送とは?
幹線輸送とは、物流の中核となる大規模な輸送区間を結ぶ長距離輸送のことを指します。
例えば、東京~大阪間や北海道~九州間といった都市間を結ぶ大規模な輸送が幹線輸送に該当します。一般的に、幹線輸送はトラック・鉄道・船舶・航空機を利用して行われます。
幹線輸送の主な手段
①トラック輸送(大型トラック)
▼メリット
・フレキシブル(荷物の種類や時間に柔軟に対応できる)
・全国の高速道路網を活用できる
・物流拠点から直接輸送可能
▼デメリット
・2024年問題(労働時間制限)によりドライバー不足が深刻化
・CO₂排出量が多く、環境負荷が高い
②鉄道輸送(コンテナ輸送)
▼メリット
・CO₂排出量が少なく、環境に優しい
・一度に大量の貨物を輸送できる
▼デメリット
・ダイヤに制約があり、フレキシブルな運用が難しい
・目的地までの最終配送にはトラックが必要
③船舶輸送(内航海運)
▼メリット
・大量輸送に最適(コストが安い)
・CO₂排出量が少なく、環境負荷が低い
▼デメリット
・輸送速度が遅い
・港までの陸上輸送(ドレージ輸送)が必要
④航空輸送
▼メリット
・最速の輸送手段
▼デメリット
・コストが高く、大量輸送には不向き
幹線輸送が注目される背景と理由
幹線輸送が注目される背景には、物流業界が直面する複数の課題があります。
2024年問題と物流の効率化の必要性
2024年問題とは、トラックドライバーの労働時間の上限規制(年間960時間)が導入される関係で、長距離輸送の担い手が減少し、輸送能力が低下する問題のことで、物流業界全体で「輸送の効率化」が求められています。
対応策として幹線輸送が注目されています。トラックの長距離運行を減らし、鉄道・海運への転換(モーダルシフト)を促進し、効率的な幹線輸送の確立が、今後の物流のカギとなってくると言われています。
CO₂排出削減とカーボンニュートラルの推進
国土交通省によると、物流業界は国内のCO₂排出量の約18%を占めると言われており、長距離輸送はCO₂排出量が多いため、低炭素化が不可欠とされています。幹線輸送の中で、鉄道輸送(貨物列車) は、 CO₂排出量がトラックの約1/10で、海上輸送(フェリー・内航船) は、環境負荷が少なく大量輸送に適しているとされています。また、EVトラック・燃料電池トラックの利用で、CO₂ゼロの車両の導入も促進されます。
物流コストの上昇とコスト削減の必要性
原油価格の変動により、 燃料費が上昇し、トラック輸送のコストが増加しています。また、ドライバー不足は人件費の上昇を招き、輸送コストが増大しているのが現状です。
幹線輸送のコスト削減施策として、複数企業で幹線輸送をシェアする、共同輸送・混載輸送の推進、物流の最適化・可視化を実現するフィジカルインターネットの導入、自動運転トラック・鉄道貨物の活用による幹線輸送の自動化が注目されています。
幹線輸送における自動運転トラックの導入事例
株式会社T2
株式会社T2は、自動運転システムの開発と、それを搭載した車両による幹線輸送サービスを提供しています。
日本の幹線輸送市場(約2兆円規模)をターゲットとし、特に関東圏と関西圏を結ぶ主要物流拠点間の自動運転トラックによる輸送サービスを提供し、ドライバー不足や労働規制の課題に対応し、安定した輸送サービスの提供を目指しています。
関東圏⇔関西圏の物流拠点間の幹線輸送を初期対象とし、段階的に拡大予定で高速直結の物流拠点が限られるため、初期は高速出口付近に「切替拠点」を設け、有人運転で拠点まで輸送するオペレーションを想定しています。
2020年7月にPoC開始以降、公道実証実験などで安全走行を確認し、政府のロードマップに沿う形で2025年度内に事業開始を目指しています。
出典)
株式会社T2の他企業との実証実験の事例
・福山通運株式会社×セイノーホールディングス株式会社×株式会社 T2
福山通運株式会社は持続可能な物流の実現に向け、陸送を長距離フェリーや鉄道に置き換えるモーダルシフトの推進、輸送生産性を向上させるための新技術の導入の検討等、様々な課題に対し施策を講じており、Value Chain Innovation Fund(2023年10月にT2が実施したシリーズA追加ラウンドでの第三者割当増資の引受先)への参画を機に、同ファンドのアンカーLPであるセイノーHDと同様に、自動運転トラックの技術・事業開発を行うT2と共に本実証に取り組むこととなりました。
本実証を通して、運送オペレーションノウハウと自動運転技術を掛け合わせた新たな運送モデルを創造し、2027年にはレベル4自動運転トラックを活用した幹線輸送の実現を目指しています。
引用)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000110471.html
・日本郵便株式会社およびJPロジスティクス株式会社×セイノーホールディングス株式会社×株式会社 T2
2024年7月、株式会社 T2およびセイノーホールディングス株式会社の2社は、レベル4自動運転トラック幹線輸送の実現を目指した公道実証を開始すると発表しました(2024年7月11日の発表)。また、セイノーホールディングス株式会社が、日本郵便と幹線輸送の共同運行に向けて業務提携していることから、日本郵便株式会社およびJPロジスティクス株式会社の本実証への参加が実現しました。
本実証では、トラック輸送のリソースを最大限生かすべく、幹線輸送の共同運行を行っているセイノーホールディングス株式会社、日本郵便株式会社およびJPロジスティクス株式会社と、自動運転トラックの技術開発を行っている株式会社 T2が手を取り合い、幹線輸送の共同運行のオペレーションノウハウと自動運転技術を掛け合わせることで、新たな輸送モデルの価値を創造します。
引用)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000110471.html
NEXT Logistics Japan株式会社
NEXT Logistics Japan株式会社が代表、株式会社豊田自動織機、株式会社アイシン、NLJパートナー企業が参加して新たな幹線輸送スキームによる省人化、環境負荷低減、働き方改革の実現のために取り組まれています。
2023年には下記の取組みが実施されました。
- 自動荷役の導入:積下ろしの自動化とオペレーション構築、機器間・荷物情報の要件定義
- 荷姿の標準化:標準荷姿9パターンの一部実装と対応範囲の明確化、課題抽出、普及に向けた課題と精度向上策の立案
- 荷物情報の一元化:・情報内容の明確化と実システムに向けた課題抽出
実証実験では、自動荷役機器の精度や作業時間が目標に近づき、荷姿の標準化による積載効率の向上とCO₂排出量の削減効果が確認されました。2025年度を目処に実施を目指しています。
出典)
自動運転トラックが変える幹線輸送の未来とは?
自動運転トラックは、AIやセンサー技術を活用し、ドライバーに依存せずに安全かつ効率的な輸送を行う次世代技術です。特に幹線輸送では、高速道路の決まったルートを安定して運行できるため、導入が進んでいます。物流業界が抱えるドライバー不足や長時間労働といった課題を解決する手段として注目されています。
自動運転トラックのメリット
①効率性の向上
車間距離や速度を最適化し、燃料消費を抑えることで輸送コストの削減や高速道路での安定した走行により、渋滞や遅延を回避し輸送時間を短縮することができます。
②安全性の向上
ヒューマンエラーを排除し、センサーやAI技術を活用して周囲の状況をリアルタイムで把握し迅速に対応することで、交通事故のリスクを大幅に軽減します。
③労働力不足の解消
ドライバーが必要な長時間労働を軽減し、24時間連続運行を可能にすることで、物流業界の人手不足に対応しながらドライバーの負担を大幅に軽減します。
④環境負荷の軽減
燃料消費を最適化し、効率的な運行によってエネルギー消費を抑制することで、CO2排出量の削減を実現します。
⑤コスト削減
ドライバーの人件費削減や燃料の効率的利用による経済的メリットに加え、メンテナンスの効率化によって運行費用の低減が可能になります。
自動運転トラックの可能性
①24時間運行の実現
ドライバーが必要な休憩時間を不要にし、24時間稼働が可能となるため、輸送スピードと生産性が向上します。
②物流網の強化
幹線輸送を効率化し輸送ルートの柔軟性を高めることで安定した供給体制を構築するとともに、地域間の物流を円滑化し災害時や緊急時にも迅速な対応が可能になります。
③スマートシティとの連携
自動運転技術を都市計画に組み込みスマートインフラと連動させることで、効率的な物流ネットワークを構築し、都市と地方をシームレスにつなぐ未来型物流を実現します。
自動運転トラック導入の課題とその解決策
自動運転トラックは、物流業界の効率化や持続可能性の向上に向けた革新的な技術です。しかし、導入にはいくつかの課題が存在します。
①コストの高さ
自動運転トラックの導入には高額な設備投資が必要です。
解決策: 国や自治体による補助金や助成金の活用で初期費用を抑える。また、大規模物流企業が先行導入し、普及モデルを確立することでコスト削減を図る。
②技術面での成熟度不足
完全な自動運転には、センサーやAIの精度向上が必要です。
解決策: 実証実験を通じて技術データを蓄積し、改良を進める。幹線輸送のような限定的な環境での活用から始め、段階的に範囲を拡大する。
③法規制の整備
自動運転車両に関する道路交通法や責任の所在が不明確です。
解決策: 政府と企業が連携し、法整備を進める。具体的には、安全基準の策定や運行管理のルール化が必要。
④社会的な受け入れ
自動運転に対する安全性への懸念が根強い。
解決策: 地域住民への説明会や透明性のあるデータ公開で理解を促進し、信頼性を向上させる。
未来の物流を見据えた幹線輸送の進化
物流業界は、人手不足や労働時間規制の影響を受け、大きな転換期を迎えています。その解決策として注目されるのが、自動運転トラックを活用した幹線輸送の進化です。特に、高速道路を活用した自動運転技術の導入は、長距離輸送の効率化に大きく貢献します。
自動運転トラックは、24時間稼働が可能なため、従来のドライバーによる運行と比較して輸送のスピードと安定性が向上し、AIとセンサー技術によって最適なルートを選択し、燃料消費を抑えながら安全性を確保することが可能になります。さらに、トラック同士の隊列走行技術の活用により、渋滞の緩和や物流拠点間のスムーズな連携が実現されます。
まとめ
自動運転トラックを活用した幹線輸送は、物流業界の効率化と持続可能性を高める重要な技術です。ドライバー不足や長時間労働の課題を解決し、24時間稼働による輸送の安定化、AIによる最適ルート選択によるコスト削減など、多くのメリットがあります。さらに隊列走行技術の導入により、燃費効率の向上や渋滞緩和も期待されています。
しかし、法整備や技術の成熟度、安全性の確保といった課題も残されており、今後の発展には官民一体となった取り組みが不可欠です。すでに国内外で実証実験が進められており、将来的には幹線輸送の標準モデルとなる可能性が高いでしょう。
今後、法規制の整備やインフラの適応が進めば、自動運転トラックは物流の基盤として定着し、持続可能な輸送モデルの構築に寄与するでしょう。幹線輸送の進化は、物流の未来を大きく変える可能性を秘めています。
この記事の執筆・監修者
 Aidiot編集部
Aidiot編集部「BtoB領域の脳と心臓になる」をビジョンに、データを活用したアルゴリズムやソフトウェアの提供を行う株式会社アイディオットの編集部。AI・データを扱うエンジニアや日本を代表する大手企業担当者をカウンターパートにするビジネスサイドのスタッフが記事を執筆・監修。近年、活用が進んでいるAIやDX、カーボンニュートラルなどのトピックを分かりやすく解説します。