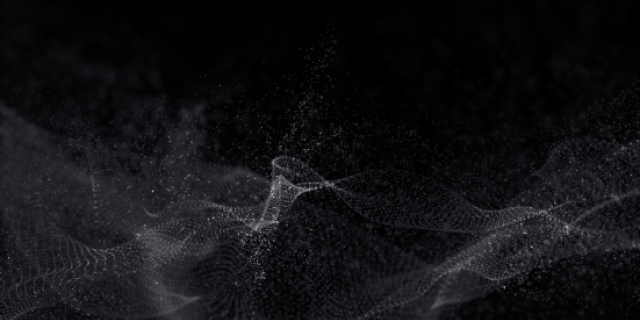AZ-COM丸和ホールディングス株式会社
AZ-COM丸和ホールディングス×アイディオット
物流業界全体の効率化と持続可能性を目指す共同プロジェクト

- 業種
- 陸運業
- 事業内容
- ・サードパーティ・ロジスティクス(3PL)事業 (EC常温3PL、低温食品3PL、医薬・医療3PL)
・ロジスティクスコンサルティング事業
・運輸事業 (一般、特別積合、引越、産業廃棄物の収集運搬 他)
・オンデマンド、文書保管事業
・倉庫業 - 課題
- ・2024年問題によるドライバー不足の深刻化
・物流ネットワーク全体の最適化が困難
・企業間の連携不足による物流効率の低下 - 解決策
- ・TMSとルート最適化技術で配送を効率化
・拠点・車両・人材を共有し輸送を最適化
・異業種共同配送を推進しコスト削減
はじめに
近年、物流業界は「2024年問題」をはじめとする深刻な人手不足や、環境負荷の軽減、さらにはサプライチェーンの効率化など、多くの課題に直面しています。これらの課題を解決するため、国を挙げて「フィジカルインターネット」の実現が掲げられ、2040年を見据えたロードマップが策定されています。「フィジカルインターネット」とは、物流の物理的なリソース(拠点、車両、人材など)をインターネットのように共有・最適化し、業界全体の効率化を図る新しい物流の概念です。
今回、AZ-COM丸和ホールディングス様は、この「フィジカルインターネット」の実現に向けて、弊社とともに新たな一歩を踏み出されました。本インタビューでは、AZ-COM丸和ホールディングス様が取り組む「フィジカルインターネット」の概要や、弊社をパートナーとして選ばれた経緯、そして今後の展望について、執行役員IT管理部長の千須和学様、IT管理部長の土屋敦洋様にお話を伺いました。
弊社で開発させていただいた「フィジカルインターネット」のシステム概要を教えていただければと思います。
土屋様:現在、物流業界では「2024年問題」による人手不足が深刻化しており、その解決策の一つとして「フィジカルインターネット」が国策として掲げられています。特に2040年を目標としたロードマップが示される中で、その重要性は社会的にも一層高まっていると実感しています。
しかし、2040年という長期的な視点で考えると、具体的にどこから着手すべきかは難しい課題です。そのため、まずは自社で取り組める領域から着手することが重要だと考えています。小売業者や問屋、メーカーなどを巻き込んで進めるのはハードルが高いため、まずは自社内のリソース(拠点、車両、人材)を活用し、フィジカルインターネットの小規模な実証実験を行うことが適切だと判断しました。
この取り組みの一環として、現在御社に開発を依頼しているTMS(輸配送管理システム)を活用しています。具体的には、御社が持つADT(高度配送技術)のルート最適化エンジンをTMSに組み込み、最適化したデータをTMSへ戻す仕組みを構築しました。これにより、自社内のデータを活用した「フィジカルインターネット」の実証実験を進めています。
今後は、この実証実験を通じて得られたデータや知見を活かし、段階的にスケールアップしながら、より広範な物流ネットワークの最適化を目指していきたいと考えています。
井上:ありがとうございます。「2024年問題」において、御社の中期経営計画にも示されているように、ドライバー不足が最大の課題となっています。そのため、輸送距離や車両台数の削減を図ることが重要であり、現在の取り組みもその方針に沿ったものと考えています。
アイディオットを選んでいただいた経緯についてお聞かせください。
千須和様:御社は内閣府のプロジェクトを手掛けており、フィジカルインターネットセンターの会員企業でもあります。当社もSIP物流標準化を掲げている中で、御社が進めていた物流標準化の取り組みと方向性が一致していたため、お話しする機会をいただきました。また、SIPとデジタルツインの観点から考えていたことも共通しており、同じビジョンを共有できたことが、大きなきっかけになりました。
さらに、社長である井上さんをはじめとした、役員、社員の方々のベンチャー気質にも強く惹かれました。御社の挑戦的な姿勢やスピード感は、当社が目指す方向性とも合致しており、大変魅力的に感じています。
井上:ありがとうございます。弊社は最先端技術を活用した社会課題の解決を掲げており、その一環として最新の技術事例を積極的に取り入れ、AZ-COM丸和ホールディングス様にもご活用いただけるような取り組みを進めていきたいと考えています。他社の事例も含め、より実践的な技術活用の機会を提供できればと思っています。
 (右)執行役員IT管理部長(統括担当) 千須和 学様(左)IT管理部 部長 土屋 敦洋様
(右)執行役員IT管理部長(統括担当) 千須和 学様(左)IT管理部 部長 土屋 敦洋様
プロジェクトの進捗と弊社の対応についての評価をお聞かせください。
土屋様:一般的な大手SIerの場合、要件定義の段階で「この部分は御社で対応してください」といった明確な役割分担が行われることが多く、それにはメリットもデメリットもあるかと思います。
一方で、御社のプロジェクトメンバーの皆様は、より現場に寄り添ったアプローチを取られていると感じています。例えば、加藤さんは実際にスマートフォンを持って渋谷を歩き回り、現場の状況を直接確認していました。また、TMS導入の際には、野田にある当社の物流センターへ赴き、作業状況や会社の運用実態を詳細に調査されていました。
通常であれば、こうした現場調査はユーザー側が実施し、その結果をSIerと共有する形が一般的ですが、御社の皆様は積極的に現場に足を運び、自ら状況を把握しようとされていました。特に、夜間22時に配車現場を訪問し、ヒアリングを行うなど、現場のリアルな状況を理解しようとする姿勢が非常に印象的でした。こうした取り組みにより、単なるシステム導入にとどまらず、現場の課題や背景を踏まえた提案をしていただける点は、大変ありがたく感じています。
千須和様:また、AZ-COMネットワークの大規模リニューアルプロジェクトにおいても、当社の意見を丁寧に汲み取りつつ、適切な方向性を示していただいたことで、スムーズに進行できました。その柔軟な対応には、大変感謝しております。
井上:ありがとうございます。現在、プロジェクトの体制や進め方、そしてアウトプットが具体的に見えてきている段階かと思いますが、システム面についてはどのように感じていらっしゃいますか?
土屋様:TMSについては確認していますが、まだ開発の途上という認識です。今後、位置情報のデータが追加されることで、更に進化していく部分もあるかと思いますので、そのあたりは今後の納品フェーズでの調整が必要になるかと思います。
千須和様:ビジュアル面での第一印象としては、TMSもAZ-COMネットワークのシステムも非常に良い仕上がりになっていると感じています。
井上:そうですね。クラウド環境に適した、モダンなUI/UXがしっかりと設計されているかなと思っております。

現在は拠点とエリアを限定してフィジカルイントラネットを展開しておりますが、今後の展望についてお聞かせください。
千須和様:私の考えとしては、現在ドメインごとに行われている配送を、同じエリア内であれば食品とドラッグストア商品などを統合できると理想的だと考えています。
土屋様:例えば、ショッピングモールのように、駐車場を共有する施設内に薬局やスーパーが併設されている場合、配送を一元化できると効率的ですよね。そのような仕組みを実現できれば、より効果的な物流運用が可能になると思います。
千須和様:また、現在、幹線輸送はそれほど多くは手掛けていませんが、例えばグループ会社の関西丸和ロジスティクスの荷物と中四国丸和ロジスティクス、九州丸和ロジスティクスの荷物を相積みできれば、輸送効率の向上が期待できるかと思います。現在は会社が異なるため、それぞれ別々の輸送になっていますが、将来的には統合の可能性も考えられるのではないでしょうか。
井上:幹線輸送は大きな効率化の余地がありそうですね。
千須和様:それは難しい課題ですが、もしそこまで対応できる要素技術があれば、活用の可能性は十分にあると考えています。実現できるかどうかはまだ不確定ですが、検討の余地はあるかもしれません。
井上:現在、弊社は幹線・ルート・ラストワンマイルのうち、主にルート配送の領域を担当させていただいています。一般的に、共同配送というと幹線輸送の共通利用が主流というイメージがありますが、これは輸送する荷物の量が多いためだと思います。将来的には、こうした領域にも徐々に取り組んでいければと考えています。
千須和様:まずは小規模な店舗が集まるエリアでの取り組みから始め、最終的にはグループ会社全体で「フィジカルインターネット」を活用できる形にしていけると理想的ですね。実際にそれだけの荷物があるかはまだ分かりませんが、例えば九州で採れた野菜を関東まで輸送するようなケースは、今後増えていく可能性があると考えています。
そのため、「フィジカルインターネット」の導入にあたっては、モーダルシフトの要素を取り入れ、コンテナ輸送や航空輸送の活用も視野に入れていくことが重要だと考えています。
井上:弊社でも、複数の輸送モードを組み合わせたシミュレーションを一部実施しており、チャーター路線を含め、鉄道や船舶を活用する可能性を検討しています。ただ、現状ではまだ課題も多く、実用化には難しい面があると感じています。
例えば、Googleマップでは「ここから先は電車、ここから先はバス」といったルートがスムーズに表示されますが、物流ではまだそこまでの最適化が実現されていません。しかし、千須和様がおっしゃる通り、今後はそうした流れが進んでいく可能性が高いと考えています。
千須和様:当社の代表は、自社の利益だけを追求するのではなく、物流業界全体の発展を目指しており、「フィジカルインターネット」やSIPの取り組みにも関心を持っています。 その理念のもとでAZ-COMネットワークも設立しました。
物流業界は各社の独自性が強く、業界全体の連携が難しい面がありますが、理想的には政府や大手事業者や郵便事業者などが協力し、統一されたルールを策定し、それに各社が順応できる仕組みが整えば、より効率的な業界運営が可能になると考えています。
井上:本日はお時間をいただき、誠にありがとうございました。
おわりに
今回、AZ-COM丸和ホールディングスの千須和様、土屋様のお二方と「物流が抱える問題にITやAIで対処をしていくか、フィジカルインターネットといった未来の取り組み」をテーマに対談をさせていただきました。
AZ-COM丸和ホールディングス様は弊社の株主でもあり、和佐見社長はじめ、多大なる連携をさせていただいております。日本における物流問題は非常に深刻で国土交通省や経済産業省が重点領域として補助事業を行なったり、法整備を進めております。そんな中でアナログな部分も多くあり、まだまだ改善の余地があります。決して簡単な課題ではありませんが、重厚長大な課題解決にともにチャレンジしていきたいと考えております。