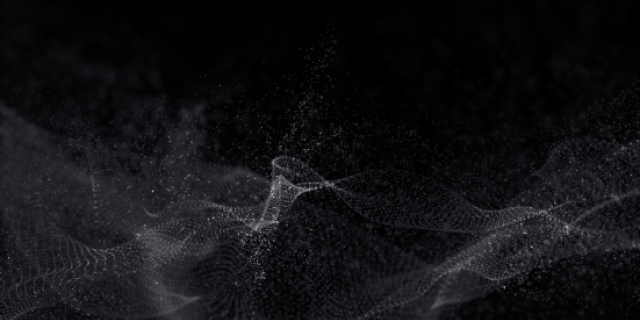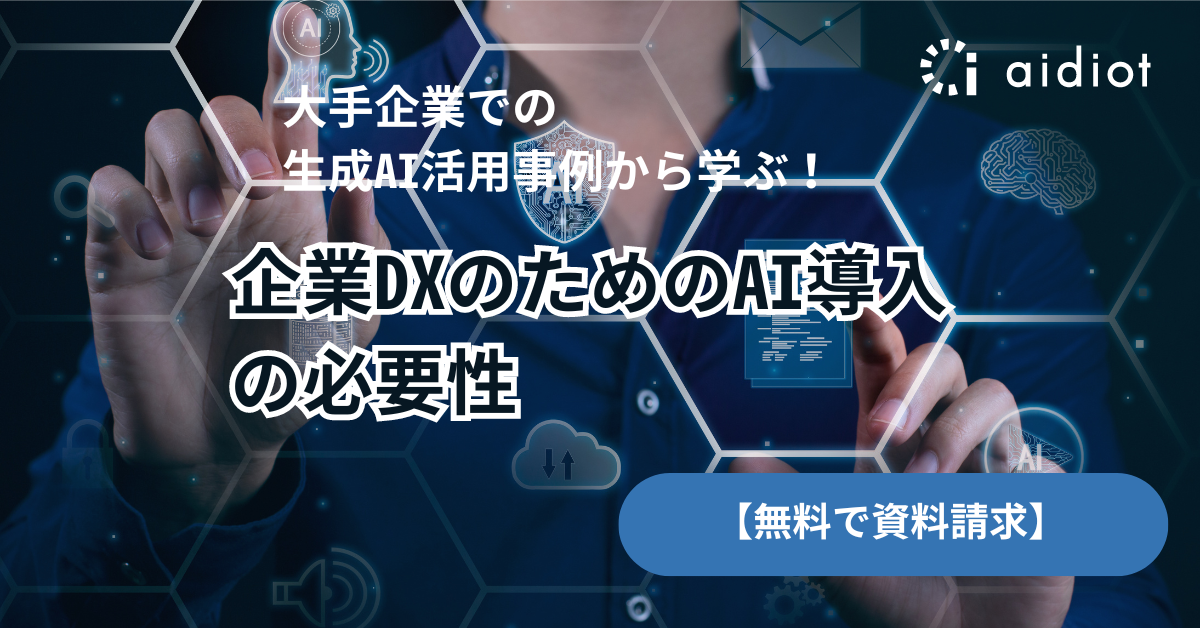旭化成株式会社
旭化成×アイディオット
カーボンニュートラルを目指したプロジェクトの取り組み事業及び資本業務提携について

- 業種
- 総合科学メーカー
- 事業内容
- 森林クレジットを活用したカーボンニュートラル実現を目指すプロジェクトの推進。
森林資源の活用を通じた持続可能性の向上と地域経済への貢献を目指す。 - 課題
- ・日本国内の森林クレジット活用率が極めて低い(0.2~0.3%)
・森林資源の有効活用とサステナビリティ確保が遅れている
・カーボンニュートラル実現に向けた排出量削減ストーリーが描きづらい - 解決策
- ・森林資源を有効活用するためのプラットフォーム開発
・多様な利害関係者が参加するエコシステムの構築
・森林クレジットの可視化やアルゴリズム開発による透明性と信頼性の確保 - 導入技術
- AIを活用したクレジット可視化システム/ 森林クレジットのトラッキングと管理のためのデジタル技術
はじめに
弊社は2年前より旭化成様とカーボンニュートラルを目指したプロジェクトを共に進めさせていただいております。更に2024年6月には資本業務提携をさせていたただくなど、非常に良いパートナーシップを築かせていただいております。今回のインタビューでは、プロジェクトを共に進めさせていただくことになった経緯や資本業務提携を決断いただいた経緯を旭化成株式会社 研究・開発本部 イノベ-ション戦略総部 事業創造推進部 部長 辻 秀之様と同部 マネージャー山田様に、弊社代表井上がインタビューをさせていただきました。
現在やられている事業のお話をお聞かせください。
旭化成 辻様:世の中の大きな流れとして、再生可能エネルギーである太陽光発電や風力発電は浸透が進んでいますが、一方で、森林クレジットの活用などはまだまだ不十分であると感じております。特に、日本は国土面積に占める森林の割合が、2/3もある正に森林大国でありますが、その中でクレジット化されているものは1%も満たない、0.2~0.3%程度だと言われています。この現状は大きな社会課題であると認識していたことと、加えて、弊社の創業の地である宮崎県延岡市を元気にしたいという想いもありました。延岡は林業が大変盛んな地域で、世の中の社会課題と延岡のポテンシャルがちょうど同じ方向を向いていたということがあり、延岡を起点にまず取り組みができるのではないかと考えたことがきっかけで事業の構想を練ることになりました。
井上:ありがとうございます。延岡市に当社のメンバーも何名か行かせていただいたことがありますが、お恥ずかしいですがそれまで市役所の「林務課」という課を聞いたことがありませんでした。延岡市はそれだけ林業が盛んなんだと感じた記憶があります。
カーボンニュートラルを目指した事業展開についてお聞かせください。
井上:旭化成様はカーボンニュートラルを目指して事業を展開されていると思いますが、カーボンニュートラルのためにはCO2を減らすか吸収するかがあって、減らすことは再エネ・省エネが有効ですが、CO2を減らして吸収していく取り組みで、現在認められているのは森林しかないのでしょうか?
旭化成 辻様:CO2削減という意味でのクレジットは他にもあると思いますが、我々が森林クレジットに注目したのは、先ほど申し上げたように日本は森林大国であるにもかかわらずそれを有効に活用できていないことにつきます。これはクレジットだけの話ではなくて、国土の大半を占める森林のサステナビリティがそもそもの大きな社会課題だと思います。森林がこれからも健全な森林であるためには、上手に活用して新陳代謝を促すことが必要です。そのための有効な手段の一つが森林クレジットであると考えています。
井上:なるほど、森林大国であるにもかかわらず、0.2%程度しか使われていない森林クレジットを掘り起こすことは森林のサステナビリティにも繋がっていく可能性を秘めているのですね。
旭化成 辻様:はい。特に製造業では大きな課題なのですが、エネルギー転換や、事業の構造転換などで、そもそも排出量を減らすこと自体は各社で色々と取り組んでいると思いますが、「2050年カーボンニュートラル実現」というものに対しては、なかなか最後まで確かなストーリーが描けていないというのが世の中全体の課題なのではと思うんですよね。
少しでもカーボンニュートラルに近づくためには、現状でほとんど手が付けられていない森林資源の活用というのは社会課題としても大きなターゲットになるのではないかと思います。

旭化成株式会社 研究・開発本部 イノベーション戦略総部 事業創造推進部 部長 辻 秀之様
今回のビジネスのきっかけは海外事例なども参考にされたのでしょうか?
井上:まさに先日、COP29でも色々なことが国際レベルで決まっていますが、今回、炭素クレジットを国際的に流通させる仕組みを作るみたいなものがあるのですが、御社では、海外の事例などを見て、今回のビジネスをやろうと考えられたのですか?
旭化成 辻様:今回のビジネスに関しては、海外の事例でロールモデルとしたものは特にありませんが、森林クレジットという観点ではチェックしています。
井上:海外の事例は私も収集していたりするのですが、森林の吸収量をかさ増ししていたとか、問題もいろいろ起きているんですよね。
旭化成 辻様:そういったグリーンウォッシュのような課題は多く、J-クレジットについてもまだまだ過渡期ではあると思っています。
そういったことをいかに社会でいかに適正化していくか、馴染ませていくかということは、テクノロジーでできることもあるでしょうし、それが今回、我々とアイディオットさんと連携させていただいている目的、アプローチの一つでもあります。
井上:ありがとうございます。J-クレジットの売買プラットフォームを手掛けている企業はいくつか出てきましたが、吸収量の可視化を行っている企業はおそらくいないのではと思っていて、今行っている検証がうまくいけば御社と当社で開発しているシステムおよびアルゴリズムがある意味でのスタンダードになることができるのではないかんと感じております。
今回事業化にあたり、どれぐらい前から構想はあったのでしょうか?
旭化成 辻様:2022年の半ばごろにスタートしました。6月ごろから構想して、すぐ実行という感じですね。
井上:構想から実行がすごく早かったですよね。
旭化成 辻様:そうですね。そこは課題が明確なので、実行に移すまでにそれほど時間は掛からなかったですね。
今回、複数募集があった中で、弊社と一緒にやってみようと思ったきっかけをお聞かせいただけますでしょうか?
旭化成 辻様:それはやはり、社会基盤のプラットフォームに事業集中し、フォーカスを当てられている点が筋がいいと思ったことと、もう一つは、最初に入った弊社のメンバーがコミュニケーションを取っていく中で、非常にコミュニケーションも取りやすいし、パートナーとしてやっていく中で、信頼関係も含めて良いのではないかという評価をしていましたね。
井上:ありがとうございます。
旭化成 辻様:私も話をさせてもらって、事業形態や会社の方向性もそうですけど、会社の雰囲気や想い、キャラクターがとても良いと感じました。実際、出資の話もこういったものがそぐわないとやはりなかなか進まないですよね。
出資や研究開発本部での構想についてお聞かせください。
井上:旭化成様のCVCはアメリカにあると伺っていますが、旭化成本体から出資するケースはよくあるんですか?
旭化成 辻様:CVCオフィス以外からのスタートアップへの投資というケースもありますが、数はそう多くはありません。その意味では、今回のアイディオットさんとの連携の仕方はこれまでにはあまりなかったケースだと思います。
井上:そうなんですね。身が引き締まりますね。
旭化成 辻様:特に、研究・開発本部としては主にマテリアル領域の事業貢献をスコープに置いていますので、素材や材料開発に関する連携は多くありますが、アイディオットさんのようなプラットフォームの会社との連携は研究・開発本部としては、かなり珍しいのではないかと思います。
井上:ありがとうございます。
研究開発本部で、オープンイノベーション 含め、多く取り組みをされていると思いますが、その中でどのくらい芽が出そうでしょうか?
旭化成 辻様:オープンイノベーションプログラムとしては、ここ数年は毎年3〜5つのテーマでパートナーを募っています。研究開発テーマの多くは何かしらの場面で社外との共創を志向しているケースが多く、むしろ、自社で全て完結してやっている方が少ないのではないかと思います。
今回の開発についてこれからディテールに入っていく中で、ビジネス側での今後の広がりについてお聞かせください。
井上:開発もこれから詳細の方に入っていきますが、ビジネス側で今後どういう広がりを見据えているのかをお聞かせください。
旭化成 山田様:延岡での現在の取り組みは社会貢献の側面も意識していますが、それは、社会実装に向けた一つの手段として有効であるとの判断からです。今後、取り組みを継続的なものにするためには、当然、経済性も意識しなければなりません。
それは弊社だけで実現できることではなくて、森林に関わる利害関係者が繋がったエコシステムが形成されることが重要だと考えています。その前提があって初めて森林クレジットが社会に根付いていくことになると思います。
すなわち、森林クレジットの創出を通して、地域の産業や環境に貢献できる仕組みを森林に関係する方々と作っていきたいと考えています。例えばそれは、林業事業体の方々や、森林制度を管理している自治体の方々、所有者の方、クレジットの購入者など、様々な立場の方がいらっしゃいます。皆に魅力を感じて頂けるような仕組みを、ぜひ実現したいと考えています。その起点となるのが、延岡協議会での実証です。協議会での取り組みを成功させて、そこから宮崎、さらには九州全域などに範囲を広げていきたいと考えています。
旭化成 辻様:補足しますと、利害関係者がとても多いんですよね。みなさんに入ってもらって、せーのでタイミングを合わせて動かしていかなくてはならなくて、そのエンジンになるものが今、御社と一緒に取り組んでいるプラットフォームということです。プラットフォームの機能を少しでも高度化し、拡張性を持たせることがポイントになりますが、そのための取り組みがまさしく、FCSの開発ということになります。
今後のマイルストーンについてお聞かせください。
井上:今後のマイルストーンについてお聞かせください。POCは次は宮崎でやられるんでしょうか?
旭化成 辻様:延岡実証を終えた後は、宮崎に活動範囲を広げていきたいと考えています。宮崎に範囲を広げることで新たなステークホルダーの方々とも繋がる必要がありますので、実証のスケールは大きくなります。
井上:その次のステップとして、エリアを広げていくのか、もしくはもう少し深めていくのかでいうとどのような展開を予定しているのでしょうか?
旭化成 辻様:エリアを広げていくことを考えています。冒頭に申し上げたように、森林のサステナビリティは日本全体の大きな課題です。森林クレジットの創出をトリガーに、経済性も備わった森林のサステナビリティ実現に少しでも貢献できればと考えています。
今後弊社に期待していることなどがありましたらお聞かせください。
旭化成 辻様:一つは事業や仕事に対する考え方、カルチャーなどを含め、我々のような伝統的な製造業の価値観とは違ったマインドをみなさんは持っておられると思います。
井上さんはじめ、みなさんリスクを取って事業にチャレンジされていて、そういったプロアクティブなマインドを学ばなければならないと思っていますし、我々もそう変わっていかなければならなければならないなと思っています。ですので、クロスカルチャーのような意味で、引き続き、パートナーとして良い関係でいたいと思っています
井上:ありがとうございます。
おわりに
今回、旭化成の研究開発本部のみなさまと「森林DXを通じたカーボンクレジット」をテーマに対談をさせていただきました。旭化成様は当社の株主でもあり、常に総合的なサポートをいただいております。現在、世界規模における最重要課題は「環境問題」と「人口問題」だと言われており、そのメガトレンドの中で結果を出していくために純国産のプラットフォームとして旭化成様とご一緒できていることを非常に嬉しく感じております。今後ともデータやAIといったテクノロジーの観点からサポートをさせていただきたく思います。

旭化成森林クレジット プロジェクトメンバーの皆様と